第6回
サマーキャンプ第1部をレポートします! 楽しかった~!(前編)
2021.08.07更新
「こどもとおとなのサマーキャンプ 2021」の第1部を先週末に開催しました!
それぞれの先生が「こんな授業受けたことない!」という最高の講座をしてくださり、こどもにとってもおとなにとっても学びにあふれた、とっても楽しい時間となりました。
今日、明日の2日間にわたって、ミシマ社メンバーより第1部の感想をお届けします。「サマーキャンプってどんなことするんだろう?」とお思いの方は、ぜひこの記事で、実際の様子をご覧いただけますとうれしいです。
第1部は終了いたしましたが、第2部からのご参加も大歓迎です! チケットをご購入の方はアーカイブをご覧いただけます。
今回レポートするのは、7/31(土)~8/1(日)に行われた5講座です。

「tupera tupera流 絵本のつくり方」
トップバッターとして、tupera tuperaのお二人に登場いただきました! 絵本づくりテクニックをたっぷり教えてくださいました。(※tupera tuperaさんの講座のアーカイブは通しチケットでのみご覧いただけます。)
◎メンバーの感想

絵本のアイデアはどうやって生まれるのか、そして実際に絵本を作るときの技術までたっぷり教えてくださったのですが、「ええっそこまで言っちゃって、見せちゃっていいの!?」というような大充実の1時間半でした。エンピツはこう使うもの、絵の具はこう、というような決まりはまったく気にしなくていいんだ、思ったようにやってみたらいいんだ!と、しみじみ感じ、つい「海は青色でしょ」「うんちなんて描かないでよ」なんて子どもに言っちゃって型にはまろうとしてしまう親こそ見るべきでは・・・と、自分を振り返りつつ思いました。
ちなみに個人的には「うんこの影の付け方」が最高で、この技術を知っているだけでなんかプロっぽいうんこができるやん、とさっそくマネしてみました。(新居)

tupera tuperaさんのお宅に伺い、配信を担当しました。配信場所になるアトリエがめちゃめちゃ素敵なのですが、この講座ではその一部も紹介! そして、アイディアの出し方、絵本紹介、本の構造のレクチャー、さらには実演など、1秒たりとも目が離せない濃密かつ超絶おもしろいお話が繰り広げられます。なかでも圧巻だったのは「絵本をかたちからつくる」で紹介のあった、丸い絵本である『あかちゃん』。なんと本書に出てくる「おっぱい」を亀山さんがライブペインティングしてくださったのでした。配信終了後に描いていただいた実物をいただき、家宝ができました。(田渕)
「こどもとおとなの料理講座」
つづいて、土井善晴さんによる料理講座です。まんまるで大きい、地球のようなスイカとともに登場され、一気に引き込まれました!
◎メンバーの感想

冒頭の、大きなスイカを切るシーン。土井先生の迷いのない所作と、目にも耳にも鮮やかにパカッと切られるスイカ、土井先生の満面の笑顔、それに続く、スイカ選びのお話。実際に見えているわけではないのに、画面の向こうの子どもたちが、一気に引き込まれていくのを肌で感じました。もちろん、その場にいた私たちスタッフも、そのかっこよさにしびれておりました。料理の方法の前に、料理とはなにかを教わる。私も子どものときに、こんな授業を受けたかったなぁと、心から思った80分でした。(星野)

土井先生のお話、今回も最高に面白く、子どもたちのために噛み砕いてお話くださったこともあり「土井哲学入門」の趣もありました。そして内容と並んで印象的なのは、土井先生が子どもたちのために工夫を凝らしてお話くださる様子です。お話の内容を巻物風の長い和紙に書いたり、本番直前に段ボール工作で紙芝居マシーン(?)を作って見やすくしたり・・・。
先生が料理について教えてくださることと同じく、作り手と受け手の間の愛を感じました。(岡田森)
「いきものとあそぼう!」
中田兼介さんは、身の回りのいきものとの遊び方を教えてくださいました!
◎メンバーの感想

昨年に続いて開催の中田兼介先生のいきもの講座。今回は中田先生が京都オフィスに生きものを連れてきたくださり、カエルの吸盤やクモの捕食の観察にもチャレンジ! 恒例?のクイズコーナーも今回は絶妙に難しい! トノサマガエルが激減したのに、そんな理由があったとは...! 昆虫を捕まえる道具として新たに「吸虫管」(まるで掃除機)という武器も伝授いただきました。
後編では、参加者のみなさんが撮ってきたいきもの写真や気になるポイントを中田先生が解説します。今年はどんないきものとの出会いがあるのか、本当にたのしみです!(池畑)

いきもの博士・中田兼介さんに、夏にできる、虫やいきものたちとの遊びを教わった本講座。博士が森でいきものを探す様子や、クモが餌を捕食する実験(結果は講座を観てのおたのしみ)を通じて、幼少期を思いだし、思わず駆け出しそうになりました。都会であっても、身近でいきものとふれあって遊ぶことができるということにも気付かされました。第2部では、参加者のみなさんがみつけたいきものたちで図鑑をつくります! どんないきものたちが集まるのか今からとっても楽しみです。(山田)
明日は、宮田正樹さんと村上慧さんの講座のレポートをお送りします!
(後編につづく)
編集部からのお知らせ
第2部からのご参加もお待ちしております!

第1部は終了いたしましたが、第2部からのご参加も大歓迎です!
チケットをご購入の方はアーカイブをご覧いただけます。


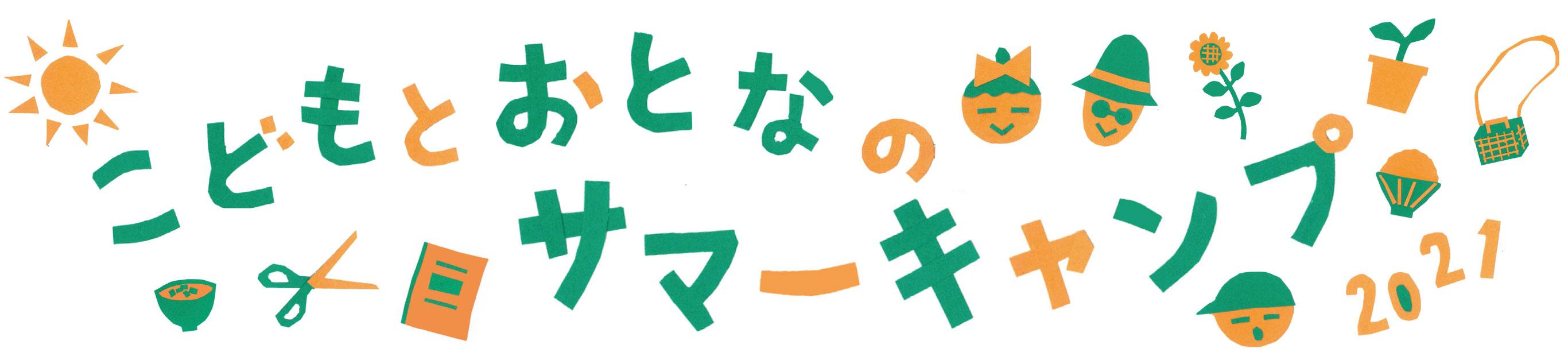


-thumb-800xauto-15803.jpg)


