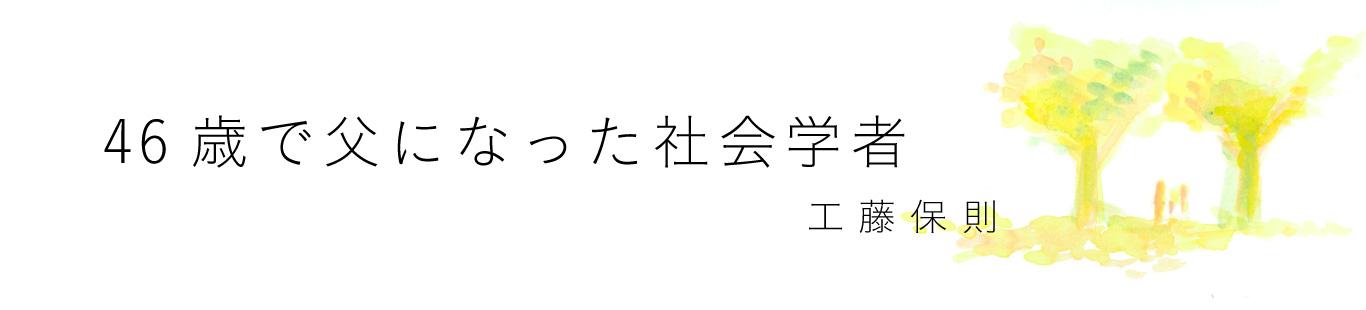第2回
妊娠
2018.12.09更新
「あのね。もしかしたら、妊娠してるかもしれない」
ある朝、妻が真剣な顔で告げた。
一瞬で眠気がふっとんだ。
私は当然のごとく喜んだ。そして、その気持ちは妻も共有しているものと思っていた。
「生まれる時は46歳。ずいぶん年を取ったお父さんだねぇ」
「うん・・・」
「もっともっと仕事をがんばります」
「うん・・・」
「家事も今以上にしますので」
「うん・・・」
妻は生返事を繰り返すばかり。その表情がさえないことに気づいた私は話しかけるのをやめた。その日、妻は、あまり口をひらかなかった。
数日後、妻は総合病院の産婦人科に行くことにした。その間、私は大いにとまどっていた。この上なくうれしい気持ちである自分と、必ずしもそうではなさそうな妻。妻がなぜ喜びに満ちていないのかよくわからないままでいた。それとなく聞いてみたりしたが、妻は言いよどんでいた。
病院には私もついて行った。妻は朝から不安そうな顔をしており、言葉も少なめだった。診察室で名前が呼ばれ、心細そうな表情で診察室に入っていった。5分後、同じ表情で出てきた。
「妊娠してた。今、2カ月。予定日は7月7日」
妊娠が明らかになり、妻はさらに困惑した様子をみせた。
妻は、若い時からなんとなく、けれどもある種の確信を持って、自分は結婚しないだろう、子どもを産むこともないだろうとずっと思っていたという。それが33歳の時に、ひょんなことから、ひとまわりも年上の私と結婚した。人生において予想外のことだったらしい。その上に妊娠ともなると、まったく想定外のことが起こったのである。
微熱やだるさをはじめとしたからだの変化もすでに始まっており、それがさらに妻をとまどわせた。「自分のからだが自分のものじゃなくなっていくみたい・・・」。
何事にもまじめな妻は、うかない顔をしつつも、書店で『初めての妊娠・出産』という本を買ってきた。ページを繰りながら、「こんなことがこれからお腹で起こるのかぁ。どうしよう。こわいよー」とつぶやいた。
「こわいよー」と口にしたことで、少し落ち着いたのかもしれない。妻はぽつりぽつりと言葉を続けた。
「出産にまる1日とか2日もかかったっていう話を聞くやん。私、体力ないし、体がもたへんかも」
「うん」
「無事に出産できたとして、子どものこと、好きになれるかなぁ。もともと子どもがそれほど好きじゃないし」
「うん」
「扱い方もわからへん。身近に小さい子がいた経験もないし」
「うん」
「私、許容量が小さい人間やから、お母さんとしての資質に欠けてると思うねん」
「・・・・・・」
「そんな私が、お母さんになれるんかなぁ・・・。なっていいのかなぁ・・・」
「お母さんになれるのか」という問いは意表をつくものだった。なんとなく、妊娠することで女性は一気に母になるかのように思い込んでいたのだ。
妻の不安はまだ続いた。
「ようやく、仕事らしい仕事ができるようになったのに、出産と育休で仕事を中断することになっちゃう。復帰しても、間違いなく子どもに手がかかり時間も取られる。また"半人前"に戻っちゃう」
「・・・」
「会社にいつ言おう」
「・・・」
「誰に、何て言おう」
「・・・」
妻はキャリア志向ではなかったが、いざ仕事を休むとなると、「会社員としての自分」が頭をもたげてきた。まわりに迷惑をかけてしまうことがなにより気がかりだった。
ありとあらゆる不安が一気に押し寄せていた。
私の方はといえば、「妊娠してた」と聞いて、ただただうれしかった。それまで「お父さんになれるのか」と考えたこともなかったし、妻が妊娠したことで、自分は自然に父になるものだと思っていた。そして頭に浮かんだのは「子どもが成人する時は66歳。少なくともそこまでは大きな病気をすることなく元気でいたいなぁ。できればその先も」ということだった。自分の年齢と健康のことだけが気がかりだったのだ。
「わが子と早く一緒にお酒を飲みたい」という言葉をよく耳にする。父親は、何事もなく、健康な20歳の若者になったわが子を想定する。そこには、子どもが生まれるまでのことや育児のことなどはすっとばされている。ましてや、自分のキャリアが中断されることなど、思い浮かぶことさえないだろう。私もそうだった。
2週間後、再び産婦人科で診察をうけた。胎児の心拍が確認できた。妊娠ははっきりと現実のものとなった。
妻の実家に電話で報告した。「よかった。よかった」とお義母さん。「あの子もお母さんになるんやな」とお義父さん。長い電話になった。続いて、私の実家にかけた。父は「母さんも喜んどるじゃろ」と10年前に他界した母のことを言い、「じいちゃんに言うわ」と。耳が遠くなった101歳の祖父に大きな声で伝えているのが受話器を通して聞こえてきた。
「やすくんに子どもがうまれるんやって」
「えー?」
「やすくんになー、子どもがなー、うまれるんやって」
「おー」
祖父が電話口に出てきた。
「こんなうれしーことはないわ。お嫁さんにかわって」
妻の持った受話器から祖父の声が聞こえた。
「ありがとうございます。こんなにうれしいことはありません。からだにきーつけてください」
祖父との話をおえた後、妻はポロポロと大粒の涙をこぼした。
「不安ばっかりで。赤ちゃんのこと、素直に喜んであげられなくて。こんなお母さんで、赤ちゃん、かわいそう」
まわりは喜び一辺倒であるなか、妻は、ずっと、孤独に不安とたたかっていた。