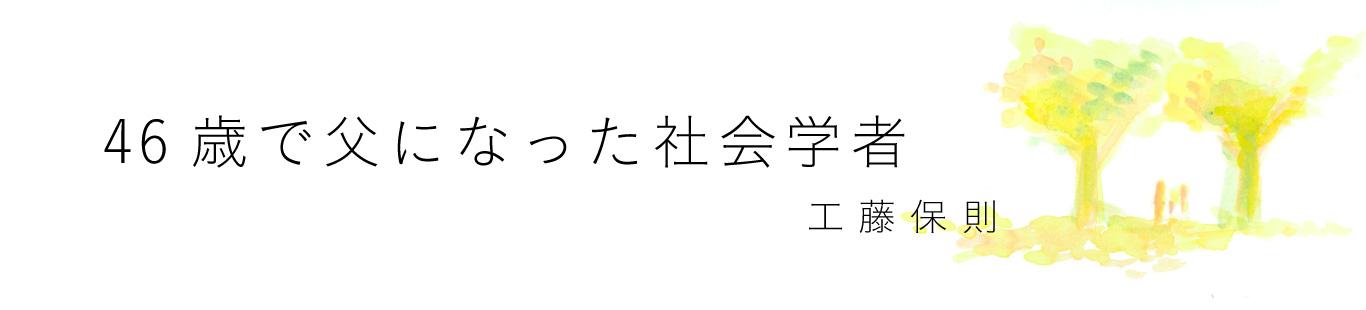第3回
変化
2019.01.06更新
妻のつわりは重かった。
つわりと言えば、ドラマや映画での、女性が「うっ」と口を押えて洗面台に向かい、周囲は「ひょっとして」と妊娠を疑う、あの場面を思い浮かべる人が多いだろう。それはある瞬間の光景にすぎない。実際は、一日中、吐き気と倦怠感を中心とした体調不良の中にいるのである。それが毎日続くのだ。
朝、目覚めても、妻はしばらく布団の中でじっとしていた。そして、観念したように「あー、またつらい1日が始まる」と言いながら起きてきた。「食べないとあかんよね」と無理して朝食をとり、のろのろと出社のための支度をし、暗い顔で家を出た。
安定期に入っていなかったので、会社のごく一部の人にしか妊娠のことを伝えていなかった。したがって、吐き気を覚えながらも普段通りに仕事をこなさなくてはならない。
夕方、電車に乗って帰ってくる。その際、最寄り駅から自宅までの徒歩10分の距離が歩けない。駅からバスに乗り、這うようにして帰ってきた。
家にたどり着くと、玄関にへたり込んで動けない。トイレに駆け込み、激しく嘔吐することもたびたびあった。
「しんどいよー」
「からだがもたへんよー」
血の気の引いた顔で泣いていることもあった。私は妻の背中をさすることしかできなかった。
鼻(臭覚)と舌(味覚)の変化もすさまじかった。
ご飯が炊けるにおいやお味噌汁のにおいを受けつけなくなり、冷蔵庫を開けるのさえも苦痛になった。キッチンに立てなくなった妻に代わり、私が食事を作るようになった。妻がその日、何を食べられるかは、お皿を前にしないとわからない。そのため、「食べられるものを作る」のは無理であり、「食べられそうなものを作る」ことになった。しかし、それも実際どうなるかはわからない。料理にほとんど箸をつけずに「ごめん。もう、無理。ごちそうさま」ということもあった。
入浴時にはシャンプーのにおいで気分が悪くなるため、無香料のものにかえた。歯磨き粉のにおいも耐えられなくなり、水で素早く磨いていた。生活の場のいたるところに、においがあることを、つわりの妻を見て知った。
眠っている間しか、つわりから解放される時はない。布団に入って「やっと、1日が終わる。ハァー」と長い息をはいた。人によっては、産み月までつわりが続くことがあると聞き、妻は「自分もそうだったらどうしよう」と絶望的な気分になっていた。出口の見えないトンネルの中にいるようだった。もともと体力のない妻は、つわりでその少ない体力を奪われ、体重も落ちた。やつれて顔はひとまわり小さくなった。
あたりまえだが、私のからだには何の変化も起こっていない。苦しみを負担しようにも、私は全くの無力だった。ただ、つわりがどれほど過酷であるかを知った。
幸いにして2カ月後、妻はつわりのトンネルをぬけた。安定期に入ると、妻の心境にも大きな変化があった。それは傍らで見ていても、よくわかった。からだとこころはつながっている。からだが消耗すると、こころも消耗する。つわりから解放されると、こころも晴れたようだった。
「何事も理性でコントロールできると思ってきたけど、自分でコントロールできることなんて、本当はあまりないんやねぇ」
「たいていは、どうなるのかわからへん。人生は予想をはるかに超えている。それでも、進んでいくしかないんやね」
「うん。もうここまできたら、進むしかない」
妻はきっぱりと宣言した。
子どもは意のままにならない存在である。つわりを経て、コントロールできないものを受け入れる覚悟が決まったようだった。
「つわりは予行演習みたいなもの。これからが本番」
妻は、腹をくくったのだ。
その頃から、妻のお腹がふくらみ始めた。といっても、最初は、二人ともよくわからなかった。ある日、鏡の前に立った妻が私に声をかけた。
「あれー、お腹、ちょっとだけ、とんがってない?」
「えー、そうかな」
「もしかしたら、ふくらみ始めたんかなぁ?」
「時期的にありうるんじゃない」
「たんに食べすぎただけやったりして」
「まあ、それはそれで、いいんじゃない」
数日後には、ふくらみがほんの少し増していた。
私はふと思いたって、それから、妻のお腹が大きくなっていく様子を写真に撮ることにした。ひと月単位で比較すると、体型の変化は明らかだった。数か月分の写真を並べると、そのお腹の成長ぶりに感動すら覚えた。
ロングセラーの育児書である『育育児典』(毛利子来・山田真、岩波書店、2007年)には、「お腹の子への気持ち」としてこういう文章がある。
男性にとっては、わが子がいるということは、リアルには感じにくいのではないでしょうか。なにしろ、胎児が自分のお腹の中にいるのではない。当然、体調や体型の変化もない。ただただパートナーの変化を見せつけられるばかり。ですから、「わが子」といっても、頭のなかで、そう思いなすほかはないでしょう。
「見せつけられる」――まさにその通りだ。過酷なつわりや刻々と変化してくからだに、私は圧倒された。妻は自らのからだをもって、子どもがいることを強烈に伝えてくれた。
そうこうしているうちに、胎動が始まった。最初はかすかなもので、それが胎動かどうかわからなかった。やがて「小魚が泳いでいるような」感覚があり、もしやこれが胎動ではないかと妻は言い始めた。「さわってみる?」と言われて、手のひらをお腹にあてたが、何も伝わってこなかった。その後、何回かお腹に手をあてたが、なかなか感触は得られなかった。ある時、かすかに「ぴく」という感触が手のひらに伝わった。今まで感じたことのないもので、とても不思議な気持ちがした。
やがてそれが「ぴくぴく」と躍動感をおび、「ごろごろ」と重量感を伴い、さらには「ごろん」「ごろりん」と目にも明らかな存在感を示すようになった。私は、妻のお腹に手をあて、その何とも言えない感触を味わった。そして、お腹の中の子どもに話しかけるようになった。
妻はといえば、脇腹から足がぬーっと出てくることや、ひっくひっくしゃっくりする胎児の感覚を「あれあれ」と言いながら楽しんでいた。女性にとって、胎動は格別な感情をよびおこすもののようだ。
『育育児典』には、「父親になることに対する心の準備」についてこう書かれている。
自分の立場を妊娠の共同の当事者として据えてしまうのです。お腹の子のことも、折をみては彼女のお腹に手をあてて胎動を感じたり、耳をつけて心臓の音を聞いたりするとよい。そうすれば、多少ともは実感できるはずです。
それまで、私は妻のからだの変化をただ「見せつけられる」ばかりだったが、手のひらに伝わる胎動によって、妻と共にいのちを実感できるようになった。なによりもうれしく、幸せなことだった。