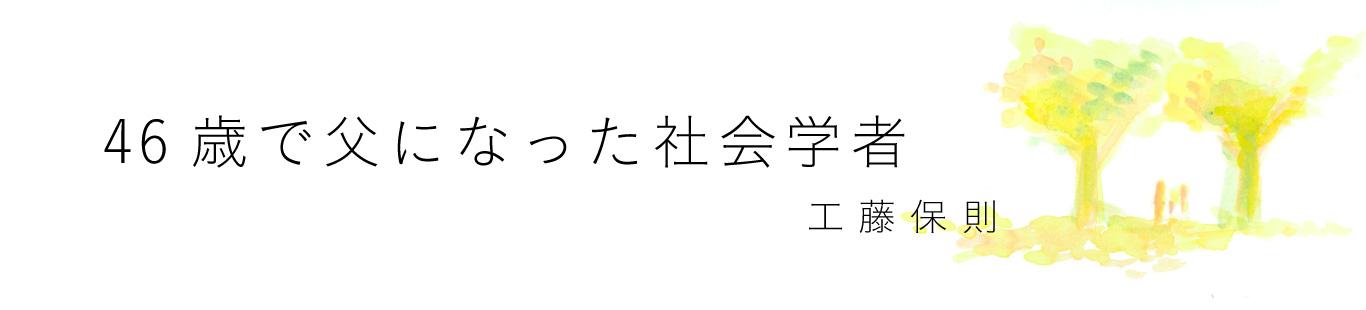第4回
誕生
2019.02.07更新
その日は妊婦健診だった。
「まだ下りてきていませんね」という医師の言葉に、妻は「本番はもう少し先か」とほっとしたという。病院から帰ってくると、その頃の恒例となっていた長い散歩や昼寝をするなどして、いつも通りに過ごした。
夜の10時すぎ、妻が言った。
「なんか、お腹がしばってくるような気がする。陣痛かな?」
「陣痛になったことないから、わかりませんねー」
「そりゃそうだ」
ふたりともまだ笑う余裕があった。
とりあえず寝ておこうと、横になる。しかし、妻は眠りにつくことはできず、だんだんしばりの間隔も短くなってきて、私を起こした。
「やっぱりこれ、陣痛やと思う」
病院に電話をして様子を伝えると、「初産婦さんは時間がかかりますので、もう少し様子をみていてください」との返答。そうはいっても眠れるわけもなく、妻は不安そうに縮こまっていた。痛みの間隔がさらに短くなってきたので、もう一度、病院に電話をかけた。
「家にいたら不安ということでしたら、来ていただいてけっこうですよ」
「はい。落ち着かないので、もう行きます」
タクシーを呼んで病院に向かった。
初産は予定日よりも遅れることが多いと聞いていた。その日は、予定日より5日前だったこともあり、ふたりとも出産に対してのこころの準備ができていなかった。
午前2時に入院。ほどなく痛みの間隔が3~4分に。妻はひと眠りすることもできず、いきなり本番に突入することになった。痛みでベッドに横になっていられなくなり、椅子の背もたれを抱えるようにして座る。タオルを握りしめながら、息を吸って、「ふぅー」と長く吐く深呼吸を繰り返す。私は妻の背中をさするくらいしかできない。
夜が明けて、看護師さんが食事を持ってきてくれた。妻はなんとかプチトマトを2つだけ口に入れた。その時、妻の両親が到着した。お義母さんが「いまが一番しんどい時やなぁ。赤ちゃんもがんばってるわ。もう少ししたら会えるで」と声をかけながら、妻の頭をごしごしなでた。妻の顔は涙と汗でぐちゃぐちゃになっていた。
8時頃、疲労のため陣痛が弱まった。妻はすでに精も根も尽きはてたという状態になっていた。顔は青白く、表情もない。助産師さんがお湯を入れたバケツを持ってきて、足をあたためながらマッサージをしてくれる。
「大丈夫ですよー。ここで一度、ゆっくりしましょう」
妻は返事もできず、こくんとうなずいた。
9時すぎ。
顔の赤みがほんの少し戻ってきた。それとともに、また陣痛が強くなった。
「あー、うー、んー」
妻はけんめいに呼吸法を試そうとするが、痛みのあまり体がこわばり、短い息つぎしかできない。
11時。
「もう限界」というところで、助産師さんが「分娩室に行きましょう」と妻をベッドにのせて運んだ。分娩台にのると同時に、酸素マスクと点滴がつけられた。私はベッドの横に座り、妻の手を握った。
「もう、いきんでいいですよ」と助産師さん。
4回ほど、深呼吸といきみをくりかえす。
11時25分。男児、誕生。
「生まれましたよ。かわいい男の子ですよ」と助産師さんが妻に声をかけた。私も何か話しかけたかったが、言葉にできない。妻は疲労と安堵が混然一体となったような顔をして、上を向いたまま、ふーと息を吐いていた。
生まれたばかりの赤ん坊は静かだった。疲れはてていたのだろう。30秒くらいたってから、「ふぎゃあ。ふぎゃあ」と小さな声をあげた。
助産師さんが赤ん坊を見せてくれる。
「あ、じゅんくんだ」
――妊娠4カ月の検診で、「男の子」であることが明らかになった。そこから、私は子どもの名前を考えはじめた。そして「じゅん」という名前を思いついた。妻に伝えると、即座に「いいね。みんなが呼びやすそう」と賛同してくれた。「生まれてきたとき、もし『じゅんくん』という顔じゃなかったら、また考えることにしよう」と私はつけくわえた。
じゅんは「ぼくも、へとへとですわぁ」という感じだった。妻は緊張がとけ、泣きじゃくっている。私も涙がとまらない。横になったまま妻がじゅんを抱く。じゅんは
助産師さんが身長と体重を計ってくれた。身長49.6cm、体重2804g。
しばらくして、妻は病室に戻った。少したってから、新生児用のベビーベッドに寝かされたじゅんも病室に運ばれてきた。ふやけてアザだらけだったじゅんは、数時間できれいになった。私はじっとしていられなくて、部屋の中を歩き回っては、何度も何度も「いい顔してるなぁ」とじゅんをのぞきこんだ。そして、ときおり、ぎこちなく抱っこしてみては、その軽さと生命の重みを味わった。
出産後、妻は「私、よくがんばった。耐え抜いた」と言った。そして、妊娠から出産までのことを振り返り、じゅんの1年間の記録をまとめた自家製冊子『じゅんくんのあゆみ』にこう書いている。
おなかに子どもを宿してから、私の体は自分だけのものではなかった。共有されていた。じゅんくんのものであり、じゅんくんの誕生を喜びとする人たちのものだった。所有とは正反対の感覚だった。
「所有とは正反対の感覚」。その感覚を、私は持てていない。
男性は「産めない」性と言われるが、「宿せない」性と言ったほうが正しいような気がする。女性は子を宿した時から、否応なく、自分以外の存在とともに生きていくことになる。それに遅れること約1年、男性は子どもが生まれることで初めてその存在を認めることになる。
だからといって、女性に対して「ちょっと待っていて」というのでは、あまりに申し訳ない。つわりの苦しみも出産の痛みもまぬがれている男性は、子どもが生まれた瞬間から、全力で走り出さないといけない。これはできるはずだ。女性と比べてこころとからだのウォーミングアップは足りないのかもしれないが、そんなことは言っていられない。もっとも、このことは私も後になって気がついたことなのだが。