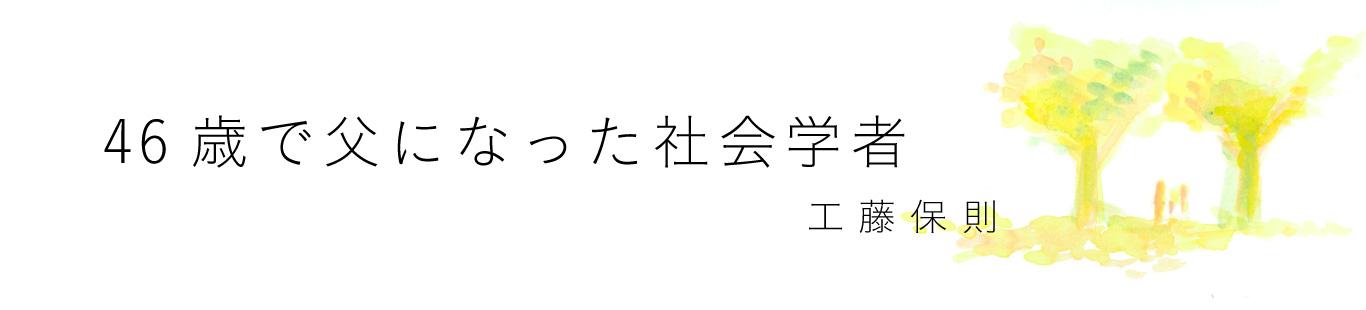第5回
ケア
2019.03.05更新
出産後5日間、妻は病院にいた。へとへとになったからだを休める暇もなく、母子同室で2~3時間おきの授乳が始まった。それがうまく軌道にのらないため、退院後の生活に不安をつのらせていた。
私のほうは、出産当日とその後の3日間仕事を休み、朝9時から夕方6時まで、病室で過ごした。4日目の土曜日はたまった仕事や用事を午前中にすませた後、急いで病院に向かった。生まれたばかりのじゅんがかわいくてしかたがなく、少しでも長く一緒にいたかった。病室で、私はずっと、ほとんど眠っているじゅんの顔を見ていた。
退院の日、お義父さんとお義母さんが病院に来てくれ、皆でタクシーに乗って自宅に帰った。お祝いということで昼食には赤飯を食べた。その後、お義父さんは「それじゃあ」と帰っていった。お義母さんは、この日から1カ月間、泊まり込みでじゅんと妻の世話をしてくれることになっていた。出産後、いまひとつ体調のすぐれない妻は、そのことをとても心強く思っていた。それは私も同じだった。おむつ替え、沐浴、粉ミルク作りとミルクやりを、私も病院で1~2回、助産師さんの指導のもとに練習したが、おたおたしてどれもうまくできなかった。
実際、本番になっても、何ひとつ満足にできなかった。沐浴では、背中を洗うために裏返すというのがなかなかできなかった。首がすわっていないので支えるのが難しく、お湯の中に落としてしまったらどうしようと緊張して余計に力が入ってしまった。粉ミルク作りでは「ひと肌」の温度にするのが難しかった。また、哺乳瓶の吸い口をただ口に当てたらミルクを飲んでくれるわけではなく、飲みやすい角度にしてあげる必要があったのだが、そのことも最初はわからなかった。おむつ替えも、下に新しいおむつを敷くのをしょっちゅう忘れた。抱っこでさえ、手をどこにあてがったら安定するのかがわからなかった。
私が何かをするとじゅんは泣いてしまった。そのたびに、お義母さんがそれとなく手伝ってくれた。
「慣れの問題だから、そのうちできるようになるわよ」
「そうですか・・・」
「慣れるためにも、次もやってみたらいいわね」
「そうですね・・・」
という会話を毎日のようにしていた。
私は大学での仕事があるので、昼間は家にいないことが多かった。じゅんのケアといっても、帰宅してから寝るまでのほんの数時間のことだ。それに、「昼間の仕事にさしつかえるから」ということで、じゅんとは別の部屋で寝ていた。昼間と夜中は、じゅんのケアを「免除」されていたのである。そういうこともあって、子どものケアをするのは、うまくできなくても、どちらかといえば楽しいことだと思っていた。私は、じゅんが生まれたうれしさだけで毎日を過ごしていた(過ごせていた)のである。その間、妻の方は、母のサポートがあったとはいえ、すでに、ケアの過酷さのまっただ中にいたことに、私は気づいていなかった。
1カ月後の8月初旬に、「後はふたりでがんばって」という言葉を残して、お義母さんが帰っていった。大学は夏休みに入っていたので、私は能天気にも「家で仕事をしながら、育児をしよう」と思っていた。
翌日、はじめて妻とじゅんと3人で過ごした。そして、すぐ、「家で仕事をしながら、育児をしよう」という考えは根本的に間違っていることに気がついた。
その日のじゅんの一日を示す。
6時30分:おっぱい練習+搾乳70cc、ミルク40cc、便、尿 / 9時:からだ拭き / 11時15分:ミルク70cc / 12時:便 / 12時40分:便 / 13時:おっぱい練習、ミルク100cc、尿 / 17時30分:おっぱい練習+搾乳90cc、ミルク40cc、便、尿 / 20時30分:尿、沐浴 / 21時:ミルク100cc / 深夜1時10分:おっぱい練習+搾乳110cc、尿
毎日、毎日、これが続く。というか、私はわかっていなかっただけで、このひと月もずっとそうだったのだ。
じゅんは最初のうち、母乳を直接おっぱいから飲むことができなかった。そして妻も母乳が十分に出なかった。そこで、助産師さんのアドバイスに従い、おっぱいを飲む練習をしてから、搾乳して冷蔵保存しておいた母乳をあたためて与え、足りない分を粉ミルクで補うという一連の「授乳」を繰り返していたのである。当然、授乳と授乳の間に妻は搾乳をしなければならないのであって、休む時間、ましてやぐっすり眠る時間などなかった。極度の疲労から妻は何度か高熱を出した。しかし、授乳の時間は母親の体調とはまったく関係なく、粛々とやってくる。今でも妻は、産後1カ月をふりかえって、「生きているのか死んでいるのかわからなかった」と表現する。
「人間の赤ちゃんは1年の早産」と言われることがある。それくらい、生まれた時は何もできない。すべてにおいて誰かがケアしないと生きていけない。じゅんのいのちは妻と私にかかっているのだ。そして、やらないといけないのはじゅんのケアだけではない。妻と私の分の食事の支度や洗濯や買い物など、生活のあれこれがくわわってくる。
私は目が覚めた。
子どものケアや家事は、「私はこれをやるから、あなたはそれをやって」というように合理的に分けられるものではない。全体を共有し、その上で、状況によって私の方がすることが多いもの、妻の方がすることが多いもの、どちらもがするもの、というふうになっていった。とはいっても、おっぱいは妻にやってもらうしかない。そう考えると、間違いなく、妻の方が多くのことをしていただろう。
お義母さんが帰ってから、じゅんのケアのかたわら、私は毎日の食事作りに精を出した。こうして後期授業が始まる9月中旬までに、ある程度のことはできるようになった。このひと月半のおかげで、遅ればせながら、私は育児に対する心構えができたように思う。
このひと月半は私にとっての「育休」だった。乳児がいかに何もできないか。24時間体制のケアがいかにハードか。それに家事もくわわると、どれほど大変か。それらを自分のこととして理解した。
育休は、育児休暇=「生まれた子どもとゆっくり楽しくすごす時間」というふうに捉えられているフシがある。恥ずかしい話だが、私もじゅんが生まれるまでそう思っていた。実際は、乳児の全面的ケアに専念するための、賃金労働の一時休業である。現在、男性(父親)の育児休業取得率はほんのわずかである(5.14%(2017年)※1)。育休を取った場合でも、その半数以上は5日未満だという。取らない理由としては「仕事に支障が出る」というのが多いようだ。裏を返せば、父親が育休を取らないことで(つまりは、子どものケアに参加しないことで)、家庭において「子どもと母親へのケアに支障が出ている」という現実があるはずだ。
まだまだ多くの男性(父親)にとって、子ども(赤ちゃん)はかわいいだけの存在になっているのではないだろうか。ケアをしないと死んでしまう存在、24時間緊張感をもたらす存在であることを理解しないまま、子どもの誕生後もそれまでとあまり変わらない生活パターンを続けている男性は少なくない。
子どもが生まれたら、それ以前の生活パターンを続けることはとうてい不可能だ。もし「変わらない」とすれば、それは妻だけに「変えさせている」ことにほかならない。「なぜ私だけが・・・」と妻たちは不安や不満を募らせていることだろう。
男性がせめて1カ月でも育休をとり、子どものケア(それにくわえて、産後の妻のケア)に専念すれば、「これが毎日続くんだ」という実感をもてるだろう。そうすれば、働き方や暮らし方、人とのつきあい方はずいぶん変わるはずだ。よほど鈍感な人でない限り、育休が終わった後も、可能な限り仕事を早く切り上げて家に帰るようになるだろう。育児をしない言い訳として「仕事」を使うこともなくなるだろう。
わが子はただかわいいだけの存在ではない。なまなましいいのちとして、父親に強く訴えかけてくる存在でもある。
参考資料