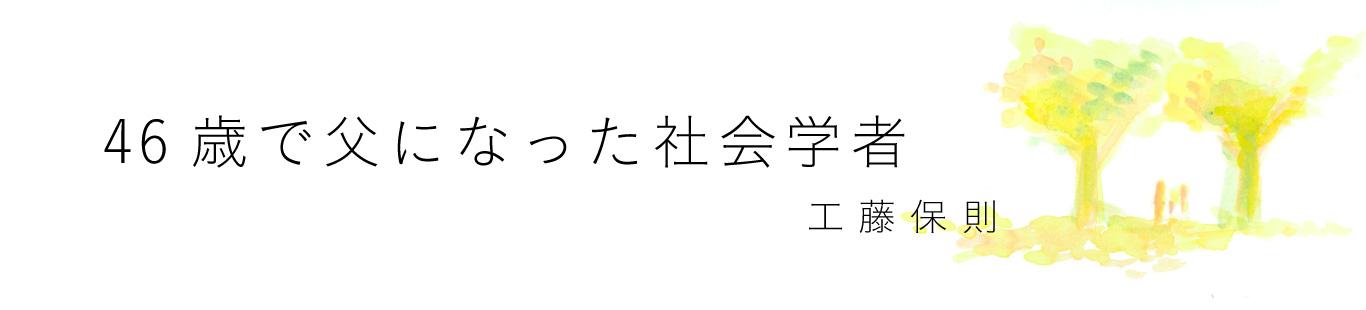第8回
札所
2019.06.03更新
私の生まれ育った町には、四国八十八ケ所の十一番札所・藤井寺がある。藤井寺は、住宅が多い地区を抜け、片側は山、もう片側は田畑という細い道を1kmくらい行ったところにある。
小学生の頃、藤井寺には1年に2回行っていた。春分の日と秋分の日、参道の両側に露店が並ぶにぎやかな市がたったからである。近所の友だちと自転車に乗って参道の近くまで行き、空き地に自転車をとめる。そこから最初の露店までは約50m。たこ焼きや焼きそばのにおいが漂ってくる砂利道を友だちと小走りになりながら、「たこ焼き、食べよー」「そーしよー」と声をかけあう。
赤や黄色、橙など原色を使ったテントが所狭しと並んでいる。アニメのキャラクターが描かれた袋に入った綿菓子、ウルトラマンや仮面ライダーのお面、金魚すくい(網が紙のお店ともなかのお店があった)、型抜き、リンゴ飴、焼トウモロコシ・・・。カラーひよこというのもあった。
露店でものを買ったり食べたりしながら混雑した道を進む。いつもより多めに持ってきたお小遣いは、あっという間になくなった。
藤井寺に着くと、境内を奥まで進み、本堂で手を合わせる。財布の中は空っぽになっているので、お賽銭はない。その後、順番待ちまでして境内の鐘を突き、その響き方を競ったりした。
帰り道でも露店を眺めながらぶらぶらするが、もう何も買えない。ただ見るだけである。それでも十分楽しかった。市のたつ日は、子どもながらにハレの気分を満喫した。
その藤井寺に、40数年ぶりに足を向けた。息子のじゅんが3歳くらいの時、家族で帰省した際のことである。妻の「天気がいいから、お散歩でもしましょうか」との提案に、父が「じゃあ、藤井寺に行くで」とこたえ、4人で出かけたのである。
父の運転する車で藤井寺の少し手前まで行き、私が小学生の時に自転車をとめていた空き地に駐車して、そこから寺までの道を歩いた。道はきれいに舗装されている。まだ朝の9時すぎだったが、徳島ナンバーだけではなく、関西各府県のナンバー、さらには東海や関東地方のナンバーをつけた車が次々に私たちの横を通り抜けていく。
「お義父さん、あの畑に植わっているのは何ですか?」
「あれは桑じゃなぁ。このあたりは、むかーしは、よーけ、おかいこさん、やっとったけんな。うちも、やっとったなぁ。家の中に蚕棚、あったでよ」
「ほんとですか!」
「おかいこさんは、もーどこもやってないけんど、桑はまだあるなぁ」
父にとってはあたり前の話だが、都会育ちの妻にとっては決してそうではない話をしている後ろを、私はじゅんと手をつないで歩く。そうこうしているうちに、藤井寺に着いた。
寺の山門の前には石段が何段かある。じゅんがその石段を登ろうとしたときに、後ろから声がした。
「きーつけないよ」
門のすぐ前で、お店を開いているおばあさんの発したものである。お店といっても、掘っ建て小屋の土間に台を置き、その上に商品を並べているだけである。そして、商品といってもわずかで、袋入りのおせんべいが2~3袋、1本の焼芋を半分くらいに切ってビニール袋に入れただけものが5~6袋である。焼芋は、80歳はこえているそのおばあさんが自らふかしたものだろう。
「こんまいのに、お参りやて、えらいな」
「段、あぶないけん、こけんときーよ」
じゅんが振り返ると、「かわいい子じゃなー」。
じゅんが石段を登り、門の手前で頭を深々と下げていると、「えー子じゃな」。
ずっとじゅんを見てくれている。私は「ありがとうございます」とお礼を言って、境内に入っていった。
境内にはお遍路さんが20人くらいいた。ほとんどが車を使ったお遍路さんだろう。そのため、お寺のすぐ前に駐車場もある。中には歩き遍路とおぼしき格好をした外国人のお遍路さんも数人いた。私と妻は「お遍路さんて、こんなにいるんだ」と驚いていると、父が「大型バスが来たら、いっぺんに40~50人くらい来るでよ」と言ったので、さらに驚いた。
本堂でお賽銭を入れ、手を合わせた。横で、じゅんも手を合わせている。「じゅんくんもお願い事したんで?」と父が聞くと、にこにこしながらじゅんはまた手を合わせた。
お参りを終え、境内を出た。山門から石段を下りていると、あのおばあさんが、じゅんを見つけて、「お参りおわったんじゃな。かしこいなー。これあげるけんな」と言いながら、ビニール袋をひとつじゅんに手渡してくれた。焼芋である。袋には「100円」とマジックで手書きされていた。じゅんが少しびっくりしたような顔で受け取ると、「また、おいでな」とおばあさん。子どもがかわいくてたまらないという様子だ。それが伝わるのか、じゅんも「ありがと」と言いながら、頭を下げる妻のまねをして、おばあさんに深々とお辞儀をした。
その様子を見ていた私に、ある記憶がよみがえった――小学生だった私は、春分の日や秋分の日以外にも、よく友だちと藤井寺に遊びにきていた。そしてこのお店で瓶ジュースを買って飲んでいた。
「おばさん、ジュース」
「ちょっと待ってな。栓、抜くけんな。はいどーぞ」
「なんぼ」
「60円やけんど、10円おまけして、50円」
「やったー。ありがとー」
「どちらいか」
毎回、おまけしてもらっていた。
目の前のこのおばあさんは、いつも、私たちに笑顔でやさしく接してくれていた、あのおばさんなのだ。40数年たって、今度は私の子どもが同じことをしてもらっている。
お店は、昔も今も利益はほとんどないだろう。利益を考えるなら、とうに店をたたんでいるはずだ。おばあさんは儲けとは違うものさしでお店に立っている。そのものさしは変わることがなく、決して古びない。
1日に何人かの子どもにやさしく接する。ひとりもいない時だってあるだろう。そして、子どもからの「ありがとう」を聞いてうれしく思う。そうした日々を40年以上積み重ねてきたのだろう。これ以上ないほど豊かな営みに思える。
じゅんが生まれてから多くの人に出会った。それは、じゅんがその人たちに出会ったということであり、同時にじゅんが私や妻をその人たちに出会わせてくれたということである。
乳幼児と一緒にいると、それまで想像もしていなかったくらいに多くの人が声をかけてくれる。わずかな時間であれ、わが子のことを気に留めてくれたことをありがたく思う。たった一度、ほんの少しだけやりとりをした人にも「出会い」という言葉を使いたくなるほどに、子どもを介した人との交流は私のこころの中に確かな変化をもたらす。このおばあさんもその「出会った」ひとりである。それだけではない。おばあさんをとおして、私は40数年前の自分にも出会えた。
京都へ帰るバスの中で、いただいた焼芋を3人で分けて食べた。お芋そのままの素朴な味が口の中でとけていき、やさしい後味が残った。