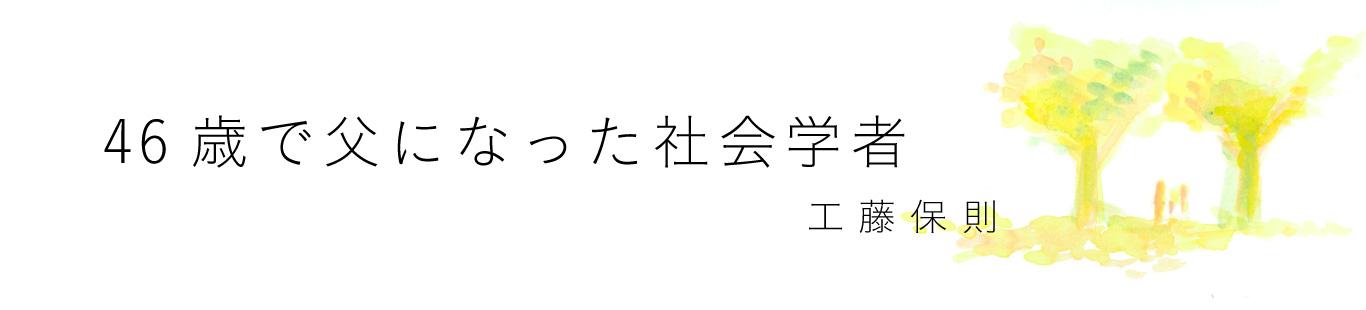第9回
無理
2019.07.04更新
自宅の徒歩圏内に一時預かり保育室があり、経験豊かな"ばぁば"が年中無休で子どもを預かってくれる。以前は別の場所にあったようだが、息子のじゅんが2歳半くらいの時に移転してきた。
妻はそのころ体調を大きく崩していた。
じゅんが生後9カ月になった春から、妻は職場復帰した。通常より約1時間半の時短勤務だが、仕事の量はフルタイムの時とさほど変わらないようだった。さらに慣れない別の業務にも関わるようになり、「まわりに迷惑をかけたくないから」と、時間の管理を徹底して、それまで以上に集中して仕事に取り組んでいた。子どもはしょっちゅう病気になる。子どもの看病疲れで自分もすぐ病気になる。いつ欠勤するかわからない。だから、なんでも締め切りの一週間前には目途をつけておかないと・・・とスケジュール帳をいつもにらんでいた。
時間とのたたかいは家でも変わらない。朝は、8時にじゅんを保育園に送るため、そこから逆算して行動する。6時に起きて夕食の下準備と朝食の支度をし、6時30分にじゅんを起こし、朝食を食べさせた後、自分の朝食。その後、掃除、じゅんの着替え、検温をし、最後に自分の支度、としたいのだが、じゅんは意思疎通がまだ十分にできないうえに常に動き回るため、思うようには進まない。家を出るのはいつもぎりぎりだった。
夕方、じゅんのお迎えの後も同様である。まだひとり遊びができないじゅんの相手を常にしながら、洗濯、お風呂、夕食の仕上げ、夕食、デザート、歯磨き、読み聞かせ、寝かしつけ、と進めていく。それらを夜の9時までになんとか終わらせたい。
これをやったらあれをやって、その次にあれをしてと、いかに効率よくこなすかを常に頭の中でシュミレーションしていた。一日中、緊張し、神経を張り詰めていた。それは寝ている時も変わらず、じゅんが「うーん」と小さく唸っただけで、妻は目をあけた。気が休まるときは、一瞬たりともなかった。
じゅんが2歳をすぎた頃、たまりにたまった無理が妻のからだを侵食した。朝、私が目を覚ますと、妻は「また寝られへんかった」とか「1~2時間、うとうとしただけ」というようになった。とうとう、からだが音をあげたのだ。
私は、最初は、一時的なことかと思っていた。今から思えばきわめて安直な対応なのだが、安眠効果があるといわれるラベンダーのポプリを枕元に置くことをすすめたり、「ぐっすり眠れる」という触れ込みの敷布団パッドを買ったりした。が、気休めほどの効果もなかった。知人から紹介してもらった鍼灸院もすすめてみた。これは先生と相性がよかったので、妻は続けて通うようになった。話をきいてもらうことでかなり気が休まるようだったが、不眠が解消することはなかった。他にもいろいろと試してみたが、どれもこれといった効果はなかった。状態は私が思う以上に深刻だった。
夜、休めていないので、妻はからだだけでなくこころも消耗しきっていた。
「夜になるのが怖い」
「一睡もできなくて空が白んでくると絶望的になる」
「もう仕事、できない気がする」
私は何もしてあげられなかった。
最終的に、妻は病院にかかった。薬の助けを借りて、やっと眠れるようになったが、薬に頼らなければいけないということにショックを受けていた。
保育室が近所に移転してきたのはそのころである。
私は仕事が終わるとすぐに帰宅するようにしていた。土日も用事を入れないようにしていたが、業務上どうしても出ないといけない時はある。そういう時、妻はじゅんを長時間ひとりでみることに大きな負担感を覚えていた。かといって、土日にじゅんを保育室に預けるのはためらっていた。「月曜から金曜まで保育園でがんばっているじゅんくんを、土日も預けるなんてかわいそう」と。
子どものために親はすべての時間と労力を差し出すべき、という考えは依然として強い。でも、親の方が無理をしてダウンしてしまったら元も子もない。世間からの、そして親の心の中にもある「子育て根性論」からは、距離をとったほうがいい。そう考えた私は妻に話した。
「土日であっても、しんどいときは、じゅんくんを保育室に預けよう」
「無理はしない。頼れるものには頼る。それが自分のためだし、じゅんくんのためにもなると思うよ」
妻はすぐに「うん」とはいわなかったが、しばらく考えた末にぽつりと「そうしてみる」といった。私はほっとした。
事前に3人で見学させてもらった。部屋は保育園の教室と同じくらいの広さがあり、絵本やおもちゃも充実していた。その日は4人のばぁばが子どもたちをみていた。ばぁばのうちひとりは保育資格を持っているとのこと。妻も自分の目で見ると安心したようだった。
じゅんの1回目の保育室行きは、私も家にいる土曜日にした。慣らし保育みたいな感じで8時半から11時半までの3時間の保育をお願いした。妻に連れられたじゅんは嫌がることもなく家を出て、妻が帰る時も普通にバイバイと手を振ったようだ。3時間はあっという間で、すぐにお迎えの11時半になった。妻とふたりで迎えに行くと、ほかに数人の子どもがいた中で、じゅんはおもちゃで遊んでいた。3人で家に帰りながら、じゅんに「どうだった?」と聞くと「たのちかった」とこたえた。それを聞いて、妻も私もさらに安心した。
2週間後にも、同じように3時間の保育をお願いした。その次は、午前9時から午後2時までの保育をお願いし、お弁当を持たせた。それもまったく問題なかった。それから月に1~2回くらいの頻度で利用した。その後、妻の体調を心配して、大阪に住む親戚がじゅんの世話と妻の話し相手に来てくれるようになったこともあり、月に1回9時から夕方5時まで預ける程度に落ち着いた。
この月に1回の保育室利用は、妻にとって貴重な自由時間となった。いつかやろうと思っていたことを片づける。気になっていた所を掃除する。ゆっくりお茶を飲む。ひさしぶりに本を開く。
精神科医の宮地尚子は、子育て中の親自身がケアされる必要があることを、次のような比喩によって述べる。
飛行機に乗ると、緊急対応用のビデオが流される。「酸素マスクが降りてきたら、たとえ子ども連れであっても、まず自分が落ち着いてしっかりマスクをつけて、それからお子さんにつけてあげましょう」という指示が、その中に必ず入っている。
私はそのビデオを見るたびに、「これって子育て全般にも言える」としみじみ納得し、そして考え込んでしまう。納得だけではなく考え込んでしまうのは、世の中に広まっている子育て指導が子どもに酸素マスクをつけることばかり強調し、母親が酸素マスクを先につけたりしたら自己中心的と批判するようなものが多いからだ。それどころか、母親にも酸素マスクが必要なことが忘れられていて、母親のためのマスクなんて用意されていないことも多いと思うからだ。(『ははがうまれる』福音館書店、2016年)
「自己犠牲」を求められるのは常に母親だけである。その自己犠牲は美談とされがちだが、そうしてはいけない。する方にとっても、される方にとっても、「犠牲」はよくない。
一方、父親は子育てにおいて、少し何かするだけでまわりからすぐほめられる。ハードルが低い。というか、母親にとってはハードルでさえないことをやっているだけである。そのことに対して、私も含めて男性は無自覚な場合が多い。
保育室の利用は、「人に頼っていいんだ」と妻が思えるようになるきっかけをつくった。同僚に体調不良のことを伝えたり、無理しないとできないことは、最初から「できない」というようにした。「今、緊急事態だから酸素マスクをつけます」と宣言したのである。そのかいあってか、妻の体調は少しずつ、ほんとうに少しずつではあったが、回復していった。いつしか保育室を利用することもなくなった。
妻の体調不良は私にとって痛恨の極みである。それまで家事育児を相応にしてきたつもりだったが、もっとやれることはなかっただろうかと悔やむ。
今でも、妻は、時折、「じゅんくんの一番かわいい時に全然笑えなかったのが悲しい。じゅんくんに申し訳ない」という。私は妻に対して申し訳ない気持ちでそれを聞いている。