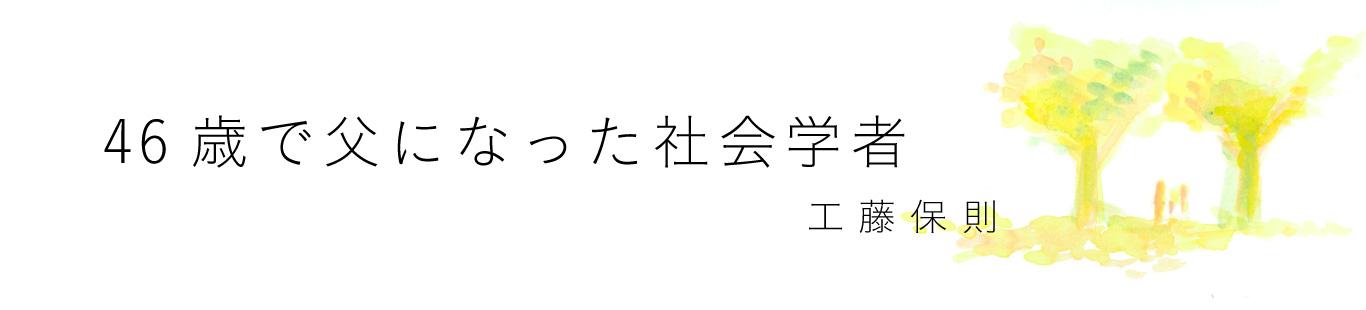第13回
物語
2019.11.08更新
わが家にはかなりの数の絵本がある。息子のじゅんが生後6カ月くらいになった時から購入し始め、今ではその収納に頭を悩ませるほどだ。数えてみたら、238冊あった。
といっても、乳児だったじゅんがすんなり絵本になじんだわけではない。最初は読んでいるのがむなしくなるほど、まったく聞いてくれなかった。数ページをまとめてめくったり、なめたりかんだり、えっちらおっちら運んだりするだけだった。絵本は、ただの「もの」だった。
1歳半を過ぎた頃、ようやく読み聞かせらしきことができるようになった。それはストーリーのない絵本から始まった。『ゆめ にこにこ』、『やさい だいすき』、『むにゃむにゃ きゃっきゃっ』など、単純な言葉とシンプルな絵からなるイラストレーターの柳原良平の作品は、じゅんのお気に入りだった。なかでも、『かおかお どんなかお』は、何度読んだかわからない。
かお
かおにめがふたつ
はなはひとつ
くちもひとつ
たのしいかお
かなしいかお
わらったかお
ないたかお
おこったかお
ねむったかお
たくましいかお
こまったかお
あまーいかお
からいかお
いたずらなかお
すましたかお
いいかお
おしまい さよならのかお(『かおかお どんなかお』柳原良平、こぐま社、1988年)
柳原作品に限らず、この頃にじゅんが好んだ絵本はごくごく単純な文章であるために、かえって、うまく読むのは難しい。私が読み聞かせをしていると、横で聞いていた妻から「棒読みやなぁ」という指摘をよく受けた。そうであっても、じゅんは私の膝の上で「うきゃうきゃ」とよく笑い、楽しんでくれた。
2歳くらいになると、図鑑に夢中になっていった。親戚のおじさんから「男の子はやっぱりこういうのが好きだろうから」と、『はたらくくるま デラックス』という図鑑をもらった。妻は「はたらくくるま」というジャンルがあることに驚いた。ここから図鑑が一大旋風を巻き起こすことになる。
図鑑は読み聞かせるというわけにはいかない。「サイレンカー」や「こうじのくるま」というページをひろげ、そこに載っている写真を指さしながらクルマの種類を読みあげる。
「パトカー」
「ショベルカー」
じゅんはそのころ、少ししゃべれるようになっていたので、たどたどしく、自分でもとなえる。
「パトカ」
「ショベルカ」
その1カ月後には、写真を指さしながら高度な(?)クルマの種類を言うようになっていった。
「ゆあつショベル」
「ロードローラー」
「カーキャリアー」
「ロードスイーパー」
その後、じゅんは「乗り物」というジャンルを開拓していった。『最新 しんかんせん とっきゅう デラックス115』、『ぜんぶわかる のりもの ものしりずかん』といった図鑑を食い入るように見ながら、列車名を次々に覚えていった。「のぞみ」「はやぶさ」といった代表的な新幹線はもちろん、JRの特急「サンダーバード」「くろしお」、私鉄の特急「ラピート」「アーバンライナー」などである。だが、「なりたエクスプレス」だけは、発音しにくいのか、もごもごと口を動かした後、「むじゅかしなぁ」と言っていた。
図鑑にハマっている頃は、妻が「じゅんくん、絵本、読もうか。好きなの、持って来て」と声をかけると、いっぱいの笑顔で「乗り物図鑑」を持って妻の膝に座っていた。「ママは絵本が読みたいんだけどなぁ」と言っても、そんなことはおかまいなし。妻はしぶしぶ図鑑をひろげ、
「屈折はしご車」
「アスファルトフィニッシャー」
「スーパービュー踊り子」
「指宿のたまて箱」
と読みあげた。次第に、妻も乗り物に詳しくなっていった。
その頃から、図鑑に負けず劣らず、カードにも夢中になった。思いたって、ある時、乗り物カードを与えたのだが、案の定というか、じゅんはその乗り物カードにはまった。新しい乗り物の名前をすぐに覚えて、カルタみたいにして遊ぶようになった。そこからカードの一大旋風が巻き起こる。食べ物カード、動物カード、あいうえおカードなどが次々と増えていき・・・、最終的に、12種類、540枚ものカードを集めるに至った。
3歳を過ぎた頃になると、図鑑やカードへの熱中は一段落した。それにかわって、ストーリーのある絵本に興味を示すようになった。
じゅんが気に入っていたのは『ばすくん』(みゆきりか作・なかやみわ絵、小学館、2007年)という絵本である。新型バスの導入によって旧型バス(ばすくん)は都会の路線をお払い箱になり、山の路線を走ることになる。山道でタイヤが外れて使い物にならなくなると、そのままばすくんは山奥に廃棄されてしまう。ひとりぼっちで寂しくしていたのだが、台風の夜、雨風をしのぎにきたタヌキを中に入れて休ませてあげる。その冬、大雪の日にタヌキに連れられて多くの動物がやってきて、ばすくんの中で冬を越させてほしいと頼む。もちろんばすくんはそれを快く引き受ける。冬が去り春になっても、動物たちはばすくんと仲良く暮らした、という話である。
もうひとつ。『しょうぼうじどうしゃ じぷた』(渡辺茂男作・山本忠敬絵、福音館書店)もずいぶん気に入っていた。はたらくくるま好きは通底している。
ある町の消防署に置かれている、はしご車ののっぽくん、高圧車のぱんぷくん、救急車のいちもくさんは、三台そろって子どもたちに人気がある。その傍らには、古いジープを改良した小さな消防車じぷたが置かれているのだが、じぷたは自分はちっぽけであまり役に立たないと思っている。ある日、隣村の警察から山小屋が火事との連絡が入った。はしご車はとどかない、高圧車は道が狭くて通れない、けが人はいないから救急車はまだ必要ない。じぷたの出番となり、かれの活躍で山火事にならずにすむ。その日から、町の子どもたちもじぷたのことを自慢するようになった、という話である。
これは、1963年月刊「こどものとも」(冊子体)として発行された後、1966年「こどものとも傑作集」として単行本になった絵本である。手元にあるのは2015年発行の第141刷のものである。
今の感覚からすれば、絵はずいぶん古いタッチであり、登場するクルマの形も旧式だ。話もどうといったことはない(ように思われる)。が、それは、おとなになった私の感覚であろう。絵本を見渡してみると、小さいものや弱いものが活躍し、まわりから評価されるというお話がけっこうある。小さなじゅんもじぷたに自らを重ね、その物語に胸を躍らせ、レトロな絵にひきつけられたのであろう。
東京子ども図書館の設立者であり理事長でもある松岡享子は『子どもと本』において、こんなことを述べている。
子どもの本の場合、新しい本――出版されたばかりの本――を追いかける必要はまったくありません。子ども自体が"新しい"のです。たとえ百年前に出版された本であっても、その子が初めて出会えば、それは、その子にとって"新しい本"なのですから。そして、読みつがれてきたという点からいえば、古ければ古いほど、大勢の子どもたちのテストに耐えてきた"つわもの"といえるのです(松岡2015:157)。
子どもにとってこの世界は、初めて出会うものばかり、知らないことばかりである。くりかえし、見たり、聞いたりすることで、世界のかけらが子どもの中でつながっていく。古い絵本は、長年、その助けをしてきたのだ。
図鑑やカードが「もの」を、絵本が「ものがたり」を表しているとすると、ものをとらえる時期があった後で、ものがたりを理解する時期に移行していったといえる。「ものがたり」を理解するためには、その前に「もの」をとらえる必要がある。じゅんの図鑑・カード熱がそれを教えてくれた。
「ものがたり」を理解し始めた頃から、じゅんの世界はぐぐーんと広がった。
「もの」と「もの」の「間」や「関係」は網の目のようにつながっており、 この世はたくさんの「物語」に満ちている。片言しゃべりの時もおしゃべりだったじゅんは、この頃から、起きている間はずっとしゃべっているくらいのおしゃべりになった。世界を発見していくのが楽しくてしかたがないのだろう。
子どもにとって、世界は常に新しい。子どもの驚きと喜びは、おとなたちの見慣れた世界も新しくしてくれる。
*参考文献
松岡亨子『子どもと本』岩波新書、2015年