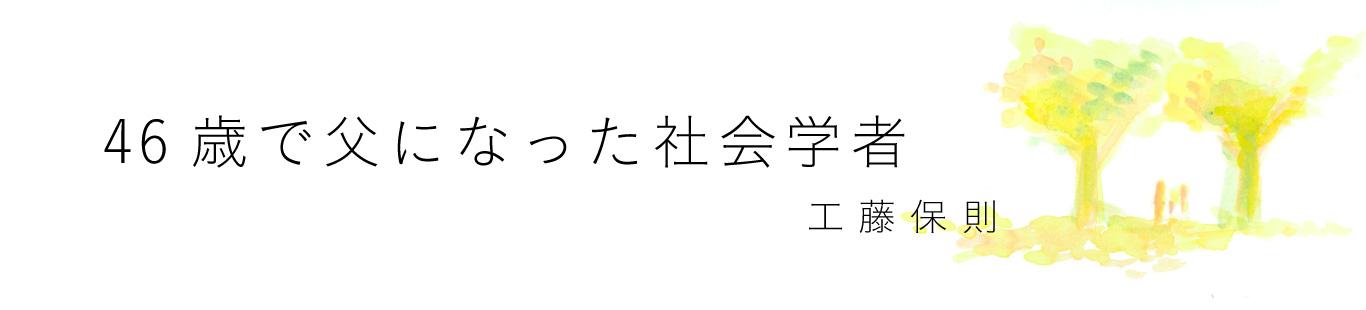第16回
甘物
2020.02.04更新
息子のじゅんは3歳の誕生日にはじめてケーキを食べた。
保育園のお友だち、とくにきょうだいのいるお友だちは、甘いものを小さい時からそれなりに食べていたようだ。しかし、3歳の誕生日まではじゅんに甘いものを与えないと、妻は固く決意していた。
「小さい時に、一度、甘さを覚えてしまうと、執着してしまうんやって」
「そら、そうやろね。甘いものはおいしいもん」
「だから歯みがきがきちっとできないうちは、甘いものを食べさせないのがいいと思うねん」
「なるほど。ごもっとも」
ついにその日がやってきた。
じゅんが赤ちゃんだった頃に開店した小さなケーキ屋さんが近所にある。30代とおぼしき女性がひとりで切り盛りしているお店で、素朴な味のケーキや焼き菓子を売っている。なんとなく、はじめての甘物はこのお店のものにしたいと思った。私は夕方に、ショートケーキを3つ買って帰った。
いつもより少しだけ豪華な晩ご飯の後、冷蔵庫からケーキを出した。妻がひとつのショートケーキに3本のろうそくをたて、それに火をつけたところで、私は部屋の電気を消した。
私と妻は、「ハッピーバースデー・トゥー・ユー」の歌詞を少し変えて歌った。
「ハッピーバースデー、じゅんくん。
ハッピーバースデー、じゅんくん。
ハッピーバースデー、ディア、じゅんくーん。
ハッピーバースデー、じゅんくーーん」
毎月ある保育園のお誕生会で歌って知っているのか、じゅんも声を合わせて一緒に歌った。
歌い終わった後、じゅんにろうそくの火の消し方を教えようと、「こういうふうに、ふーして」といいながら、妻がろうそくに息をふきかけた。その途端、ろうそくの火が消えてしまった。あっけにとられる私。「あっ、ごめん。消してしまった」――慌てた妻の声。
じゅんは私たちの様子がおもしろいのか、楽しそうにケタケタと声をあげて笑いだした。それにつられて、私も妻も笑いがとまらなくなった。
ひとしきり笑った後、ろうそくに火をつけなおした。もう一度、3人で「ハッピーバースデー、じゅんくん」と歌い、じゅんがふーと息をふきかけた。たった3本のろうそくだが、じゅんの息では1回では消えなかった。2回、3回とつづけてふーをして、やっと火が消えた。ろうそくの火をふき消すことが楽しくなったじゅんが、「もういっかい」とリクエストするので、結局3回も、火をつけてふーをくりかえした。最後は、ひと息で消すことができた。
それから部屋の明かりをつけ、ケーキを食べ始めた。
「はじめてのケーキ」に大喜びしたじゅんだが、ケーキそのものには少し口をつけただけであまり食べなかった。甘いものを食べ慣れてないので、甘物に対する執着があまりない様子だった。けれども、「ふー」への執着はあるようで、「また、ふーしような。また、ふーしような」と繰り返した。
「1年後、じゅんくんが4歳になった時、またふーしようね。その時は、ママ、もうふーしないからね(笑)」
「来年は、ろうそく、4つ。ふーで全部消せるかなぁ」
「できるっ!」
誕生日は年中行事のひとつである。お正月などの伝統的な年中行事がそもそも神と人を結ぶ契機であったとすれば、子どもの誕生日のような人生の節目の年中行事は家族それぞれの存在を確認する契機である。
社会心理学者の井上忠司は、家庭の年中行事に関する本の中でこう述べている。
思えば、人はだれしもわが子をさずかってはじめて、母親であることができ、父親であることができる。つまり、親であることは、実子であれ養子であれ、わが子との関係において、はじめて成り立ちうるのである。しかしそれだけでは、かならずしも親になることはできない。家庭におけるわが子とのふだんの相互作用の過程で、"親らしく"なっていくのである。
人生の節目を祝い、感謝しあう年中行事。――それは、家庭内の人間関係のありようを、あらためて考えさせてくれる機会である。言いかえれば、発達の段階ごとに「である」から「になる」へ、間柄を結びなおす儀礼にほかならない。(『現代家庭の年中行事』、講談社現代新書、1993年)
親にとって子どもの誕生日は自分が育てた子どもの成長を確認する日であり、また、とくに母親にとっては、自分が命懸けで子どもを産んだことを思い出す日であろう。
「誕生日が来ると年をとるから嫌やなぁって思っててん。でも、誕生日って、お母さんががんばった日なんやな。もちろん、赤ちゃんも。ふたりでがんばった日なんよ」
じゅんを産んだあと、妻が語った言葉だ。
じゅんが甘いものにそれほど執着しないとはいえ、虫歯にならないように気をつけなければならないことは変わらない。
じゅんの歯みがきをはじめたのは、歯がはえはじめた1歳になったころだった。じゅんの歯みがきは、私たちにとって毎日の大仕事であった。「格闘」と言っても過言ではない。
妻がじゅんをあおむけに寝かせ、頭の後ろに座って、両足をじゅんの両腕の上に置く。じゅんが手をバタバタできないように固定するのだ。私はじゅんの足を押さえる。ふたりがかりで身動きが取れないようにしてから、妻が手に持った歯ブラシをじゅんの口にもっていく。
「お口、あー、して」
なかなか口をあけてくれない。
「お口、あー、してください」
じゅんは口をあけないどころか、逆に歯を食いしばっている。
「それでは、みがけません」
根くらべである。じゅんは歯ブラシをかんだり、体をよじらせたり、あげくのはてには逃走したりする。
そうこうしているうちに、じゅんは次第に観念して、少しだけ口を開ける。その瞬間、妻はさっと歯ブラシをじゅんの口の中に入れ、素早く奥歯をみがく。
「今度は、いー、してください」
前歯をみがけるまで、また同じことが繰り返される。
なかなかいうことを聞いてくれない時は、「あっ、お口の中にバイキンマンがいたよ」「ドキンちゃんもいたよ」「キャーッ、じゅんくんの歯をガリガリしようとしているよ」と脅かす。バイキンマンに、どれだけ助けられたことだろう。
歯みがきをした後は、口をゆすぐ代わりにお水を飲ませる。
妻の努力のかいあってか、保育園での歯科検診では問題なしだった。また虫歯予防のためのフッ素塗布ではじめて歯医者さんに行った時も、「問題ありません」と言ってもらえた。毎日の「格闘」の成果だろうか、診察台の上で口を上手にあけることができて、それを先生から褒められもした。
子どもの歯をみがくというのは、とても面倒なことである。子どもにとっては、意味も分からず、口の中に歯ブラシを入れられ、ごしごしされるのだから、嫌なのは当然である。子どもが嫌がることをするのは、親も気が進まない。
じゅんがはじめてケーキを口にした3歳の誕生日の夜、妻はいつもより念入りにじゅんの歯をみがいた。
子どもの歯を気にかける。子どもが嫌がっても歯をみがく――とるにたらない日常のひとコマだ。歯みがきに限らず、私たちはこのような些細なことを、日々、無数に繰り返している。そうしていくうちに、知らず知らず、子どものあしらい方が板についてくる。私たちは劇的に親になるのではない。こまごましたルーティンの営みと小さな努力の積み重ねによって、だんだんと親になっていく。
参考文献
『現代家庭の年中行事』井上忠司、講談社現代新書、1993年