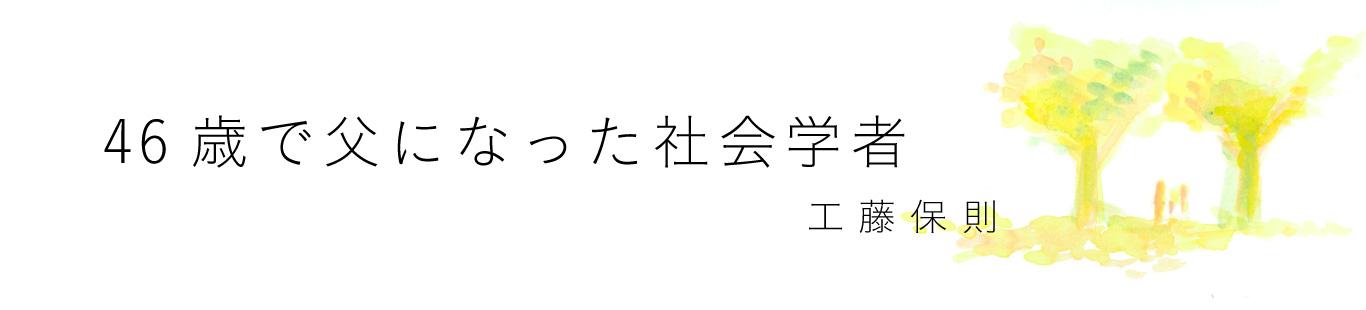第19回
時間
2020.05.08更新
息子のじゅんが生まれてすぐ、1枚の写真を撮った。分娩台で横になっている妻がじゅんを抱きかかえている写真である。妻は泣いている。じゅんは妻の胸にしがみついている。じゅんがこの世界に生まれてきて一番はじめにされたことは、抱擁なのだ。
助産師さんから「生まれましたよ」といわれた時、私はどう表現していいのかわからないくらいにうれしかった。どんな言葉を使っても足りないように思えた。
「ありがとうございます」
ただ、そう繰り返すばかりだった。
ほんの少し落ち着いてから、ズボンのポケットにカメラを入れていたことを思い出し、急いでシャッターを押した。それが、先の写真だ。私にとってかけがえのない1枚である。
じゅんが新生児用のベッドに移されてから、また1枚、写真を撮った。そこには、試合後のボクサーのような青紫の顔をして、こぶしを胸の上に置いてベッドに横たわるじゅんが写っている。その顔は「ぼく、へとへとですわぁ」といっているように見える。安産だったとはいえ、妻のおなかの中から出てくるということは、じゅんにとって人生最初のとてつもない試練だったことがうかがえる。
数時間後、病室に戻ってから撮ったじゅんは、赤ちゃんらしい桃色の顔をしており、帽子をかぶせてもらいおくるみにくるまれて、気持ちよさそうに眠っている。その姿もカメラに収めた。
その日の私は、ふんわりとした空気の中にゆらゆらと漂っている感じのまま、一日が過ぎていった。自分の行動はあまり覚えていない。しかし、アルバムの写真を見ると、頭の中にある記憶のスイッチが入る。
これまでどれだけ写真を撮ったかわからない。今では、大型のアルバム10冊分の写真がある。私は時おりそれを見返し、これまでのじゅんとの時間をかみしめる。
ある時から、そこにビデオが加わるようになった。私たち夫婦はデジタル音痴で、スマホを持ち始めたのも数年前だし、動画撮影機能も使わないできた。そういう私たちがビデオを買おうと思ったのは、徳島の実家で父と暮らす祖父のからだのことが気になったからである。
明治44年生まれの祖父は、若くして父親を亡くした後は、農業によって家族を養ってきた。じゅんが生まれた時は102歳だった。祖父はもともとからだが大きく、体力もあったので、100歳を超えてもずっと元気でいてくれるような気がしていた。
ところが、ある帰省の際、私は祖父のからだのことが、ほんの少し気になった。特別な変化があったわけではない。けれども、何かを感じた。そして、「じゅんくんとじいちゃんが一緒にいるところを映像で残しておきたい」と思うようになった。
2015年6月末、じゅんが2歳になる少し前に――それは祖父が104歳になる少し前でもある――、ビデオを買って、実家に帰った。
「はい。OKです。『録画』になってます」
私の声からその映像は始まっている。じゅんも祖父も、ビデオカメラをまったく意識せずにいる。妻がじゅんの横で、祖父に向かって「こんにちは」という。じゅんは腰をかがめる。祖父はじゅんのことをじっと見つめている。
「じゅんくんのお鼻は?」
そう尋ねた妻の鼻をさわるじゅん。
「じゅんくんのお耳は?」
妻の耳をさわるじゅん。
その様子に、にっこりする祖父。
そのころのじゅんはシールが大ブームだった。当然のようにシールブックを持って帰省しており、椅子に座る祖父の手のひらに次から次へとシールをはっていく。祖父は、はられるがままにしている。
「じゅんちゃん、ありがとう」
祖父の声はやや曇っているが、きちんと聞き取れる。
今度は、じゅんは「シール、返して」というように、祖父の手からシールをはがしていく。
「じゅんちゃん、いそがしいのー(笑)」
じゅんはシールブックを持って、部屋の中をちょこまか歩きまわり、何かの拍子にころんだ。
「あぶないのー(笑)」
じゅんはひとりで立ち上がって、また部屋の中を歩きまわる。
「京都から来たというのに、いっちょもつかれとらん。元気やなー」
祖父はずっとうれしそうにしている。表情はそれほど変わっていなかったが、こころでは大きく笑っていることが分かる。それがじゅんにも伝わるのか、時折、恥ずかしそうにしながら、小さな声で「じーたん」といっている。
温かく包みこむような祖父のまなざしの先で、じゅんは無邪気に遊んでいる。
11月に帰省した時は、じゅんがいるにもかかわらず、ほとんどの時間、祖父は車椅子に座ったまま寝ていた。その姿も撮っている。その翌日、急に体調を崩し、入院することになる。
入院した後、3人で見舞いに行った時もビデオカメラを携えていた。12月は、今から思えば、祖父はまだ元気だった。映像の中の祖父は、電動ベッドの背中部分をあげて上半身を起こした状態でじゅんのことを見つめている。ベッドの脇でミニカーを走らせるじゅんの姿も一緒に映っている。
1月に病院に行った時は、祖父はあまり話せなくなっていた。けれども、じゅんの肩に手をやり、何かを話そうとしている姿が映っている。言葉はなくても、動きはなくても、やはりそこには写真ではとらえきれない時のながれがあり、淡々とした映像であるが見入ってしまう。
私がひとりで病院に行った時や、2月の祖父の最期の様子は撮っていない。映像として残したかったのは、じゅんと祖父のふたりの時間だった。まだ、ものごころのつかないじゅんは、おそらく、曾祖父との時間を忘れてしまうだろう。だから、ふたりの時間が確かにあったということを映像のかたちでじゅんに残してあげたかった。
じゅんはたまに「ビデオ、見たい」といって、自分が映っている映像を見たがる。運動会など保育園の行事や家族でのお出かけの映像は嬌声をあげながら見ているが、曾祖父と映っているものは静かにじっと見ている。
「大きいじいちゃん、お話、してるなぁ」
「大きいじいちゃん、じゅんくん、見てるなぁ」
「大きいじいちゃん、ねんね、してるなぁ」
などと言い、見終わると
「大きいじいちゃん、お空、いったなぁ」
とつぶやく。
じゅんなりに感じることがあるのだろう。
哲学者の鷲田清一は「『ふれあい』の意味」と題されたエッセイの中でこう述べる。
他に向かって身を開くことができるためには、まずいちど包まれなければならない。ここにひとつの真実がある。(『おとなの背中』角川学芸出版、2013年)
じゅんは生まれてきてすぐに母に包まれ、お空に行く準備を始めた大きいじいちゃんにも包まれた。その証である写真やビデオ映像を、これから先も、折につけ、じゅんは見返すだろう。
妻とともに写る、じゅんの人生最初の写真。祖父の人生最後の8カ月を彩るじゅんのビデオ映像。どちらも、いのちは他者の温もりによって満たされ輝くことに気づかせてくれる。そして、「今、この時間」が、それぞれにとってかけがえのないものであることも。