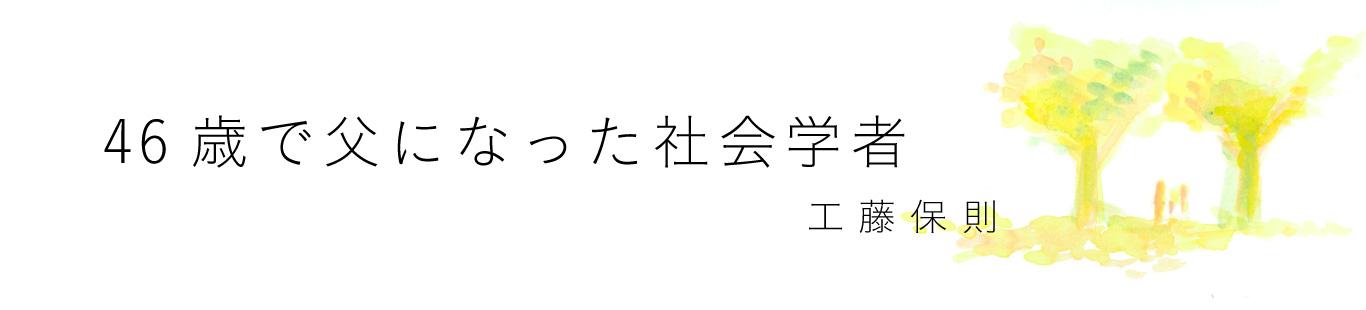第21回
別れ
2020.07.05更新
祖父にとっては、結婚の遅かった孫(つまり、私)の子どもであるじゅんは、何かしら特別な存在のようだった。はじめてじゅんを連れて実家に帰ったのは2013年11月のことである。その時、じゅんは生後4カ月だった。祖父は102歳。頭はまだしっかりしており、からだのほうも自家製の竹の杖を両手に持って歩けるくらいしっかりしていた。
常々、「目がよー見えん」とか「耳がよー聞こえん」とかいっていた祖父だが、じゅんの顔を覗き込むなり「えー顔しとる」といい、じゅんの泣き声を聞くなり「元気な声じゃなぁ」と喜んだ。私は「じいちゃん、はっきり見えとんと違うの」「はっきり聞こえとんと違うの」と冗談をいいながらも、赤ん坊の持っている力に心底驚いた。
「じいちゃん、じゅんくん、抱いてみる?」
「あぶのー、ないか」
「下で支えておくし」
「ほうか。ほれじゃあ、抱かせてもらおーか」
椅子に座っている祖父が両手を前にしてじゅんを抱える体勢をとった。そこにじゅんをそっと置く。じゅんは祖父の腕の中にすっぽりとおさまった。
「重いのー」
祖父は顔をほころばせた。
「ゆーことなし」
はっきりした大きな声でそういうと、私と妻のほうに向き直った。
「えー子に育ててください」
祖父は頭を下げた。
その後、2~3カ月に1度くらいのペースでじゅんを連れていなかに帰った。それを、祖父と父は楽しみに待っていた。祖父は玄関から入ってすぐの畳の部屋でいつもの椅子に腰かけており、私たちはそのまわりに座ってくつろいだ。じゅんがハイハイをしはじめ、やがてよちよち歩きができるようになると、その部屋と横の仏壇のある部屋がじゅんの遊び場になった。
2015年6月。2歳手前になったじゅんがトコトコと祖父に近寄ると、祖父はしみじみと「目がうすーになっとるけん、よー見えんけんど、じゅんちゃんは、えー顔じゃ」といった。
部屋の中でさんざん動きまわり、やがて遊びつかれたじゅんは、祖父の前で大の字になって昼寝をはじめた。祖父はじゅんのことをただじっと見つめている。そのうち、妻も昼寝をはじめた。祖父は、ふたりを見つめ続ける。
「もー、ゆーことなっしゃ」
小さくつぶやいた。
9月末に帰省した際、祖父は、転ぶと危ないからと車椅子に座っていた。それ以外は特に変化はなく、いつものように、飽きることなくじゅんのことを見ていた。その次、11月末に帰った時は、祖父は、前日、ほとんど寝ていなかったようで、じゅんがいるにもかかわらず、車椅子に座ったままずっとうとうとしていた。私は、祖父のからだのことが気にかかった。案の定というか、その翌日、体調を崩し、病院に入院した。
入院してすぐ、12月のはじめに、私はひとりで見舞いに行った。祖父の顔色は思ったよりよかった。
「この2年はえーことばっかりやったけん、いつ死んでもえーわ」
「じゅんちゃんはえー顔しとる。(頭を指して)ここもえーわ(にやりと笑う)」
「じゅんちゃんのことよろしゅーにな」
「じゅんちゃんはほんまえー子や。あっちにいったら、あーちゃん(私の母=祖父の娘の愛称)にそーゆーとく」
「むこーにいったら、上からみんなのこと見とるけんな。心配ないけんな」
祖父の言葉ははっきりと聞き取れた。ほとんどがじゅんのことだった。
12月中旬。妻とじゅんとともに3人で見舞いに行った。病室に入った時、祖父の顔のピントが合ってないように感じたが、じゅんがいることがわかるとすぐにピントが合い、にっこりした。
後から思うと、この時の祖父はまだ元気だった。電動ベッドの背中部分をあげて上半身を起こした状態で、ずっとじゅんのほうを見ていた。
じゅんは、徳島駅のキヨスクで買ったアンパンマン列車のミニカーを、うれしそうに祖父に見せている。
「じーたん。アンパンマンでんしゃ」
「あー」
祖父がうなずく。何かしゃべりたがっているが、声にする体力がないようで、言葉にはならない。
じゅんは、片言ながら、ずっと何かをしゃべっている。
「メロンパン、おいしかったなぁ。また、かおな」
その日の朝食は高速バスの中でパンを食べた。そのことをいっているのだ。
「これ、えきで、かったなぁ」
アンパンマン列車のミニカーをまた祖父に見せた。
「よーしゃべるな(笑)」
祖父の言葉が聞き取れた。
その後、祖父はまた黙ったままじゅんを見つめている。しばらくたって、
「もーしぶん・・・」
と祖父。
「もうしぶん・・・ない?」
と私。
祖父がうなずく。
「ないのっ」
じゅんがうれしそうに続く。
祖父はまたうなずく。
別れる間際、祖父は前の帰省の時と同じことをいった。
「じゅんちゃんは・・・、えー子や。あっちに、いったら、あーちゃんに、そーゆーとく」
「(妻に向かって)じゅんちゃんのこと、よろしゅう、お願いします」
12月末に転院し、その病院に3人で見舞いにいった。この時も、祖父は何かをいおうとするのだが、言葉がうまく出てこなかった。やがて、少しずつ、言葉らしきものになっていった。それは聞き取りにくくはあったが、だいたいのことは理解できた。
「じゅんちゃんのこと・・・、ありがとうございます」
「じゅんちゃんのこと・・・、お願いします」
妻に向かって、繰り返しそういっていた。
最期に3人で見舞いに行ったのは1月末だった。祖父はほとんど何も話せなくなっていた。けれども、じゅんの肩に手をやり何かを話そうとしていた。
じゅんが生まれてから、祖父はずっとじゅんのことを想っていた。
2月20日のお昼前に、病院にいる父から電話があった。父は、祖父が入院した日からずっと病室に泊まり込んでいた。
「今日ということはないと思うけんど・・・、この2~3日かもしれへん」
私はとるものもとりあえず、病院へむかった。バッグに喪服を入れるのを少しためらったが、グッと押し込んだ。
途中、いつもの高速バスの車窓の風景が、何か違って見えた。祖父のことを思いながらその景色をぼんやりと見ていた。
病院には夕方に着いた。病室に飛び込み、祖父の顔を見た。その瞬間、「じいちゃん、がんばってくれているなぁ。でも、いつ最期になってもおかしくないなぁ」と感じた。
家に電話をかけ、私が家にいない事情をじゅんに説明した。そして、祖父の耳元にスマホを持っていき、じゅんの声を聞かせた。
「じーーーたーーーん」
祖父の閉じている目がほんの少し動いたのがわかった。
その日から私も父とともに病室に泊まり込んだ。
21日と22日は祖父に大きな変化はなかった。しかし、少しずつ、祖父の精気がなくなっていっているのがわかった。
23日。少しうとうとしただけで朝を迎えた。祖父の様子が、明らかに違う。息がずいぶんあれている。「今日なんだ」と思わないわけにはいかなかった。
すぐに妻に電話をかけ「じいちゃん、今日だと思う」と伝えた。妻は急いで支度をして、じゅんを連れてこっちへ向かった。慌てていた妻は高速バスにバッグを忘れ、JRの列車にマフラーを忘れ、12時少し前に病院に到着した。その時、祖父は酸素マスクをつけ、朝よりもさらに息があらくなっていた。
「じーーーたーーーん」
じゅんが大きな声で呼びかけた。祖父の顔が和らぎ、頬に涙がつたった。
「じゅんくんが来てくれたで。よかったな」
父がそういいながら、祖父の頭をなでた。
祖父の最期がもうそこまできていることを、みな、わかっていた。
「はーーっ、はーーっ、はーーっ」
息がさらにあらくなっていった。じゅんは私の膝の上でじっと祖父を見ていた。
15時25分。祖父、永眠。
入院中ずっと家に帰りたがっていた祖父を連れて帰り、仏壇のある畳の部屋に敷いた布団に寝かせた。じゅんは状況がいまひとつわからないようで、祖父が横になっている布団の傍らできょとんとしていた。私も、なんだか妙な感覚だった。死んだ祖父がそこにいるのだが、「じいちゃんが死んだ」という感じはあまりなく、「じいちゃん。家に帰ってこれて、よかったなぁ。家でゆっくり休めて、よかったなぁ」という安堵の気持ちが勝っていた。
翌24日。前日同様に、じゅんは横になっている祖父のまわりをうろうろしていた。祖父の顔が笑っているように見える。妻にじゅんをみてもらいながら、私と父はお通夜(夜伽)と告別式の準備をした。お通夜は、この日に自宅で行った。それに先立って、夕方から近所の「ねえさん」たち(おもに70代以上の方たち)が手伝いに来てくれ、いろいろと準備をしてくれた。
25日の11時から町の葬儀場で告別式を行った。1時間ほどの式の最中、私の膝に座っていたじゅんは「じーたん」と何度も何度も言っていた。大きいじいちゃんがいなくなったことを、この段階で少しずつ理解し始めたようだった。
火葬場での最後の対面では、じゅんは大きな声で「じーたーん」と呼びかけた。父がじゅんの頭をなでながら「大きいじいちゃん、喜んどるよ」と泣き笑いの声で言った。その場にいたみんなが泣き笑いになった。
焼かれて骨になった祖父に向かって皆で手をあわせた。じゅんも神妙な顔で手をあわせた。お骨をひろい壺に入れてお墓に向かう際には、じゅんに骨壺を入れた桐の箱をもたせた。祖父は喜んでくれただろう。
じゅんは、この日まで、何回、祖父に会っただろう。ごろんごろん寝返りができるようになり、つかまり立ちができるようになり、ヨチヨチ歩けるようになり、トコトコ歩けるようになり、話ができるようになり。祖父は、会うたびにグングン成長していくじゅんに目をみはり、その度に「ゆーことなし」と喜んだ。祖父の104年の人生において、じゅんと一緒にいることができた2年半は、それこそ「ゆーことなし」だったろう。
祖父の長い人生にはさまざまなことがあった。家族の多くが自分より先に(それもずいぶん先に)他界したので、人の何倍も悲しい思いをしたはずである。そういう祖父にとって、じゅんは未来に続いていく希望そのものではなかったか。
人生は「出会いと別れ」である。出会ったなら、必ず別れなければならない。しかし、私たちはそのことを忘れがちである。いい出会いは人生を豊かにしてくれる。いい別れもまた、そうであろう。
祖父との別れは、じゅんにとって、人生最初の別れだった。その最期に立ち会えたことは、これから先、大きな意味を持つように思う。永遠の別れではあったが、祖父はじゅんのこころの中にずっと残っていくだろう。
じゅんのおかげで、私も祖父といい別れ方ができた。