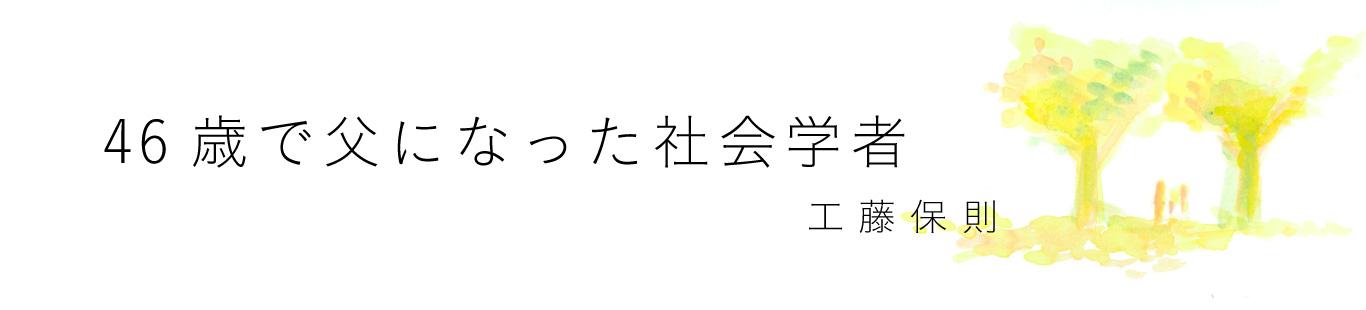第22回
先祖
2020.08.06更新
徳島の私の実家に帰った時、息子のじゅんが最初にすることは決まっている。玄関から続いている部屋をかけ抜け、その奥の部屋に置いてある仏壇の前まで走っていくのだ。ふたつの部屋はふすまで仕切られているのだが、いつもそのふすまはあけたままになっている。
チンチンチーーン
じゅんは大きな音を立てて鈴を鳴らし、立ったまま手をあわせる。
「むにゃむにゃ」
口に出してそういう。
じゅんが生まれる前から、私と妻は実家に帰ると、まず仏壇に手をあわせていた。じゅんが生まれてからは、私がじゅんをだっこして、いっしょに手をあわせた。はいはいができるようになって、じゅんは仏壇まで自力でたどりつけるようになった。そして、よちよち歩きができるようになった頃には、私たちよりも先にじゅんが仏壇の前まで行くようになった。仏壇の脇には、ずっと前から私の母の遺影が置かれている。
祖父が元気だった時は、じゅんが仏壇の前で「むにゃむにゃ」といっている姿を、椅子に座って、目を細めて見ていた。
「じゅんちゃん、えらいのー」
「あーちゃん(私の母=祖父の娘の愛称)も、よろこんどるわ」
祖父が声をかけると、じゅんはふりかえり、にっこりする。そして、祖父の前で遊ぶのだった。その祖父も、今はもういない。口を大きく開いて笑っている祖父の遺影は、母の遺影と並んでいる。
「じいちゃん、じゅんくん、来たよ」
「じーたん」
「かあさん、じゅんくん、来たよ」
「ばーちゃん」
「じゃあ、じゅんくん、むにゃむにゃ、しよーか」
「むにゃむにゃ」
ひととおりに儀式がすむと、父が「はい、これ」といって、鈴の横手においてあるポチ袋をじゅんに手渡すのが恒例になっている。袋の中身はおこづかいなのだが、じゅんは意味がよくわからないので、そのまま妻に渡す。
「はい、どーじょ」
「お義父さん、いつもすいません。じゅんのものを買うのに使わせていただきます」
妻が父にそういうのも、もはや恒例である。
それから、じゅんは、ふたつの部屋を行ったり来たりして遊ぶ。祖父と母だけでなく、仏壇に位牌が入っている人たちがみなそれをあたたかく見守ってくれているような気がする。
妻はじゅんの写真やじゅんが描いた絵を私の実家によく送っている。父はメールもしないし、家にはパソコンもないので、「もの」で送っている。祖父が存命中は、ふたりで写真や絵をみた後、仏壇にあげていたようである。祖父が他界した後は、まず仏壇にあげて、その後で父が見ているようである。
「写真、ついたけんな。今、お仏壇にあげとるけん。明日にでも、見せてもらいます」
電話で父がそういうのを聞いて、妻は驚いていた。
「何でもお仏壇にあげるんやね」
「そうやね。子どもの時から、いただいたものは『まずお仏壇』やったなぁ。その習慣がずっと続いてるんやね」
「あの世とこの世の連絡口なんやね。お仏壇ってすごいなー」
妻にいわれるまで気がついていなかったが、仏壇はすごいのだ。
仏壇とお墓は、ある意味で、セットである。
私たちは帰省のたびに、父の運転する車に乗り、10分ほどかけてお墓のある山に向かう。車をとめてからかなり急な坂道を登るのだが、その最後は人ひとりがやっと通れるくらいの細い道になる。じゅんが妻のお腹の中にいた頃は、この細い道の脇に、父が竹を使って手すりを作っていたのだが、それはもう朽ちている。
今ではじゅんも道を覚えていて、ひとりで先に坂道をかけのぼる。
私が後を追いかけ、妻と父がそれに続く。
父は坂道の途中にある水道でバケツに水をいれる。
足元に気をつけながら細い道を上がったら、見晴らしのいい場所にお墓がふたつ並んでたっている。ひとつは家の代々のお墓で、もうひとつは母と祖父が入っているお墓である。
父は竿石に水をかけ、水鉢に水をそそぐ。線香に火をつけ、線香たてにたてると、私に封筒を手渡す。封筒にはお米が入っている。お米をひとつまみとり、線香たての手前におく。続いて妻が、そして私にだっこされたじゅんも同じことをする。家から持ってきた花を父がたてる。それらがおわると、みんなで手をあわせる。
「むにゃむにゃ」
じゅんはここでもそういう。
「大きいじいちゃん、よろこんどるわ。ばあちゃんも」
父も毎度そういう。
お墓からは私が生まれ育った町だけでなく、吉野川をはさんだ対岸の町まで見渡せる。私は「ここで生まれ育ったんだなぁ」と、毎回、しみじみ思う。
仏壇やお墓はイエのしがらみやめんどくささの象徴として扱われることが多い。私も、かつてはそう思っていた。いや、今も、「将来、どう守っていけばいいのだろう」という心配はある。それでも、母の死と祖父の死を経て、母や祖父とつながる場所として、仏壇やお墓を大切にしたいと思うようになった。仏壇やお墓に手をあわせるとき、自然と「じゅんのことを見守ってください」とお願いする。自分を見守ってくれた人たちに、自分の子どものこともお願いしたくなるのである。
仏壇やお墓は、父にとってはより大きな意味を持っている。帰省のたびに気がつくことだが、仏壇にはいつも新しい果物が供えられている。お墓の花もいつも新しい。父が頻繁にお墓に行っていることがわかる。仏壇やお墓を大切にし、あの世の人とつながることで孤独がやわらげられているのかもしれない。
ここまで書いてきたことは、今から70年以上前に民俗学者の柳田国男が『先祖の話』(筑摩書房、1946年)で書いたことに通じるだろう。柳田の大きな関心は日本人の信仰の問題であり、『先祖の話』は日本人の祖先観・霊魂観について民俗伝承をもとに書かれたものである。その中で、柳田は死んだ人は祖霊となって長く子孫と交流するという日本人の信仰を明らかにしている。
若いころは先祖のことを考えたりすることなどなかった。けれども、じゅんの誕生、育児の日々、祖父の他界などを経験するなかで、仏壇やお墓、そして先祖のことを身近に感じるようになった。人の生き死にに直面すると、それが遠くにあるものではなく近くにあるもの、さらにいうと、自分の中にあるものとして実感するようになる。単に年をとったということかもしれないが、自分でも少し驚いている。
先祖と子孫は見守る/見守られることでつながっている。仏壇やお墓は、そうしたつながりを時間と空間をこえて取り結ぶ回路のように思える。