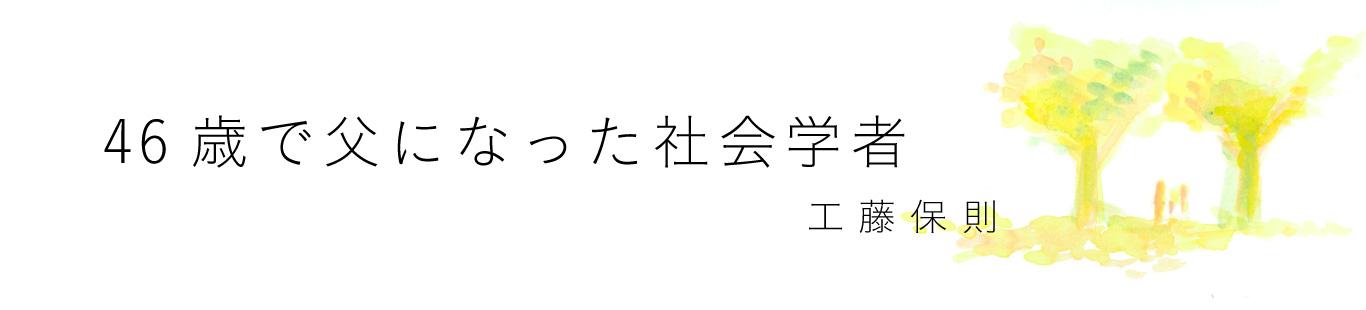第28回
法事
2021.02.03更新
祖父の一周忌法要を2017年2月11日土曜日に行った。祖父は1年前の2月23日に他界したのだが、私の仕事や息子のじゅんの保育園の行事などの都合もあり、父と相談して命日より少し前に行うことにした。
「来てくれる人は、だいたい、もう仕事していない人やけん、仕事しとる人と学校にいっとる人が優先じゃ」
日程を決める際、電話のむこうの父はそういった。
いつもの帰省と同じように、私たちは前日の朝に京都を出て徳島にむかった。とても寒い日だった。祖父が逝った日も寒い日だった。
午後1時過ぎに実家に着き、これもまたいつものように、じゅんが仏壇の鈴をたたき「むにゃむにゃ」ととなえる。そして、鈴の横に置いてあるポチ袋を指さした。
「これ、くれるのかなー」
じゅんは実家に帰って最初にすることとして、仏壇に手をあわせることと、私の父からお小遣いの入ったポチ袋をもらうことが頭に入っているようだ。私と妻は、思わず笑ってしまった。
「ほーじゃな。はいどーぞ」
父がじゅんにポチ袋を手渡す。
「ありがと」
じゅんは腰をかがめて受けとり、中身のことはどうでもいいのか、そのまま妻に渡した。
少しくつろいだ後、翌日に備えて、部屋の掃除をすることにした。実家には父がひとりで暮らしている。それなりに片づけてはいるものの、やはり部屋の隅などにはほこりがたまっている。
妻が掃除機をかけはじめた。
「じゅんくんも」
そういいながら、じゅんは妻が持っている掃除機のホースを握った。
「じゅんくん、手伝ってくれるのはうれしいけど、かけにくいなぁ」
困っている妻のことなどおかまいなしに、じゅんは楽しそうにホースを前後に動かす。
仏壇の右横には、翌日の法事に備えて祭壇が用意されていた。そこには祖父の100歳のお祝いの際に撮った写真が遺影として置かれている。部屋のふき掃除をしていた私には、祖父がじゅんと妻の様子をみて笑っているように思えた。
掃除が一段落したところで、父がじゅんに声をかけた。
「じゅんくん、お団子つくるんも、手つどーてくれるか」
私はまったく知らなかったのだが、祭壇に供える団子を49個つくる必要があるようだ。
「はーい!」
お団子という言葉から楽しそうだと察知したのか、大きな声で返事をした。
台所では、お鍋の中にお湯が沸いていた。その横に、水で溶いた団子粉がボールに入っている。私たちが部屋の掃除をしているときに、父が準備を終わらせていたのだろう。お手本を見せるかのように、父はその団子粉を手に取り、両手でピンポン玉よりやや小さいくらいの大きさにまるめた。私も見よう見まねで、団子をつくった。
「あつい?」
じゅんが聞く。
「あつくないよ」
私の返事に安心したじゅんの手のひらに、父がほどよい量の団子粉の塊を置く。
「きもちいなー」
じゅんは思いのほか器用にまるめていた。
まるめた団子をお鍋の中に入れると、1分くらいで茹であがる。それを取りだし、片栗粉を敷いたお盆に入れ、その上でころがす。まるめた団子がお盆の中でころころところがって片栗粉がついていく。
「おもしろいなー。じゅんくんも」
そういって、じゅんは私の手からお盆を奪った。
そうしてできあがった49個の団子を、祭壇の左右2台の高坏に盛った。それ以外の準備は父がすでに終えていたので、これで明日の準備が整ったことになる。
一周忌当日も、とても寒い日だった。9時半頃から親戚が集まり始め、最後に大阪の親戚が11時前に到着し座布団に座ったところで、おじゅっさんの読経が始まった。
実家は建物が古く、窓枠のサッシも木製である。隙間風が入り放題で、家の中にいてもとにかく寒い。エアコンは壊れていて動かない。寒さ対策として、電気ストーブを3台、部屋に置いた。8畳の部屋に、仏壇と祭壇、おじゅっさん、おとなが9人、子どもがひとり、電気ストーブが3台。ぎゅうぎゅう詰めだ。
約30分間の読経の間、じゅんは神戸のじいちゃんの膝の上でおとなしくしていた。皆、祭壇にある祖父の遺影をみたあとで、じゅんのほうに目をやる。そしてにっこりとする。それを何度となくくりかえしていた。
その後、昼食をとる仕出し屋さんの出してくれたマイクロバスに乗り、山にあるお墓にむかった。マイクロバスに乗るとき、父はじゅんと妻に卒塔婆を、私には線香とお米を入れた小さな手提げバッグを渡した。山のふもとでバスを降り、10分ほど山道を登ってお墓についたとき、私は手提げバッグをバスの中に置いてきてしまったことに気がついた。私があわてていると、じゅんが小さな声で「パパ、すぐわすれるなー」といって笑った。急いで取りに帰ろうとしたが、父が「別になかっても、じいちゃん、困らんけん」といったので、そのままお墓の前で皆で手をあわせた。じゅんも小さな手をあわせた。
山道を下るときも、じゅんは「パパ、わすれたなー」と嬉しそうにいった。私があたふたしていたのが、よほどおもしろかったものとみえる。
「パパはダメだなー。じゅんくんが頼りだなぁ」
「そうやなー」
「これからは、パパが忘れものしていないか、確かめてな」
「うん。わかった」
ふたりの会話を皆が聞いていた。
仕出し屋さんでの昼食のとき、じゅんはテーブルの椅子にちょこんと座り、にこにこしていた。細巻き寿司が気に入ったようで、私と妻の分も食べた。
「じゅんくん、小さいお寿司、好きなんやねぇ。ばーちゃんのもあげる。食べて」
「ありがとー」
神戸のばあちゃんの分も食べた。「しっかり食べて、えらいなー」と皆が口々にいった。
食事の最中、父のきょうだいや亡き母のいとこたちが、次々にじゅんのところにやってきて、話しかけてくれた。
「おじゅっさんがお経を読んどったとき、えー子にしてたなー」
「お墓まで、よー登れたなー」
「お寿司、好きなんか。いっぱい、食べーな」
私もひさしぶりに会う人たちだ。じゅんは誰が誰だか、わかっていない。
父のきょうだいや亡き母のいとこは、じゅんからみれば、どういう名称になるのだろう。そういう関係はもう親戚とはいわないのかもしれない。しかし、日常的に共食する関係を家族というならば、人生儀礼において共食する関係を、つながりの近遠にかかわらず、親戚といっても間違いではないだろう。
法事と子どもは相性がいいようだ。子どもがいると、法事の場がほどよく明るく保たれる。死んでいく人がいれば、生まれてくる子どももいて、そこに終わりはないのだということを納得させられる。こうした「つながり」の実感は、「家」とか「血」とかだけに由来するのでは、おそらく、ない。「未来」や「希望」の共有があるのだと思う。子どもはそれを象徴するとともに、体現する存在である。
祖父の一周忌法要をすませ、私たちはその日のうちに京都まで帰ってきた。
夜、布団に入ってから、私は横で寝ているじゅんに声をかけた。
「じゅんくん、いろいろ、ありがとうね」
「いえいえ、どーいたしまして。おおきいじーちゃん、うれしかったなー」
じゅんはそういうと、しばらくして小さな寝息をたて始めた。