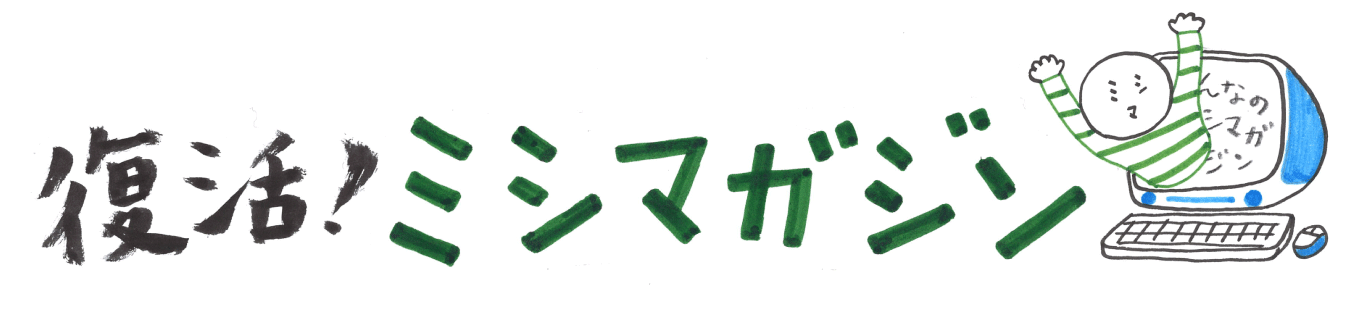第13回
本屋さんと私 滝口悠生さん編(前編)
2019.12.26更新
こんにちは、ミシマ社京都オフィスのノザキです。
本日、2019年12月26日、ある一冊の本が発売日を迎えます。小説家・滝口悠生さんによる、『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』(NUMABOOKS)。2018年、世界各国の作家や詩人がアメリカのアイオワ大学に集まる滞在型プログラム「インターナショナル・ライティング・プログラム(IWP)」に参加された滝口さん。当時の日記とエッセイが一冊の本としてまとめられています。
本の中には、『ちゃぶ台Vol.4』にご寄稿いただいた「チャンドラモハン」も出てきます。そして滝口さんには最新号の『ちゃぶ台Vol.5』でも、小説「競馬と念仏」をご寄稿いただいています。そういうご縁から、ミシマ社でも新刊の発売を盛り上げるぞ〜! ということで、今日と明日の2日間で「旧みんなのミシマガジン」にご登場いただいた際のインタビューを復活します。
※本記事は、「旧みんなのミシマガジン」にて、2017年11月13日〜11月15日に掲載されたものです。
今回の「本屋さんと私」は小説家の滝口悠生さんにお話を伺いました。そして新人ノザキの人生初インタビューです。本の虫でもなければ、小説を山ほど読んできたわけでもない、そんな私がたまらなくいいと思った書き手の滝口さん。日記にも書き残さないような日々の出来事や感情を捉える語りには、電車の中で読んでいても、ついつい口元が緩んでしまいます。
「たしかにあったどうでもいいことは、この世界にどのように残りうるのか。それともどうでもよさゆえに忘れられ、いつかは消えてなくなってしまうのか。」――『死んでいない者』滝口悠生
これが私のお気に入りの一節です。さて、西武線のこと、小説を書き、届けるということ、そして最新刊の『高架線』についてもたっぷり伺いました。滝口さんのお話を前編・後編にわたってお届けします。どうぞお楽しみください。
(聞き手・構成・写真:野崎敬乃 構成補助:星野友里)

書いていく中で思い出されるもの
―― 滝口さんの小説には、日々の生活で目にする小さな面白さや自分の中に生まれる微妙な感覚を掬いとってくれる印象があります。滝口さんは小説をどのように書き始めるのですか?
滝口 書こうと思うことをためておいてそれを書くというよりは、書く内容としての準備はあまりない状態で書き始めるんです。書いていく中で、旅先で見た光景だとか、見かけた人のことを思い出すことはあるんですけど、ネタ帳にストックをして、みたいなことは全然しないです。普段から歩いたり、電車に乗っていろいろなものを見たりすることが好きなので、面白いものを見つけて、なんだこれ? と思うことを見つけることは多いかもしれないですね。
―― そうなんですね。
滝口 たとえば『死んでいない者』だったら、自分が親戚の集まりとか、お葬式でも結婚式でもいいですけど、冠婚葬祭みたいな場で目にしてきたことっていうのがやっぱりもとにはなっているんですけど、それを書こうという動機で書き始めたわけではないです。書き始めっていうのはもう少しぼやんとしていて、雰囲気とかムードとか、場所とか土地とか、最初にあるのはそういうものですかね。『死んでいない者』の場合は、ちょっと田舎のほうの土地とか、空が開けた景色とか。あまり細かいことというよりかは、そういう大雑把なことだけがあって、それからじゃあ葬式でも書いてみようかい、というふうに書き始めることが多いです。
―― 地方や田舎へはよく足を運ぶのですか?
滝口 そうですね。最近はふらっと旅行に行くことはなかなかできなくなっちゃいましたけど、昔はよく行きました。今だと、たとえば仕事で関西のほうに行って翌日何も用事がないと、ぶらぶら1日街を歩いてから帰ってきたりします。
―― 海外にも行かれますか?
滝口 海外は機会がなかったり、若いころはお金もなかったりしたので、全然行っていなかったんですけど、今年ヨーロッパで友だちの結婚式があったので初めて行きました。あと昔から空路の移動がだめで。飛行機そのものは平気なんですけど、移動の方法として陸路じゃないと動いた感じがしないというか、距離がよくわかんないことになっちゃう感じがあって。昔アルバイトしていたころに九州に飛行機で仕事しに行ったら、90分くらいで着いちゃうじゃないですか。90分で羽田から福岡って、どっかでなにかワープみたいなことが起こっているとしか思えなくて。
―― 千葉-東京間でも電車の各駅に乗ったらそれくらいかかりますよね。
滝口 90分だと飛んでも大阪くらいかな? っていう気がして、九州だったら嘘でもいいから3時間くらいはかけてほしい。当時は埼玉に住んでいたので、家から羽田まで2時間くらいかかるのに、そこから90分で九州に降り立つというのはどうも納得がいかなくて。新幹線も速すぎてずっと嫌いだったんですけど、最近は体力がなくなってきて、昔みたいに鈍行だとつらいので、許せるようになりました。飛行機も、このあいだはロンドンまでいったので12時間くらいかかったんですけど、12時間くらいかけてくれると、わりとどこに連れてかれてもまあ着くかなと思える。
東京の奇妙な距離感
―― 今のお話、とても面白いです。ある場所に対する近さと遠さの感覚というものは、滝口さんの小説の中に豊かに書かれている気がします。例えば、『高架線』の新井田くんと田村くんが一緒にかたばみ荘を見に行った後に公園で過ごすシーン。そこでの会話には、池尻大橋と春日の地名が出てきます。田村くんが春日の家に誘ったときに、新井田くんは「遠いかな。今日は。気分的に。」と言うのですが、その会話には、場所に対する近さや遠さの感覚が人によっても、状況や気分によっても違うということが表れていて、そこに共感しました。あのシーンが『高架線』の中での私のベストシーンです。
滝口 そこをベストシーンに挙げる人は初めてだ、面白いですね。僕は実家が埼玉の西武池袋線にあって、池袋まで電車で40分弱ぐらいなんです。新宿とか渋谷に出ようとすると電車だけで1時間、家からだと1時間半くらいかかって、どこに行くにもそれくらいかけて出かけていく感覚がベースにありました。今住んでいるところは渋谷まで10分で、渋谷から東京の真ん中のほうに行こうとしても20分くらいなので、1時間以上かけてどこかに移動するっていうのが都内に関してはほとんど無くなったんですね。電車に乗る時間もすごく細切れで、どこ行くにも近いなって思って暮らしていて。でもだんだんこっちに暮らす時間が長くなってくると、前に比べれば全然すぐの場所なのに、ちょっと面倒くさいなとか出にくいなっていう感じが出て来るんですよ。『高架線』のその場面は、そういう東京に住んで暮らしている人独特の距離感とか移動の感覚を、新井田さんがちょっと言い訳に使っているんです。
―― そうなんですね。
滝口 もう一つは、慣れるとどうってことないのに、不慣れな路線に乗らないといけないっていう緊張とか抵抗とか、そういうのもありますね。僕は大江戸線とかがそうで、青山一丁目とかだと乗り換えもわりとすぐなんですけど、ほかの駅で大江戸線に乗ろうとするとめちゃめちゃ歩かされたりするじゃないですか。そのイメージが強くて、だから大江戸線はなるべく乗りたくないとか。
―― わかります。
滝口 さっきの場面で、新井田さんはすごく曖昧に、田村の家に行かないっていうことを表明するんだけれども、彼は西武線で育って、東京に出てきて、今は東急線の池尻大橋にいるっていう鉄道の属性が僕と一緒なので、大江戸線使うのいやだな、みたいな感覚はたぶん僕と同じです。乗っちゃえば何分だからすぐだよ、みたいなことではないんだっていう。
東長崎から春日に行くのと池尻大橋に帰るのって大して変わらないか、もしかすると春日のほうが近いかもしれない。だから遠いって言うのは理屈としておかしいんですけど、そこにはまず彼の行きたくなさがあって、それに乗り換えとか地下鉄の深さみたいな抵抗が重なっている。それに、たぶん田村もその筋の通らなさをよくわかっている。そういうやりとりだから、あそこは理屈が通っていなくてもいいんです。
鉄道属性
―― 先ほどの「鉄道属性」という言葉がすごく面白いと思いました。なぜ滝口さんは西武線を書くのかということについて改めてお伺いできたらなと。ちなみに私は属性が東急線です。
滝口 はいはいはい、ライバル関係。池袋とか嫌いでしょ。行きたくないでしょ。
―― あまり行ったことがないです。
滝口 そうですよね、用がないですもんね。池袋に行ってもその先は埼玉にしか行けませんからね。なぜ西武線を書くのかということについては、西武線を自分の十八番のようにいつも使おうという意識はあんまりなくて、ただ、そこに住んでいないと生まれない感覚や、さっき言ったような独特の距離感や心理的な抵抗みたいなのがどの沿線にもあると思うんです。そういうことが人物を書いていくときに重要だったりするので、そうすると、そこを知っている、ということがすごく大きいんですよね。だから自然とそれを選んでしまう。ただもうさすがに毎回書いてるんで、そろそろやめようかなと思ってるんですけど。
―― では今回のは集大成ですね。
滝口 これだけ書けば、次やりにくくなるだろうってうのはあります。
登場人物の名前の付け方
―― 滝口さんの小説に出てくる登場人物の名前は、突飛すぎるわけではないのに、どこか耳に残ります。名前の付け方について教えてください。
滝口 名前は、作品によってなんですけど、難しくていつも悩んじゃうというか、そんなにすっとは決まらないんです。ずっと語り手が一人で一人称の作品だと、語り手の名前はあまり出てこなかったりするので、なんでもいいやって感じなんですが、『高架線』の場合はいろんな人が出てくるので、ちょうどいい名前というか、やりすぎもせず、でもよくある名前ばっかりだと引っかかりにくいしっていうので、やっぱりいろいろ考えました。決めるときに意味を考えすぎたり、人物像と絡めようとし始めると凝った名前になってしまうので、なるべくすぽんと出て来たものを付けるように気をつけています。その結果、僕が書く登場人物の名前は、ものすごく数字が多いんですよ。
―― 三郎とかそうですね。
滝口 三郎とか一郎とかやりがちなんですよね。数字が一個入っていると、ちょっと簡単な感じが出て、なんかいい塩梅になる。新井田千一さんもそうだし、七見さんもそうだし、三郎もそうだし。変な言い方ですが、いかに適当に付けてそうな名前を付けるかということにはすごく気をつけています。新井田さんの文通相手は成瀬文香という名前で、別に普通の名前だけど、僕のなかではちょっと色っぽい名前をつけたつもりで、でもこの人は実際には登場しないからそうやって少し凝っててもいい。たくさん喋ったりよく出てくる人は凝った名前だとうるさいので、なるべくあっさりとしつつ、ちょっと特徴があるようにとか。新井田さんも、新井千一さんだとあっさりしすぎかな、と思って田を付けるとか、適当さに適当さを加える足し算のような。すると、おかしくはないけど少し覚えやすくなる。
―― 今回の『高架線』では、木下目見(きのしたまみ)ちゃんが最高でした。「木登りしてる女の子を下から見上げたらパンツが見えた、みたいな名前」という説明のユーモアがたまらなくて。
滝口 目見ちゃんは多分音を先に決めて、字を考えていたときに、「きのしたまみ」ってわりとポピュラーな苗字と名前の組み合わせなので、少し変わった字にしようと。そうすると少し引っかかりができるし、その字にまつわるやりとりを他の登場人物とできたりもする。目見っていうのはいい名前をつけられたなと思います。
―― いい名前です。
滝口 あの人が中心に出過ぎてきちゃうと、またちょっと違うかもしれないけど、この人もそんなに前面に出てくるわけではないから、ちょっと変でもいい。そういうバランスを気にしつつ、でも基本的にはぱっと決める感じですね。あまり考えすぎるとよくない。目見っていう字は変換候補に出てきて、あ、これいいや、って決めたんだった気がする。じゃないと思いつかないですね。
無駄なことの愛嬌
―― 滝口さんの小説では、すでにある慣習に対して、単に批判するのでも茶化すのでもない姿勢が印象的です。そういうことは意識して書かれていますか?
滝口 そうですね。慣習とか、馴れ合いみたいなものって、よくないものもあるとは思うんですけど、なんとなく続いてしまっていることの愛嬌みたいなのもあって、そこが僕は結構好きかもしれないです。
前に小さいお店で働いていたんですけど、仕事場って効率的にしようとするとできることがいろいろあるんですよね。僕は立場的にそれを改善していくような仕事が多くて、ここをもうちょっと切り詰めて作業効率を上げようとか、経費削減とか、そんなことばっかり考えていました。仕事だからそうしていくし、それはそれで面白さもあるんですけど、僕個人の指向としては無駄なこととかダラダラしたことに惹かれるので、小説にはそういうしょうがないなあみたいな感じを書くことが多いんじゃないかな。『茄子の輝き』に入っている「お茶の時間」という短編はまさにそういう話なんですが、ダラダラしている人がダラダラする中で結構有意義なことを考えていたりするかもしれないし、お店とか仕事場って、どんなに非効率で無駄に見えても、そこを省いたら全部崩れちゃうみたいな、絶対変えちゃいけない部分もある。慣習とか無駄の功罪は、奥が深いです。
―― 小説の終わり方についても伺いたいのですが、これまでの作品では淡く終わっていくものが多かったのに対して、『高架線』でははっきりした終わりがある印象を受けました。あれは意図した結果ですか?
滝口 最後に物語が収束するというか、伏線を回収していく形になったのは、意図していたわけではなくて、書きながら勝手にそうなっていったんです。それこそ最後はエンディングらしいエンディングみたいになって、すごいベタなんですけど、そこに抵抗がなかったかというと、これが実はあまりなくて。
小説の終わりってすごい不思議で、なんで終わったのかってうまく説明ができない。僕の作品は人が大勢集まって集合したり、誰かが死んじゃったりして終わることが多いんですね。そうしたくてそう書いているわけではないし、そう書いたからといって必ず終わるってものでもないんですけど、どんなにベタなことでも、書いている自分にとって、無理やりそこに持っていったっていう感じがなければ何をやってもいいと思っています。
最初から終わり方が決まっていて、そういうふうにしようと思って本当にそうなっちゃったらダメなんだけど、そんなつもりはなく書いているうちにああそうだったのかっていう驚きが自分の中にあれば、それはどんなにベタでも典型的でもオッケーというふうに思っていて、そこが線引きですね。自分の中で驚きがあるかどうか。こうやって説明するとどうとでも言えるというか、自分の中の免罪符みたいに聞こえるかもしれないですけど、でもその驚きみたいなものは多分文章の中にもあるはずなので、それがあればテキストとしてもなんらかの面白みとか、驚きみたいなものがそこに活きてくると思っていて、そうじゃないと読んでいても面白くないというか退屈してしまう。予定通りにそういうことを書いてもやっぱりつまんないと思うんです。
―― そうなんですね。
滝口 これはここ最近で結構はっきり思うようになったことです。だいたい僕の作品は毎回そんなに暗くならずに、ああよかったね、ちゃんちゃんっていうふうに終わることが多くて、それでいいのかなっていう疑問というか不安もあったんですけど、そうしたくてそうしているというのがなく、勝手に終わるっていう感触があれば、それはどんな形でもよいかなと思えるようになりました。
―― 面白いです。
滝口 書くものと書き手の距離をちゃんと保つために、あまりどうするかを決めずにこちらで驚きながら書くということが僕にとって丁度いい距離ということなんだと思います。
(後編へつづく)