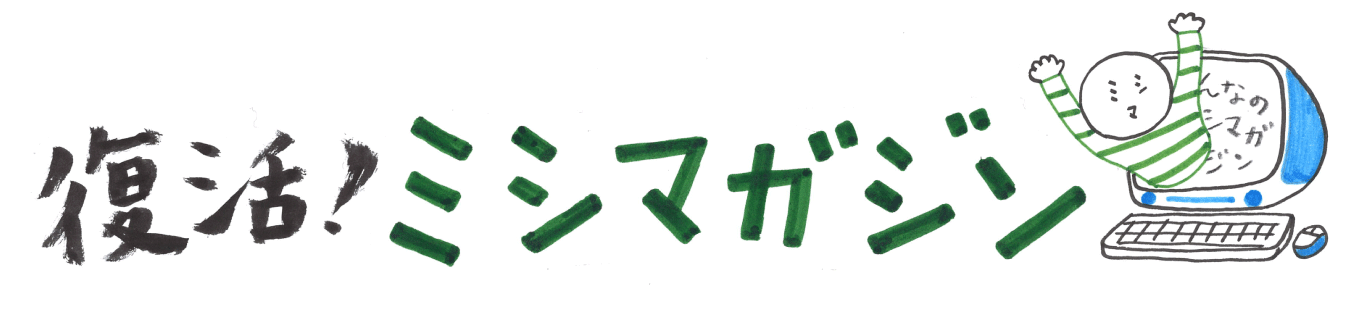第13回
本屋さんと私 滝口悠生さん編(後編)
2019.12.27更新
こんにちは、ミシマ社京都オフィスのノザキです。
昨日、2019年12月26日、ある一冊の本が発売日を迎えました。小説家・滝口悠生さんによる、『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』(NUMABOOKS)。2018年、世界各国の作家や詩人がアメリカのアイオワ大学に集まる滞在型プログラム「インターナショナル・ライティング・プログラム(IWP)」に参加された滝口さん。当時の日記とエッセイが一冊の本としてまとめられています。
本の中には、『ちゃぶ台Vol.4』にご寄稿いただいた「チャンドラモハン」も出てきます。そして滝口さんには最新号の『ちゃぶ台Vol.5』でも、小説「競馬と念仏」をご寄稿いただいています。そういうご縁から、ミシマ社でも新刊の発売を盛り上げるぞ〜! ということで、昨日と今日の2日間で「旧みんなのミシマガジン」にご登場いただいた際のインタビューを復活します。
※本記事は、「旧みんなのミシマガジン」にて、2017年11月13日〜11月15日に掲載されたものです。
前編はこちら

本を届けるということ
『茄子の輝き』と『高架線』、2冊の刊行を記念して、大阪のスタンダードブックストア心斎橋では、2017年8月31日から10月31日の2ヵ月間、大規模なフェア「滝口悠生の本棚」が開催されました。聞き手ノザキも東京から大阪まで行ってきたのですが、70冊にも及ぶ選書や、滝口さん直筆のPOP、本棚の写真の公開やフリーペーパーの発行など、とにかく熱い熱いフェアでした。
―― スタンダードブックストアのフェアについて教えてください。
滝口 今回『高架線』と『茄子の輝き』が近い時期に出るので、両方をがんばって売るために何かできないかなと考えました。僕も知らなかったんですけど、同時期に2冊出すと、売れにくいんだそうです。そこで、一方を手にした人がもう一方も手にしたくなるような仕掛けを考えようということで、2冊をつなげる小冊子を作ってみたり、フェアをやってみたりしたんです。
―― フェアが日々成長して行く様子が面白かったです。
滝口 お店の方が本当に熱心にかかわってくれて。あれを2ヵ月間やってくれたというのはすごいことで、びっくりしました。
小説との事故のような出会い
―― 本を届けることについての思いを聞かせてください。
滝口 本を作って全国に流通させるということに関して、当たり前ですが僕は全くの素人で、大きな書店さんに本をたくさん並べて売ってもらうということは版元さんの力がないとできないことなんですけど、それだと届かない場所もあると思うんです。たとえば、大阪のスタンダードブックストアには、小説にはあまり興味がなくて、音楽とかファッションとかに興味があって来るお客さんも多いと思う。そういう場所で今回のようなフェアをやったりすると、事故のような出会い方というのが起こりうるんじゃないかと。
紀伊國屋さんの文芸売り場には行かないんだけど、スタンダードブックストアには行くという人もたしかにいて、その中には、普段小説は読まないけど、あのフェアのPOPが付いていた本に興味を持って、そこから僕の小説にも手を伸ばしてくれて、読んでみたら面白かったって思ってくれる人がいるかもしれない。そういうところに届かせるようなこともしないといけないんじゃないかなと思っています。
―― なるほど。
滝口 あんまり大勢ではなくても、僕が好きで聞いているような音楽を好きで聞いていて、同じ音楽が好きなんだったら、この人の小説は面白いかもしれないとか、そういう繋がり方を介さないと届かない、潜在的な読者が多分いるなというのは前々から思っていたんですね。『死んでいない者』は芥川賞の本だから、マスに向けてがっと売る方法でよかったと思うんですけど、いきなりマス的な状況に置かれた時の戸惑いや疑問もやっぱりいろいろあって。でも、芥川賞ですよーってがーっと売っても、案外そういうところに届く感じはなかったりして、じゃあどうしたらいいのかなっていうのは結構ジレンマだったんです。
それでなんか著者が手足を動してできることはないかなっていうので、小冊子とか、大阪のフェアとかの話になっていきました。あのフェアは、僕とスタンダードブックストアの書店員さんが直接やりとりして、こういうことやりましょうって先に決めちゃって、版元さんには事後承諾で、可能な範囲で協力してもらうっていう形にしました。そうしないとなかなか大胆に動けないんじゃないかなと。当然僕のやらないといけないことも多かったんですけど、新潮社の担当者も講談社の担当者もいろいろ協力してくれたし、大変ではありましたがおもしろかったです。
―― フリーペーパーを作るなど、紙でやる取り組みにこだわりはありますか?
滝口 こだわりというか、単に自分ができることですね。まわりを見ると、いろんな書き手や編集者がいろんな取り組みをしていたりして、それぞれに合ったやり方を探して試行錯誤しているんだと思います。僕はネットとか詳しくないし、年寄りくさい作風なので、アナクロに紙を使ってちょこちょこやるのが合っているんじゃないかと。
まだ開拓されていない読者を探して
―― 今回のフェアの情報はほかの本屋さんや作家さんも絶対見てると思いますし、こういうことができるんだっていうことをみんなが思うのは大事だと思います。
滝口 僕よりひとまわりとかふたまわり上で、小説書いて本が出ている人と、僕らぐらいの10年代デビューの書き手って、次の本が出るかどうかっていうところでやっぱり状況が違うんです。書き手は書いて原稿をお渡しすることしかできないので、本にして全国に流通してもらうってなったあとでできることはかぎられています。でもなにかやって少しでも動きがよくなるとか、届かなかったところに届くみたいなことをして、5冊でも10冊でも書店で本が売れるのはとても大きなことだと思っています。
部数の少ないものが売られるときに、何万部とか何十万部とか売れるものと同じ売られ方をしちゃうとどんどん売れなくなっていくだけなので、少ない中でもどんな売り方ができるかを考えていかないと、少ない部数のものはどんどん作りにくくなるんじゃないかと。多分全部の著者が同じやり方をしてもだめだと思うんですが、僕の本で大阪でああいうふうにやったことによって、滝口の本がこのぐらい売れるんだったらあの人の本もここに置くといいかもしれないみたいな、いろんなモデルができていって、それが相互に交換できるようになっていくと、さっき言ったような普段手にとらない人が手に取るっていう機会が少し増えると思う。なんか結構それが一番大事で、まだ開拓されていないところのような気がするので。
―― 本当にそうですよね。
滝口 すでに小説をいっぱい読みますっていう人は好きか嫌いかで選んでもらえばいいんですけど、小説はそんなに読まないんだけど、こういうのだったらピンポイントで興味あるみたいな人は多分いると思うので、そういう人に届けようとすることは必要なのかなと。何がきっかけになるかわからないし、小説は体系的に読まなければいけない訳ではまったくない。そうやって楽しめばいいものだと思うので。
―― まさに私がその一人でした。きっとこれからもいろいろなきっかけを介して、滝口さんの小説の虜になっていく人がたくさんいると思います。
*
*2日間にわたってお届けしてきたインタビュー、いかがでしたか?「無駄なことやダラダラしたことが好き」と穏やかに話をされる一方で、文芸書が置かれる今の状況を見据え、「どう届けるか?」を考えながら書き手としてできることに取り組む滝口さんの姿勢が印象的でした。これからミシマ社の本づくりに関わるひとりとして、お守りになるような言葉と時間をもらった気がします。滝口さん、本当にありがとうございました。(おわり)