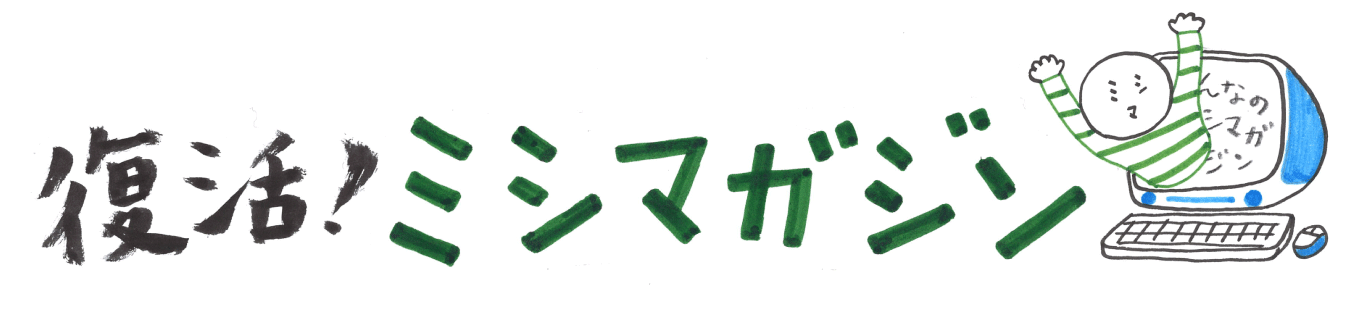第17回
言葉はこうして生き残る 河野通和『言葉はこうして生き残った』発刊記念インタビュー
2020.02.23更新
現在渋谷パルコで開催中(2/22〜2/24)の、ほぼ日の学校Presents「本屋さん、あつまる。」に、ミシマ社の本屋さんが出店しています。
お知らせしております通り、最終日の24日(祝・月)に開催を予定していた、本イベントの発起人である「ほぼ日の学校」学校長・河野通和さんと代表・三島のトークイベントは、やむなく中止とさせていただきます。楽しみにしていただいた方々、申し訳ございません。
中止のお詫びに、本日のミシマガジンでは、2017年に『言葉はこうして生き残った』が発刊した際に行ったトークイベントの様子を再掲させていただきます。24日もイベントはなくなりましたが、ミシマ社スタッフは常駐しておりますので、ぜひいらしてくださいませ。

「本屋さん、あつまる。」
たのしい本屋さんが渋谷PARCOにやってきた!
期間 2020年2月22日(土) -2020年2月24日(月)
場所 渋谷パルコ8F・ほぼ日曜日 (アクセス)
時間 10:00〜21:00
入場料 無料
※本記事は、「旧みんなのミシマガジン」にて、2017年3月6日〜3月8日に掲載されたものです。

今年1月に発売となった『言葉はこうして生き残った』。
おかげさまで、「こんな本が読みたかった」「360ページ、一気に読んでしまった」等々、たくさんの嬉しい感想をいただいています。
本書は、中央公論社(現・中央公論新社)で30年、新潮社で6年8ヵ月、編集者として、そうそうたる作家、装丁家、ジャーナリストの方々と仕事をされてきた河野さんが、雑誌「考える人」の編集長としてこの間、毎週綴られてきたメールマガジンから厳選した37本を書籍化したもの。
『言葉はこうして生き残った』河野通和(ミシマ社)本書の制作や販売、イベント等を通して、河野さんにお目にかかり、お話をうかがう機会は、まだ会社としても若いミシマ社の面々にとって、自分たちが受け継ぎたい出版を知る、豊かな時間となっています。
そんな河野さんの言葉をみなさまと共有すべく、今月の特集では、1月24日に東京堂書店で行われたイベント、そして2月13日に銀座EDIT TOKYOで行われたイベントで語られた河野さんの言葉を編集し、3日間にわたってお届けします。どうぞお楽しみください。
 そっとオフィスに置いて帰ることにしました
そっとオフィスに置いて帰ることにしました
三島 河野通和さんの初の著書となる『言葉はこうして生き残った』。できたてほやほやでございます! 昨夜、河野さんに「遂にできましたよ!」と直接お届けにあがったばかりでして、では河野さん、実物をお持ちになっての第一声をお願いします!
河野 正直、「ホンマにできてるんかなぁ...」と思うくらい心配していたんです(笑)。物理的にかなり大変なスケジュールだったので、昨日手にしたときは「とにかくできたか!」という気持ちで、感激というか安堵感が先に立ちましたね。
三島 たしかに大変でしたね(笑)。
河野 でも実際に手にしてみると、これは本当にブックデザイナーである寄籐文平さんの渾身の力作ですね。タイトル、帯、本文の文字のひとつひとつに対する思いがたいへん細かいところまで込められているのが伝わってきます。そして編集に関わってくださった方々の熱量がぎゅうぎゅうに詰まっていて、昨日は格段と寒い夜だったのですが、本を手にした瞬間は温まりました。ありがとうございました。
三島 いえいえ! とんでもないです。ですが河野さんは編集者として僕の大先輩にあたる方ですので、まぁ...これほど緊張するものかと思いました。
河野 本づくりを始めるにあたって、まず過去の記事のプリントアウトを三島さんに委ねました。300回といいますと1回分がA4用紙6~7枚なので膨大な量になります。たまたま京都へ出張した際に、紙袋2袋にパンパンに詰めて京都のオフィスまで持って行きました。これだけの量の原稿を面と向かって、「よろしくお願いします」と差し出すのは気後れするような感じで...。ですが、その日は三島さんが京都におられなかったので、そっとオフィスに置いて帰ることにしました(笑)。
三島 しばらくはとりかかる踏ん切りがつかず、1週間くらいは出社して毎日、積み上がった紙の束を拝んでいました(笑)。
他人に勧めたい気持ちが湧いてこないものは書いちゃいけない
三島 小分けにして読むことはできないと思ったので「ここだ!」というタイミングで、ある日突然貪るようにダーーッ! っと選抜しました。その作業のなかでとにかく驚愕したのが、このクオリティの記事を毎週書かれているということなんです。普通ならプロの編集者でも1カ月に1本くらいが限界でしょう。
河野 週に1回、原稿用紙15~6枚の記事を書くのですが、本業は『考える人』の雑誌づくりですから、これだけで昼間の時間はほとんど失われますし、夜も時間がない。メールマガジンというのはとにかく怠りなく書かなければいけないので、仕事が終わった夜中や週末に書くということをやってきました。
三島 配信を始められた頃は思いもほとばしっているでしょうからわかるのですが、ずっとこのクオリティを保ちつづけることはプレッシャーになりませんでしたか?
河野 「今週はこの本を取り上げよう」と思って、途中まで読んで「あ〜、だめだこれは...」と思うことが夜中に起きたりします。書いて書けないことはないけれど、他人に勧めたい気持ちが湧いてこないものは書いちゃいけないと思いました。そういうときは別の本を探します。書く以上は絶対ほめたいと思っているんです。ただ、焦りますよね。ところで私は三島さんの安眠を相当妨害してしまったらしいですね(笑)。
三島 はい(笑)。この本のなかに「出版社にとって一番うれしいのは再版である。重版がかかっていくことである。そして誤植を直せるのがとてもうれしい」という言葉が出てくるんです。本当に「これ以上はできない」というくらい目を通していてもミスが生じることはあるんですね。とはいえ「この本でミスは許されないぞ!」と思っていましたので、何度もチェックを繰り返しやっていたんです。そんなある日、ついに入稿し終わった夢を見まして。
「あー! 終わったー!」と思っていると印刷所の方が見本を持ってきて、それをパラパラッとめくる。すると「...直っていない!!」「指でつき合わせもして、直したはずなのに!」「うそ! どーすんの!」というところで目が覚めるのですが、そんな朝を1週間くらい迎えていました。
多様な一芸を持った先輩たちに洗礼を受けた20代
三島 メールマガジンでは、紹介する本だけではなくそのテーマにまつわる本の引用なども毎回入ってきますよね。ああいった引用は「この本を読むならこれだな」と、河野さんのなかで紐付いてくるんですか?
河野 そうですね。書き始めるとツルツルと、言葉が言葉を呼んで流れが決まっていきます。
三島 なるほど。その引用された資料というのもコピーをすべて残しておられるんですよね。実際に読み返されたのは、書籍化が決まって初めてだというのに、これだけの資料を残しておくというのは、河野さんにとっては当たり前のことになっているのでしょうか。
河野 やはり編集者の習い性とでもいうのでしょうか。後になって原典と照合しようと思ったときに、本の該当箇所、その掲載物、週刊誌や新聞記事などはなかなか探し出せないんですよ。どれだけ検索エンジンが発達しようが現物にはなかなか辿りつけない。
なにかを書いたときになにを根拠としたのかを残しておかないと後で大変な思いをするぞ、ということが身体に染み付いているんです。書いたものに対しての責任があります。間違いが指摘されるかもしれない。そのときに根拠になるものがあれば、話もできますので。
三島 その徹底ぶりというのは河野さんが中央公論の編集者を始められた頃の先輩から教わったことや影響が大きいのでしょうか?
河野 そうですね。私が入社した頃の中央公論社は多士済々というか、おもしろい先輩がたくさんいました。たとえば、宮脇俊三さんという後に紀行作家になる先輩がいらっしゃって。中公新書というレーベルを立ち上げた大功労者でもあるのですが、本当に鉄道について詳しいんですね。
私が出張の際に旅程表を書いていると「君そこ行くの。だったらねぇ...」と言って「何時何分にこういう電車に連絡して」「ここに行って、こういう行き方をしたらおもしろいんだよ」というようなことをスラスラ教えてくださる(笑)。
他にも山が本当に好きでご自身も山登りをされる上に、山に関する書物は万巻の書を読んでいる方もおられました。とにかく一芸に秀でた方がたくさん社内にいるんです。なので「迂闊なことは言えないな」とはずっと思っていました。言葉を発する以上はちゃんと調べて、「これに関してはどんなプロがいようが、これだけは言えるぞ!」というくらいでないと、相手にされない。そのおかげで鍛えられました。
三島 おぉ...それはすごいですね。20代の頃に洗礼を受けたということですね。
河野 いやぁもう...、生きた心地のしない感じでした。凝り性ばっかりだったんですよ。

出来の悪いAIが経営しているようではいけない
三島 現状の出版界はどうご覧になっていますか?
河野 出版危機を乗り切って生き延びなければならないと必死になるあまり、どうしてもお金を稼ぐことに経営の目が向いてしまいます。それは当然だし、やむを得ないのですが、本来は何がやりたくて出版社に入ったのか、という原点が見失われていくんです。
ただ、「確実な企画」「失敗のリスクが少ない作家」「この人は初版を出すと大体このくらい売れて、会社にこれくらいの利潤が出てくる」というところで企画が選別されていく。非常に出来の悪いAIが経営をやっているみたいなんです。せいぜい10とか20くらいの過去のデータをもとに、「これだったら大丈夫そうだね」と"安全運転"に走っているのが、今の出版をとてもつまらなくしている理由です。だからきっと、もっと優れたAIが出版社経営をやったら、いまの出版社って要らなくなると思います。
三島 なるほど。たしかにそうですね。
河野 いまやもう、わざわざ高給を求めて出版社に来る人もいない。だから、本とかクリエイティブということに関心を持って出版社の門を叩く人を、そういう出来の悪いAIみたいな道に誘導して押しこめるのは、とてもまずいことだと思っています。『言葉はこうして生き残った』にも書きましたが、そうではない思いで言葉に関わってきた出版人たちに、彼らが考えていたことをもう一回聞いてみたいな、という思いが私自身にありました。
当時の社長からもらった、忘れられない言葉
河野 バブルの時代、私は「中央公論」という雑誌をずっと編集していました。その頃、日本は経済大国になって、「アメリカ何するものぞ。日本は世界の超大国(スーパーパワー)である」という勢いがありました。経済面では、自動車や半導体が売れて、それがアメリカを席捲していく。アメリカでは製造業が全部頭打ちになって、国を支えてきた中産階級の人たちが、みんなそろって苦しんでいく。いまのトランプ現象の予兆です。日本企業が脅威だと言われ、日米貿易摩擦といったものが生まれた時代で、当時の日本人は非常に驕っていました。それからしばらくして、私は、そういう天下国家について大きな言葉で議論する「中央公論」から、「婦人公論」に配置転換になったんです。
三島 出版がお金を強く意識するようになったのは、その時代頃からなのかもしれませんね。
河野 そのときに、当時の嶋中鵬二(しまなかほうじ)社長に呼ばれて言われた言葉が、今でも忘れられません。社長のご尊父、嶋中雄作氏が、「婦人公論」を創った人だったんですね。
明治に「中央公論」という雑誌が生まれ、大正年間に「中央公論」の臨時増刊として「婦人問題号」が出て、そこから「婦人公論」が生まれます。明治の近代国家が誕生したにも関わらず、日本の女性たちはいまだに、少しも自由になっていない。選挙権も無かった時代ですし、あらゆる意味で江戸時代の延長のような状況に女性は置かれていた。そこで、これから日本が真の近代国家になっていくために避けては通れない、女性の問題――自我の確立、地位の向上をテーマにした雑誌が創られたのです。
私は新人時代に一度「婦人公論」に配属されました。当時この雑誌は月に40万部売れて、ブイブイいわせていました。でもそのあとのバブルの時代に、「婦人公論」はいかにも旧時代の雑誌だという印象を持たれて、年間だいたい1万部ずつ下げていくかたちで、発行部数が20万部くらいまで減りました。そこへ私は副編集長としていくように言われたんです。
私が社長室に呼ばれたとき、社長は「この雑誌を立て直してほしい」と言いました。私はそのとき、「儲かる雑誌にしてほしい」という言葉が続くのかなと思ったんですが、社長からは全然違う言葉が出てきたんです。
「きみが入った頃の「婦人公論」は部数が40万部で、とてもいい雑誌でよく売れて会社に貢献してくれたが、残念ながら今はそういうふうになっていない。そこで、君に頼みたいのはこういうことだ」と。「40万部売っていたときの編集長は、いまの女性たちのテーマを見事なまでに汲み取って、売れる雑誌をつくった。あのときの編集長は、女性に対する好奇心は非常に旺盛で、色々なテーマを見つけ出した。ただ、彼に欠けていたのは女性に対する敬意である。私はそれがとても残念だった。日本の女性たちの解放を目指して「婦人公論」を創った父にあったのは、女性に対するリスペクトの気持ちだった。きみにはぜひ、その気持ちを持って編集部にいってほしい」。短時間でしたが、こういう話をされたんです。
三島 すごいですね。
河野 それは、びっくりしました。40万部が20万部に下がった、広告がたくさん入る雑誌にしてくれ、「婦人公論」という誌名を今風のカタカナ名に変えたり、判型を大きくしてビジュアルに訴える恰好にして、もっと儲かる雑誌にしてくれ。そういう言葉が続くのかなと思ったら、社長は全然違う言葉を吐いた。
「婦人公論」は、日本の女性の幸福を実現するための雑誌、というところに拠って立ってきたのであり、その志をもう一回、いいかたちで現代の女性に届けてもらいたい。そうなれば必ず、いまの女性たちは自分たちに切実な問題を考える雑誌として、婦人公論に手を伸ばしてくれるはずだ。社長は、そういうことを語りたかったんだと私は解釈しています。
そういう言葉を経営者に言われて異動先に送り込まれたとき、私はこの会社に入って本当に幸せだなと思ったんです。お金を儲けることも大事だけれど、クリエイティブなことや理想やロマンを追うのもまた、こういう仕事の喜びであり意義であるということを、そのとき叩き込まれたような気がしました。
先人からのヒントを受け継ぎ、いまの時代のなかで考えていくこと
河野 それから数年経って、私は編集長として「婦人公論」のリニューアルをやりました。その内容は、判型を大きくしたり、表紙を写真にしたりというもので、先の社長の言葉とは一見真逆のように思われるかもしれません。でも、私のなかでは全く矛盾していません。社長に伝えられた志をいまの出版界でどういうふうにかたちにしていくか、と考えたときに見えてきた答えがそれだったんですね。
メールマガジンを毎週書きながら、昔話や自分の手柄話を書くつもりは全くありませんでした。ただ、自分に影響を与え、自分を勇気づけてくれた先輩の言葉、出版のDNAというのかな、やはりそれを、いまの人たちに伝えていかないといけないなと思っていました。それは、金科玉条のようにその通りやれば上手くいく、というものではなくて、その魂を各人がどういうふうに自分の頭のなかで咀嚼して答えを出すか、ということです。私は私のやり方でやってたまたま上手くいった。もしかしたら失敗したかもしれません。昔の人たちは、その時代その時代に似たような壁にぶつかって、悩み、考え抜き、乗り越えてきた。そのことは僕らにとって遠い話ではないんです。
あのときの5分か10分の異動の通達に込められたメッセージによって、私は大きな教育を授けられたと思っています。だから、きょうここに来られている編集長の方々で、せっかく出版社に入ったのに面白いことを少しもさせてもらえない、こんなはずではなかったと思ったらさっさと見切り付けていいぞ、と。大っぴらには言いませんけど、内心ではそう思っています(笑)

「言葉」そのもののなかに託された役割
河野 最新号の『考える人』で「ことばの危機、ことばの未来」というテーマを設けたのは、去年の後半くらいから「言葉」ということをすごく意識せざるを得ない状況が日本でも世界でも生まれてきていると感じたからです。例の「保育園落ちた日本死ね!!!」もそうですが、強烈な挑発の言葉がインパクトを持って伝わっていく。一方で、ヘイトスピーチが問題になり「土人発言」なんてものも飛び出してくる。
世界を見渡せばイギリスのEU離脱の一連の流れを見ていても、必ずしも正しいことを言っている人の言葉が浸透していくわけではなく、あきらかに事実に反していても強いインパクトを持ち感情に訴える言葉が人々を揺り動かし、そちらに現実の流れを引っ張っていくということが起きています。それが最たるかたちで現れたのが、アメリカ大統領選だったと思います。別にアメリカの国民が愚かだということを言いたいのではなくて、いま「言葉」というもの自体にある種の危機が訪れていると思うんです。「ポスト・トゥルース(ポスト真実)」の政治状況だといわれ、「オルタナティブ・ファクト(もうひとつの真実)」とか「フェイクニュース(偽ニュース)といった流行語がまことしやかに飛びかっているありさまです。ではそれをどうやって克服していくのか。
結局は、「言葉」そのもののなかに託された役割があるはずで、「ことばの危機」はやはり「言葉」自身が修復していく他ないわけなんです。「こういう言葉に支配されているのはおかしいぞ」と再び言葉によってそれを正していく。そこから新しい流れが出ていくんだろうと思います。
三島 はい。
河野 ですが、一方で言葉というのは生き物ですから、いまの人たちがおもしろいと思って使っている言葉、いまの我々の感覚にフィットした言葉が生き残っていくんです。それはもう古代からずっとそうだったはずで、どの言葉遣いが正しくて、どれが間違っているという話ではないはずです。世につれ、人につれ、言葉はうつろっていく。規範によって縛られるものでもない。
言葉のダイナミズム、言葉の「動的平衡」のあり方も興味深いと思ってこの特集を組んだのですが、やはりそういう関心を共有していた方が多かったみたいで、とても反響がありました。
作家の人たちの言葉にすごく期待している
三島 『ちゃぶ台vol.2』のなかで、なにもない藪を数年かけて機械をいれずに自力で開墾した農家さんを訪ねた特集があるのですが、農家さんの話を聞いていると、ゼロから耕していって、それこそなんの保証もない、ちゃんと芽を出して野菜になっていくのかわからないという状態で畑を耕す行為と同じことが言葉の世界でもやっぱり求められているんだなということを感じたんです。
ぼくは同業者よりも農家さんとか、もう一度ゼロからいろんなことをやろうとしている方々からこの数年間励みをもらっていて、自分もそんなふうに出版のフィールドでやっていこうとしているのですが、河野さんはいまの時代、これからの突破口をどう開いていくべきだとお考えでしょうか。
河野 私は時代時代にそういう突破口を開く役割を担ってきた人たちが有名無名を問わずたくさんいたと思うんですね。ただ自覚的にそういう役割を担っている一群の人たちがいると思うんです。
端的に言えばものを書く人たちの言葉(作詞家を含めて)にすごく期待しているところがあります。たとえば、今号の『考える人』にも登場していただいた武田砂鉄さんという若い書き手がいますが、彼は「紋切型」の言葉を茶化しながら、我々の硬直した思考法を解きほぐしている。これもひとつの突破口、関節外しとしてあるんです。
踊りやスポーツのパフォーマンス、アートの世界が、言葉を超えた、まだ言語化されていない感性の世界を見せてくれる場合もありますよね。それも面白い。
もっと楽しくやればいい
河野 最近でいえばアニメ映画で『この世界の片隅に』がすごくヒットしていますよね。あの主人公の浦野すずという少女の個性、それから周りの人たちがそれに応じながら見せていく世界。あれは言葉の力以外のなにものでもないですね。
あの力と、それによって掘り起こされていく、あるいは発見させられる私たちの奥底にある感受性というのは何だろうと思うわけです。
三島 たしかにその通りですよね。
河野 私は自分が恵まれていたなと思うのは高校時代に野坂昭如、五木寛之、井上ひさしという3人の、当時としては若くて、個性も作品もフレッシュな人気作家が次々と出てきたことでした。やはり彼らが突き破った言語空間というのは本当に爽快だったんですね。
当時「うっとうしいなぁ...」と思っていた、お定まりの世界を井上さんは笑いの力で、五木さんは颯爽とジャズと旅の小説を書くことで、野坂さんは饒舌で独特な文体のなかに、人の"原罪"をあぶり出していくような荒業をやってのけたりとか。言葉の冒険をやった人たちが見えやすいところにいたんです。
私はいまも作家たちへの期待はそのあたりに持っています。私たちが言葉とともに生きている限り、言葉を活性化するプロの役割が消滅するはずはないと思っています。
編集部からのお知らせ
「本屋さん、あつまる。」
たのしい本屋さんが渋谷PARCOにやってきた!
期間 2020年2月22日(土) -2020年2月24日(月)
場所 渋谷パルコ8F・ほぼ日曜日 (アクセス)
時間 10:00〜21:00
入場料 無料
今回のイベントでは、周防大島のはちみつやジャムなども「ミシマ社の本屋さん」で販売いたします! 詳細は下記になります。
島のはちみつ【タカノスファーム(周防大島)】
島のはちみつ3種セット【タカノスファーム(周防大島)】
島のはちみつイチジクジャム【タカノスファーム(周防大島)】
島のはちみつりんごジャム【タカノスファーム(周防大島)】
島のはちみつウメのジャム【タカノスファーム(周防大島)】
島のはちみつうめシロップ【タカノスファーム(周防大島)】
島のふりかけ【タカノスファーム(周防大島)】
STOMACHACHE. ×中村農園エコバッグ(ブラック)【寄り道バザール(周防大島)】
そのまま食べれる 『ひじっ好いりこ』【寄り道バザール(周防大島)】
トマトジュース【みやた農園(周防大島)】
プレミアムみかんジュース(極早生)【森川農園(周防大島)】
かりんとう【養鶏家・小林さん(周防大島)】
無農薬レモン【石原農園(周防大島)】
お米1合【白山米店(東京・自由が丘)】
栄福寺てぬぐい【栄福寺(愛媛・今治)】