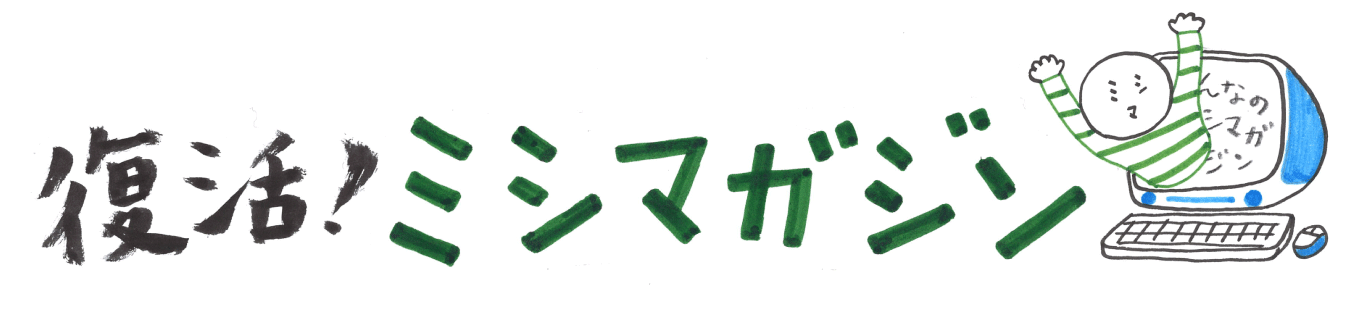第30回
『味つけはせんでええんです』発刊記念
中島岳志先生による「土井善晴論」
2023.10.13更新
10月20日(金)、いよいよ、土井善晴先生の新刊『味つけはせんでええんです』が発刊となります!
「なにもしない」料理が、地球と私とあなたを救う。私たちの生活をずっと支えてくれる、土井先生の料理の思想の真髄が詰まった、一生ものの雑文集です。
本書の発刊を記念して、本日のミシマガでは、政治学者の中島岳志先生による「土井善晴論」を再掲いたします!
土井先生と中島先生はこれまで、『料理と利他』『ええかげん論』という2冊の共著を上梓されました。コロナ下に、あらためて「私たちにとって家庭料理とは何か?」を探り、圧倒的支持を受けたお二人の対話。そのなかから、中島先生が「いまなぜ、土井先生の思想が大切なのか」についてお話しくださった部分をお届けします(本対談は、2021年1月9日に行われました)。
土井先生の最新の思考『味つけはせんでええんです』とあわせて、ぜひお楽しみいただけましたらうれしいです。
(構成:角 智春)
なぜ、一汁一菜は念仏なのか?
土井さんの発言で、私が最近注目しているものがあります。それは、『月刊住職』2020年12月号に載った土井さんの文章のなかの「一汁一菜は念仏だと思います」という言葉です。土井さんは、釈徹宗さんとの対談でも「一汁一菜は「南無阿弥陀仏」だと思うんです。[・・・]味噌汁は、それこそ仏さんの掌に乗っているようなもので、人間の力でおいしくもまずくもできません」と言っています。
なぜ土井さんは、一汁一菜や料理を「念仏」だと考えているのか。この言葉には、土井さんの料理論のエッセンスが込められていると私は思います。
「南無阿弥陀仏」は仏教における浄土門の念仏です。直訳すると「阿弥陀仏に帰依します」となります。「念仏を唱えると、往生して極楽浄土に行ける」と一般的に説かれたりもしますよね(のちほど、この解釈についても考え直してみましょう)。念仏と料理の問題に近づくために、まずは土井さんと家庭料理の出会いから話をはじめます。

「家庭料理は民藝や」
土井善晴さんを語るうえで欠かせない人物は、お父様の土井勝さんです。家庭料理の第一人者として知られる方です。土井善晴さんは、高校生のときに料理の道に進むことを決心しました。しかし、父の勝さんを継いで家庭料理の世界に入ろうは思っていなかったそうです。
土井善晴さんは大学に入ると、1年休学をしてスイスのローザンヌで料理の修行をし、帰国後は、大学に通いながら神戸のレストランで働きました。大学を卒業すると、こんどはフランスに渡航します。「和食の家庭料理」という土井さんのイメージとはかけ離れた経歴で、すこし驚く方もいるかもしれません。
フランスで土井さんが見たのは、世界のトップクラスの料理人たちが、ミシュランの星をとるためにしのぎを削っている姿でした。若い頃の土井さんは、自分もかれらの仲間入りをして、名のある料理人として活躍したいと強く願ったそうです。帰国してからは、京都の「瓢亭」の料理長に「仕事をさせてください」と懇願し、大阪の「味吉兆」の新店舗で働きました。一流の料理人になって、パリで日本料理屋をオープンさせることが当時の夢だったといいます。
そんなとき土井さんは、父の勝さんから料理学校を手伝ってほしいと頼まれました。一流の料理人を目指していた土井さんは、「なんで私が家庭料理やらなあかんの」と思ったそうです。そして納得しきれないまま、父の仕事を手伝うことになります。このとき、土井さんにとって重要な出会いがありました。
それは、京都の河井寛次郎記念館における「民藝」との出会いでした。河井寛次郎は、濱田庄司や柳宗悦とならんで、日本の民藝を切り拓いた人物です。記念館に行った土井さんは、「家庭料理は民藝や」と気づきます。なぜ、土井さんは家庭料理を民藝だと思ったのか。それを考えるために、民藝の本質に接近してみましょう。
民藝という概念をつくった中核の人物は、柳宗悦です。柳は、浄土宗・浄土真宗や時宗から強い影響を受けていました。浄土門において重要な考え方は、「自力」に対する「他力」の重視です。自分の力でなんでもやれるという発想は、人間のさかしらなはからいであり、思い上がりである。自分の力では及ばないものがあると知ったときにやってくるのが、仏の力(阿弥陀の本願)としての他力です。
他力本願というと「他人まかせ」と捉えられることもありますが、本来はそうした通俗的語用とはちがって、他力は人間が及ばない仏の力のことです。民藝の世界は、ここに美を見出しました。「自分の力で美しいものをつくろう」「アートを作ろう」という作為ではなく、無名の人たちがつくった、日常で使う(ご飯を食べる、お茶を飲む・・・)ための道具のなかに、自力を超えた他力の美が宿る。柳はこれを民藝の「用の美」だと考えました。
土井さんはこういうふうに言っています。
日常の正しい暮らしに、おのずから美しいものが生まれてくるという民藝の心に触れたとき、「ああ、これって家庭料理と一緒や、家庭料理は民藝なんや」という確信が初めて持てた。そう捉えたら、「これはやりがいがある世界や」と思えるようになりました。
家庭料理や民藝は作為に基づくのではなく、家族に食べてもらうため、日常で使ってもらうために毎日淡々とつくられているものですね。そういうものに、はからいを超えた美しさが宿る。これが「家庭料理は民藝や」という境地です。
おいしさや美しさを求めても逃げていくから、正直に、やるべきことをしっかり守って、淡々と仕事をする。すると結果的に、美しいものができあがる。
これは、土井善晴の料理論の根本にある概念だと私は思います。
レシピという設計主義を超える
私がとても面白いなと思うのは、レシピという設計主義を超えようとする土井さんの姿勢です。土井さんはたしかに、テレビの料理番組に出演し、料理のテキストも作っています。そこにはつねにレシピが出てきますが、しかし土井さんは「あんまりレシピにこだわりすぎてはいけない」と言っているのです。
ひとつひとつの料理で、どの粗さで混ぜるのをやめるか考えはじめたら、すごくおもしろくなるんです。ポテトサラダでも「ああ、おいしそう!」という時点でそれ以上混ぜたら、不味くなりますから。
一般的なレシピでは、「何回くらい混ぜる」などと書かれていたりしますが、土井さんはその考え方をやんわりと否定します。「ああ、おいしそうやな」というところで止めるのがいい。レシピよりも、私たちがもっているある種の身体的感覚と呼応するほうが重要であり、数値化できないものを身体で感知して判断したほうがいい、と。
「なんとなく気持ちいいな」とか、心地よさとか、違和感のなさとか、そんなふうに、身体が感じることで判断していったほうがいい。
まあ、レシピは設計図じゃありませんから。記載された分量とか時間に頼らないで、自分で「どうかな」って、判断することです。自然の食材を扱う料理には、自然がそうであるように、いつも変化するし、正解はない。というよりも、違いに応じた答えはいくつもあるんです。だから、失敗の中にも、正しさはあるかもしれません。
自然の食材は、その日の天気、獲れてからどのくらい経っているのか、という状況によって大きく変化します。だから、レシピにしたがって厳密に計量しながら料理しても、うまくはいかない。それよりも素材との呼応、つまり、目の前にある素材を見て、自然に沿って料理していくことが重要です。だから、「レシピは設計図じゃない」。料理人からはあまり聞かれることのない言葉かもしれません。
土井さんは、「火の力に任せる」、「混ぜすぎない」、「触りすぎない」、「計りすぎない」とよく言います。私たちが介入しすぎるのではなくて、いろいろなものに任せることが重要なのではないか。そうして生まれる味のむらこそが、おいしさになります。
味噌に任せればレシピの計量は不要です。
任せることやゆだねることが、土井さんの重要な料理論です。私はこれを、「与格」の考え方だと思っています。
私が「器」になる、与格的料理
「与格」は、インドのヒンディー語にある文法構造です。私たちはふつう「主格」を使って話します。「私はご飯を食べます」、「私は今日〇〇をしています」というふうに。「〜は」「〜が」ではじまるのが主格の構文です。これに対して、与格は「〜に」ではじまります。たとえば、これは「私はとてもうれしかった」というヒンディー語の文章です(写真)。直訳すると、「私に大きなうれしさがやってきて、とどまっている」となります。
 私はヒンディー語を習ったときに、与格は「行為が自分の意志に還元されない場合」に使われると教わりました。たとえば、「私は風邪を引いた」という文は、ヒンディー語では与格で表されます。風邪を引こうとみずから思う人はあまりいませんよね。私たちの意志とは違うものによって私たちの行為がなされているので、与格が使われるのです。
私はヒンディー語を習ったときに、与格は「行為が自分の意志に還元されない場合」に使われると教わりました。たとえば、「私は風邪を引いた」という文は、ヒンディー語では与格で表されます。風邪を引こうとみずから思う人はあまりいませんよね。私たちの意志とは違うものによって私たちの行為がなされているので、与格が使われるのです。
私はインドで暮らしながら、与格って重要だなと思っていました。近代人はどうも、「私が」という主格的な世界観のなかにいますが、与格の構文では「私に」なにかがやってきてとどまっている。私が「器」のような存在になっています。
じつは、与格はヒンディー語だけではなくて、世界中の言語の古い文法によく含まれていた構造です。日本語にも残っています。たとえば、「私には〇〇だと思える」という言い方。「私は思う I think」と「私には思える」とでは、ニュアンスが違います。私に思いが宿ったり、私のなかを思いが駆け巡ったりするところが重要です。
私は、土井さんの料理は「与格」的なものだと思っています。主格は自力の世界なのに対し、与格は他力の世界です。自分の力を超えたところからやってくるものを受けとめる「器」のような存在として、私があり、そこから料理や民藝が出てくる。
人間業ではない料理ーー「塩むすび」に込めた思い
土井さんは、味噌造りのマイスターの雲田實さんについて、こう言っています。
「良き酒、良き味噌は人間が作るものではない、俺が作ったなどと思い上がる心は強く戒めなければならない」と口癖のように言う実直な人柄
味噌作りのプロが「味噌は自分がつくったものではない」とおっしゃるわけです。私は、発酵というものは思想的にとても重要だと思っていますが、土井さんは最近もこう発言しています。
「このうまい酒をつくったのは俺だ」という思い上がった考えは強く戒めなければならない。
まずは、人が手を加える以前の料理を、たくさん体験するべきですね。それが一汁一菜です。ご飯とみそ汁とつけもんが基本です。そこにあるおいしさは、人間業ではないのです。人の力ではおいしくすることのできない世界です。みそなどの発酵食品は微生物がおいしさをつくっています。ですから、みそ汁は濃くても、薄くても、熱くても、冷たくても全部おいしい。人間にはまずくすることさえできません。そういった毎日の要になる食生活が、感性を豊かにしてくれると、私は考えています。
人間業ではない料理。この究極的なあらわれのひとつが、2014年10月30日に放送された、NHKのきょうの料理の「塩むすび」の回です。土井さんファンのなかでは「神回」とも言われた放送です。ふつうは、料理番組で塩むすびの作り方は紹介しないですよね。土井さんは、この回に強い思いを込めていたのではないでしょうか。手で米に触れる。ほどよい大きさ、固さに整える。塩加減を整える。私たちにできることは、この「整える」ということだけであると、土井さんは言います。そこに、おいしさがおのずからあらわれる。そのことによって、心が落ち着く。
本当のおいしさは安心感を伴うのです。
これが、今日の対談のタイトルである「料理はうれしい、おいしいはごほうび」につながります。料理は、私が喜ぼうとしてやるものではなく、私に「うれしさ」が宿る与格的なものです。そして、おいしさはごほうびとしてやってくるものであって、私がつくりだしたものではない。
念仏とはなにか?
ではなぜ、「一汁一菜は念仏」なのか。
そもそも、念仏とはなんでしょうか。吉本隆明は『最後の親鸞』のなかで、念仏と親鸞の問題を考えました。さきほど私は「念仏を唱えれば浄土に行ける」という考え方に触れましたが、親鸞はこの考え方を否定したはずだと吉本は指摘します。「念仏を唱えれば、浄土に行ける。だからみなさん念仏を唱えましょう」という考え方は、「念仏」と「浄土に行くこと(往生)」に因果関係を認めてしまいます。すると、浄土真宗において一番大切なものである念仏は、他力ではなく自力の世界に取り込まれてしまう。だから、親鸞は「念仏を唱えれば浄土に行ける」という考え方を認めなかったというのです。吉本は、念仏とはなにかという問題が残ると言います。
涙と念仏
この問題と、土井さんの「一汁一菜は念仏である」という考え方は強くつながっていると思います。私は、念仏と他力の関係について考えていたとき、こんな経験をしました。
私には息子がいるのですが、息子は生後数カ月で迎えた初めての正月に高熱を出しました。大晦日の夜からとつぜん咳き込みはじめ、熱が39度まで上がってしまった。夜間救急に連れていくと、そこは急病の人で溢れる野戦病院のような状態で、私たちは1時間半ほど待ってからやっと診察を受けました。息子は入院しないといけないような容態でしたが、大晦日なのでできない。「薬を出すので家で様子をみて、急を要するときは救急車を呼んでください」と医者に言われ、帰されてしまったんです。不安に苛まれながら徹夜して、年が明けました。しかし、息子の熱は全然下がらない。お乳も全然飲みません。妻と私は、どうしようと狼狽えながら、息子を抱きかかえることしかできませんでした。
数日間そのように過ごしたあと、1月4日の朝に、息子の熱がすーっと下がりました。咳も止まってきて、顔色がすこしよくなったのでお乳をあげてみると、ごくごくごくっと飲んだんです。ああよかった、なんとかなったと思いました。私はほっとして、部屋の窓を開けて新しい空気を入れました。朝の日差しがキラキラと家に入ってきました。
そのとき、私は張り詰めていた気持ちが解けたのか、ふと鼻歌を歌いました。無意識に選曲されたのは、天才バカボンの歌でした。「青空の梅干しにパパが祈るとき・・・」という詞です。これを口ずさんだとき、突然、私の目からザーッと涙が出てきて止まらなくなりました。しゃくりあげて泣く私に妻が驚いて、どうしたのと訊いてきたのですが、わからない。涙が止まりませんでした。
あとから、私はこの涙の理由がふっとわかりました。私は数日間、沈黙のなかで祈っていたんだと気づいたんです。「青空の梅干しにパパが祈るとき」。私は、言葉にならない祈りをずっと発していました。そして、それに「祈り」という言葉が与えられたとき、私の目からザーッと涙が落ちてきた。私は、そうか、これが念仏の構造かと思いました。
無力に出会ったとき、他力がやってくる
浄土真宗は「祈り」という言葉に自力が含まれると考えるので、この言葉を使いません。たしかに、「〇〇大学に合格させてください」とか「宝くじが当たりますように」という祈りは、自力的なものですよね。しかし、本当の祈りは言葉にすらならない。「息子を助けてください」と言うこともないまま、熱を出したかれを抱えておろおろしているとき、私は無力と出会っている。このときに私にやってきたものが、他力としての念仏でした。意思を超えて自分のなかからどんどん出てきてしまうもの、それが私の涙であり、おそらく親鸞が到達した念仏の境地は、その涙のような念仏だったんだろうと思います。念仏は目的のための手段ではありません。仏の力に促され、自ずから湧き出してくるものです。
「一汁一菜は念仏である」とは、こうしたものではないでしょうか。鈴木大拙の『日本的霊性』には、妙好人の話が出てきます。妙好人は、名もなきふつうの庶民です。南無阿弥陀仏を唱えながら、ずっと畑を耕している庶民。鍬を動かすかれらのひとつひとつの動作は、南無阿弥陀仏そのものです。土井さんの菜箸を持つ手、そして、おにぎりを整える手は、妙好人の鍬のようなものだと思います。これは、自分の力でおいしいものを作るのではなく、おいしさが宿るように、自然に沿って整えていくことが料理であるという考え方につながります。決して「おいしいものを作ってやろう」という意思的なものではありません。料理をやっているとうれしさが宿り、おいしさがごほうびとしてやってくる。だから、「一汁一菜は念仏である」は、土井さんの料理論のエッセンスを捉えたとても重要な言葉だと私は思うのです。
(終)
★土井善晴先生の最新刊『味つけはせんでええんです』