第33回
小山哲×藤原辰史「中高生と考える 戦争・歴史・ウクライナのこと」前編
2024.07.11更新
7月20日、『中学生から知りたいパレスチナのこと』がリアル書店で発売となります。
3人の人文学者が、ガザのジェノサイドを前に、今の「歴史」の学び方・捉え方への痛烈な危機感を抱いて執筆した、「生きるための世界史」の書です。アラブ文学者の岡真理さん、シオニズム運動を生んだ地・東欧の専門家の小山哲さん、ナチズムを研究してきた藤原辰史さんの対話から、パレスチナ―ヨーロッパ―日本をつなげる、まったく新しい歴史観が立ち上がります。
ミシマ社は2022年6月に、小山哲さんと藤原辰史さんの共著『中学生から知りたいウクライナのこと』を刊行しました。ロシアのウクライナ侵攻を受け、ウクライナという地域の歴史をほとんど何も知らなかったという反省から、本書では「小さな国・地域・民を見過ごすことのない歴史」の学び方を考えました。
あらゆる人が、今起きている暴力と自分を結びつけ、歴史に出会い直すために、この2冊をひとりでも多くの方にお手にとっていただけたらと願います。
*
2022年8月1日、『中学生から知りたいウクライナのこと』の刊行を記念して、小山さんと藤原さんと、イベント「中高生と考える 戦争・歴史・ウクライナのこと」を行いました。『パレスチナのこと』とあわせてぜひお読みいただきた本イベントの記事を、本日から3日間にわたって復活でお届けします。
(構成:角智春)
三島邦弘(司会、以下「三島」) みなさんこんばんは。本日はお集まりいただいてありがとうございます。
本日は、「中高生と考える 戦争・歴史・ウクライナのこと」と題して、小山哲さんと藤原辰史さんにお話しいただきます。会場にはご招待というかたちで中高生の方々も来てくださっています。ありがとうございます。
まず両先生に30分ずつお話しいただき、そのあと、参加者の方々からの質問にお答えいただきます。では、小山さん、藤原さん、よろしくお願いいたします。
 (左:小山哲さん、右:藤原辰史さん)
(左:小山哲さん、右:藤原辰史さん)
ポーランドの専門家がウクライナの歴史を書く理由
小山哲(以下「小山」) みなさんこんにちは。今日はお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。
私は『中学生から知りたいウクライナのこと』の執筆者のひとりで、小山哲と申します。京都大学の文学研究科で西洋史を担当しております。
私自身の専門の研究領域は、ポーランドの歴史です。ちょっと古い、いまから4~500年前の近世と言われる時代のポーランド史を研究しています。
この本にはウクライナのことが書かれているわけですが、なぜポーランドを研究している私がウクライナのことを語ったり書いたりするのか、すぐにはつながらないかもしれません。だけど、歴史を紐解いていくと、この二つの地域には深いつながりがあるということがわかるんです。
私が研究している4~500年前のポーランドという国は、いまのポーランドと比べてかなり大きな国で、その大きな領土の一部分にいまウクライナと呼ばれている国の領域の大部分が含まれていたんです。私は自己紹介するときには「ポーランド史の専門家です」と言うことが多いのですが、自分が研究している時代の領域には今のウクライナにあたる地域が入っているのです。
そういう事情があるので、ウクライナの歴史は私にとって他人事ではありません。
どうして歴史の教科書に「ウクライナ」が出てこないの?
小山 いま私がお話しているようなことは、中学校や高校での歴史の勉強ではあまり出てきません。ポーランドの歴史のなかにウクライナの歴史が含まれているみたいなことって、ほとんど習いません。教科書にもパッとわかるようには書いていないです。
今回、このイベントのために、あらかじめ質問を寄せてくださった方がいらっしゃいます。そのなかに「どうして日本の中学・高校の歴史の教科書には『ウクライナ』がほぼ一度も登場しないのでしょうか?」という質問がありました。
いま毎日、テレビなどでウクライナのニュースが流れています。2月24日に戦争が始まってから、ウクライナのことを聞かない日はないくらいです。なのに、日本の学校できちんと歴史を勉強しても、ウクライナの歴史について中世から現在までずーっとつながったかたちで頭の中にイメージできる人は、たぶんほとんどいないんじゃないでしょうか。なぜそういうことが起こるのかというのは、たしかに大きな問題です。
これにはいろんな理由があります。
ひとつは、教科書を作る仕組みや、教科書の考え方の問題です。たとえば、日本において世界史の授業で教える内容はどのように決められているのか。
それからもうひとつは、日本でウクライナの歴史を私のようにポーランド史の立場から研究するとか、ロシア史の立場から研究するのではなくて、ウクライナにしっかりと足場を置いて研究する歴史家が本当に少ないんです。ウクライナ史の専門家がちゃんとたくさんいたら、たぶん私が出る幕はないでしょう。そういう意味では、私がこの問題について語っている状況は決して好ましいものではありません。
なんでそうなってしまっているのか、というのが、まず最初にお話ししたい問題です。
「日本史」が基本になった授業
小山 文部科学省が定めた学習指導要領には、中学校の社会科の歴史分野で何を教えるべきかということが書かれているのですが、中学校の歴史は日本史が基本で、その日本史に関係のある世界史について教えていく、というかたちになっているんです。それはそれで意味のある歴史の捉え方だし、教え方だと思うのですが、そうなると、ウクライナの歴史は、日本との直接的な関係があまりなかった、という事情があります。
だから、中学校の歴史の教科書を読んでもウクライナは出てこない。いろいろ探っていけば両者には関係があるのですが、おおまかな日本の歴史を語るときにはウクライナに触れなくても語れてしまう。そういうことがひとつ、あるんですね。
「国を主語にした歴史」のなかに居場所がない人びと
小山 もうひとつの問題は、なぜウクライナ史の専門家がほとんどいないのかという話に関わりますが、ウクライナという地域がひとつの国家になったのはすごく最近のことなのです。しかも、自分たちの国家を作るのにものすごく苦労した歴史があります。「主権国家」という言い方をしますが、やっと自分の国のことを自分たちで決めることができる状態になったのは、30年前ほどのこと。ソ連邦が解体してからですね。
それまでは、独立国としてのウクライナではありませんでした。ところが、日本の歴史の教科書の書き方とか、研究の設定の仕方は、概して「国別」になっています。国を主語にした歴史を英語で「ナショナル・ヒストリー」と呼ぶのですが、教科書の書き方は基本的にナショナル・ヒストリーなんです。ドイツの歴史、イギリスの歴史、フランスの歴史、というふうにいいますよね。そのなかで、日本人にとって一番大事なのは日本の歴史、というふうに捉えられる。
だけど、世界には自分の国を持つことができない、あるいは持つのにすごく時間がかかった人たちもいて、その人たちの歴史は教科書のなかで居場所がありません。
ウクライナには、国家ができるはるか以前から、ウクライナ地域の言語を話す人たちがいました。19世紀にウクライナがオーストリアやロシアの支配下に入っていた時代に、自分たちはウクライナ語を話すウクライナ民族だという意識を持つ人たちが増えていって、自分たちの国を作りたいという主張をするようになるんですね。
だけど、それを実現するのにはすごく時間がかかりました。30年前に一度は実現しましたが、いままたこういう状況になっています。
そういう民族は、実は世界にたくさんあります。
私が専門にしているポーランドも、国があった時代と、なくなってしまった時代があります。19世紀、ちょうどウクライナ民族意識ができていくのと同じ時期に、ポーランド民族意識も強くなっていくのですが、このときポーランド人は自分の国を持ちませんでした。18世紀の終わりまでは国があったのですが、ポーランド分割――これは高校の世界史の教科書にも出てきますね――によって国が分割され、周りの国に領土を併合されて無くなってしまいました。
第一次世界大戦が終わったあと、状況が変わってポーランド人は自分の国を取り戻します。同時期にウクライナも独立宣言をしますが、このときは認められませんでした。
こういう問題は世界中で起こってきました。
私たちがウクライナの歴史を学んだり語ったりすることの意味は、ひとつは、「国民」とか「民族」という言葉で学んでいるまとまりが、歴史のなかにいつどんなふうに出来てきて、そのなかでどういう人たちが自分たちの国を持ち、どういう人たちが国を持つことができずに難しい状況に置かれているのか、ということをあわせて学べるということです。

人びとが出会い、ぶつかりあう地域
小山 もうひとつ話しておかないといけないのは、この本のなかで私は中世から20世紀までのウクライナの歴史をほんとうに駆け足で辿っているのですが、そのときに「ウクライナという地域の歴史」を語ります、とくりかえし言っていることです。
「ウクライナ国家の歴史」とか「ウクライナ人、ウクライナ民族の歴史」を語りますとは言っていません。それには意味があります。
先ほどお話したように、ウクライナ人、ウクライナ民族、ウクライナ国民の意識を持つ人たちが自己主張を始めたのは19世紀以降です。
それ以前にも、ウクライナという地名はありました。地名があって、そこに人が暮らしていた。だけど、その人たちは自分がウクライナ人だという意識を必ずしも持ってはいませんでした。それでもウクライナという地域はあって、そこの歴史を語ることはできるんですね。
これはすごくおもしろい歴史で、いろんな方向からいろんな人たちが、ウクライナに流れ込んでくるんです。
あとで藤原さんからお話がありますが、ウクライナと呼ばれる地域はものすごく豊かなところなんです。だから、いろんな人がいろんな方向からやってきました。言語も宗教も文化もみんな違う人たち、さまざまな背景を持った人がやってきて、そこで出会うんですね。
「出会う」と言うとどこかきれいな感じがしますが、いつもきれいなわけではありません。お互いによい影響を与えあうこともあるけれど、衝突し、武器を取って殺しあう関係にもなります。光もあれば影もある。中世からウクライナ民族意識ができるまでのあいだは、そういうふうにして多様な人たちが交わりあう世界でした。
そういう地域としての歴史を語ることはできるし、そう見るべきだと思っているので、私はあえて本のなかでこういう語り方をしています。歴史の教科書にはすごく書きにくいタイプの地域ですね。でも、そこにも歴史はあり、人びとの営みがずっと続いてきたことを私たちは知っておくべきだと思います。
「ロシア文化」の担い手をよく見てみる
小山 研究者の世界においても同じ問題があります。ヨーロッパの東の地域を研究する人たちは、スラブ学という学問のくくりの中にいることが多いのですが、この枠組では最初に勉強する言語がどうしてもロシア語になっちゃうんです。ロシアは領域としてやはり大きな存在だし、文化的にも歴史的にも重要なところです。だから、ロシア語を学び、ロシア語で書かれた文献を読み、ロシアの歴史家や文学者が書いたものを読んで勉強し、彼らと議論する。
一方、ウクライナは、モスクワを中心に見ると、はずれたところに位置しています。ウクライナにはウクライナの文化や歴史があるのですが、それをメインに研究しようという人がどうしても出てきにくい構造があります。
日本では、ウクライナの専門家にどんどん出てきて発言してくださいと言っても、難しいのが現状です。でも、いまこういう状況になってウクライナに関心を持つ若い方が出てきて、現地に足がかりを持ちながら本格的に研究をする人が育っていってもおかしくないと思うし、そうであってほしいと私は思います。
藤原さんがこの本のなかで書いていますが、私たちがロシア人やロシア文化の担い手だと思ってる人のなかに、ウクライナ出身の人はたくさんいます。チャイコフスキーの祖先はウクライナ・コサックでしたし、ヴァーツラフ・ニジンスキー、文学者ニコライ・ゴーゴリといった人たちはウクライナで生まれました。ロシア音楽や文学やバレエの人だと捉えられていても、よく見ると出自はロシアに限りません。
人類の文化、歴史のなかですばらしい貢献をした人がウクライナという地域からたくさん出てきています。このこと自体、私はすごくおもしろいことだと思うんです。いろんな文化が混じりあう多様性をもった社会から、普遍的な次元で活躍する人が出てくるということは重要だと思います。
なんで年号を暗記しなきゃいけないの?
小山 すでにたくさんお話ししましたが、いまお答えしておきたい質問がふたつあります。
ひとつは、「歴史は、単語や年号を覚えるだけの授業が苦痛でした。先生方はどうやって歴史を好きになったのですか?」というご質問です。これは、私と藤原さんの二人に対する質問ですね。
あの・・・、私も年号を覚えるのは苦痛でした(笑)。
藤原辰史(以下「藤原」) 僕もそうでした。
小山 そりゃそうですよ、全然楽しくないですから。しょうがなく、語呂合わせで暗記したりしていました。いまでも覚えてるものもあります。「坊さん飛んでく、アヴィニョン」とか。
藤原 なんですかそれは。
小山 1309年の、教皇のバビロン捕囚です〔注:この年にローマ・カトリック教会の教皇座がローマからアヴィニョンに移されました。中世後期に教皇の権威が衰退しつつあったことを示す出来事とされています〕。
藤原 (笑)
小山 ただ、歴史の勉強では、いろんな出来事を時間軸の上に並べて考えなきゃいけません。たとえば、アメリカ独立革命とフランス革命だと、アメリカ独立革命が前に起こって、フランス革命がそのあとに起こる。何年かを正確に覚えていなくても、どっちが先に起こって、あとの出来事に影響を与えたのか、ということはけっこう大事なんですよね。
だから、年号を暗記するのは自分のなかに「座標軸」を作るためだと考えたらいいと思います。そうすれば、歴史に関わる本を読んだり映画を観たりしたときに、座標のなかに置いて考えることができますよね。それができるようになると、相互の関係がつながって見えてきてすごく面白いんです。
座標軸を作るところまではちょっと苦痛なんだけど、いっかい自分のなかに出来てしまえば、そのあとは楽しい世界が待っている。だから、我慢して暗記してみるのもいいかなと思います。

戦争は本能によって起こるものではない
小山 それから、この質問にも触れておこうと思います。
「歴史をふりかえれば、人が死ぬ、土地が痛む、食糧、経済危機が起こるなど、戦争をしたら絶対にいやなことが起こるとわかっているのに、それでも人が戦争することをやめないのはどうしてだと思いますか?」。
ウクライナでの戦争のニュースを見るとつらいですよね。なんでこんなことが起こるんだろうと思うじゃないですか。しかも、過去にたくさんの戦争があって、「こんなひどいことがあった」という歴史を私たちは勉強してきたはずです。それなのにまた戦争が起こってしまう。
それはなぜか。私も、はっきりした答えを知っているわけではありませんが、つねづね考えていることがあります。
たとえば、こんなことを言う人がいますよね。「人間というのは、本能で戦うことを運命づけられている生き物。生物として闘い合うようにできている」と。
私は、それはちがうのではないかと思っています。
私は生物学者ではないので、専門家としてこれを科学的に根拠づけることは難しいのですが、さきほどの質問を読んだときに、大岡昇平という小説家のことばを思い出しました。若い世代の方は名前を知らないかもしれませんが、私にとってはとても大事な作家の一人です。
大岡は、アジア太平洋戦争のときに従軍します。1909年生まれですので、戦争中はすでに三十代でしたが、召集を受けてフィリピンに送られました。そこで戦火をなんとか生き延びて、米軍の捕虜になったのち、復員して帰ってきます。
大岡は自身の戦争体験をふまえて、『野火』『俘虜記』『レイテ戦記』といった衝撃的な作品を残しました。兵士として戦場に身を置いた経験のある彼は、『戦争』(岩波現代文庫)という本のなかで、こんなことを言っています。
この戦争というものは人間の本能の攻撃性によって起こされたためしってのは一度もないわけですね。未開的な部族間の争いだってそうです。ことに近代戦になると、必ず作戦計画を練り、自分の方の軍事力と相手方の軍事力を計算し、そこで初めて開戦ということになるんであって、その決断というものは、国家の最高組織によって行われるわけですね。その決断する国家の組織というものは、本能によって導かれているのではなくって、理性と計算によって導かれるんです。
攻撃性という本能によって戦争が起こるという理論が出てくるのは、実際はそろばんをはじいてやることを、攻撃性という個人の心理の中へ擬態的に持ちこんでごまかすんです。結局軍産共同体には、戦争とか、攻撃性とかいって、いつも人民を刺激状態におくことが利益だからですよ。その利益に合致している学者、イデオローグ、煽動者の理論なんですね。
私は大岡のこの考え方に強く共感します。戦争は本能によって起こるものではないです。戦争は、国家の指導者がやると決めてやるものなんですよね。
ですから、考えるべきなのは、どういうときに国家の最高組織が戦争をやると決めるのか。どういう状況でそれが起こるのか。それから、そういう状態にならないようにするために国民は一体どういう態度を取るべきなんだろうか、ということだと思います。
戦争をすることをやめるためにどうしたらいいか。簡単には答えは見つからないかもしれません。しかし、どういう人を指導者に選んだらいいのかを考えることはできるでしょう。少なくとも日本の場合、私たちは選挙で指導者となる人たちを選びます。選ぶのは、憲法で主権を認められている国民ですので、少なくとも今の日本の制度を前提として考える場合には、国民として、私たち一人ひとりが何を考え、何を議論し、どうふるまったらいいのかということが問われていると思います。
ほかにもとても大事な質問をいろいろいただいているので、またあとで、時間の許すかぎりお答えできればと思います。
三島 小山さんありがとうございました。では、藤原さん、よろしくお願いします。
(中編につづく)


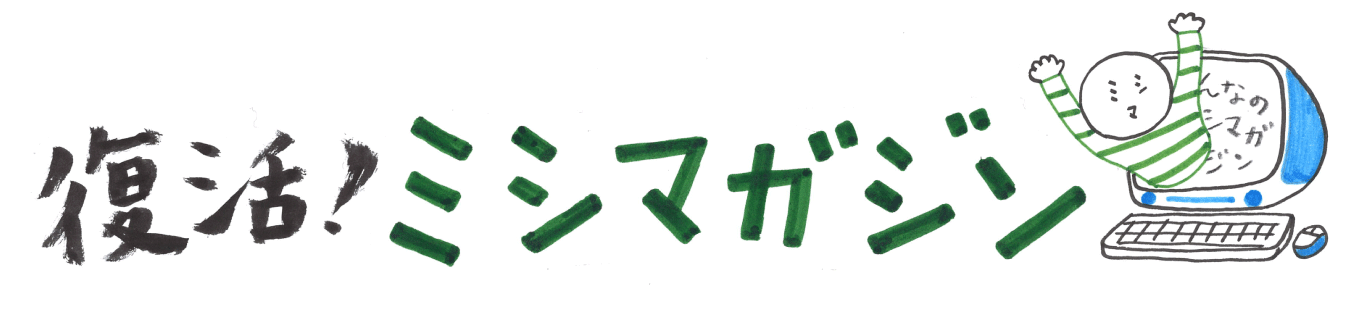



-thumb-800xauto-15055.png)



