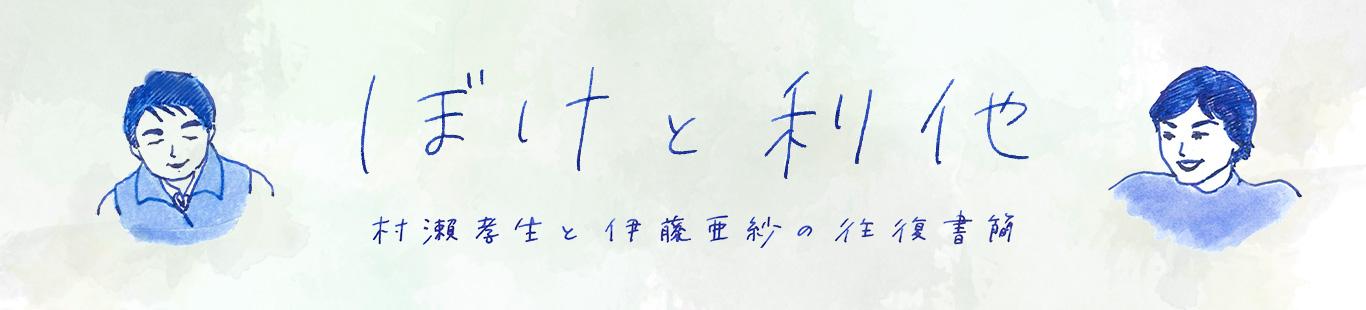第2回
アナーキーな相互扶助(伊藤亜紗)
2020.09.17更新
答えを手放す。
さいきん読んだ文章 (※)のなかで、ブレディみかこさんが、アナキズムの話をされていたことを思い出しました。ケアっておそらく本質的にアナーキーなことなんでしょうね。
※ブレディみかこ×栗原康「コロナ禍と"クソどうでもいい仕事"について」『文學界』10月号、文藝春秋、212-222頁
ブレディさんがあげていたのは、英国がロックダウンしたときの相互扶助の光景でした。ブレディさんの住むブライトンでは、一人暮らしのお年寄りや自主隔離している人に食品を届けるネットワークを作るから電話をしてください、と連絡先が書かれたチラシが郵便受けに入っていたり、自宅の壁にチラシを貼ったりしている人がいたそうです。アナキズムというと、暴動を起こして一切合切破壊するようなイメージがありますが、相互扶助のために勝手に立ち上がるという顔もある。政治が右往左往したりしているときに、組織とか利害とかと関係ないところで、他人をケアするために、できることを生き生きとやり始める人たちがあらわれた、と。
村瀨さんからうかがう介護の話は、いつもアナーキーだなと思います。計画を立てながらも「計画倒れをどこか喜ぶ」態度しかり、声をあげて叫ぶおばあちゃんに般若心経を、おじいちゃんにおりんを渡してとっさのセッションをさせてしまう即興性しかり。場の瞬発力によって、介護する人からも、介護される人からも、想定外のものが引き出されてしまい、ともに負けることで介護らしき出来事が成立しているような面白さがあります(介護のプロに対して、なんだか失礼な物言いですみません笑)。
荒ぶるぼけのある人のほうが実は介護しやすいんだ、というお話は目からウロコでした。こちらの思い通りにならない「抗い」という反応があるからこそ、恐れ慄いて、相手を尊重したと思えるわけですね。(この「思える」というところがポイントですね。これについてのちほど書きたいと思います。)
全盲の女性と、片足を切断した男性に対談をしてもらったことがあります (詳しくはこちら)。全く異なる身体条件をもった二人が意気投合したのも、「抗い」の問題でした。女性は盲導犬と、男性は義足とともに生きているのですが、盲導犬も義足も、完全に自分の思い通りにはならない、抗う存在なのです。盲導犬が買い物の途中でストライキしちゃうこともあるし、義足も自分の足のように動いてくれるわけではない。でもその「こちらの都合を聞いてくれるものではない」感があるからこそ、信頼関係を結べるのだそうです。
よりあいの森にいるお年寄りからすると、そもそもよりあいの森にいる理由がないというお話がありました。盲導犬もたぶんそうなんですよね。少なくともその女性はそう考えていました。それで、たまたま来てくれたその盲導犬が「これでよかったなあ」と思えるにはどうしたらいいんだろうと考えているうちに、盲導犬のほうが「立場的に彼女と対等かちょっと上」になっていった。でも、そうやって犬を尊重しようと思ううちに、彼女は「私の人生が豊かになった」って言うんです。彼女にとっての盲導犬は、自分をケアしてくれる存在である以上に、ケアすべき存在であることが重要なのだと思います。ケアすることはケアされることなのでしょうか(ここも気になっているポイントです)。
「ここにいる理由」が問題になるのは、実は義足の場合も同じようです。その男性は「義足がどういう歴史を背負っていまここに来ているのか、ということを理解しようとしてあげないと、使いこなせない気がした」と語っています。本当は、歴史なんか知らなくたって使えるように、作られているはずです。でもその男性は、物理的な構造や機能をマニュアル的に理解するだけでは、それを乗りこなすのに必要な「信頼」を生み出すことができないと思った。だから、自分のあずかり知らないところにある義足の「大きさ」を実感するために、歴史も知ろうとしたのだと思います。二人の様子は、盲導犬や義足とうまくつきあうために、相手のうちにある抗いの要素を積極的に見出しているようにも見えます。
対談は二時間以上続いたのですが、二人の会話は最終的に「ママ友のおしゃべり」みたいになっていました。なるほど、子供とは、その存在理由の一旦を自分が担っている、にもかかわらず/だからこそ自分に抗いもする存在です。二人にとっては、盲導犬や義足が、まさにそのような存在だったということです。そしてママが友になってしまえば愚痴も言える。「ウチの子はかなりやんちゃで・・・」。夜遅くまで話はつきませんでした。
この話のポイントはやはり、「思える」というところだと思います。抗いがあるからこそ「相手を尊重できる」のではなく、「相手を尊重したと思える」と村瀨さんが書いているところ。この盲導犬がたまたま自分のもとにやってきた偶然性に向き合うことや、この義足が作られるまでの長い歴史を知ろうとすることも、自分の思惑を超えた「抗い」の要素を自ら探し求めている点で、「思える」と同じこころの動きだと思います。
わたしが7月の対談でつぶやき、その後村瀨さんが改めて拾ってくださった「利他の問題を考えるときに、お年寄りとかかわることは究極な感じがする」という話は、ここに直結していると思います。
利他は、「自分がする行為の結果は自分には分からない」ということから始まるのではないか、というのがさいきんわたしが考えていることです。困っている人に手を貸すとか、苦しんでいる人をなぐさめるとか、そういった分かりやすい善行には、昔から警戒心があります。「自分はこんなに善いことをしてあげているのだから、相手が喜んで当然だ」と思ったら、それは相手を自分にとって都合のいい道具に仕立てて、支配しているだけだからです。その意味で、利他には「自分が勝手にやってるだけなのかも」という過剰さの自覚が必要です。そして、だからこそ管理を逃れるアナーキーなものなのだと思います。
ところが、村瀨さんがあげた二つ目のタイプ、つまり「荒ぶりのないぼけの人」を介助する場合には、この「思える」が揺らいでくるわけですよね。強い抵抗がなく、思いどおりになってしまうから、自分の行為の過剰さを自覚しにくくなってしまう。手応えがなくなると、相手との距離が測れなくなって、何だか相手が自分の一部になったような錯覚を覚えてしまいそうです。完全に以心伝心の犬。生身の足と同じように動く義足。一見すると楽なようにも感じますが、そこにはケアという関係は生まれようもないということに気がつきます。
ブレディさんがあげていたブライトンのアナーキーな相互扶助の光景は、新型コロナウイルスの危機という共通の敵を前にした、災害ユートピア的な状況だからこそ成立したものだと言うこともできます。一時的な非日常だからこそ、人々は自分の行為の結果がどうなるかを顧みないまま、過剰に行動することができた。でも、よりあいの森で介護にあたる人たちにとっては、それが日常なわけですよね。「荒ぶりのないぼけの人」と継続して日々をすごすということを想像すると、そこにどうしたら利他的な「ケア」という関係が成立しうるのか、深い悩みに入ってしまいそうです。
だからこそ、村瀨さんの「協力を請う祈り」には、深く引き込まれました。「本当は今、あなたの元に行くべきなのですが、荒ぶるぼけが僕を呼んでいます。お許しを」。どうしても荒ぶるぼけのお年寄りのケアを優先せざるを得ないときに、後回しにされる荒ぶらないぼけのお年寄りに向かって、村瀨さんは目をつむってそう祈る、と書かれていました。
これはつまり、荒ぶらないぼけのお年寄りに、ケアされる側ではなくケアする側のほうに出てきてもらっている、ということなのかな、と思いました。確かに物理的には、排泄が遅れたり、食事を待たされたり、荒ぶらないぼけのお年寄りはケアをされていない状況にあります。けれども、その「待ち」こそが、荒ぶるぼけのケアを可能にしている。その意味では、荒ぶらないぼけのお年寄りは、村瀨さんと同じ介護者の立場にいるようにも見えます。もちろん、それは村瀨さんの一方的な祈りであり、過剰な「思える」なのかもしれません。けれども、そうやって協力を請うことによって、村瀨さん自身も、荒ぶらないぼけのお年寄りをケアすることが可能になっているようにも見える。ケアする側になってもらうことによってケアしている、というか。
ケアの先に祈りがあるというのも面白いです。わたし自身もそうですが、吃音のある人はけっこう祈っているのではないかと思います。言葉を出すためにいろいろな工夫をしますが、工夫したとて常にうまくいくとは限らないので、しゃべりながら、「次のこの言葉が出ますように」と祈りつつ、出る方に賭けているようなところがあります。自分の体なのに、ケアのしようがないところに行ってしまうんですよね。難発になって体が緊張し、音がまったく出なくなってしまうときは、目の前にいて待たされている会話の相手にも、「どうか、わたしの体がしゃべれるように、一緒に祈ってください」と心の中で勝手に協力を請うていたりします。
わたしには分からないことだらけですが、ケアすることとケアされることのあいだには、面白い関係がありそうですね。それから、ケアする人どうしの関係や、ケアされる人どうしの関係も。一対一ではない、集団のなかで生まれる相互扶助のアナキズムというものがあるのでしょうか。的外れな質問かもしれませんが、何かヒントをいただけたら嬉しいです。