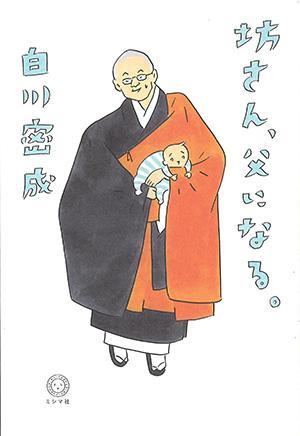第21回
選ばずに加える
2019.08.06更新
「なにが好きでしたか。」
栄福寺は、お寺の檀家さんが少ないので、僕は年間で数件しかお葬式に行かない。しかし最近、立て続けに檀家さんが亡くなった。その時の僕の役割は、仏教の弟子となった名前である戒名(法号)を考えることからはじまることが多い。そしてその時、亡くなった方の奥さんや子供に電話をして、
「亡くなった人はどんな人でしたか? なにが好きでしたか」
という意味の質問をすることがある。
そこからイメージを膨らませて文字のいくつかを選びたいからだ。でも当初は、自分で決めたことでありながら、その質問をすることに大きな抵抗があった。
身内の「死」という一大事を前にして、動揺したり、慟哭している家族に「どんな人でしたか?なにが好きでしたか」と質問するということが、ひどく礼を欠いているのではないかという気持ちがあったからだ。
しかしやはり戒名を「その人の雰囲気」を持ったものにしたくて、勇気を出して聞いてみることが多い(直感的に聞かない時もある)。
すると多くの場合、電話口で家族と僕の間の空気が、一種の「やわらかさ」「あたたかさ」を持つことが多い。
いったんお葬式の準備に入ると家族の中ではとても事務的な話題が多くなる。「葬式はいつにするか?」「お花は誰がお供えするか?」「葬儀会場をどこにするか?」「法的な手続きは誰がするか?」「呼ぶべき人を呼んでいるか?」そんな無数の事務的案件が家族には、一斉にふりかかってくる。
そんな中で、ふと湧いて出た「どんな人だったですか? なにが好きだったですか?」という質問は、その状況の中で数少ない「亡くなった人に関する話題」のようだ。家族は多くの場合、不意を突かれたようにしばらく沈黙し、だけど確かな言葉で「その人」のことを語り始める。
「とにかくおだやかな人でしたね。あと意外と出かけるのが好きだった」
家族から聞くその姿は、僕が生前知っていた故人のイメージとは大きく違うことも多く、驚くこともある。
電話ではなくて、直接家族と話せることもある。若い娘がまずは口を開く。
「とにかくひと言でいって自分勝手。淋しかったのかな」
「繊細という言い方もできるかな。おっさん(和尚さん)戒名は、さっきの姉さんの自分勝手ではなくて<繊細>という線でお願いします」
もっと若い弟がそう口にすると、堪えきれず親戚が吹き出す。
「おい! 父ちゃん起き上がってくるぞ」
そんな様子を僕は、家族ではない坊さんという立場で眺めながら、その場にたしかに存在する愛くるしい「人が生まれ死ぬ」というやわらかい木綿のような手ざわりを感じ続ける。
この大事な質問は、僕が「坊さん」だからできることなのかもしれない。
僕たちは、例えば自分にも生きている時にもっとその質問をしてもいいのかもしれない。
「どんな人ですか? なにが好きですか」
死者を送り、迎える。
僕たち坊さんの具体的な役割は、江戸時代ぐらいからはじまっていることも多く(生前ではなく死後に戒名を授けることがあるのは、平安時代にはじまっていることだろうけれど)、つまりかなり前からやっている役割が多いので、「今を生きている人にきちんと受けいれられているのかな?」と一抹の不安を感じることがある。少なくとも僕はそうだ。
例えば人が亡くなった後に、1周忌、3回忌、7回忌、13回忌と行ってゆく死者の供養である「法事」などにしても、「みんなこの儀式をどう思っているのかな?」と改めて考え込んでしまうことも正直ある。
そんな風に漠然と感じていたのだけれど、好きな映画監督の映画を観ていたら登場人物が、
「あの人だって自分の母親の3回忌ぐらい来るでしょ」
と話す場面があって、「ああ法事って意外と社会通念の中でなんとなく認められた概念なんだ」と何というか感心してしまった。
「だから何だ」というわけではないのだけど、「坊さん」という当事者であると意外と見えないことがあるけれど、どんな形であれ、人々は「死者を送り迎える」行為なしには、たしかに「生きにくい」。
宗教やお寺に関することが「すべてがこのまま」ではいかないし、いくべきでもないと思うのだけど、それは確かだと思う。「人は死者を送り、迎える」のだ。
ANDの思想
いいことなのか悪いことなのか、わからないけれど(どちらでもないのだろう)、最近は昔書いた文章がパソコンに残っていることがある。僕が20代前半で大学の卒業論文を制作していた頃に書いた文章がパソコンから発掘された。考えてみると20年ほど前に書いた文章である。
僕の卒論テーマは「密教と現代生活」という密教学科という範疇を超えようとする内容だったので、まずは「密教」というものを自分なりに定義する必要があると思い「密教とは何か」ということを文章に書いていた。
今からみるとそれは「自分なり」というよりは、尊敬する先生の定義を何人かそのまま書いているだけなのだけど(きちんと引用をあきらかにしつつ)、その卒論には結局収録されなかった文章を読んでいて、仏教の中の「密教」という存在が「総合性」という側面を強く持っていることに、目がとまった。
密教は、既存の様々な思想、習俗を仏教に取り込んで行く。インド古来のタントリズムをもとに持つ呪術や宗教儀礼、ヒンドゥーの思想、民間思想、自然科学・・・。例えばバラモン教が神々への供養として行っていた火を使った護摩を、供養だけではなく、自己の煩悩を焼く密教儀礼に昇華していく。
すこしシンプルすぎる言い方かもしれないけれど、それは、「ANDの思想」だと今、あらためて思った。僕たちが現代の中でいつも求められているのは、圧倒的に「OR」だと思う。「これなのか?」「あれなのか?」「とにかく自分の意見をひとつに決めなさい」「明確な自分を持ちなさい」と僕たちは、常に問われ続ける。
しかし僕たちの密教の思想は、乱暴に言えば「それもいいな!」「全部やってしまおう」→「でも中心の軸になるのは密教だ」ということだ。
その「ANDの思想」成分は、もっと社会や個人の中にあってもいいと僕は思っているし、圧倒的に不足しているはずだ。「人は変わるし、変わってもいい」「明確な自分などなくてもいい」「両方やってもいい」「全部やってもいい」。
その<選ばずに加える>そして<ひとつの包括的なコンセプトでまとめ上げてゆく>という密教の伝家の宝刀的な「動き」を、僕たちが、もう少し持つことができれば、僕たちの世界はもう少し軽やかになっていく気がする。
決めなくていい。加えるのだ。全部やればいい。そして色が変わったとしても「染まるな」。
道の上に忘れるもの
四国遍路を歩いていると、当たり前だけど道を間違うことがある。そして殊勝にも間違え多き我が人生を振り返ったりする。
引き返す道を歩くのは、苦痛だ。そこは既に通った道であるし、無駄な道だと感じてしまう。
「しかしまてよ」と僕は自分に語りかける。「戻る道も道だよな」と。
おそらくこの道は「戻るに値する道」だと僕は、直感する。いや「戻ることに意味があるのだと」すると道は新しい言葉を語り始める。「じつはまだ隠している物があるんです」と骨董屋のような表情をみせる。
「戻る道も、<知っている>新しい道なのだ」僕はそのことを真言のように唱え続ける。そして「戻る」勇気のようなものを携える。
その中で、ふと「私」のような存在を忘れるような瞬間が訪れる。
「求道の志は己(おのれ)を道法に忘る」(弘法大師 空海『性霊集』巻十)
【現代語訳:道を求める志は、「自分」を覚りに至る道の上に忘れることである】
今まで、自分だと思っていたものを、忘れることのおもしろさ。
"道の上に私を忘れる"
そんなものを、ちょっと見つめてみたい。
仏さまが、そこにいるのだと思う
そして、私もまたそこにいるのだと思う。
忘れたはずの懐かしい新しい顔で。