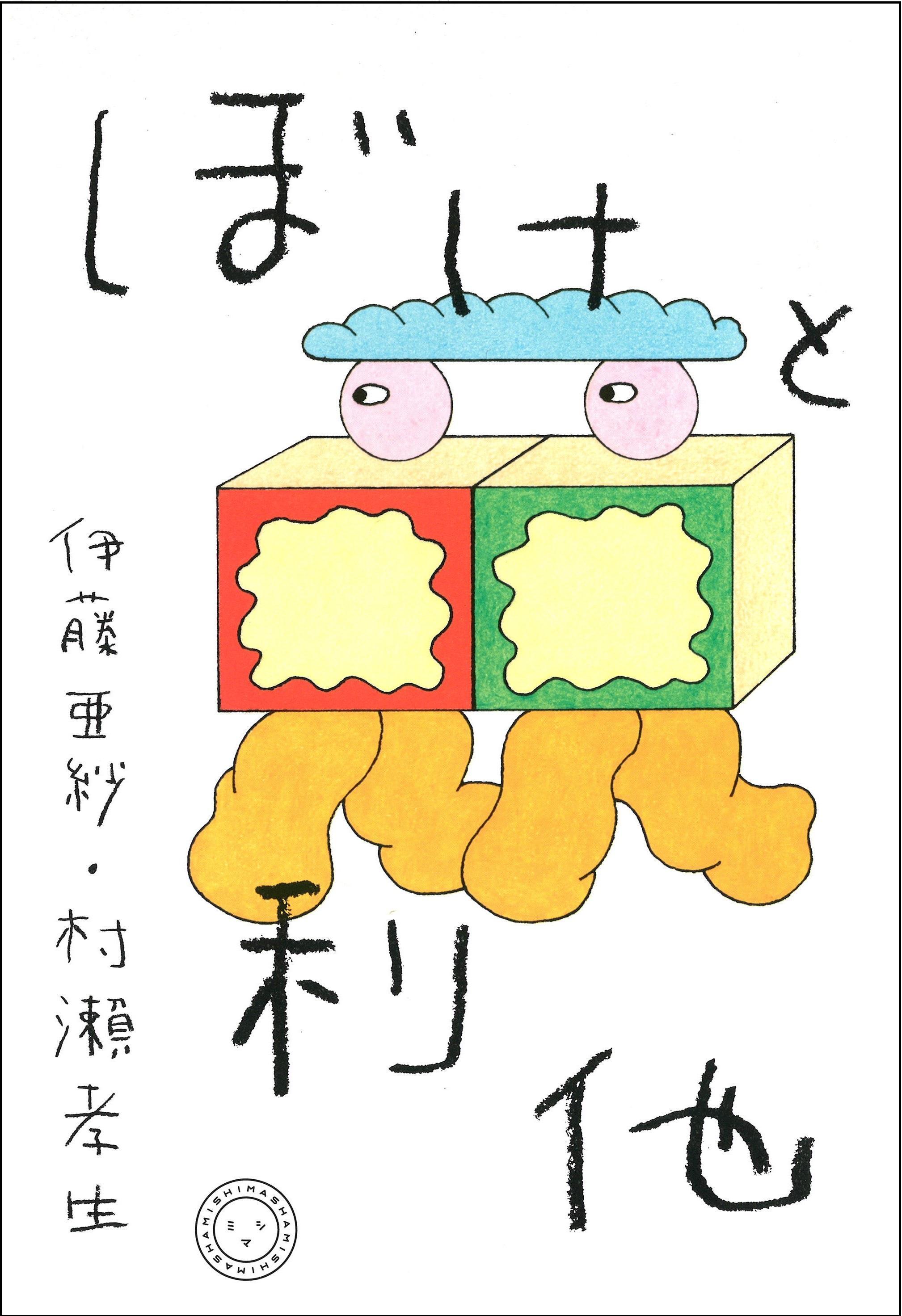第18回
物と情報を減らす
2024.10.18更新
パソコンを開くことを躊躇してしまう。デスクトップには、無数のデータが散らばっていて、足の踏み場もないのである。
内容に応じて類型化されたフォルダがあるので、そこに放り込むだけでよいのだが、その作業すら溜め込んでしまうのは、僕の性分によるところが大きい。
デスクトップが一杯になり始めると、仕事の進捗が途端に悪くなる。パソコンは順調に機能しているが、僕だけがフリーズ気味になってしまうのであった。
パソコンだけでなく、紙情報もいっこうに減る気配はない。職場の棚には12のファイルが並んでいる。レジュメや資料を収めるために用意したものだ。ところが、それらの書類を仕分けしてファイルに綴じること自体が面倒で、机の上に重ねられたまま高層化する始末。
さらに、どのファイルにも属さない印刷物がクリアファイルに挟まれたまま増え続けている。デジタル上の机もリアルな机も情報で溢れかえっている。
スッキリさせたい。心からそう思った。いっそのこと類型化することをやめたらどうだろうか。分かりやすくするために分けたのだが、分かれすぎて分からなくなってきた。
「いま行っていること・これから」と「終わったこと」のふたつに分けて管理してみた。保管するファイルはあえて厚紙製のものにしてみる。2リング式ではなく、綴り具を外さないと書類を取り出せない古典的なフラットファイルである。
あえて、不便なものにした。僕の場合、2リング式のファイルは書類が溜まりやすい傾向がある。便利すぎるせいか、関心の薄い書類がいつまでもファイル内に残り続けていたからだ。
ささやかな改革は上手くいっている。パソコンもこの方式で管理しようと思う。書類の仕分け作業や増え続けるフォルダもなくなると思うと、なんだかホッとした。
一番良かったことは、12種類あったファイルが2種類になり、どこにも収まらない書類が無くなったことである。物が少なくなることに安堵するようになったのは、僕の老いが進行し始めた証のように感じている。
「物を所有することにもエネルギーが必要である」と実感させたのは引っ越しだった。業者さんに依頼しないで引っ越しを行ったことが2度ある。
建築年数が60年近いビルはエレベーターのない所が多い。家賃の安いことを目当てに住み替えるようにしていた。
50代初めに引っ越したビルでは3階にある部屋を棲み処とした。あの頃は物欲が旺盛だったのだろう。所有する物たちを「どのように配置しようかな」と考えることも楽しかったので、意欲的に階段を上り下りした。
55歳を過ぎて引っ越したビルの棲み処は4階だった。あの時ばかりは、物の多さを呪った。自ら欲して手に入れた物であるにも関わらず、「なんで、こんなにあるんだろう」と嘆いた。
僕を苦しめたのは家具よりも雑貨である。大量にある雑貨類は、これでもかと荷造り用段ボールを増やした。その数だけ、階段を上り下りする羽目となった。わずか3日の引っ越し作業だったが、身も心もヘロヘロになり、見た目が変わるほど痩せたのであった。そんな時に行われたセミナーで「村瀨さんは自我を手放したような人ですね」と評されたが、あれは単にクタクタだっただけである。
業者に委託して行われる引っ越しでは、自分が所有している物の量と重さを体感できない。あのトラウマのような引っ越し以来、「自分で運べるか、否か」が所有できる量を定める基準となった。最終的には棺桶に入るだけを所有できれば理想である。
そのように感じる今日この頃にあって、少し危惧していることがある。調理道具が増えているのだ。母に食事を作ることもあって、「あっ、これは便利だな」と思えるものや「こいつは使い勝手が良いな」と感じさせる器具を野放図に買い求めている。
はっとした。きりがない。
フライパンひとつにしても、さまざまな種類の商品が開発されている。「卵焼きにはこれを!オムレツにはこれを!パエリアにはこれを!すき焼きにはこれを!グリルにはこれを!肉を焼くなら鉄より鋳物がいい!」とそれぞれの商品が無言のまま話しかけてくる。
かくして便利を追求した商品は数限りなく存在し、痒いところに手が届きすぎるほどの付加価値が際限なく生まれ続ける。商品というものは、このように専門分化し、広がり続けるのだと思った。
そんなこともあって「これはいいなぁ」と感じて、手にした商品をいったん見つめ直して「これは、僕よりも長生きするな。今あるもので事足りる」と呟いて、棚に戻すように戒めている。
母は調理の好きな人だった。寝たきりになった今、母が買いそろえた器具たちが、部屋の棚だけでなく、倉庫の中にも眠っている。無水鍋に圧力釜、パンやお菓子の型、包丁だけでも数種類はある。埃や蜘蛛の巣のかぶったそれらは、僕にとって無用なものだ
誰からも使ってもらえず、手入れもしてもらえない大量の調理器具や生活雑貨が亡霊のように溢れている。そのすべての器具には意味と価値が与えられており、物質であると同時に物語でもある。かつてピカピカに光っていたアルミ製の無水鍋は朽ちかけたトタン板のように煤けている。そういえば、あの鍋で母はいろんな御馳走を作ったものだ。
父が死んで独りになった頃の母は、所有物を持て余していただけでなく、処理しきれない情報に翻弄され、混乱していたのだと思う。あの時、運転免許証を返納してもなお、異常なまでに車検証に執着していたのは、押し寄せる物と情報の中でフリーズしていたんじゃないだろうか。
母の食事に接しても、物と情報は少ないほうがよいと思った。テーブルに並ぶ品数が多いと、箸が進まなかった。どれから箸を付けてよいのか分からないといった感じで僕を見る。ややもすると、隣に座る人の食事に箸を付けようとする。
人の食事に手を出す母は活き活きとして、それはそれでよいのだけれど、テーブルの上の情報を減らすように配慮した。ご飯、主菜、副菜、汁物といった品数から、一汁一菜へと至り、最後は丼ぶりに落ち着いたのである。
定番の丼ぶりものだけでなく、ふつうはご飯の上に盛らないおかずでも食べやすいように工夫して丼ぶりにする。母の食事介助をするヘルパーさんから「これは何の料理ですか」と尋ねられたりもした。当初は手を抜いているような、うしろめたさがあったが、パクパクと食べる母を見ていると「これもありか」と思う。最近は「ええんです、ええんです。丼ぶりで、ええんです」と呟いて調理している。