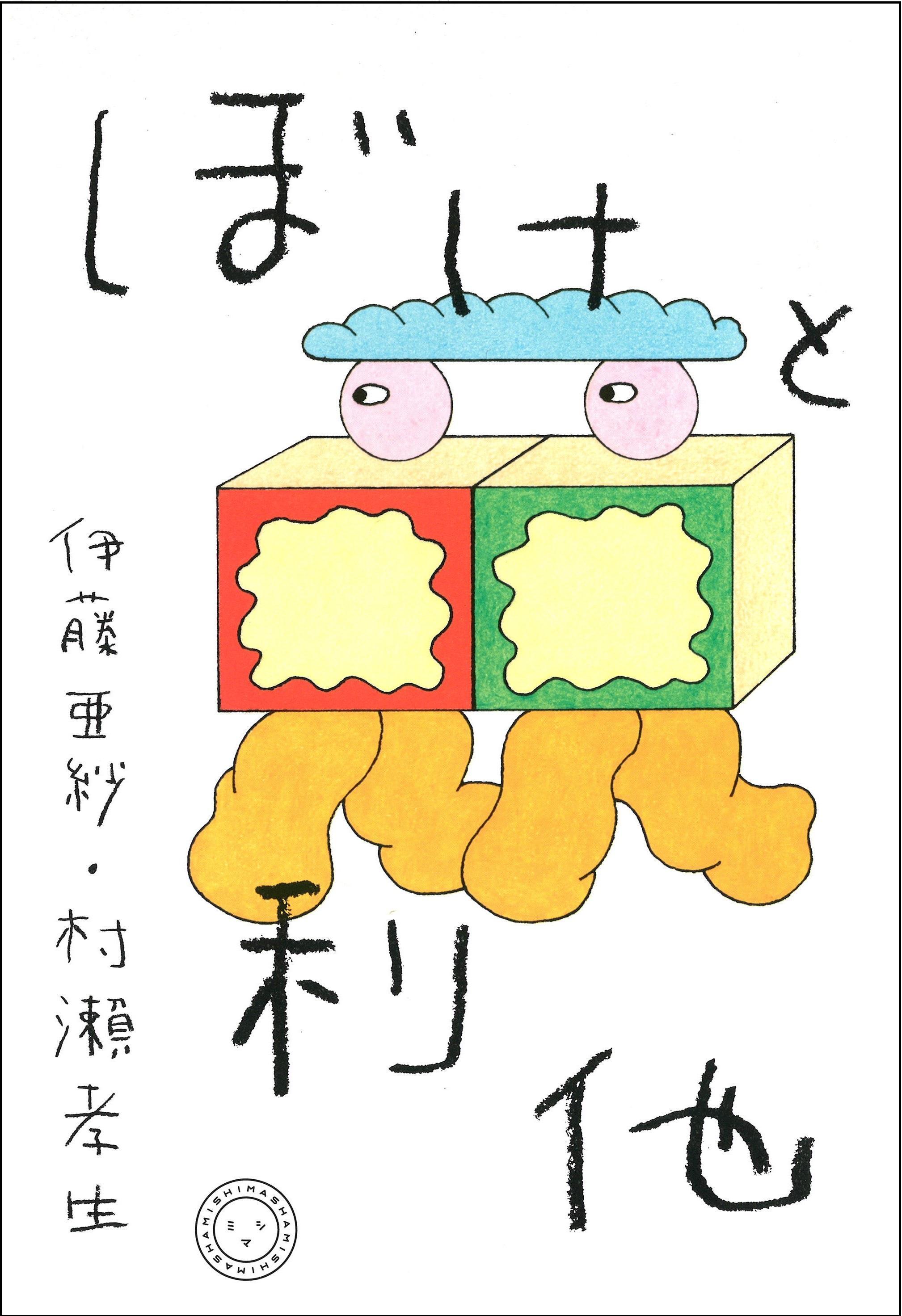第23回
体を軸とする時空
2025.03.30更新
東京大学駒場キャンパスにてイベントが行われることになった。10時30分の打ち合わせに参加するには、実家を何時に出ればよいのだろうか。そして、どんな交通手段で行くべきか。
こんな時、役立つのはパソコンである。乗り換え案内をサクッと開き、出発地と到着地をチャチャッと入力する。すると、瞬時に最適と思われるルートが示された。
福岡から羽田までは飛行機で1時間35分。羽田から駒場東大前まで電車を乗り継いで30分。歩く時間や待ち時間を入れて、2時間53分で到着するとのこと。僕はこの案内に従って難なく目的を果たすことができた。こんな離れ業ができるのは、機械文明のおかげである。そして、この恩恵を空気と同じくらい当たり前に感じている。
実家から駒場東大前まで1059㎞ある。生身の体で歩いてみると244時間かかるとグーグル先生が教えてくれた。日にちに換算すると10日と半日ほどである。けれども、これは一時も休まず歩き通した場合なので、1日8時間ほど歩くと決めて試算すると31日はかかりそうだ。実際はもっと時間を要するのだろう。
つまり、僕が体一貫でこのイベントに参加すると、31日以上かけて東京へ行くことになる。さすがに、クタクタのままで参加することもできないので、イベントの7日前には到着して体を休ませたい。イベントが終了しても体調を整えて帰りたいものである。7日ほどで力を養おう。せっかく東京に来たのだから見物などして楽しむと、7日ではすまないかもしれない。そして、31日かけて福岡に帰る。たった1日のイベントのために最低でも76日を費やすことになる(僕は計算が苦手なので、日数換算の精度は低いです・・・とにかく、体は多くの日にちを要するのです)。
機械を軸とするか、体を軸とするかで、そこに立ち現れる時空は全く別ものになるんだなと思った。
機械軸で僕が得る時間とは何だろうか。母の介護。仕事。NETFLIXとYouTubeの鑑賞。代り映えのない日常の時間である。体が76日かけておこなうものを機械の力を借りると、5時間ちょっとで済ませることができる。つまり機械は75日分の時間を短縮することで時間を増やす。
今の暮らしを手放すことなく、もっと活動を増やせる。その活動を換金することもできる。まさに「時は金なり」である。僕らが忙しくなるのは必然だと思う。
これらを実現たらしめているエネルギーの元は石油だ。石油が燃え盛っている。
体軸では、とんでもないことになりそうだ。たった半日のイベントために、2か月半をかけて移動する。今回のイベントは東京の団体の企画だった。依頼の手紙も31日かけて誰かが持ってくる。僕の手紙も同じ時間をかけて誰かに運んでもらう。準備から考えると、このたった1日のイベントは1年がかりになりかねない。
依頼がありました。「はい、行きます」ともならない。赴く側の僕は相当な覚悟がいる。道中に何があるか分からないし、還暦を迎えた僕の体力がどこまで持つかも不明である。母の介護も誰かに委ねざるを得ない。帰福を前に母が死ぬには十分な時間になるとも言える。仕事場にも長らく顔を出せない。つれあいと連れ合う時間が少なくなる。僕を送り出す側にも、覚悟が求められる。大袈裟かもしれないが、これは小さなお別れじゃないか。行き倒れという言葉がリアルになる。それでも行くだけの理由が、僕だけでなく帰属している集団にも必要になるだろう。
ということは、呼ぶ側もその覚悟を強いる覚悟がいるのである。イベントもさることながら、歩いてやって来た僕の顔を見るだけで、依頼者は感無量となるのではないか。「よく来て下さった」と心から感じるのではないか。初めて会う関係でも旧知の仲のような絆が生まれてしまいそうだ。なんだか密度が違う気がする。1日の密度というものが。単なる想像なのだが。
そこで、さらに想像を膨らませると空間もかなり豊かになりそうだ。なぜなら、福岡から東京まで道中には、山口、広島、岡山、兵庫、大阪、京都、滋賀、愛知、静岡、神奈川が横たわっている。
山口にはフグと瓦そばがある。広島にはお好み焼きと牡蠣。岡山はとどめせとマスカット。兵庫は明石焼きと蛸。京都はおばんざいとにしんそば。滋賀は瀬田しじみと近江牛。愛知はひつまぶしと味噌煮込みうどん。静岡は浜松餃子と富士見焼きそば。神奈川はあなごとシロコロホルモン。一度はその土地で食べてみたい物たちが待ち構えている。ただの素通りは出来そうもない。
それぞれの土地を五感で受け止め、自らの足で踏みしめながら歩き抜く。人を始めとして、それぞれの大地で生きるものたちの営みを肌で感じながら歩く。僕は、僕の体は、何を感じるのだろうか。そして、何を思い、何を考えるのだろうか。イベントに参加することを実現たらしめているのは体である。歩くほどに体が燃えてパッションが弾けるに違いない。
きっと、体に導かれた意識は求めたんじゃないだろうか。もっと、いろんな物を食べたい。もっと、いろんな物と触れ合いたい。もっと、いろんな人に会いたい。もっと、もっと・・・。生身では到達できない地平を感じたくなった、知りたくなった、そこで感動したくなったのかもしれない。生存戦略に留まらず、切実に希求し始めたんだと思う。その結果として、生身の限界を補完・拡張し始めたのだと妄想する。
しかしながら、機械軸は現代社会において、そのような時間を創り出しているのだろうか。遠方へと移動するたびに、このような想いに駆られていた。
確かに、機械軸は時間を増やし「できる」ことを生産してきた。それと引き換えに「過程」を失ったようにも思う。「過程」を失うことは実感を失わせ、感覚を不稼働にする。感覚の不稼働は主体を鈍らせ負担感を増産する。そんな循環が巡っているように思えて仕方ない。主体とは「おもなからだ」とも読めるのだから、意識に在るものではなく、体から生じるものかもしれない。僕たちの社会はそれを体から失いかけているのではないだろうか。
僕が働く老人ホームには26名の人が暮らしている。そのうちナースコールを鳴らして職員を呼べる人は2~3名。そのご老体ですら、ナースコールを押すことのできない日がある。だから僕たちは、感覚をフル稼働して夜を過ごす。
「カリカリ」とする音に誘われてユキさんの部屋に招かれる。人差し指で壁紙を剥がしていた。炊いてもいないご飯の炊ける匂いを辿って、フミヱさんの部屋に導かれる。ほやほやのオシッコがパットに出ていた。不穏な空気を肌で感じて、マコトさんの部屋に訪れる。今まさに、窓から外に出ようとしていた。など、意思によって行くのではなく、感覚に誘われて行く。呼ばれもしないのに、自ら行くのであった。
そんな時、僕は負担を感じなかった。ところが、ナースコールで呼ばれて行くことには負担を感じた。時にはナースコールのコードを外してしまいたい衝動にかられたこともある。
眠りという生理的欲求を抑制して徹する夜勤。コールに呼ばれていくときは負担感が生じるのに、感覚に導かれていくのは負担感が生じない。なぜだろうか。感覚に促されていくときは、なんだか冒険というか、謎解きというか、そんなものがある。だからだろうか。
近年、介護現場にセンサーが導入されようとしている。人手不足に対する負担軽減を図ることが目的のひとつとされているが、おそらく、負担は減っても負担感は増えていくだろう。ナースコールと同様で、今度はお年寄りから直接呼ばれるのではなく、体の感覚を補完するセンサーがパソコンを通して「行け」と指示するからだ。
きっと、「取るべき負担」と「取ってはいけない負担」があるのではないか。負担を軽くするための効率や便利の追求は、解消し得ない負担感を増殖させるのだと思う。
このような考えは、爺捨て山の開拓に影響を与えた。草を刈る、木の枝を払う、樹木を切り倒す、石を運び、穴を掘る。そんな作業にできるだけ機械を持ち込まないようにしている。手に馴染む道具に留める努力をしている。
40年以上放置された畑で、繁栄し続ける野ばらの群生を相手に、剪定鋏ひとつでチョキチョキする。野ばらという植物がどのように地を這い、根を張っているのか。古い枝が重なり合って茎を隠し、その上を覆い隠すように若い蔓を伸ばしながら、すそ野を広げていることがよく分かる。その広がり方は棘もあって、他の者を寄せつけない。まさに棘の道である。そして、その蔓は枯れたものと、生きているものの境が曖昧である。
「重機を入れた方が早いバイ」とご近所さんは言うのだが、「そうですね~」と答えながら(機械で過程をショートカットしたくないんです。体で感じたいんです)と心の中で呟いている。