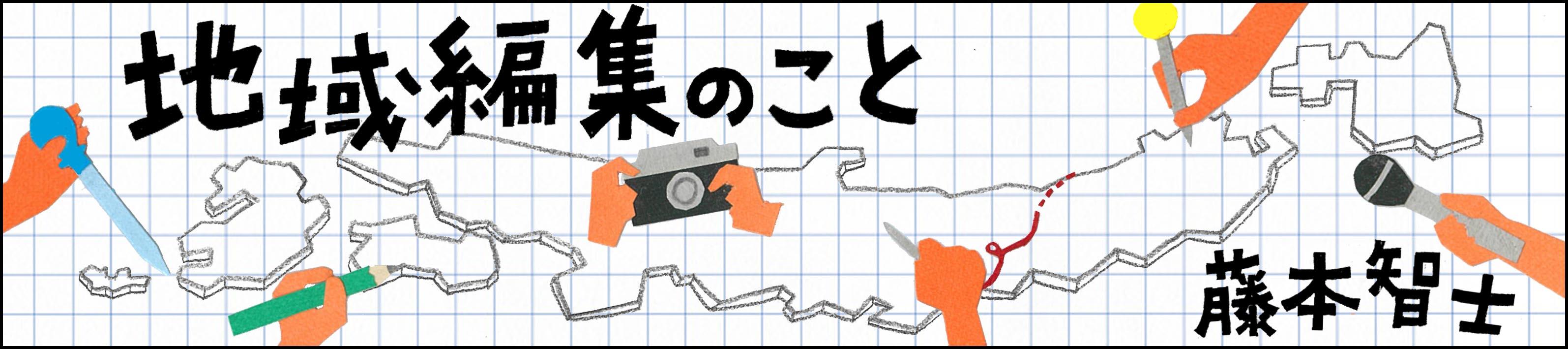第38回
地域編集者としての街の本屋さんのしごと。
2021.12.11更新
群馬県がすすめる「湯けむりフォーラム」というトークセッション企画がある。群馬といえば、真っ先に思い浮かぶ草津温泉。群馬県知事の山本さんは草津町出身だというし、知事自ら、オードリー・タン氏、落合陽一氏といった錚々たる方々と対話されている動画を僕も拝見して、かなりの肝煎り企画であることを感じる。
そんな「湯けむりフォーラム」の一企画に声かけいただき、先日、群馬県の高崎を訪れた。今回書きたいのは僕を「湯けむりフォーラム」に呼んでくれた人の話。
群馬県高崎市といえば、僕にとっては本屋『REBEL BOOKS』の街だ。4年前に自著の出版記念イベントでトークさせてもらったご縁から、店主の荻原(おぎわら)くんと仲良くなり、以来、彼は僕にとってとても大切な友人。今回同行した後輩編集者の徳谷柿次郎が、会うなり「俳優さんじゃないですよね?」と聞いてしまうくらい、昭和映画の主人公的銀幕感が漂う彼は、実に落ち着いた佇まいと声が素敵で、僕は彼に本を勧められるとほぼ100パーセント買っちゃう。参ったもんだ。
10坪もないような小さな書店ながら、何かに特化しすぎたり、専門的になりすぎたりすることがなく、とても開いた選書を感じるのは、きっと彼のなかで高校生くらいの若者がやってきてくれることを願っているからだろう。彼は以前、書店をはじめたきっかけについてこう話してくれたことがある。
「もともと本好きというか、本屋好きなんですけど、高校を卒業してからずっと東京にいて、大学生の頃とかは、ヴィレッジヴァンガードの下北店によく行ってて、当時は特にポップも元気だし、漫画とかめっちゃ教えてくれるじゃんって興奮して、こういう本屋が高校時代にあったらよかったのになって思ったんですよ」
もちろんヴィレッジヴァンガードとREBEL BOOKSではテンションがまったく違うけれど、それでも同じ人たちを見ていることは伝わる。コーヒーの苦味とともに、自慢の機材でお勧めのレコードをかけて、そのアーティストの生き様について教えてくれる喫茶店のマスターのような、そんな空気を彼自身やお店から感じるのだ。実際REBEL BOOKSでは、荻原くんが淹れるコーヒーも飲める。
もうおわかりだと思うが、今回、「湯けむりフォーラム」に呼んでくれたのは荻原くんだった。そもそも、そんな彼に企画に関わって貰うように声をかけた若い県庁職員さんがいたことがまず素晴らしいなと感心したのだけど、今回は荻原くんの話。結果、彼が「湯けむりフォーラム」のディレクターの1人を務めることになり、ソトコト編集長の指出さんと、上述した柿次郎(ジモコロ編集長)と僕の3人の鼎談をみなさんで企画、荻原くん自ら出演オファーをくれたのだった。
少し先輩の指出さんにお会いするのも3年以上ぶりな気がするし、柿次郎とはよく会っているものの、その分、安心感もある。だからシンプルに楽しそうだなと思ったのだけれど、何より僕は、荻原くんのお誘いだから引き受けた。
鼎談の模様は「湯けむりフォーラム」のサイトでいずれUPされるようなので、ここでその内容は書かないけれど、久しぶりにお会いした指出さんが、先輩ながら進行役になってくださったことで、ある種のライブ編集が出来ていて、とても見やすい動画になっているんじゃないかと思う。指出さん、さすがだった。そして何より楽しかった。それもこれもディレクションが見事にはまった結果だと思う。
以前から僕は編集者の最も大切な仕事はディレクションだと言い続けている。それが雑誌の特集記事であれ、イベントであれ、ものづくりであれ、座組みが決まればあらゆるものが動き出す。そしてアウトプットはその座組みによって決まる。以下は、自著からの引用。
ここからすでにものづくりははじまっているのだという自覚がないディレクションは、取り急ぎだからと一○○均で買った器で、結局日々暮らしていくのと似ています。
あの日、あのとき、何気に「とりあえず一○○均でいいんじゃね?」と言っちゃった自分が、いまの暮らしのスケール感をすでに確定させてしまっているわけです。だからこそ僕たちは、誰に頼むか? ということに、とても神経をとがらせます。
何度も言いますが、このもっとも大切といっていいディレクションを多くのローカルメディアは大切にしていません。ー魔法をかける編集(2017年)
僕が今回「湯けむりフォーラム」に参加して思ったことは、荻原くんのような街の本屋さんが、イベントやトークセッションのディレクションをすることのメリットだ。よい書店員さんが企画に関わることは、いろんな意味でとても理にかなっている。特に今回のような県をあげての肝煎り企画のディレクションを任せるには、最も適任で、僕はそこに街の小さな書店の大きな役割を見る気がした。
REBEL BOOKSのような個人書店は、大型書店のように日々大量に届く書籍を次から次へ捌くことよりも(それはそれですごい仕事でリスペクトしている)、それら出版物の海の中から自分の店に適当なもの、もしくは自分の店を好きでいてくれるお客さんたちが欲しいと望むものを見出して仕入れることが大切。しかしそれら曖昧模糊とした感覚の拠り所となるのは、結局は、店主がその本を地域の人に読ませたい、と思うかどうかだ。
僕は昔から、書籍の編集者というのは、世の中に新しい提案を投げかける一番最初の役割を担う人で、それはテレビや新聞、WEBといった即時性を求められるメディア編集者には出来ないことだと信じている。書籍は他の媒体と違って、着実に文字数を積み上げ、ページの地層をじっくり積み重ねていく、とても時間と手間のかかる媒体だ。だからこそ、そうやってかけた時間と同じだけの時間、またはそれ以上の時間をかけて世の中にその考えを浸透させていくことができるんじゃないかと思う。
そういう意味で、書籍はまだ世に問うていないことを問うには、抜群の媒体だと言える。「わからない」「理解できない」と、なかなか受け入れてもらいづらい新しい考えや価値観について、丁寧に説明出来るのが書籍の強みなのだ。
前述のとおり、荻原くんをはじめとした全国の良い個人書店さんの特徴は、そういった、新しい提案をともなう書籍や、いまの世の中にフィットするであろう思想を感じる書籍を、地域の人たちに読ませたい、読んでもらいたいと考えているところにある。つまりはこれが流行っているとか、これが売れている、ということを一番にして本を選んでいないということ。
出版業界という大海にむけて、そんな視線を向け続けている店主が、見出したその書籍を仕入れるように、その著者を呼ぶことの自然。その特殊能力を自治体が活用しない手はない。そういう意味で前述の、県庁職員さんはほんと素晴らしいなと思う。
書籍編集者が投げかける問い(一冊)を、最初に受け取るのは街の書店さんだ。書籍編集者が渡すバトンを街の書店が受け取り、そのバトンを行政のみなさんとともに、地域に暮らす人たちに届ける。地域編集者としての個人書店(店主)の役割はとても大きい。