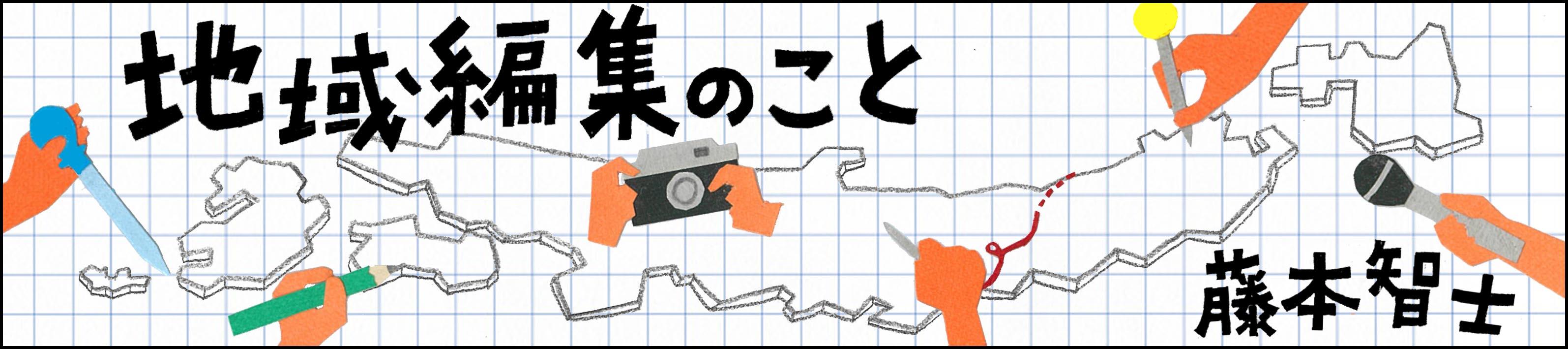第59回
僕が海外に出た本当の理由
2023.09.06更新
49歳にして初海外旅となったバリ島取材。それはもう何もかもが新鮮で、50を手前にしてこんなにもドキドキできるものかと興奮しっぱなしの日々。しかしそもそもどうして海外に出てみようと思ったのか。その理由について、僕はこの連載ですでに以下のようなことを書いていた。
日本で生まれ育った日本人男性の僕は、決して裕福ではないけれど、それでも五体満足で安穏と暮らしてきた。小さな悲しみや寂しさを感じることがあっても、支えてくれる家族や仲間がいて幸福な日々だ。そんな僕は、マイノリティな状態である自分を感じる機会がほとんどないままに生きてきた。しかしそれはただの偶然でしかない。僕にとって、海外に行くことは、いっときでもそういったマイノリティな状態に身を置く経験として重要なものになるんじゃないかと考えた。〈第56回「Act Global, Think Local」〉
日本から一歩も出たことがなく、英語ひとつ話せない僕はバリ島で49歳にして見事なまでに不自由を得た。この経験はやはり僕にとって大切な経験だったように思う。しかし、それもあくまで理由の一欠片に過ぎない。僕が今回海外に出たいと思った一番ど真ん中の思いをまだきちんと言語化できていなかったので、今回はそのことについて書くことで、バリ島の話を終えたいと思う。
30歳くらいのときだったろうか。海外に行くならそのぶん日本の地方をまわろう。だから僕は海外に行かない。と、そんなふうに決めた僕が、ここにきてどうしてそれを覆そうと思ったのか。それはある意味で自分の過去15年を否定するような思いに近く、だから僕はここまでそれを言葉にすることができなかったのだと思う。
本連載のテーマ「地域編集」。この言葉に集約されるように、僕は長年、地域×編集というフィールドで活動を続けてきた。そのスタートは2007年。僕が編集長を務めていた雑誌『Re:S(りす)』の「地方がいい」という特集だったように思う。そもそも雑誌『Re:S』をつくる際に、版元であるリトルモアの社長の孫さんに言ったのは「東京で売れない雑誌を作りたい」という我ながら謎の言葉だった。それはなにもアンチ東京みたいなことではなく、地方で暮らす人間の一人として、どうして東京のメディアだけが、日々当たり前のように「代官山だ、麻布だ、赤坂だ」と地方に住んでいては到底行くことも叶わない店の情報を堂々と発信しているのだろう? という疑問に端を発していた。それならば、地方の町の情報だって堂々と全国に向けて発信していいはずだ。そんなシンプルな思いから、当時の僕は東京の人にとっては情報価値が低いであろう、地方の小さなお店や人物しか出てこない雑誌をつくりたいと、そんなことを漠然と考えていた。
その頃から、とにかく日本中を旅してまわった。そこで僕は、これまで「しがらみ」とか「不便」といったネガティブな言葉で片付けられていた事象のすばらしさを実感。それを地方の良さに転換して発信し続けた。その後、嵐のメンバーと日本中をまわった『ニッポンの嵐』(2009年)をつくったことをきっかけに、彼らが司会を務める紅白歌合戦など、エンタメの世界を通して「地方」や「日本」そのものに注目が集まるようになっていった。まさにエンタメの世界のプロフェッショナルのチカラを思い知った2000年代初頭だった。その後、東京一極集中の是正と、地方の人口減少に歯止めをかけるべく「地方創生」なる言葉が、その施策とともに広がっていった2014年頃から、僕は一抹の不安を感じ始め、最近までなんとなくそこに蓋をしながら活動を続けてきたように思う。
地方の魅力を発信していくことは、僕の大きな役割の一つだと思いながら編集者を続けている。それは今後も変わらないだろう。しかし僕はいま、「地方の魅力=日本の魅力」という構図に大きな違和感を覚える。多様な文化が、ある種のナショナリズムに絡めとられてはいまいか? という大きな懸念が僕にはあるのだ。
20代の無知な僕を救ってくれた大先輩編集者、沢田眉香子さんがつくられた、その名も『WASHOKU』(淡交社)という一冊がある。ユネスコが無形文化遺産登録した「和食」のリアルを、イラストと英語解説で伝える一冊で、僕はこの本を密かに何冊も購入し、若い編集者やライターに贈ったりしている。後輩たちに贈っている理由は、その編集とライティング能力へのリスペクトゆえだけれど、今回ここで取り上げたいのはそういうことではない。この一冊ほどに忖度なく「和食」のほんとうを伝えている本はほかにないと僕は感じている。
和食はすばらしい。つまり、日本はすばらしい。そんなふうに無邪気に歪曲された論説が多いなかで、「和食」と呼ばれるものが、そもそも「洋食」あってこその言葉であり、またその「洋食」は決して西洋料理ではなく、日本独自の料理であるという事実について淡々と解説されているのを読んで、僕は大先輩の編集に胸がすく思いになった。代表的な和食とされる「寿司」は、東南アジアで親しまれてきた発酵食品である「なれずし」を、ある意味でファストフード化したものだ。また恵方巻きも、1998年にコンビニが展開して広まった風習であるといったようなことが、明快に書かれていて。なんて気持ちのいい本なんだろうと感動すると同時に、これこそが、ここ最近の僕の違和感の正体のような気がした。
2年ほど前に出版されたこの一冊が、僕のなかにぼんやりあった違和感の輪郭をハッキリさせてくれたのは間違いない。和食万歳。ローカル発酵食万歳。ニッポン万歳。こういった短絡的な流れにNOを掲げたい気持ちが、僕にはふつふつとあった。それは、一緒に発酵ツーリズムなる概念をつくり、本や展覧会づくりをともにした、発酵デザイナーの小倉ヒラクも同じだったように思う。日本の発酵文化を丁寧に取材アウトプットしながらも、彼は常にその視野を世界に広げていた。彼も、日本のローカル発酵の賞賛が、ナショナリズムへと転換されることへの懸念を持ち続けているように思う。
地方や地域の良さは真の多様性にある。その土地の風土に紐付き、さまざまに変化する食文化のように、それは=日本の良さと大掴みに語るべきものではない。もし自分が発信する地方の魅力がそういったものに集約されてしまうくらいなら、僕は海外の良さをも体感して発信したい。そう思ったことが、49歳にして僕を初海外に向かわせた一番大きな理由だった。