第75回
ゴジラ映画で感じた警鐘の継承
2025.01.08更新
昨年末とある飲み会で、昭和の第1作から欠かさず観ている先輩と、子供の頃に観た平成シリーズ以来のファンという友人にゴジラ映画を勧められ、年末年始は初代ゴジラから順番に映画を見返している。
僕が子供の頃は、よく夏休みに昭和のゴジラ映画をテレビ放映してくれていたので、何度も観ているはずなのだけれど、やはり大人になってみると見えてくるものがまったく変化していて面白い。
深海で眠っていた恐竜の生き残りがアメリカの水爆実験によって変異し、目を覚ましたゴジラ。そこには、1954年3月1日マーシャル諸島ビキニ環礁でアメリカがおこなった水爆実験、および、その降灰によって、静岡県焼津港所属の遠洋マグロ延縄漁船の乗組員23名全員が被爆した「第五福竜丸事件」が大きな影響を与えている。
世界で唯一の被曝国である日本にとって、原爆投下から10年も経たないうちに起こったこの事件が、どれほど屈辱的で辛いものだったか。つまりゴジラ映画の本質にあるものは、明らかな反原子力という意志であることが、第1作からの流れをみてとてもよくわかった。もちろんそれくらいは知識として持ち合わせていたつもりだったけれど、シリーズとして作品を連続して見ていくなかで、より深く濃く、それを感じることができた。
なかでも、1964年制作の第4作「モスラvsゴジラ」は、ゴジラ作品に通底する、人間の無闇な科学信仰を憂う、強い意志がもっともわかりやすく描かれていて、大きな衝撃を受けた。
1964年と言えば、東京オリンピックの年、つまり高度経済成長期まっただなか、職場旅行と言われる団体観光旅行が増え、ともなって過剰な観光開発が進んでいた時期だ。時代の流れに真っ向から勝負しようとするエンタメのチカラに、スマホの小さな画面を見ながら一人興奮した。
その作中にこんなシーンがある。怪獣モスラの卵を観光商材にして儲けようとする開発業者やそれを促す政治家に対して、なんとかペンの力でそれを制そうとする新聞記者が先輩にこう嘆く。
「無駄ですね、いくら書いたって。俺はもう書くのやめます。もともと勝てっこないんですよ。何年も言うように、新聞には裁く力もなければ命令権もないんですよ。」
それに対して先輩はこう返答する。
「何年新聞記者やってるんだ? 新聞がそんな力を持って権力機関になりあがったらどうなるんだ? 新聞は大衆の味方だ。」
報道メディアに必要なのはその政治的影響力ではなく、あくまでも大衆の目線からの違和感を提示していくことにある。報道マンの矜持に、僕は作中ながらとても感動した。
ここでゴジラ誕生前年に話を移す。1953年12月、国連総会で、アメリカのアイゼンハワー大統領による「原子力の平和利用」についての演説が行われた。そしてそれを機に、日本でも原子力政策が動き始めた。唯一の被爆国である日本でどうしてそのような流れになるのか不思議に思うけれど、忘れてはいけないのは日本が敗戦国であるという事実。アメリカの属国である日本では、その演説のたった3か月後、1954年3月には原子力予算が計上されたという。ちなみにその中心になったのは、改進党(現自民党)の中曽根康弘。後の首相だ。しかし、そんなタイミングで第五福竜丸事件が起こる。原子力の平和利用という、人間の科学信仰への驕りに対する警鐘としては、23人の尊い犠牲はあまりに大きな代償だけれど、確実に反原子力の世論は高まっていった。
だが、それでは都合がわるいのはアメリカ。そしてその配下にある政治家たちだった。戦後の日本における政治家たちがアメリカの意向の影響を受けないわけはないし、ある意味それも仕方がないとすら思う。けれど、ゴジラの先輩記者の言葉のように、メディアがその役割をしっかり果たしていれば、世の中は変わっていたかもしれないとも思う。
しかしあろうことか、反原子力の世論をもはや力技で抑えたのが、当時読売新聞社の社主、正力松太郎だった。読売新聞紙面や、まだ設立間もない日本テレビ放送でも原子力推進をPR。そして1955年衆議院選に出馬し、当選。第3次鳩山一郎内閣で初代の原子力委員長に就任し、日本に原子力発電所を5年後に建設するという構想を発表した。とにかくこの正力松太郎という人がアメリカの意のままの人だった。
敗戦国、日本にとって、権力のトップは米国だ。そういったなかでゴジラ映画が放つメッセージはとても大きなものだったに違いない。その強固なメッセージを多くの大衆がまっすぐ受け止めたからこそ、その後70年にもわたってゴジラという怪獣の思想が継承されている。
あらためて見たゴジラ映画のおかげで、シンプルな物語の強靭さと、そこに明確なメッセージを込めていく編集のチカラを感じさせえてもらった、そんな年末年始だった。


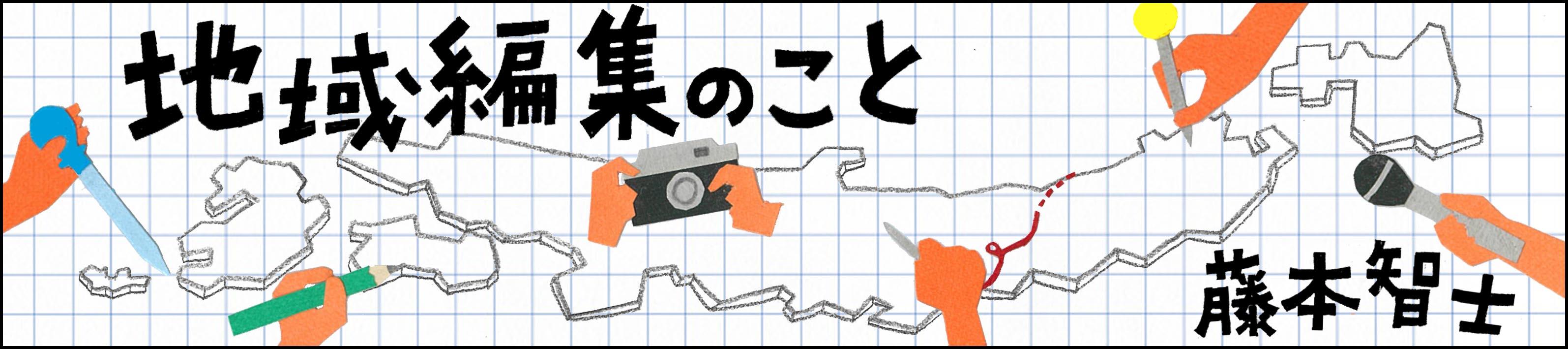



-thumb-800xauto-15055.png)



