第78回
リノベーションスクール、熱海
2025.04.07更新
地域の遊休不動産(空き家、空き店舗、空き地など)を活用し、地域課題を解決するためのビジネスプランを立案する、リノベーションまちづくりという取り組みがある。北九州市での事例から生まれたこのモデルは、短期集中の実践プログラムに落とし込まれ、「リノベーションスクール」として日本各地で開催されており、多くの町で空き物件が再生され、新たな人の流れを生み出している。
そんなリノベーションスクールを静岡県の熱海市で行う、株式会社machimoriのみなさんに呼んでいただいて、ユニットマスターという立場で、その動きに伴走させてもらった。ユニットマスターというのは、各物件ごとに分けられたユニットの一つを担当し、そのファシリテーター、つまりユニット内の議論を整理したり、背中を押したり、ときに方向修正したりして、facilitate=促進する役割。リノベーションスクールは、このユニットマスターが誰になるかというのも一つの肝になっていて、過去に担当された方々の錚々たるメンツに、なんだか腰が引けてしまいそうになった。
ユニットマスターは、日本各地で活躍する各業界のプロフェッショナルという定義があり、僕は僕でそれなりにプロフェッショナルであることの矜持があるけれど、それはあくまでも編集者としてのもの。空き物件を活用して新たな事業を起こしていくなんてことが僕に向いているとは到底思えなかった。実際これまでのユニットマスターは、それぞれに「まちづくり」という文脈のなかで数々の事業を起こし、そこに経済を生んでいくことで街を再生していった当事者たちで、僕のように編集こそすれ、その事業化に対して本質的に興味がないような人間は、ある意味でリノスクのこれまでの実績を壊してしまうんじゃないかと思うほどだった。
僕をよく知るまわりの友人や後輩たちは、口々に「藤本さんがリノスク?」「ほんとに?」「想像できない」と言っていて、そうだよなと思う。僕自身なぜディレクションされたのかわからなかった。けれど、苦手だと思っているような世界ほど、学びと気づきに溢れているのは、それこそ編集者人生で何度も学んできた。不動産、建築設計、リノベーション、事業計画、さらにはファシリテーターのような役割と、わかりやすいくらい露骨に一定の距離をとって生きてきた。それはシンプルに苦手で、僕には向いていないと思っていたからだ。そんな自分がこの数か月、熱海のリノベーションスクールに関わってきた結果、なんというか、メチャクチャ楽しかった。向いているかもしれないと錯覚しそうなほど楽しかった。いや、こんなに楽しいならそれはもう向いていると言っていいかもしれない。
ユニットマスターの最初の仕事は、自らがいる業界で果たしてきたことの実践事例の紹介、つまりは成功と失敗のシェア。そしてこの街において、自分の役割があるとするならここじゃないか、という部分を受講を考えている人たちにメッセージする、事前講演から始まる。そこで僕は、編集視点で実践してきたさまざまな取り組みについて話したけれど、自分で話しながら、そうかあのときは「事業」を起こしている自覚がなかっただけで、僕は知らず経済効果を生んでいたのか、あ〜あのとき、自分が率先して事業をすすめるという思考を持っていたら、もう少しちゃんとお金を稼いでたかも、などといろんな考えがよぎった。けれどもちろん、だからこそ僕はこんなにも呑気に楽しく生きられているんだなとも思う。
僕が担当させてもらったのは、熱海駅からさらに電車で15分ほど離れた網代という町で、海と山が近く、瀬戸内海と太平洋の差は大きいものの、その高低差ある風土が自分が住む町にも少し似ている気がして親近感を覚えた。豊かな漁場に加え、温泉もある。さらにはかつて「ひもの銀座」と言われた、干物屋さんが連なる通りがあり、のどかな空気が心地よい。そんな網代にUターンしたザッキーこと、山﨑くんという男性が町の未来を思いながらすでにいろんな活動を続けていて、そんな彼のやさしくて朗らかでそれでいて情熱的な人柄に、多くの人たちが惹かれ、共感者が集まっている。そんなザッキーがユニットメンバーにいてくれたことや、ユニットマスターの補佐的な役割のローカルマスターを、網代と藤枝の二拠点で活動し、かつ、本業がバリバリ不動産デベロッパーの有希ちゃんという女性が担ってくれたおかげで、網代ユニットはなにかと机上の空論に陥らない、現実的な事業計画を積み上げていけたように思う。だから僕は、このユニットにおいて自分を無理に変化させたり、何かに合わせたりすることなく、一人の編集者としてありのままに振る舞うことができた。これは本当に奇跡的にありがたいことだ。そこについては特にmachimoriのみなさんのディレクションに感謝している。
 網代ユニットが取り組んだ物件は海に近い一軒家。そこで僕たちのユニットが考えたのは「泊まれるパン屋」だった。街の人たちが求めているパン屋さんを営みつつ、いまひそかに増えている網代への移住希望者が町の暮らしを実感できる長期滞在型の宿を2階につくる。そんな計画を練り上げていった。ユニットメンバーに建築系の大学生がいてくれたことも大きく、サクサクと描かれる改修図面をもとに、有紀ちゃんが本業の経験則から改修費を積み上げる。街の人たちへのリサーチや実感値は安心安定のザッキーの役割。その頼もしさったらなかった。
網代ユニットが取り組んだ物件は海に近い一軒家。そこで僕たちのユニットが考えたのは「泊まれるパン屋」だった。街の人たちが求めているパン屋さんを営みつつ、いまひそかに増えている網代への移住希望者が町の暮らしを実感できる長期滞在型の宿を2階につくる。そんな計画を練り上げていった。ユニットメンバーに建築系の大学生がいてくれたことも大きく、サクサクと描かれる改修図面をもとに、有紀ちゃんが本業の経験則から改修費を積み上げる。街の人たちへのリサーチや実感値は安心安定のザッキーの役割。その頼もしさったらなかった。
 しかし網代の町は熱海と違って観光地ではない分、飲食店の数も多くないし、何かしらのアクティビティが用意されているわけでもない。そもそも電車で熱海駅から3駅、およそ15分先の網代に来ることは、頻繁にあるわけではないバスや電車の時間を待つなど、常に待ち時間がつきものになる。その時間を豊かに過ごすためにも、パンとコーヒーは提供する予定だけれど、そこに掛け算するのは、それぞれの趣味や思想。読書するもよし、ただ海を眺めてぼ〜っとするもよし、いろんな意味で、熱海のエンタメ性の享受とは違う頭になってもらう必要がある。そのためにどんな言葉をメッセージできるかが、この事業の肝になるような気がした。すぐ近くの巨大観光地、熱海の賑わい。それゆえ、常に急かされるような空気とは違って、網代の空気はとてものんびりしている。それがこの町の良さであることは間違いない。
しかし網代の町は熱海と違って観光地ではない分、飲食店の数も多くないし、何かしらのアクティビティが用意されているわけでもない。そもそも電車で熱海駅から3駅、およそ15分先の網代に来ることは、頻繁にあるわけではないバスや電車の時間を待つなど、常に待ち時間がつきものになる。その時間を豊かに過ごすためにも、パンとコーヒーは提供する予定だけれど、そこに掛け算するのは、それぞれの趣味や思想。読書するもよし、ただ海を眺めてぼ〜っとするもよし、いろんな意味で、熱海のエンタメ性の享受とは違う頭になってもらう必要がある。そのためにどんな言葉をメッセージできるかが、この事業の肝になるような気がした。すぐ近くの巨大観光地、熱海の賑わい。それゆえ、常に急かされるような空気とは違って、網代の空気はとてものんびりしている。それがこの町の良さであることは間違いない。
 待ち時間や空白というネガティブをポジティブに価値転換できるのが言葉のチカラであり、編集のチカラでもある。そこで浮上してきたのが、網代港はかつて風待ち港だったという歴史。風待ち港とは、帆船が風向きや風力を待つために停泊した港で、岡山の牛窓港や広島の鞆の浦など全国に存在する。ここ網代は「京大阪に江戸網代」といわれるほど、風待ち港として多くの船乗りや商人が訪れて栄えたという。つまり網代は、風を待つ町だったということが、事業の背骨を作っていった。
待ち時間や空白というネガティブをポジティブに価値転換できるのが言葉のチカラであり、編集のチカラでもある。そこで浮上してきたのが、網代港はかつて風待ち港だったという歴史。風待ち港とは、帆船が風向きや風力を待つために停泊した港で、岡山の牛窓港や広島の鞆の浦など全国に存在する。ここ網代は「京大阪に江戸網代」といわれるほど、風待ち港として多くの船乗りや商人が訪れて栄えたという。つまり網代は、風を待つ町だったということが、事業の背骨を作っていった。
 いまもなお、網代の海沿いでは干物を天日干しする風景がある。機械乾燥ではなく、そうやって天日干しするという行為も、ポジティブな「待ち時間」と言える。なにかとネガティブに語られがちな「待つ」という行為を、網代はポジティブにチェンジしてくれる。そんなビジョンをみんなと共有できた瞬間、まさにこの事業計画に新しい風が吹き込んだ。
いまもなお、網代の海沿いでは干物を天日干しする風景がある。機械乾燥ではなく、そうやって天日干しするという行為も、ポジティブな「待ち時間」と言える。なにかとネガティブに語られがちな「待つ」という行為を、網代はポジティブにチェンジしてくれる。そんなビジョンをみんなと共有できた瞬間、まさにこの事業計画に新しい風が吹き込んだ。
 今回、このリノベーションスクールに参加させてもらって、僕は事業をつくっていくということに対して編集のチカラが重要な役割を果たすことを認識できてとても幸福だった。そんな気づきをくれた網代という町に、僕は今後も訪れるだろう。そしてこの記事で網代を知ってくれた方は、一度足を運んでみてほしい。ぜひ網代に。
今回、このリノベーションスクールに参加させてもらって、僕は事業をつくっていくということに対して編集のチカラが重要な役割を果たすことを認識できてとても幸福だった。そんな気づきをくれた網代という町に、僕は今後も訪れるだろう。そしてこの記事で網代を知ってくれた方は、一度足を運んでみてほしい。ぜひ網代に。
あなたも、まち(町・待ち)に来ませんか?



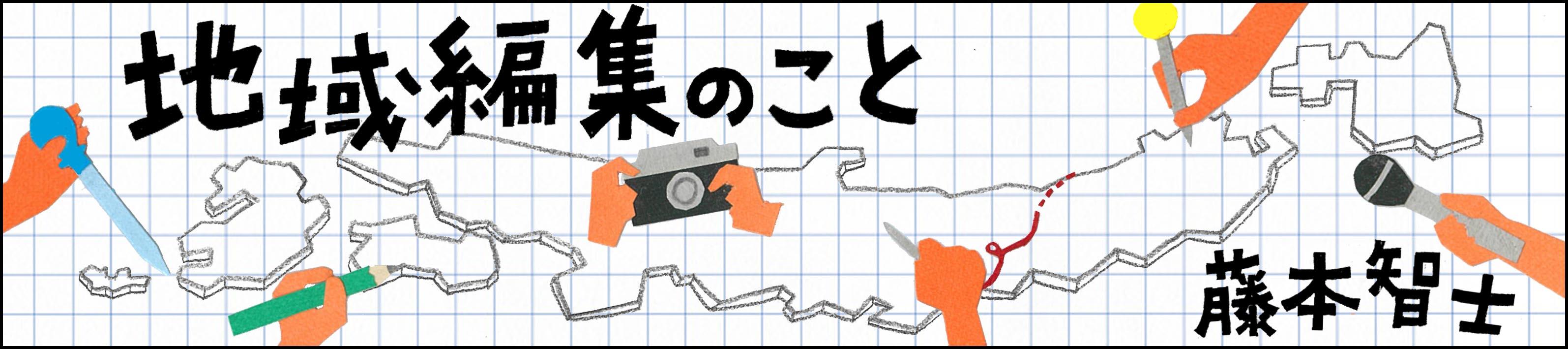

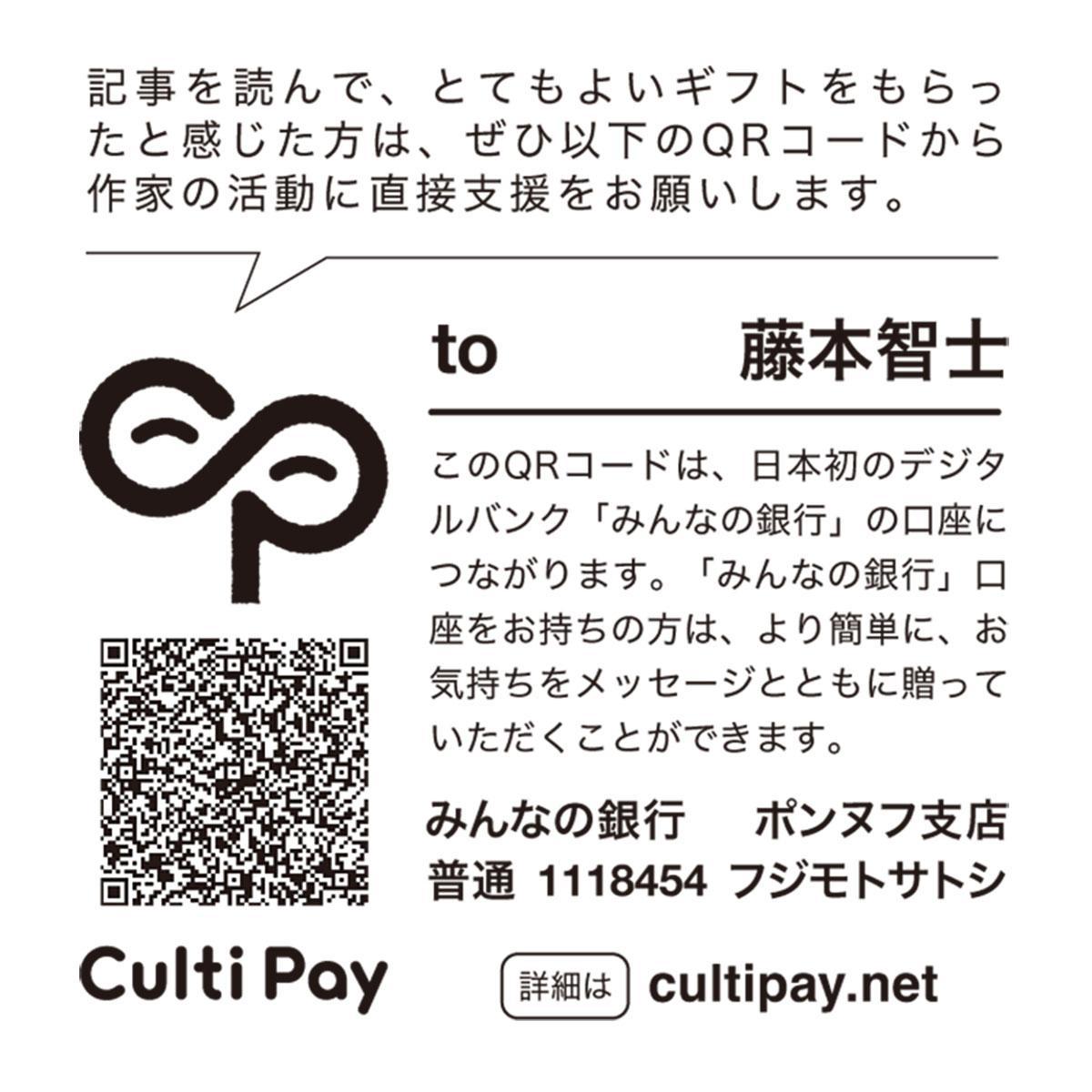

-thumb-800xauto-15055.png)



