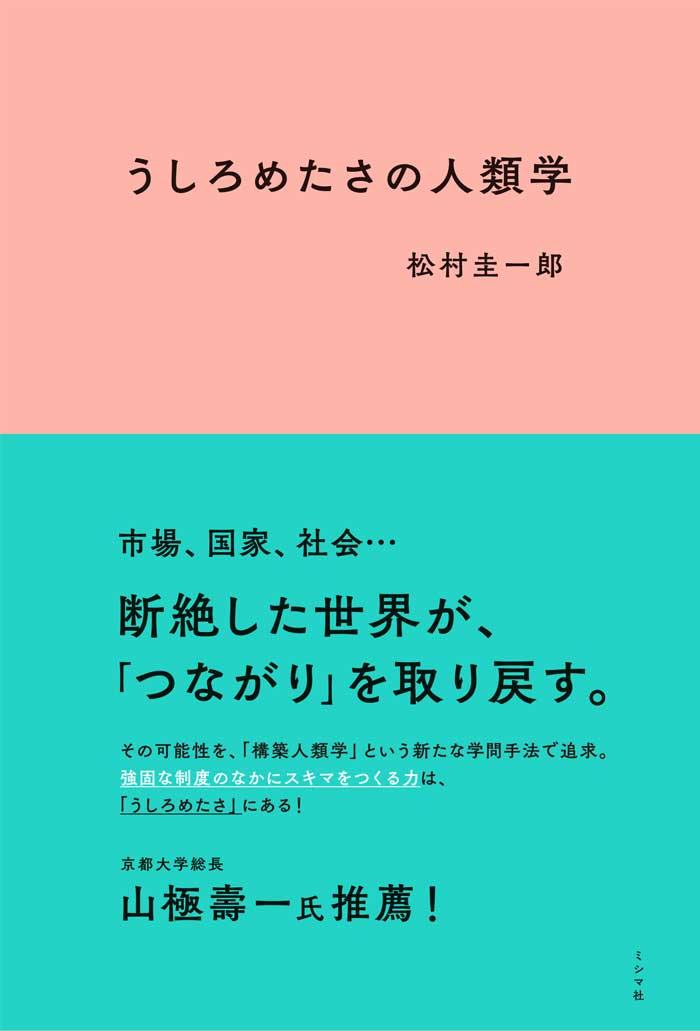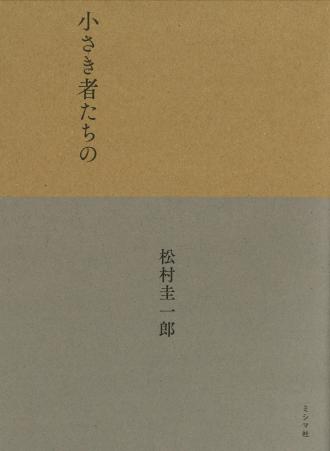第1回
はたらく
2018.04.16更新
学校の教科書に出てくるのは、英雄や文人たちの歴史ばかりだ。でも、いまこの瞬間も世界を支え、動かしているのは、教科書には載らない、名もなき小さな人びとの営みなのだと思う。ぼくら人間は、これまでどんな暮らしを営んできたのか。歴史のなかで忘れ去られてきた小さき者たちの生活誌を綴りながら、いまの世の中をとらえなおしてみたい。
***
「これまでの事業の信用のあればこそ、人さまが名を重うしてくるる。我がふところは損をしても、事業の恥はぜったいに残しとらん。人は一代、名は末代、信用仕事じゃこれは」(石牟礼道子『椿の海の記』河出文庫,216頁)
石牟礼道子の自伝的小説の一節から。「みっちん」の祖父松太郎は、石工の棟梁として建築や墓に使う美しい石を発掘したり、石山を開いたりして「石の神様」と称される人物だった。天草から水俣に移り住んでからは、道路の建設や港の開港などの事業を請け負っていた。上の言葉は、湯ノ子温泉の基礎工事にとりかかっていたときの松太郎の言葉。
松太郎は、採算を度外視した事業を重ねるたびに、自分の持ち山や土地を売り払って資材を仕入れ、人夫への払いに充てていた。娘婿(みっちんの父親)の亀太郎がその尻ぬぐいをしながら資金繰りをした。松太郎は「人さまに迷惑かくるな」と言いながらも、「お主がよかあんばいにしてくれい」と細かいことにはこだわらない。
請け負った河川工事が梅雨の大雨と大風にあって滞ると、松太郎は言った。
「請負いも人間の仕事じゃけん、信用が第一。わが請負うた仕事が、雨風のためとはいえ、期限におくれたなりゃ、財産潰してでも、出しかぶる。それが人の道。銭というものは信用で這入ってくるもんで、人の躰を絞ってとるもんじゃなか。必ず人の躰で銭とるな」(137頁)
労働者の身体を痛めつけ、病気や過労死に追いやりながら、企業が空前の利益を上げる。名だたる大企業が品質基準の数値を改竄して偽りの商品を世に出しても、露見すれば社長が交代するくらいで平然とやり過ごす。そんな世の中で、ひときわ松太郎の言葉は痛烈に響く。
いつも原稿の締め切りを過ぎてもぐずぐずしている私自身にも向けられる言葉なのだが・・・。
親族の身になれば、たまったものじゃない。姉から「どぎゃんするつもりか、こういうざまで。孫子の末まで落ちぶれさせて」と責められると、松太郎は身を小さくしながら言う。
「まあ、そういい申すな姉女。たしかに銭は、末代まで残るみゃあが、仕事だけは後の世に恥かかぬ仕事をし申したで」(138頁)。
この姉とのやりとりをふすま越しに土工たちが聞いて恐縮しながら首をすくめあう。その思いがまた、男たちの献身的な働きを引き出す。
大雨の河川工事の現場は緊迫した空気に包まれていた。松太郎は言う。
「手え抜いて決壊どもしてみろ、末代の恥ぞ。おまいどもが賃銭ば小切ったりはけっしてせんけん。・・・(土留め用の)ケンチ石のなるべく丈夫なのと取り替えて、充分、惜しまずに打ち込んでおいてくれい。素人には見えん土台のところが、いちばん肝心ぞ」(139頁)。
日暮れどき、4歳のみっちんの待つ家には、どしゃぶりの雨の中ずぶ濡れになった土工たちが脛も指の先もまっしろに水にふやけ、唇を紫色にして帰ってきた。
なんのために働くのか、会社の事業はだれのためのものなのか。仕事が自分や会社の「稼ぎ」に矮小化されている時代に、松太郎の言葉や土工たちの佇まいをしみじみと噛みしめてみる。