第2回
おそれる
2018.05.11更新
なむはちまんだいぼさつ
八大竜王さま 末神々さまに申す
今日のよか日に身をば浄め
畏(かしこ)み畏み申し ここに願いあげ奉る
(中略)
ここに香ぐわしき五穀の酒と
山なる猪の肉と珍しか山の果物 くさぐさをば供え奉る
あなかしこ あなかしこ(石牟礼道子『あやとりの記』福音館文庫, 119-121頁)
前回紹介した石牟礼道子の自伝的小説『椿の海の記』と対をなす『あやとりの記』から。同じく幼い「みっちん」の視点から、かつての水俣の小さくも豊穣な世界が描かれる。
馬車ひきを生業にする片足の仙造は、いつも萩麿(はぎまろ)という馬を連れ、野生の蘭を求めて山中をめぐり歩いている。あるとき山奥で、たくさんの「んべ(ムベ)」の実をつけた蔓が藤の大木の蔓と絡み合って館のようになった洞(うろ)に出会う。いい匂いに誘われて6畳敷ばかりの洞に入ると、木の瘤穴に「んべ」の酒が湧いていた。
酒好きの仙造は、思わずその酒を呑んでしまう。しばらく洞のなかでいい気分でうたた寝していると、愛馬の萩麿の啼き声が聞こえてくる。その日以来、萩麿は背中から尻尾にかけてひどく病んでしまい、荷を背負えなくなった。
もしかしたら、あのとき萩麿は「あの衆(し)たち」に襲われたのかもしれない。仙造は、うつろな目をしながらつぶやく。
母さんの生きておらすうちに聞いておけばよかったが、彼岸の入りの日だか、醒め日だかに、川の衆と山の衆とが入れ替わらすげなで。親が在ったあいだはおろそかに聞いておって、うっかり萩麿連れて山に往たてしもうた。しかも〔昔から馬が怖がる〕七曲りの淵の傍に。(105-6頁)
この川の衆と山の衆というのは、自然のなかに棲まう精霊や妖怪のような存在。川の衆は、山がめずらしく、いたずらをして回る。とくに馬をみつけると、尻尾の先にぶら下がったり、そこから背中に飛び乗ったりする。萩麿が啼いたのは、川の衆たちが大勢で尻尾のほうから代わる代わるぶら下がったからかもしれない。
仙造は夢うつつのなかで、「大事な萩麿 貸しやんせ さすれば 酒壺さしあぐう」という花々の声を聞く。
あの声の主は女神である山の神だったのか。「おとろしかおなご神さまぞ」。そう言う仙造に、それならこの萩麿の病を治すには男神である竜神さまに頼んでみるのがよかろう、と伝えたのは、人里離れた火葬場でひとり働いて暮らす岩殿(いわどん)だった。冒頭の祈りは、異界のことに通じた岩殿が、岬の突端の大岩に彫り込まれた八大竜王像の前で唱えた祝詞(のりと)の一節。
みっちんも、この竜神さま詣りの一行に、うしろからひょこひょことついてきた。大岩の前の木の葉を払って祈りの場を浄め、背負籠(しょいこ)からお神酒やたくさんのお供え物をとりだして盛大に飾る。ヤマモモ、ビワ、ヤブイチゴ、ヤマイモ、キノコや猪肉など、海の神である竜神に山の幸が捧げられた。みっちんも、何かないかと探して香りのよい小さな花かずらを折りとって供える。
岩殿は、うやうやしくひざまずいたり、立ち上がったりしながら、事の子細を竜神さまに説明する。
ここに中尾山の仙造が馬 萩の麿
仙造が伴をして 七曲り峠の沼に遊びに参りて
山なる姫神さまに遭い奉る
姫は神代の姫にて ことにもみめうるわしい姫なれば
畜生の魂が思わず患いまして 今日の日まで
あちらにゆきこちらにゆきして惑うて
まことに畏れ多きことながら 今日おん前に
姫神さまを乗せ参らせて 来ましてござる
いっしんに拝みつづけたあと、岩殿は竜神さまの湯呑みにお神酒を注ぎ、深く礼拝しておしいただいてから、萩麿にも呑ませる。萩麿も神さまの前にいることがわかるらしく、歯を食いしばってお神酒をいただく。
帰り途、みっちんは眠くなって岩殿におんぶされていた。眠ていると重く感じるので、「もう目ぇ覚ましとけよ、我が家が近かぞ」という岩殿に、仙造やんが声をかける。
爺やん、どら、こっちに渡しなれ。萩麿がどうやら元気じゃけん、その子は、萩麿に乗せてゆこや。(124頁)
この世は、人間だけの世界ではない。森や山には人間が不用意に足を踏み入れてはならない領域があり、あやまちを犯せば報いを受けねばならない。『あやとりの記』に描かれる多くの神々や精霊たち、そしてその異界の者たちを畏れ、祈る人びとの姿に、気づかされる。
現代の豊かな生活を可能にした石油や木材などの天然資源は、もとはといえば自然の恵みだ。人間が自分たちの力でこの繁栄を成し遂げたと考えるのは、思い上がりにすぎない。世の秩序を生み出す政(まつりごと)は、本来、こうした異界の力との交わりを司る「祭り事」だった。
自分たちをとり囲む大きな力をあたりまえのように畏れていた、謙虚で慎ましい小さき者たちの暮らしは、私たちの無知で傲慢な顔を静かに照らしだす。






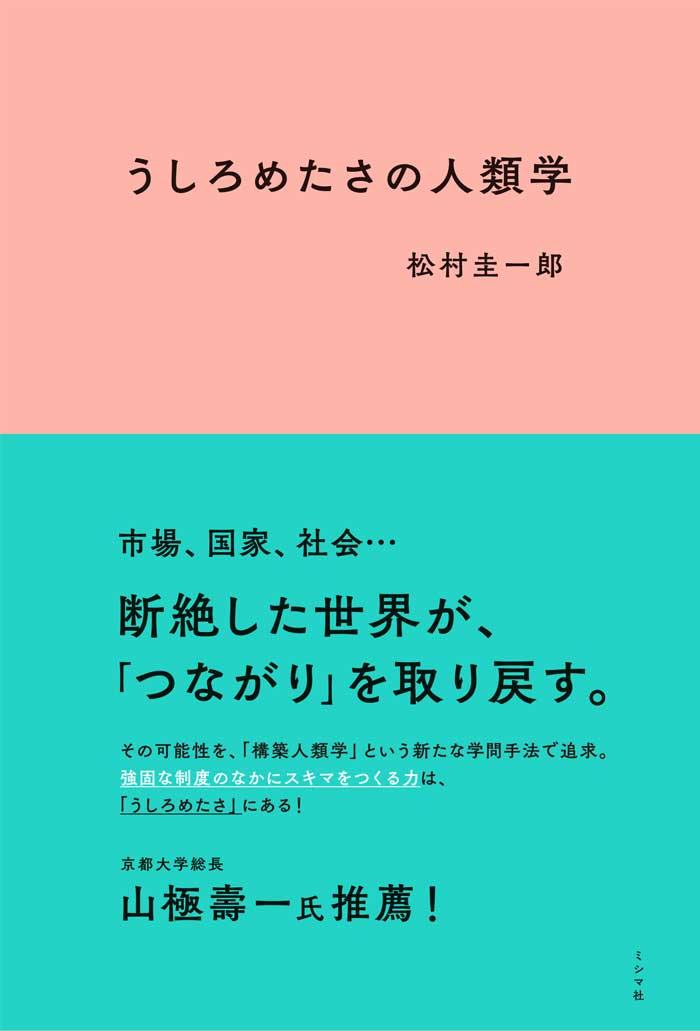
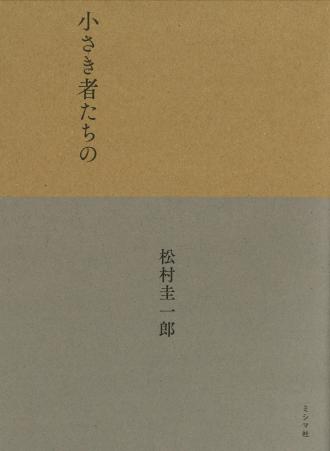




-thumb-800xauto-15803.jpg)
