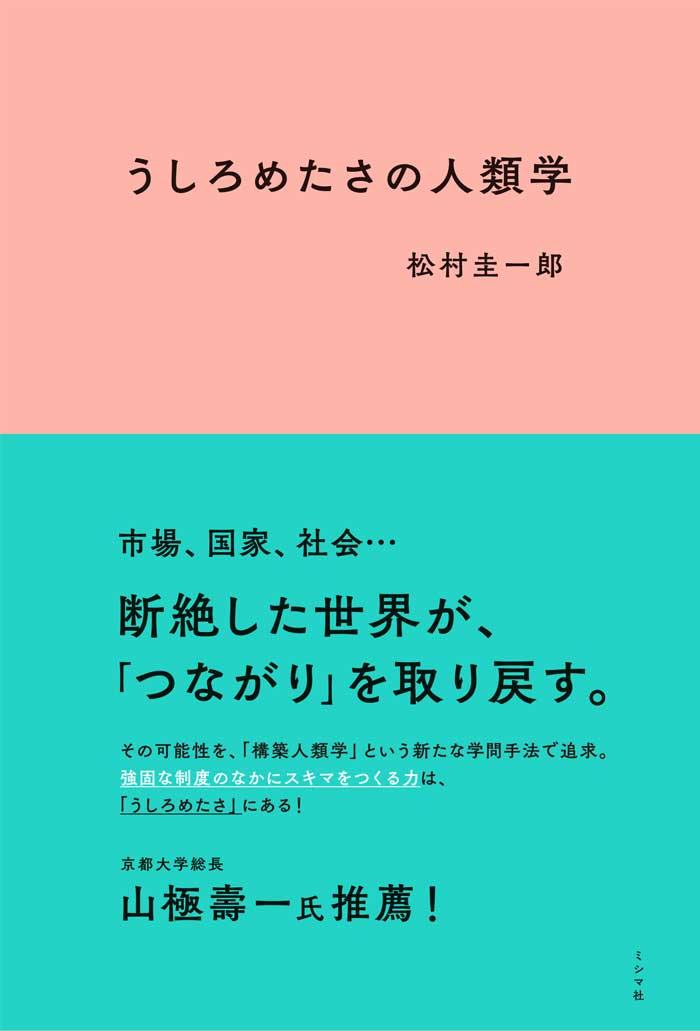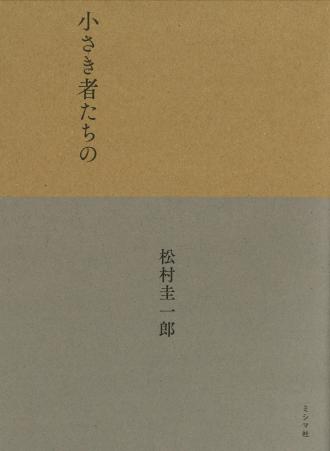第3回
いのち
2018.06.18更新
「チッソってどなたさんですか」と尋ねても、決して「私がチッソです」という人はいないし、国を訪ねて行っても「私が国です」という人はいないわけです。そこに県知事や大臣や組織はあっても、その中心が見えない。そして水俣病の問題が、認定や補償に焦点が当てられて、それで終わらされていくような気がしていましたし、チッソから本当の詫びの言葉をついに聞くこともなかったわけです。
(緒方正人『チッソは私であった』葦書房、40頁)
水俣病患者への認定と補償を求める運動に身を投じ、のちにその訴訟から身を引き、独自の運動をはじめた緒方正人の著書から。
緒方は、6歳のとき、漁師だった父親を水俣病で失う。自身もめまいや痺れに悩まされながら、父親の仇を討とうと、水俣病患者の運動に加わる。チッソに責任をとらせるため、国や熊本県にチッソに荷担した責任を認めさせるために、県庁や環境庁、裁判所などを何度も訪ねるうちに、疑問がわいてきた。そこにあるのは、ただ手続きとして制度化され、金銭に換算された「責任」だけだった。もっとも大切なはずの「人間の責任」はどこにもなかった。
緒方は、そのときの心境を「自分が目に見えないシステムと空回りしてけんかしているような気がしてきました」と吐露する。チッソの社長や役所の担当者もころころと替わり、訴訟のなかで裁判官も入れ替わっていく。そこには問いを受けとめてくれる相手も、責任をとるべき人間もいなかった。その問いかけは、むなしく自分自身に跳ね返ってくる。
商品を作れば作るほど売れて儲かるチッソという会社で自分が働いていたとしたら、「加害者」として責任を追及してきた相手と同じことをしたのではないか。絶対にしないとは断言できない。
気がつけば、自分も車を買って運転し、家には家電製品があり、仕事でプラスチック製の船に乗っている。チッソのような化学工場で生産する材料で作られたものに囲まれた生活をしている。近代化し、豊かさを求めるこの社会に、自分も生きている。そうして緒方は「チッソというのは、もう一人の自分ではなかったか」と自問する。
水俣病の認定申請をする協議会から離脱し、自身の認定申請も取り下げてひとりになったあと、緒方は3ヵ月ほど「狂いに狂っていた」。テレビの画面を見るだけで耐えられなくなり、外に放り投げて壊す。信号機や道路標識を見ても抑えがたい嫌悪感を覚える。
テレビを見ていると「あれを買いなさい、これを買いなさい、観光にはハワイに行きなさい」と一方的に言ってくる。信号や道路標識は「ここは右に行くな」「何キロで走りなさい」と決まりを押しつけてくる。あらゆる一方的に指示してくるものに、強烈な拒絶感を抱くようになった。
それは巨大な「システム社会」への拒絶反応だった。法律や制度だけでなく、時代の価値観が構造的に組み込まれている世界の恐ろしさ。このままいけば、システムが生み出す空虚な「責任」の仕組みのなかに自分も取り込まれてしまう。
水俣病事件が提起したのは普遍的な問いだ。いまも同じことが繰り返されている。では、どうしたらいいのか。緒方が手がかりにしたのは「命の記憶」だった。
不知火海の漁師たちは、「奇病」や「伝染病」が騒がれながらも、魚を食べつづけてきた。チッソを恨むことはあっても、魚や海を恨むことはなかった。子どもが水俣病にかかっても、子を産むのをやめる者はいなかった。毒を背負って生まれてくる子も受けとめ、同じように抱き、育てた。水俣病の患者は何人も殺されたにもかかわらず、被害者・漁民は加害者を一人も殺さなかった。緒方は、そこに自分の命の源を見つめてきた記憶があったのではないかと問いかける。
魚を毎日たくさん獲って、それで自分たちが生き長らえる。魚によって養われ、海によって養われている。一年に、二、三遍は鶏も絞めて食って、あるいは何年かに一遍は山兎でも捕まえて食っている。そういう、生き物を殺して食べて生きている。生かされているという暮らしの中で、殺生の罪深さを知っていたんじゃないかと思います。(62頁)
かつて漁民たちは海の潮の満ち引きとともに生きていた。満ち潮になると人が生まれ、引き潮になると人が亡くなると言われていた。そこには海と人とが心を通わせ、ことばを交わし合う世界があった。
家の下のところの、満ち潮のときは海水がひたってきて、引き潮のときに洗うように帰っていくのを見ていると、"元の海のところまで行きたいんだ"という潮の意志、海の意志みたいなものを感じるんです。"ここまでは人間たちのものじゃなくて、海のものだったんだ"という、何か意志めいたもの。これはすごいなあと思うんですね。(167頁)
問題の本質は、認定や補償ではない。世界に生かされて生きている。命がさまざまな命とつながって生きている。それを身近に感じられる世界が壊され、命のつながりが断ち切られた。水俣の漁民や被害者たちの「闘い」は、この尊い命のつらなる世界に一緒に生きていこうという、あらゆる者たちへの呼びかけだったのだ。
空虚な制度化された「責任」が垂れ流される時代に、緒方が投げかける言葉は私たちの胸を鋭くえぐる。