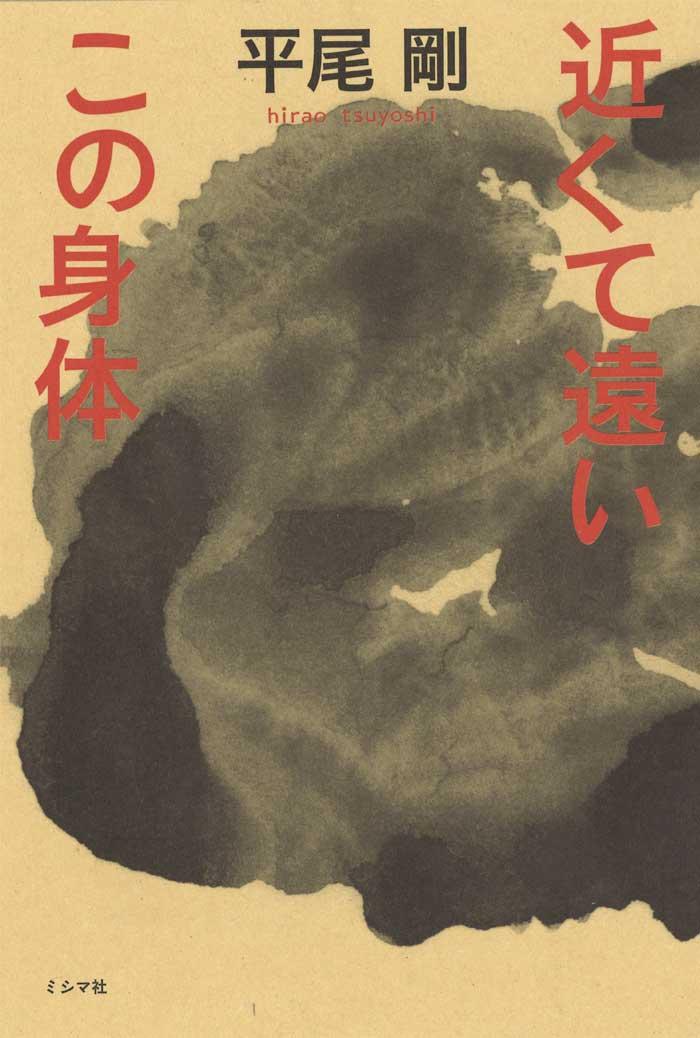第3回
努力の可視化
2018.06.11更新
前回は筋力アップのメカニズムについて書いた。筋トレとは、生理学が明らかにした「超回復理論」に基づくからだの鍛え方である。ウサギ跳びや階段ダッシュを繰り返すなど、根性論のもとにひたすら苦行的運動を繰り返していた時代を思えば、隔世の感がある。
いや「隔世の感」という表現はいささか大げさかもしれない。というのも僕がラグビーを始めた30年前には膝を痛めるとされるウサギ跳びはすでに行っていなかったし、水分補給にしても3時間弱の練習中にたった2回、許されているだけだった。
現在のように、薄めたスポーツドリンクの入ったスクイーズボトルがグラウンドのあちこちに置かれ、喉が乾けばいつでも飲めるようになったのは、ようやく大学に入ってからである。制限されたり推奨されたり、「いったいどっちが正しいねん」と当時は思いながらも、喉の渇きを我慢しなくてもよい環境への変化はやはり歓迎すべきことで、もうトイレに行くふりをして蛇口に口をつけなくてもよいのかと、安堵したのを憶えている。
ウサギ跳びをしたり、喉の渇きを我慢するなどの非科学的で苦行的な取り組みが常識だった時代を、僕は直接的には知らない。かなり年上のOBから、「昔はなあ・・・」というやや上から目線の語りの中で聞くことはあっても、実際には経験していない。
僕がラグビーを始めた1988年から大学を卒業する1998年くらいまでは、根性論に換わって科学的知見に基づく考え方が徐々に広まりつつある時代だった。
僕が最初に筋トレを始めたのは高校3年生のときだった。今からちょうど25年前だ。正確にいえば高校に入学してからすでにバーベルやダンベルを持ち上げてはいたが、それは雨天時にグラウンドが使えないときに限って仕方なく行っていただけで、本格的にからだを鍛えていたとは到底いえない。どのくらいの重さを何回持てばいいのかも、正確なフォームもわからずに、練習時間が過ぎ去るまでのほとんど「時間つぶし」だった。
それが最終学年になったことで向上心が芽生えたのか、あるときからチームメイトと一緒にせっせと励むようになった。
昼休みのチャイムが鳴るや否やすぐウエイトルームに足を運んだ。おもに大胸筋を鍛えるベンチプレスにハマっていて、チームメイトと互いに補助をしながら肉体の限界まで追い込んだ。するとみるみるうちに持ち上げられる重量が上がってゆく。と同時に、胸のあたりが盛り上がってくる。重量という具体的な数値が上がれば努力が実っている実感が湧くし、鏡越しに見る自分のからだがだんだんたくましくなってゆくのだから、楽しくてやめられない。
そのうち腕を鍛えるアームカールもメニューに組み込んだ。トレーニングを続ければ続けるほど胸が盛り上がり、腕も太くなった。胸板や二の腕の太さは男らしさの象徴だ。だから思春期の男子にとって筋肉を鍛えるのは男らしさを身につけることと同義だった。ラグビー選手だからそれなりにゴツいからだでなければいけないという見栄もあった。さらにぶっちゃけると、女の子にモテたいという不純な動機も大いにあって、今から思えば決して模範的とはいえないラグビー選手だったように思う。
高校3年生だった当時の僕が筋トレに励んだ理由は、恥ずかしながら「見た目のたくましさ」を求めてのことだった。ラグビー的な動きを研ぎ澄ますために筋力をアップさせるという意識は乏しく、ほとんどなかったといっていい。競技を極めるという意志は皆無に等しく、筋肉がつけばそれなりに競技力は上がるだろうという、漠然とした期待は抱いていたにせよ、目的はあくまでも見た目に映えるボディだった。
残念なことに当時の顧問は筋トレに関する専門知識を持っていなかったし、からだを鍛えるための方法を指導するトレーナーという職業も今ほど重要視されておらず、身近にもいなかった。筋肉がつくことでもたらされる競技面での効果や、ラグビーに求められる動きの向上につながる鍛え方などを教えてもらう機会に恵まれなかったという切ない理由もある。これはなにも僕が所属したクラブだけでなく、一部の強豪校を除けば似たような環境だったのではないかと思う。
まだまだスポーツ科学が未発達で、実際の活動現場に浸透していなかった時代に僕は筋トレを始めたのである。
バーベルやダンベルの上げ下げを繰り返す単純な運動が、なぜあんなにも楽しかったのか。たぶんそれは先ほど述べたように「目に見えるかたち」で成果が現れるからだろう。
持ち上げることのできるバーベルの重量がトレーニングを重ねるごとに上がってゆく。30kgが35kgになり、40kg、50kg・・・と、「日ごとに」というのは大げさにしても時が経つにつれて上がる。それと合わせてバーベルを上げ下げする回数も確実に増える。先々週よりも先週、先週よりも今週と、右肩上がりに成果が上がる様子を数値として把握できるのが、この上なく楽しかった。来週になれば今よりもっと重い鉄の塊を持ち上げることができるようになるのだろうという明るい見通しも立つのだから、意欲もどんどん湧いてくる。
それにともない、鏡越しに映る自らのからだも目に見えてたくましくなる。今まで着ていたTシャツがタイトになることも一つの「勲章」で、気に入って購入した洋服が着られなくなった切なさよりも、からだが鍛えられてゆくその手応えには大いなる充実感があった。通りすがりに窓ガラスに映る自分の姿に惚れ惚れし、胸や腕を触っては筋肉の張りやその太さを体感する。「オレも一端のラグビー選手になったか、いや、男らしくなってきたやないか」と自画自賛していたあのころは、思い出すのも憚られる苦い思い出である。
努力が可視化できる。おそらく筋トレがもたらす最大の愉悦はこれだろう。
運動習得の場面を具に観察してみると、動きの習得に至るまでのプロセスにおいて自分が上達しつつあることへの実感が湧くことはほとんどない。ある技術が身につくまでの道のりでは、今の自分が上達しつつあるのか、それとも停滞しているのかを、目に見えるかたちで把握するのは原理的に不可能である。なぜなら上達の手応えは、あくまでも感覚的なものだからだ。練習を続けることでからだがその性能を高めてゆくことに間違いはないのだが、そのプロセスに身を置く者が自らの習得度合いをリアルタイムに実感することは難しい。練習に励む選手は、ときに上達の大いなる手応えを感じることはあっても、その競技に取り組むほとんどの時間は「上手くなっているような気がする」という感覚的な余韻を、ほのかに感じるだけである。
運動習得を主題に置くスポーツにありがちなこの「わからなさ」の、依ってきたるところを表現したものが「気合」や「根性」だろう。
スポーツを始めとするすべての身体運動において、上達を果たすためには苦しくツラい練習は避けられない。自らの限界を超えて上達を果たしたのはそうした練習を乗り越えたからである。苦しい練習に耐えることができたのは強靭な精神が備わっていたからで、つまりのところ「気合」や「根性」などの精神性こそ上達するためには欠かせない。「気合」や「根性」なくして上達することなどありえない。
と、これが根性論が大手を振ってまかり通る大まかなロジックなわけだが、この論を認めてしまうと上達のプロセスはブラックスボックスと化す。とにかくツラい練習に励めばよいのだと勘違いしてしまう。
この身に渦巻く「わからなさ」のただ中で、ああでもこうでもないと試行錯誤することこそが運動習得の醍醐味なのに、なかなか結果が出ない中で感覚を探りながら練習に打ち込むことで、数値化に馴染まないさまざまな身体の能力が開発されるのに、上達の源を「気合」や「根性」とみなすことでこの実りあるプロセスが覆い隠されてしまうのは、スポーツの価値そのものを毀損することにつながりかねない。
話が逸れた。
筋トレは上達のプロセスそのものが可視化できる。重量や回数が数値で表される。鏡に映る姿がたくましくなる。洋服のサイズが合わなくなる。さらには力んだときの身体実感である「力感」がありありと感じられるなど、上達途上で具体的な手応えが返ってくる。これは清々しい。とても気持ちがよい。
根性論的な指導に慣れ親しんだ18歳の青年は、ここに無上のよろこびを感じていた。
スポーツ界において非科学的で根性論的な指導が当たり前だった時代に、突如として筋トレという鍛錬法が導入された。僕がそうだったように、努力が可視化できるこの方法におそらく幾多の選手が飛びついたのは想像に難くない。これまで曖昧にしか捉えられなかった上達の軌跡が目に見えるかたちで示されるのだから、楽しくないわけがないのだ。
指導者の立場からみても、数値を比較することで選手を「公正」に評価できるようになるのだから当然のように歓迎される。1カ月前の数値と比較して、上がっていれば努力した、下がっていればサボっていたと判断する。レギュラーメンバーを決める際にでも、数値の上げ幅で努力の度合いを図って、高い方を選べば反論をかわすことができる。数値は誰の目にも明らかなエビデンスとなるからだ。
かくして筋トレはスポーツ界に広く行き渡った。曖昧模糊とした「気合」や「根性」でしか説明できなかった努力の度合いや上達のプロセスが、筋トレという科学的な手法を用いることで数値に置き換えられ、可視化できるようになった。以前に比べてわかりやすくなったことは確かだ。
だが、そうすることで失われるものがある。つい見落としてしまうものが、ある。
次回はそれについて書いてみよう。