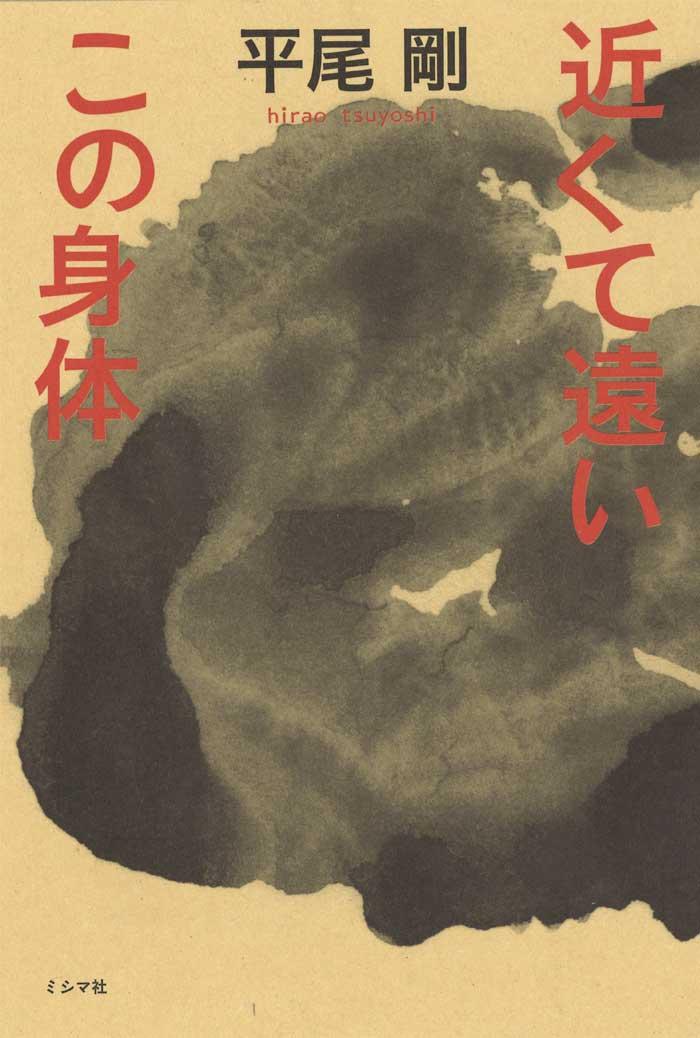第8回
筋肉が枷にならないように
2018.11.07更新
前回は各競技のトップアスリートがどのようにからだを捉え、練習に取り組んでいるかを取り上げた。言葉による表現にニュアンスの違いはあっても、その根底にあるのはやはり「全身をくまなく連動させる」という考えだった。特定の筋肉に負荷をかけて鍛える筋トレは、きっぱりと忌避するか、あるいはそのやり方に工夫を凝らすなどして、彼らは独自の方法を編み出していた。
各選手のコメントを読み解くなかで、思わずドキリとした言葉がある。長友佑都選手の「逆に鍛えた筋肉が重くなるだけ」と、谷口徹選手の「(...)柔軟性が失われる」である。
あれは三菱自動車工業京都に入社したばかりの社会人1年目だった。翌年にW杯を控えたこの年、僕は日本代表候補選手に選ばれていた。足の速さとステップの鋭さが買われて候補選手に選出されたものの、如何せん体格がまだまだ華奢だった。からだをぶつけ合うラグビーでは、体格差がそのまま競技力に直結する。いくらスピードがあっても体格に劣ればパフォーマンスは発揮できない。181cmの身長に対して当時は80kgを少し切るくらいの体重で、これだと世界レベルでは到底通用しない。
日本を代表する選手として世界の舞台で戦うためには今よりもっと筋肉をつけて体重を増やさなければならない。スピードとステップは認めるが、それを発揮するためのからだの強さを身につけなければ代表に選ぶことはできない。当時代表監督だった故平尾誠二さんから直々にそう言い渡された。タックルやDF突破などのコンタクト局面で脆さを露呈していた僕は、耳は痛いが至極もっともな指摘に一念発起し、体重増量のため本格的に筋力トレーニングをすることに決めた。
仕事が終わったあとに、またチーム練習の合間を縫ってトレーニングに励んだ。グラウンド横に建つクラブハウスの2階にジムがあり、そこで汗を流した。筋肉で体重を増やすには大胸筋や大腿四頭筋などの「大筋群」を鍛えるのが近道だ。そうトレーナーから教えられ、それらを重点的に鍛えるベンチプレス、スクワット、デッドリフトを中心に、来る日も来る日もバーベルやダンベルを持ち上げた。重量やその回数を、無印良品で買ったシンプルなノートに記録した。
上半身と下半身に分け、一日ごとにそれぞれをいじめ抜く。だから毎日が筋肉痛との闘いだ。階段の上り下りはもちろん、職場のデスクに座ってパソコンのマウスを動かすのさえつらいときもあった。
だが、日が経つにつれて、いつも疲労感がつきまとうからだにも徐々に慣れてくる。それと同時に、持ち上げられる重量も体重もだんだん増える。目に見えるかたちで努力の成果がわかるこの日々に、僕はいつしか充実感を覚えるようになった。
そうして2ヶ月が過ぎる頃に、体重は約10kg増加した。重量も体重も目標設定された数値をクリアした。90kgの大台に乗ったときのうれしさは今でもはっきりと覚えている。これでようやく代表候補選手としてスタートラインに立てる。ホッと胸を撫で下ろした。もしかするとW杯に出場できるかもしれない。期待に胸が躍った。
しかし、である。
体重増加後の生まれ変わったからだで出場した公式戦で、思いもよらない事態が待ち受けていた。これまで感じたことがないほどからだが重いのである。まるでギトギトした油が全身にまとわりついたように、からだが言うことをきかない。とにかく動きが鈍重なのだ。
なにより驚いたのは、僕が最も得意としていたステップが踏めないこと。パスを受けて走り出そうとしたその瞬間、いつものようなキレがない。頭に描いた「左に行くと見せかけて右に走る」というイメージとは裏腹に、その一歩が出ない。とにもかくにもスローなのだ。ステップを踏むときに体内で流れるいつものリズムを刻むことができず、すぐ相手DFにタックルされてしまう。
焦った。頭が真っ白になった。
とはいっても試合は進行中だ。この鈍重なからだでも、ひとまずこの試合は乗り切らなければならない。頭を切り替え、長所を奪われた身でこの試合をどう乗り切ればよいかを考えた。たどり着いた結論は、相手DFを揺さぶるステップを封印して、パスを受けたらとにかく相手にまっすぐぶつかることだった。
幸い、以前より体重が増加したためにぶつかったときの威力は高まっていた。コンタクトが生じた瞬間のあの安定感は、今までに経験したことがない体感だった。これが筋トレの効果なのかと、今まで取り組んできた成果を感じて少し安堵した。
でも、全然楽しくなかった。いくら筋トレの効果があったとしても、長所が発揮できないでいる今の状態を肯定できるはずもない。世界の舞台で鋭角なステップを活かすための筋力増量が、そのステップを封印する枷となっていた。翼をもがれた鷹は、もはや鷹ではない。牙を抜かれたライオンは、猫にも等しい。ラグビー選手としてのアイデンティティを揺るがすこの事態に、僕は大いに戸惑った。
試合後すかさずある先輩から、「お前ってそんなプレースタイルやったっけ?」と突っ込まれた。まさか「からだが重いんです」とは言えず、適当な受け答えをしてその場をはぐらかすしかなかった。
今だからわかる。あのときの僕のからだは、単純な筋トレの繰り返しで連動性が失われていたのだ。全身をしなやかに使わなければ発揮できない高度な動きとしてのステップは、だからできなくなった。「つけた筋肉」が単なる重りと化し、柔軟性をも損なってパフォーマンスを阻害していたのである。
そこからは筋トレを控えた。ほどなく体重は5kg減り、それでもまだしばらくは重苦しさが残ったものの、ひたすらラグビーの練習に励むうちに、徐々にではあるがこれまでの感覚を取り戻した。この間、約半年。「つけた筋肉」が「使える筋肉」になるまでに、つけるまでに費やした時間の3倍もの時間を要したのである。
それ以降も筋トレは続けたものの、どこか「手を抜いていた」ように思う。体重を維持するために、あるいは首脳陣にアピールするために、仕方なくバーベルを握った。だが、著しくパフォーマンスが落ちたこのときの経験が脳裏から離れず、どうしても真剣になれなかった。きっぱりやめられなかったのは僕の意志の弱さゆえのことだ。
だからといって、あのとき筋トレに励んだことを後悔していない。90kgという目標には届かなかったものの5kgの体重増加に成功し、その甲斐もあって1999年のW杯に日本代表として出場することができたのだから。筋肉痛と闘ったあの日々があるから、31歳までラグビーを続けられたわけで、だから否定はしない。ただ、もうちょっと違う方法があったのではないかという反省はある。ラグビー的な動きに即したかたちでからだ作りに励んでいれば、結果は違ったのではないか。もっと上達できたのではないかという、ちょっとした後悔が今もまだ胸に渦巻いている。
ここから汲みとるべき教訓は、短期間で急激に行えばそれ相応の反動がくるということだ。筋力トレーニングは、金属の塊を上げ下げするための筋力を養いはするが、ラグビーに求められる複雑な動きを可能にする筋力はつかない。専門的で特殊な動きはやはりラグビーに特化した練習をするなかで徐々に身についてゆくもので、ただ筋力だけを鍛えるのはパフォーマンスを高める方法としては間違っている。
それでも筋トレに励む。ラグビーのような体重増加が必要な種目では、僕がそうであったように筋トレを行う必要がある人も多いだろう。あるいはチームとして筋トレを強いられている。筋トレ信者が後を絶たないスポーツ界だから、そんな環境下での子供や選手は多いはずだ。どうしても筋トレを免れない人たちに、筋肉が重りにならず、柔軟性を損なわないための取り組み方について以下の点を提案しておきたい。
・メニューごとに設定された正しいフォームにこだわらず「ラクに」持ち上げる
・短期に結果を求めない
・筋トレ後は、その種目における専門的な動きを取り入れる
・筋トレ期間中は練習でも試合でも全力でプレーしない(連動性が失われたからだは怪我をしやすいから)
・重さや軽さなどからだの内側から得られる体感に耳を傾け続ける
ここに通底するのは、身体感覚に正直になることだ。ここまで繰り返し書いているように、感覚世界に身を置くということ、つまり感覚を鋭敏にすることこそがパフォーマンスを向上させ、健やかなからだになるのだ。
からだは機械ではない。自然科学的な論理にも馴染まない。からだを機械に見立て、合理的かつ効率的に鍛えるための筋トレは、適当な距離を置きつつ慎重に行わなければならない。もちろん単純な筋トレはやらないに越したことはないのだが、どうしてもというのなら、もともと高性能なからだの機能を毀損しないために身体感覚を手放さないのが、ミソなのである。