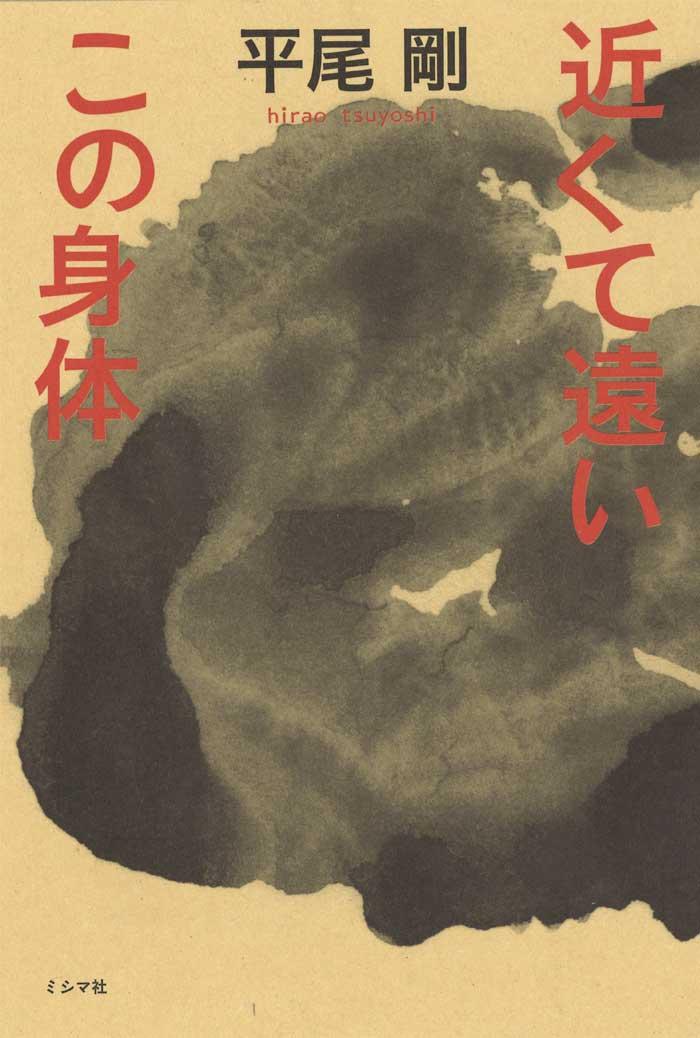第11回
身体知とは〜形態化身体知その2〜
2019.02.11更新
前回記事「身体知とは〜形態化身体知その1〜」はこちら。
コツについて書いている途中であった。
かんたんにおさらいをしておこう。
発生論的運動学では動きを形作るためのコツとカンを形態化身体知といい、それをさらに細かく分けるとコツを自我中心化身体知、カンを情況投射化身体知と呼ぶ。からだの内側に意識を向けるという意味で「自我中心化」と表し、動きの正当性を身体感覚としてつかむのがコツである。この動感はさらに細かく4つに腑分けすることができる。運動しているときに体感をつかもうとするのが触発化能力、その体感が「しっくりくるかこないか」を判断できるというのが価値覚能力である。
と、ここまでが前回で書いた内容である。
よって今回は残りの2つを説明することにしよう。
まずは共鳴化能力である。一言でいえば、これは動きの流れがわかる力のことだ。
走る、投げる、シュートをするなど、どのような動きであっても必要なのが「ある一定の時間」である。動きの種類によってその長さは変わるにしても、動き出してから一連の動作を終えるまでには「ある一定の時間」を要する。
たとえば「跳び箱を跳ぶ」という場面を観察してみると、助走を始め、ロイター板を踏み込み、上体を前方に投げ出しつつ跳び箱に両手をついて脚を開き、着地に至る。どれだけ助走をするかによってその時間は変わってくるが、長く見積もっても10秒に至らないほどの時間がかかるわけである。これらを一連の流れのなかでスムースに行うことが、跳び箱を跳ぶ、ということになる。
共鳴化能力は、この時間感覚をからだが理解しているということである。
学校体育の授業を思い出していただきたい。跳び箱の授業では、助走は全速力ではなく勢いをつける程度で、ロイター板は両脚で踏んで反動をつける、両手をつく場所は手前ではなく奥に、両手をつくと同時に脚を開く、着地は両脚をそろえるなどの、動きを細分化してそれぞれに求められるコツを、個別的に体育教師から教えられたはずだ。
これらのコツをつかむために、助走をする、ロイター板で踏み切る、手をつく、あるいは着地をするなど、全体の動きから切り取って個別具体的な練習をする。そうしてつかんだひとつひとつの動感をつなげて、一連の流れで行うことによってようやく跳び箱を跳ぶという動きは完成するわけだ。
助走の速度はわかる、ロイター板を踏み込む感じもわかるし、両手の置きどころもなんとなくわかる。でも何度試してみても一向に跳べないという事態に、心当たる人は多いのではないだろうか。わかっているのにできないというこのつまずきは、一連の流れで動くというこの「共鳴化能力」が空虚である蓋然性が高い。
また、できない動きに挑戦するときにはそれなりの恐怖や不安がつきまとう。それらを乗り越えなければならないという点で、一定の精神力が求められるが、ここにもまた乗り越えなければならないハードルがあるわけで、流れに身をまかせるという所作は感覚的にも心理的にも思いのほか難しい。
発生論的運動学には「動感メロディー」という専門用語がある。一連の流れで動くときに内在的に発生する動感を、「音楽」にたとえているのはとても興味深い。
細分化された動きに必要なそれぞれのコツをつかむことで生成された動感が音符だとすれば、それにリズムやテンポを加えることで一つのメロディーになる。つまり、個別的な動きの動感を身につけるのは「五線譜に音符を書き込むこと」、一連の流れで動くというのは「その楽譜をもとに実際に奏でること」になり、この後者を共鳴化能力というのである。
だからこそ個別的な動感がおおよそ芽生えたあとは、細かいことを考えずにやってみることが大切だ。「助走は勢いをつけるだけ...」「ロイター板には両脚でしっかりと...」「手は奥につかなくては...」などと、頭の中で復唱しているだけではこの力は養われない。細かなコツを思い浮かべるのを一旦やめて、時間の流れに身を委ねる。自らのからだが動きたいままにまずはやってみるという態度が動感同士のつながり、つまり「動感メロディー」を生む。求められる動きの全体像を朧げながらでも描けていれば、たとえ細部が詰め切れておらずまだまだ不明なことがあったとしても、とにかくやってみることで互いのコツが共鳴化し、「動感メロディー」が流れるのである。
たとえばピアノならば、人差し指で音符をひとつずつ押しているだけでは耳に心地よい音楽にはならない。手のひらを広げ、リズムよく鍵盤を押すことで音符と音符がつながって旋律が生まれる。そういうことである。
もうひとつは「図式化能力」である。これは「確かめ」ができる力のこと。もっと具体的にいえば、その動きの中でどのコツが重要なのかが体感的にわかるということである。
先にも述べたように、一つの動きの中にはいくつもの細かなコツが散りばめられている。実際に運動する際にはそのすべてを意識して行うことは難しい。動きを細分化して個別的に練習をするときにはコツを意識化できるが、動感メロディーが流れているときにそれは不可能に近い。これはひとつひとつの音符をすべて意識しながらでは曲を演奏できないのと同じである。反復練習で身についた無意識的な動きができなければ、より高度な曲を奏でることも、もっと複雑な動きを実践することは叶わない。
とはいえ、やはりポイントなるコツは押さえておかなければ、体感を深化したり、動きそのものに修正を加えるときには路頭に迷う。習得した動きを再現する際のフックとしてのコツを、いくつもの細かなコツの中から抽出しておく。動き全体を図式化しておくことで、しっくりくる動きとそうでない動きの区別ができる。つまりあるコツがもたらす動感だけは手放さないという態度が重要になる。
逆にいえば、この図式化能力が充実していればわざと失敗できる。フックとなるコツをあえて手放すことで、求められる動きを解体することができるというわけである。
音楽でいうなら、フォルティシモやピアニッシモ、クレッシェンドやスタッカートがこれにあたるだろう。今までのスポーツ経験や運動そのものへの好悪によって、その人が動きを身につけるために最適な楽曲は異なる。コツを集めて楽譜を完成させたあとは、その楽曲を自分のからだにあった曲調に仕立て上げていく。楽譜をもとに楽曲を演奏するように、動きを仕上げるために必要な身体知が図式化能力である。
以上がコツの構造である。
おそらく多くの人が動きを習得するためにコツをつかむときに、知らず知らずのうちにこうした能力を発揮している。
その昔、ひとつひとつのコツを身につけるために真面目に取り組んだものの思うように動きが身につかなかった人は、もしかすると「価値覚能力や共鳴化能力が空虚」だったのかもしれない。そもそも動感を感じようとしていなかった人は「触発化能力が空虚」だった蓋然性が高い。あるいはしばらくその動きをせずにいたら途端にできなくなった人は、「図式化能力の空虚」に思い至るかもしれない。
感覚世界はとかく奥が深い。
次回は情況投射化身体知であるカンについて書く。