第14回
身体知とは〜洗練化身体知〜
2019.05.20更新
ここまで身体知について書いてきた。
私たちが「生まれつきの運動神経」と認識しているのが「始原身体知」、それに基づいて「特定の動きを身につけるための能力(コツとカン)」が「形態化身体知」である。この2つについて、ここまで身近な例を挙げながら説明してきた。
運動習得のための身体知にはこれらに加えて「洗練化身体知」も含まれる。これは読んで字のごとく、動きを洗練させていくための動感感覚である。形態化身体知が、できないことができるようになる、すなわち「ゼロを1にする」ためのものであるとするならば、この洗練化身体知はすでに身につけた動きをより精妙にしていく、つまり「1を2や3」にしていくために発揮される。
野球ならば、投げるという動きを身につけたのちに、球速を上げる、カーブなど様々な球種を投げ分ける、制球力を上げるといったことになる。バッターだと打ち方を身につけたのちに、ライトにもレフトにも打ち分ける、わざとファールをするなどがこれに当たる。動きそのものの質を深める、すなわち磨き上げていくときにも固有の身体知が存在するのである。
ただこの身体知は、集中的に一つの種目に打ち込むときに主に必要となるもので、その内実はより専門的な分析と、それに基づいた記述が求められる。その性質から微に入り細を穿った表現をせざるをえず、そうして書かれるテクストはどうしても論旨が複雑になってしまう。身体感覚は言葉で理路整然と語れないからだ。たとえ複雑性を伴うテクストであっても、集中的にスポーツに取り組むなど運動習得にわりと真剣に打ち込んだ人なら腑に落ちると思われるが、運動そのものに二の足を踏む人たちにはいささか意味不明な内容になる蓋然性が高い。
そもそもここまで身体知が何たるかを説明してきたその目的は、筋トレがつい見落としがちな感覚世界を明らかにすることであった。この当初の目的から逸脱しないよう、またあまりに複雑なロジックで読者が置き去りにならないように、ここでは洗練化身体知のうちのいくつかを抜粋するにとどめたい。その全貌についてはまた稿をあらためて書くことにする。
でははじめる。
身につけた動きを洗練化するための身体知のひとつに「優勢化能力」がある。これは左右差を感じ取ることができるというものだ。
誰しも利き手や利き足、利き目がある。操作しやすい方の手でお箸を持ち、鉛筆を持つ。ボールを蹴るとき、あるいは道端に落ちている石ころを蹴るときには、利き足を使う。ものを見るときに私たちは両目で捉えていると感じてはいるが、実は利き目を中心に使っている。手も足も目も右と左が一対になっていて、そのあいだではどうしても得意不得意の差が生じる。
だがほとんどのスポーツにおいて左右差はない方がよい。サッカーなら右脚でも左脚でも蹴れた方がよいのは言わずもがなだ。バレーボールのオーバーハンドパスやアンダーハンドパスは、利き手に力が入りすぎないように両手をうまく調和させないとうまくボールをコントロールできない。ラグビーだとパスやキックは左右差なく行えるのが理想だ。
利き手や利き足の使いやすさに頼るのではなく、その使いやすさから出発して利き手や利き足とは反対の手足に意識を向けてその差を感じ取る。そして、使いにくさという違和感を解消すべく左右の調和を図ることで動きは洗練化されてゆく。だからアスリートは、あえて苦手な方の手足を使って投げる、蹴る、箸を使うなどして、身体感覚を深めるように努めるのである。
ちなみに私は利き手とは逆の左手でも箸を使って食事ができる。これは左右の調和を図るべく、ある時期に左手での食事を集中的に取り組んだ結果である。
この他には「力の入れ方」を仕上げるための身体知がある。
そのうちの1つであるリズム化能力とは、文字通り動きのリズムを感じる力だ。これは形態化身体知のときに述べた共鳴化能力の発展版といっていい。動感メロディーが奏でられるようになったのちに、そのメロディーのリズムを意図的に変えることでその動きは洗練化する。
4ビートよりも8ビート、8ビートよりも16ビートの方がより小刻みな動きになるのは自明だ。同じ楽曲であっても刻むビートの数で曲調は大きく変化する。リズムを変えることで動き全体をハンドルし、情況に応じて力の入れ方を調整する力がリズム化能力である。
これに続く2つ目は伝動化能力である。これは勢いを伝える力で、たとえば幅跳びでは助走の勢いを損なわないようにジャンプしなければならない。速度を上げて勢いよく助走しても、踏み切るときにそれをうまく伝えられなければ遠くに跳ぶことは叶わない。ボールを投げるという動作も、体幹をひねったり振り被るなどして得た勢いをうまくボールに伝えなければ、速球は投げられないし遠くまで飛ばない。勢いはからだの内奥に溜め込んだエネルギーを放出することで生まれる。助走や振り被ることで溜め込んだエネルギーをうまく利用する力が伝動化能力である。
これと似たような身体知に弾力化能力がある。これは反動を利用する力で、たとえばボールを蹴るときだと軸足で、あるいはボールを投げる場合なら踏み込み足で、地面からの反力を受け取る動感である。この弾力化能力は先ほどの伝動化能力とセットで発揮されることが多く、さらにリズム化能力とも連動していて、総じて「力の入れ方」を深める身体知だといえる。
以上が、私たちのからだに備わっている身体知の概要である。すべての動きは、これらの身体知がそれぞれ連動し、呼応し合いながら発揮されている。運動主体は、そのように動きたいという意欲に支えられて、ほとんど無意識的にこれらの身体知を駆使している。
これまでにも述べたけれど、運動そのものを根っこで支えている身体知のひとつひとつは、決して数値化できない。だからわかりにくい。向上しているかどうかの手応えも曖昧で、身体実感に乏しい。だから瞬発力や持久力、筋力などの目に見えてわかりやすい数値化できる能力につい意識が向く。
だが、運動習得場面では実際にこのような身体知が「このからだ」に息づいていることは、忘れてはならない。
筋トレは身体知が発揮される豊穣な感覚世界から意識を逸らす蓋然性がある。怪我を誘発し、動きの質を深める契機を損なうというこの弊害を見過ごすことは、長らく「このからだ」と向き合いつつスポーツに打ち込んだ者からすれば到底できない。ハイパフォーマンスを獲得するためにあくせくした日々から学んだことは、後世に正しく伝えなければならない。あとに続くスポーツに親しむ者、とくに子供たちに向けて、ここに落とし穴がある、この先は断崖絶壁が立ちはだかるといった標識を立てておくのが、先輩としての使命だと私は思っている。
科学はスポーツを変えつつある。しかもその変容のスピードはものすごく速い。わかりやすく、そして便利になるということは歓迎すべきではある。だが速度があまりに速すぎて、決して変えてはいけない真理をも侵食している気がしてならない。科学的知見によって発展したことはもちろんあるが、「わかりやすさ」を追求するがあまりに捨象される現象が多すぎると私には感じられる。
その一つが感覚世界なのだ。
19年ものあいだラグビーというスポーツに打ち込んで、ようやくたどり着いた地点から見える景色のひとつが筋トレの弊害である。それはすなわち感覚世界の矮小化であり、身体知の空虚化である。紆余曲折の過程でつかんだ身体実感と、これまでの研究を合わせて、ここに警鐘を鳴らす次第である。
*この連載が『脱・筋トレ思考』として単行本になります。発売は、2019年8月刊行予定! ぜひご期待ください。





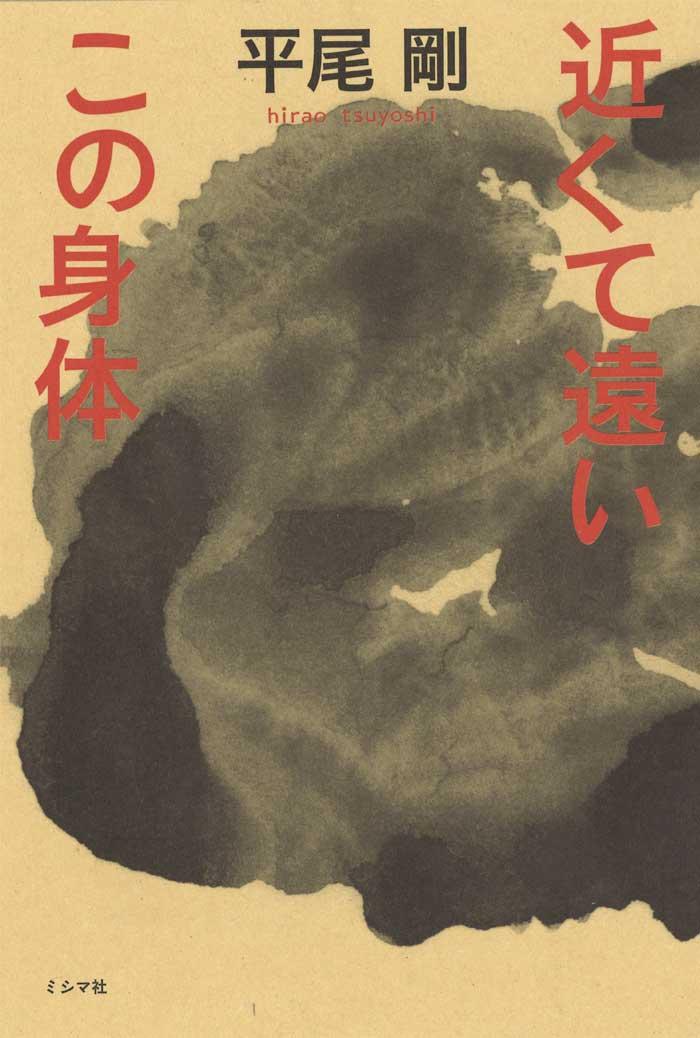


-thumb-800xauto-15803.jpg)


