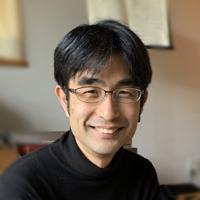第2回
「もれ」についてーー「直耕」としての食(2)
2020.03.23更新
「もれ」の効用
どうやら、「育つこと」と「交合すること」は、「もれる」というはたらきと深い関係にあるらしい。そういえば、私たちはいつの間にか「予選漏れ」や「申告漏れ」という言葉を無意識のうちに脳内の覇者にし、「もれ」のポテンシャルを見失ってきたらしい。そういえば、木もれ陽のきらめきは、葉と枝が吸収できない光のおこぼれがもたらす空気の建築である。窓枠の設置、すなわち外気と外光のもれこそが、囲われた空間に光と温度を与えることは、建築の基本中の基本だ。ところが、私たちの脳内は、完全遮断か完全開放かの二者択一にずっと支配されてきた。もれるという現象は、自然の成り行きなのに。
安藤昌益は、自然を「
つまり、自治と自立の世界は、おのずからもれることが、誰かによって強制されない自由な世界だとも言える。そもそも、飲食物もまた「もれ」の芸術だと言ってよい。めったに食べられない「いくら軍艦」からこぼれ落ちたいくらのつぶつぶに、私は鮭の慈悲を感じる。お皿の上のコップに注がれる日本酒。居酒屋では、わざとこぼしてくれる。ご主人と思わず手を合わせたくなる。砕いたコーヒー豆のフィルターからもれるあの香り高い液体の洩れは、身体中の細胞を活性化する。かつお節からお鍋に染み出るあの旨味。ああ、早く私の心を温めておくれ、と願いたくなる。どんぶりの上からはみ出た海老の天ぷらや穴子の天ぷら。ハミ出れば出るほど、ありがたい。ハンバーグを切り分けたあと洩れ出るあの肉汁。洪水になればなるほど、舌が湿る。新鮮なトマトをかじる。口の中にほとばしるあの汁。
豊穣の象徴である「もれ」「こぼれ」「あふれ」。私は拙著『分解の哲学ーー腐敗と発酵をめぐる思考』(青土社、2019年)で論じたように、それは、ちょうど夜の闇が曙光によって明けるような「ほどけ」、そしてその語源が同じである「ほどこし」でもある。決壊して溢れ出る喜び。緊張と解放。生成と分解。食べることや飲むことは、この二局の競り合いの中に生まれる行為である。
思えば、人が集まった場所で、いろいろと意見を出し合うとき、独り言のようにぽろっとこぼれた声が、議論を大きく前進することを私はたびたび経験してきた。おそらくそれは、「自治」の問題と密接につながっているだろう。そのような言葉を「支配・強制・教導」することなく、かといって過剰に救い上げることをしない空間づくりは、私の職場の重要な仕事である研究会運営の基本である。
基本的に食べものは「あまる」
ところで、少し話が変わるが、最近日本で食品ロスがあまりも多く問題となっている。食品は、食べられるのに、どんどんゴミ箱に捨てられる。パックに入ったまま、水分もたっぷり含まれたまま、化石燃料を用いてどんどん燃やされる。水分の多いゴミがどれほど収集者たちの腰を痛めているかについては、藤井誠一郎『ごみ収集という仕事----清掃車に乗って考えた地方自治』(コモンズ、2018年)という優れたエスノグラフィーを読んでいただきたい。ホテルの宴会では、ソースのたっぷりかかったローストビーフも、トロトロのコーンスープも、まるでそれが以前生きものではなかったかのように、捨てられていく。凄まじいエネルギーロスが日本では毎日焼却場で繰り広げられている。
とりわけ経済先進国の人びとは、しばしば、このような状態に対して、人間の倫理を問題にする。食べものを捨てるなんて、人間の風上にも置けないと、怒りの対象になる。私もこれまで何度も批判および自己批判してきたし、それを撤回する予定は今のところない。
けれども、食品ロスの問題を、一人一人の心がけの問題に落とし込む風潮には、大いに疑問を感じる。そもそも、食べものは人数に対して「あまる」ものことが前提の行為ではないだろうか。問題は、その「あまり」をできるかぎり社会や自然に再び流すことができる受け皿構築の弱さではないだろうか。
かくいう私は、割り算で「あまり」が出てくる式がとても嫌いだった。憎しみさえ抱いていた。小学生特有の潔癖主義なのかもしれない。「12÷3=4」は気持ちよかった。でも「12÷5=2あまり2」では気持ちが晴れなかった。割り切れないのは、何か悪いものを見ているかのようだった。私にかぎらず、世間は「あまり」に対して冷たい。居酒屋に7人で訪れて、餃子が12個だと困る。
けれども、私も大人になってようやく「あまり」の魅力に気づき始めた。ちょうど、木もれ陽のように、料理してできたものは、その食卓を囲む人たちの推定可食量よりもちょっと多めに準備されるのが本来的ではないだろうか。もちろん、それが不可能な経済状況や政治状況にある人びとが、つねにその不足に悩んでいることはいうまでもない。あまる食べものどころか、満たす食べものさえないことが、飢餓問題である。この現実は厳然として存在する。だけれども、どうして、地球の成員が食べて生きていけるほどの食料が生産されているのに、地球上の8億の住民が飢えるのか。それは、経済先進国なり経済先進地域なりがその剰余の「もれ」と「持ち帰り」と「配分」というシステムを作り上げず、ひたすら過剰な衛生観念のもとに新品のまま捨てるという不完全かつ不健全なシステムしか作ることできなかったからではないのか。
食べものを商品化するとは、食べものを数値化することであり、食べものが値段と一対一の対応をすることである。けれども、その場合、食べものが作られすぎると値段が急落するので、市場に出回る前に廃棄処分になる。この余剰は、飢えた人びとには届かない。
けれども、もしもその処分される農作物が、商品になる前に、市場とは別のルートで直接、調理場に運ばれ、そこの料理が直接、人びとによってほどこされるのであれば。もしも、その調理場では大量なカレーや豚汁が作られて、たまたま近くに立ち寄った人にも無料で振舞われるとすれば。いや、そもそも全ての食材が商品化を断念して、直接、無銭食堂に運ばれるような国があれば。その国にももちろんレベルの高い優れたレストランがあって、そのレストランは、この無銭食堂のあまりものの食材を購入するとすれば、それでもあまったものは、家畜に食べてもらったり、土壌の微生物に食べてもらったりできるとすれば。社会の競争からもれでた人たちがふらっと立ち寄れる食べる場所が増えるとすれば。いったいそれはどんな社会だろうか。
別にそうなったからと言って、政府広報のポスターのように、人びとの笑顔が突然溢れだしたり、希望に満ち溢れたり、太陽が若者を照らしたりはしないだろう。ただし、自殺も、過労死も、食品ロスも、飢餓も、減少することは否定できない。弁当を作れない親の罪悪感も、シングルペアレントの罪悪感も、栄養たっぷりの朝ごはんを作れない親の罪悪感も、本来抱く必要のないはずのこれらの感情もまた、不必要な社会になることも間違いないし、それゆえに女性の社会進出も、女性の閣僚の数も、女性の大学教員の数も、増加することは想像できるだろう。家庭の台所に特定単数の性のみを貼り付けない、という未完のプロジェクトや、食の前の平等という歴史上ほとんど例をみない事業が人間の内面の何を変えるかは、シミュレーションに値することだと思う。
このような食の究極的なあり方を、私は縁食と呼んできた。もちろん、現在の食の形態が縁食の完成型に到達することは不可能に近いだろう。それほどまでに、食は激しく商品化され、オートメーション化され、硬直した所有権観念に侵犯されているからだ。だが、食を商品化することの無理は、多くのシステムを機能不全にしている。この国で賞味期限前に食べものが捨てられることが、その証である。
農業をすることは、植物が合成したブドウ糖のあまりを
自然の耕した食べものが
編集部からのお知らせ
ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台』Vol.2〜Vol.5に、藤原辰史さんによるこれまでの「縁食論」を掲載しています。ぜひ、お手にとってみてください。
*
◉ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台「移住×仕事」号』藤原辰史が語る「食、戦争、そして」
◉ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台Vol.2 革命前々夜号』縁食論(1)孤食と共食のあいだ
◉ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台Vol.3「教育×地元」号』縁食論(2)弁当と給食の弁証法