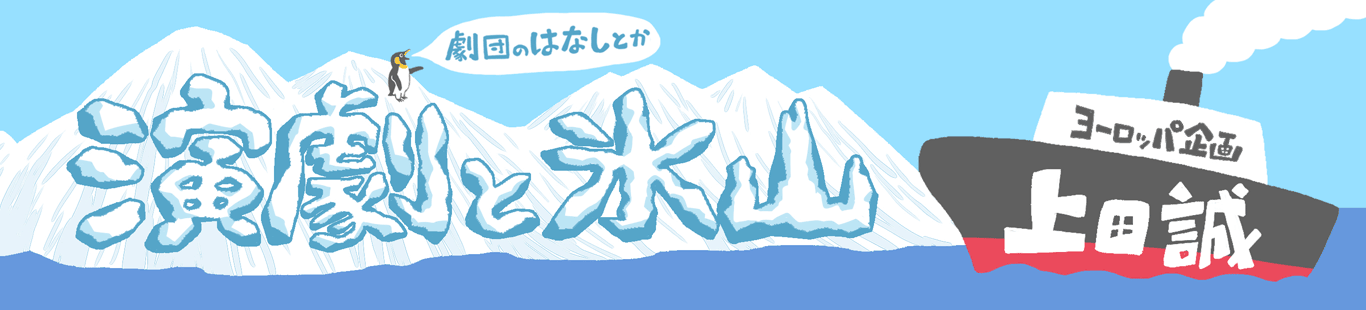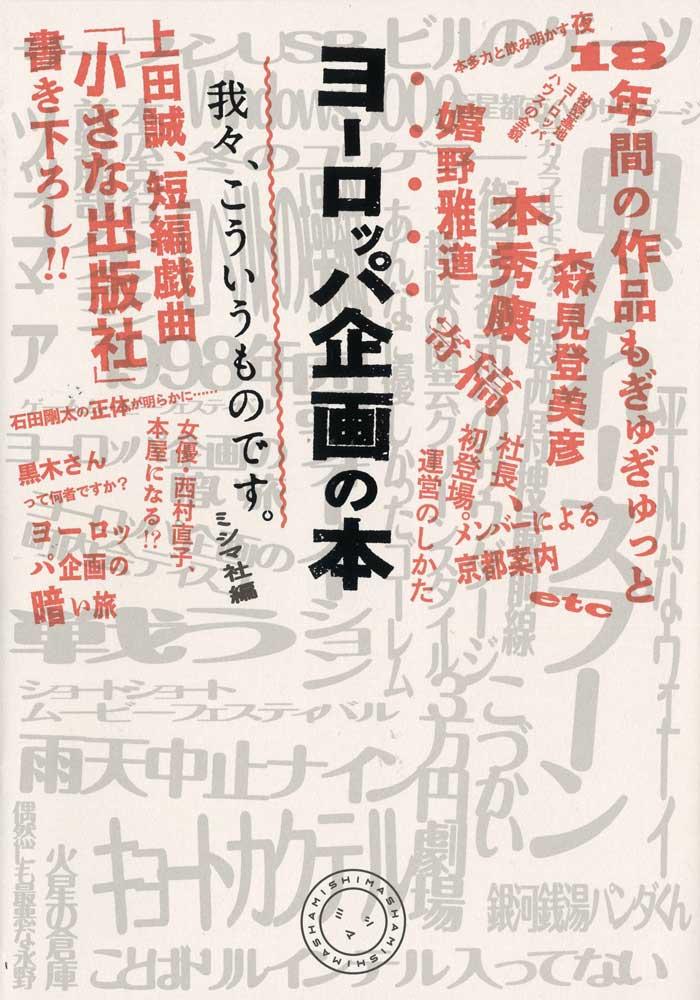第11回
続・時をかける少女と少年とアダルトチームと関係者
2019.01.17更新
濁流のような年の瀬を枯葉のような舟でなんとか乗り切り、年明け、久しぶりの休息がやってまいりました。劇団というのはなかなかオールを漕ぐ手を止められないもので。見えない氷山がいつだって迫ってますから。そういった意味では2018年は、非常にシビアな漕ぎを要求された年でありました。
結成20周年の大型ツアーや、新人スタッフの加入、新番組の立ち上げ、劇団員のひとりが「ボヘミアン・ラプソディ」の主演俳優に酷似、など抜き差しならぬ局面がいつになく続き、干支をまたいでようやく水面は凪いだ表情を見せ、一息つきながらオールをリモコンに持ち替えて、ふと昨年の2月にやった舞台「続・時をかける少女」のDVDを、感慨深く眺めている深夜です。本当にね、進むときは何もしなくても進む船なんですけど。
なんてことを思いながらDVDを見終えて、一年前の思い出に胸が熱くなり、そうして書かなければ年を越せなかったはずの原稿を、いま威風堂々と書きだそうとしています。遅すぎる旅はないと言いますからね。土下座に似た形でパソコンを打っています。「続・時をかける少女」のプロダクションノートの後編です。前編はこちらをお読みください。
プロデュース公演の顔合わせほど、居ずまいの悪いものはありません。勝手知ったる劇団公演ではなく、僕とやるのが初めての役者やスタッフ、様子見のプロデューサー、訝しむマネージャー、ねめつける関係者・・・、と周りすべてが敵に見えてしまうほどに、演出家にとってそこは薄氷を踏むような場所なんです。ことさら脚本をまだ書き終えられていない作・演出家にとっては。
いやもちろん本当はそんなわけはなくて、皆さん公演を成功させようとこの場に集まっているわけだし、ただお互いまだ打ち解けてなくて空気がこわばっているだけなのだけど、その「こわばり」が非常にこう、メンタルの脇腹を抉ってくるのであります。
なのでここは、演出家からのスピーチで、カンパニーの心を一気に斜め上方へ鷲掴みたいところ。泥船だかなんだか分からないような船に、いかに体重をかけて全乗っかりしてもらうかが分水嶺ですから。なのに邪念が混じってなんだかパッとしない挨拶をしてしまい、忸怩たる思いでいましたら、そのあとの主演の上白石萌歌ちゃんの挨拶が、ため息が出てしまうほど凛々しく、ああこれで公演の成功は約束されたようなものだ、と万座が胸を撫で下ろしました。主演かくあるべし、と目を細めたものです。
稽古場は狭く、舞台の実寸の6掛けくらいのサイズしかとれず、700席からなるグローブ座の劇なのに、アトリエ公演かな、と思うほどコンパクトな稽古となりました。
しかしお互い慣れない僕らにはそれがよかった。いきなり広い稽古場だと構えてしまうんですよね。なのでできるだけ親密に、資料の共有や話し合い、プロジェクターで動画を観たり、休憩時間を長くとって駄弁ったり。そんなことをしながら、別々のジャンルや世代から集まった、キャストスタッフの肌感覚をすり合わせてゆきました。
萌歌ちゃんや健太郎くんなど若い役者が、登美丘高校のおかげでバブル期に案外なじみがあること。島田桃依さんがシノラーだったこと。中山祐一朗さんやバッファロー吾郎A先生が「ホットドッグ・プレス」を読んでいたこと。めいめいの時代と場所で過ごした青春を、まずは6掛けの稽古場に持ち寄るところから。
「話し合い」は、劇作にも大いに役立った。元々の原作では、和子が未来人ケン・ソゴルに、「言わずもがな自明のように」惚れるのですが、現代を2018年に置き換えると、なんだかそこが通らないように思えた。きっと原作が書かれた1972年には、未来は無条件に明るく、未来人は無条件に素敵、だったんでしょう。和子はまるでフランス人に憧れるかのように、未来人ケン・ソゴルと恋に落ちます。
和子役の萌歌ちゃんに聞いてみると、「未来に対しては、憧れというより、怖い気持ちの方があるかもしれない」とのことでした。幼馴染の吾郎役・健太郎くんは「SNSとか、そんなやんないっすねー。部活とかの方が好きかも」だそう。なんだか今や「未来」という言葉自体が過去のもので、2018年からみた未来は銀色には輝いていなさそうに思えた。
なので衣装家の髙木さんと相談し、ケン・ソゴル役の戸塚くんの衣装は、モスグリーンのつなぎにしました。素っ頓狂な銀色にするまえに立ち止まってよかった。そして物語の焦点と戸塚くんの命題は、「西暦2700年から来た、モスグリーンのつなぎの冴えない未来人が、いかに2018年の女子高生の心を奪うか」となりました。
和子とケンが時代時代を駆け抜けてゆく話で、スタートは2018年から、1996年の渋谷、1990年の六本木、1980年の原宿、1968年の新宿、へと遡ってゆきます。稽古もその流れで、1996年から順番に、映像資料を見てはそのころの時事風俗(とくに踊り)をコピーしていくことに。
渋谷のギャルの口調とカラーギャングのライム回し、お立ち台ギャルの腰つき、竹の子族の振り付けとローラー族の足さばき、テクノポップの佐藤チカの動き。フォーク集会のインテリ学生同士の議論はラップバトルのよう。そしてフォークゲリラの力強いギターストロークと歌唱。遠くまで聴こえるようにガシャンガシャンと弾くんですって。
ある種なんていうか時代祭です。ひとり何役も演じ分けるので、着替えの忙しいエレクトリカルパレード、あるいはものまねメドレーでもあります。0秒のバッファで早替えを要求される役者と、それを取り仕切る演出部からは、シーンのタイムをとるたび深い嘆きが漏れます。
資料映像はどの時代もいちいち空気が濃く、見終えて2018年の稽古場に戻るつど、ふーむ、と唸らざるを得ないのでした。これらの時代を踏まえて僕ら「2018年人」がどう渡りあうか、が後半のテーマでもあり、そしてそこはまだ書いてないのでこれから考えないといけなく。とりあえず稽古場でSNOWをやってみたり、「マジ卍」「なしよりのあり」とかの台詞をおずおず書いてみたりして。
21世紀に入ってからの流行ワードを調べてみると、軒並み「ブログ」「YouTube」「ツイート」「AMAZON」「ツムツム」「インスタ映え」「バズ」みたいな感じでした。あとはスポーツ選手と「壁ドン」くらいで。なんなんですかね2018年って。
そんな中、熱く稽古は続いていきます。台本はたいへん高密度で、目まぐるしいものになりました。これ2時間の劇じゃないでしょ、3時間でしょ、という瘴気が各セクションから漂います。台本の分厚さも物語の量も、ベンティサイズぐらいの盛りになってしまい。
異常な数の段取りをこなしながら、舞台を縦横無尽に駆けなくてはいけない萌歌ちゃんは、しかしおっとりとマイペースで、気持ちからきちんと演技を作ってゆく正しさを崩さずにいてくれました。マグネットを動かしながら口角泡を飛ばして出ハケのタイミングばかり言う僕とはよいコンビでした。打ち上げじゃ僕の弾くギターで「時をかける少女」を歌ってくれましたし。のちにうちの石田くんには「黒歴史」と言っていたそうですが。
戸塚くんは、おもしろ先輩方にほだされて、恋愛軸を担う役ながらつい笑いを欲しがってしまう浮つきを見せはしたものの、さすがのコメディセンスとセリフ回しだったし、焼肉屋さんで熱弁するあまり服の袖を燃え上がらせてしまうガッツも見せてくれました。
健太郎くんは初舞台ながら、惚れ惚れするような運動神経で、これがめきめきということか、と思うほど日々上手くなっていった。稽古の終盤、「もっと演技上手くなりてーなー」と言ったときには、あいつ抱きしめたいなあ、とヨーロッパ企画みんなで言ってました。
乃木坂46の新内さんは、極度の人見知りで、そして動きが独特でした。現役のアイドルが80年代のアイドルを演じるさまははかなく可憐だったし、荒々しくコールされながらぶりぶりの振りで歌うさまは胸熱だった。早替えで弱腰になっていたら「乃木坂じゃ2秒で衣装チェンジしますよ」と発破をかけてくれた。
MEGUMIさんは変幻自在で頼もしく、船にまっさきに全体重をかけてくれる人で泣けた。本番前みんなで発声練習しようよって言ってくれたのもMEGUMIさんだった。A先生は、カラーギャングの完コピを超まじめにやってくださったし、バブル期の若社長の役を「宅麻伸のイメージで」って言ったら、理解が光より速かった。本番前にはいつも「おーポカホンタス」で景気づけてくれた。中山さんは先輩なのに誰よりチャレンジブルで、そして稽古を遮って即席ワークショップを催してくれた。「普通じゃ口出さない時もあるんだけど、若い子たち居るから」って。演出家の僕じゃどうしても手の届かないところってあるんです。それが役者同士なら通じ合える。島田桃依さんは、名門・青年団にいる人なのに、舞台セットを壊してたし、通し稽古でメガネを折ってた。千穐楽じゃ泣いてた。
そうやってみんなが少しずつ、やらなくてはいけない領域を超えてやってくれているのは、たいへん大人げなく痛快なことでした。ビジネスでやろうと思えばできてしまうのがプロデュース公演ですからね。でもこの公演はそれじゃいけないと思った。青春にかどわかされたといいますか。劇中に出てきた「エモい」という言葉が、いつしかカンパニーの中で流行語にもなってた。気恥ずかしいし2018年に使う言葉じゃないながら、エモい公演に違いなかったんです。
稽古場も大きくなり、初めての通し稽古の前に、出ているヨーロッパ企画メンバーに伝えました。「今日までは和気藹々とやってきた、だけどこの通し稽古ではギュンとドライブをかけたい。ついては芝居の速度を限界まで速く、かつ演じこみも充実させて、出力も本番の劇場さながらにやってほしい」と。
ここ一番でそういうことを頼めるのが劇団員です。石田くん、諏訪さん、土佐さん、永野さん。やったことあるタイプの劇でも別になかったし、4人にしたって初めての通し稽古だったけど、加圧トレーナー役を立派にまっとうしてくれ、劇は見違えるように精悍になり、ランタイムも2時間ジャスト。誰より命拾いしたのは僕なんでした。ここからシーンをひとつ切るなんてことになると凄惨でしたから。そして手ごたえのある通し稽古は、カンパニーに翼を授けました。
劇中音楽の伊藤さんもまた、肚をくくったのか、時代ごとの流行音楽を模倣した、26曲のオリジナル曲を仕上げてくれました。タイムアタックのような納期で一日2曲ペース、さらにカーテンコールの「時をかける少女」のアレンジでは、それらのリズムや音色をタペストリーのようにするという凝りよう。
衣装の髙木さんは50着以上にわたるファッション50年史を編み上げてくれ、舞台美術の片平さんは書き割りパネルという頓智のようなアイデアと勇気で6つの年代を描いてくれた。
すべてに一度もNOと言わなかった舞台監督の川除さん、ファミレスで朝から晩まで調べものに付き合ってくれた翠さん、劇中映像のためにたまごっちを飼育までしてくれた映像の大見さんと制作チーム。絶対に間に合わない着替えをなんらかの魔法で実現してくれた演出部や衣装ヘアメイクチーム、絶対に時間が足りない場当たりを間に合わせてくれた照明音響チームは、僕の中で時をかける少女とおっさんたちでした。
おびただしい量の未来小道具やリゲインをこなしてくれたさおりさん、インベーダーや太陽の塔などいろんな許可関係で時空を飛び回ってくれた後藤さんやプロデューサーチーム。パンフ宣伝マネージャー陣、そのほか書ききれませんけどいい大人が垣根を超え、時を超え、キャパを超え、かけまわっているんでした。こう書いてて、単にこれ僕が迷惑をかけたんじゃ、と、一年越しに手汗をかいてもいますが。
萌歌ちゃんをはじめヤングチームは、本番じゃ底なしの体力を見せてくれ、着替えでヒットポイントを奪われているアダルトチームを尻目に、ノンストップで2時間を駆け抜けた。いくつもの時代を超え、ラストには大人たちを巻き込んで、感受性とスマホを武器に、2018年人の戦い方をまっとうしてみせ、笑いとスリルと、恋と涙まで。そこにはシトラスミントの風が吹いていて、それは紛れもないモノホンの青春で、それに比べると我々のは作られた青春で。
千穐楽の高知公演が終わって、キャストが泣いているという噂を聞き、会いにいったらそんなには泣いておらず、シトラスミントの風に吹かれた青春乞食の僕だけがいました。
プロデュース公演の寂しさは青春の寂しさに似ています。それはきっと二度と戻らないということ。DVDを見終えた僕のそばにはスマホがあります。公演を終えて買ったものです。エモい。