第9回
語尾好きに優しい英語
2022.12.14更新
英語はあまり得意ではないのですが、たまに話す際、語尾がないことにどうも落ち着かない自分がいます。
「Would you tell me the price?」などと言った後に、何となく「right?」と言ってみたり、なぜか「yea?」と付け加えてみたり。「値段を教えてもらえませんか、ヤァ」というと、なんだかビートルズがやってきそうですが、ともあれ「ぎこちない英語を使うやつだなぁ」と思われていることは必至でしょう。
「OK」すらも「OKっす」とつい語尾を追加したくなります。多分相手には「何でこいつ、OKの後で呼吸を止めるんだ?」と思われていることでしょう。
なんにせよ、何かを言いっぱなしにすることに不安を覚えるのかと思います。ちょっとした病気ですね。
ただ、そんな私に優しい英語があります。
それがシンガポール英語。「シングリッシュ」などとも呼ばれます。
多民族国家であるシンガポールで自然発生的に生まれた英語で、こうした言語のことをピジンとかクレオールとか呼びます。
このシングリッシュにはいくつかの特徴があるのですが、一番わかりやすいのが、語尾に「lah」という語を付けること。「ラー」という感じです。
「OK lah」(オーケー、ラー)とか、「NO lah」といったように使い、別にこれを付けることによって意味が変わるわけではなく、本当に純粋に語尾のような存在です。
もともとは中国語の「了」から来ているそうで、この言葉自体は語尾というよりも完了を表す言葉なのですが、シンガポールではほぼ語尾化しているのが興味深いところです。
さらに興味深いことに、「lor」とか「leh」とかいう語尾もあるらしく、生粋のシンガポール人はこれらを微妙に使い分けているのだとか。日本語の「ね」と「ねぇ」「よねぇ」くらいの使い分けなのかもしれません。
シンガポールは多民族国家で、中国語、マレー語、タミル語を使う人などが混在しているのですが、リー・クアンユーの強力なリーダーシップにより英語を公用語にすることで、各民族の融合を図るとともに、国際社会への進出を果たしました。中でも中国人人口が最も多いため、このような中国語の影響を受けた「シングリッシュ」が生まれたのでしょう。
ぜひそのすてきな語尾を使いこなしたいところなのですが、私が以前、数回シンガポールに行った際は、皆ごく普通の英語を使っていました。外国人に対してだからかもしれません。確かに日本人も外国人に日本語で話すときは、語尾の微妙な使い分けなどしません。
さて、このシングリッシュを知ってふと思ったことがあります。
それは、「もし日本の公用語が英語になっていたら、どんな言語が生まれていたんだろう」ということです。
実は明治の日本では、「日本の公用語を英語にしよう」ということを大真面目に主張する人がいました。有名なのは政治家の森有礼で、イギリスに留学したことで彼我の差を大いに見せつけられたのでしょう。今思うととんでもない主張ですが、当時、欧米との格差を目の当たりにした彼らがそう思うのも無理からぬことだったのかもしれません。
さすがに当時から暴論だと思われていたらしく、実現はしませんでしたが、その後も志賀直哉が「日本の公用語はフランス語にすべき」と主張したりと、なかなかこの欧米コンプレックスは抜けなかったようです。
ともあれ、もし本当に英語が公用語になっていたら、どうなったのか。ちょっと考えてみると面白そうです。
I have a penですね
とか
Why notね
みたいな珍妙な表現が生まれていたかもしれません。
「Japanese Economy はですね、極めてbad situationでありまして、we must take measureであり」
といった、まるでルー大柴のような言語になっていた可能性もあります。
それでも、個人的には、「I have a penですね」と言われたら、それは英語というより「日本語」であるようにも思うのです。
ということはやはり、語尾さえあれば日本語は日本語のままなのではないかとも思うのです。
ということで、今後も「語尾」は不滅でしょう。日本語の神髄は語尾にあるからです(言い過ぎ)。




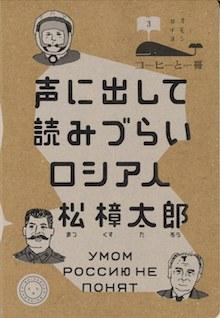
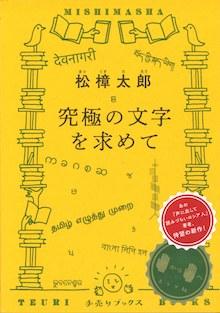

-thumb-800xauto-15055.png)



