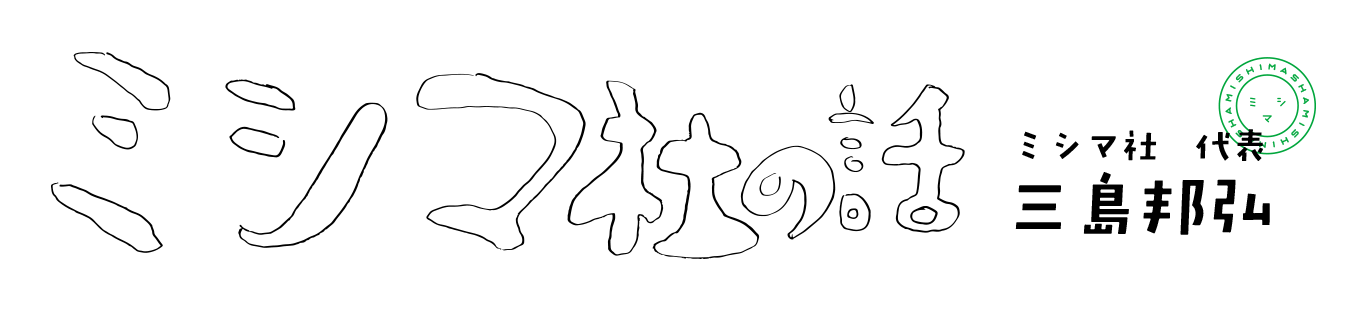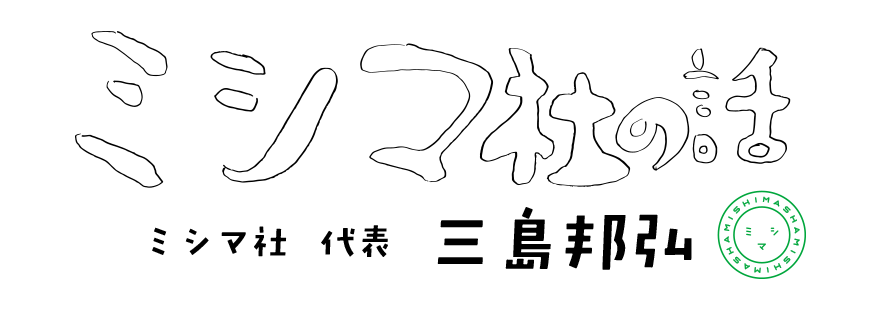第89回
「さびしい」と共有地
2022.02.21更新
ときどき不思議なことが起こる。
完成に至った仕事が、とても個人的なことと重なることがあるのだ。自分で企画しながら、その時点ではまったく気づかずにいた企画意図に、ずいぶん後になって気づく。もしや、こういうことのために、この企画を立てたのかもしれない。と自らが驚かされる。
今、まさにそうした事態に出逢っている。そのことを語るため、しばらく個人的な話になることをお許しいただきたい。
*
先月、おじが他界した。母の二歳上のおじは、何かと私たち家族の面倒をみてくれた人だ。それを書き出せばそれだけで一冊になりかねず、ここでは割愛する。ひとつだけ言えば、母は二歳のときに父親を病気で失い、おじは若い頃から妹である母のことを気づかってきた。私の記憶のなかでさえ、間違いなく、経済面ではかなり支えてもらった。だが、精神面でもそうとう支えてくれていた。そのことに思い至ったのは、おじのお通夜へと向かうサンダーバードの車中なのだったが。
お通夜を終えた翌日、葬儀の前に私は次のような手紙をミシマ社サポーターの皆さまへ書いた。というのも、その日は一年に一度の「サポーターデイ」だった。京都オフィスからサポーターの皆さんとオンラインでつないでお茶をご一緒する予定だったのだ。
サポーターの皆様
こんにちは。本日はサポーター茶話会にご参加くださりありがとうございます。
オンラインとはいえ皆さんと直接、お話できるのを楽しみにしておりました。が、今こうして代読してもらっているのは、サポーター制開始以来ずっとサポーターをしてくれていた私のおじが他界したためです。いま、おじの実家のある石川県小松市でおじの見送りをしております。今日は、私自身のサポーター会はサポーター代表としておじとの最後の時間を過ごすという形になることをお許しいただけましたら幸いです。
長くなり恐縮ですが、少しだけおじの話をさせてください。この数日、おじがいなければミシマ社はそもそもなかったなぁ、とあらためて感じております。というのも私が20代前半の社会人一年目、一家離散の危機に見舞われました。父が大病を患い商売を畳むにあたり、京都の自宅を売り、借金を返済。そうして両親は住むところを失いました。その時、石川県小松市にいたおじが安い借家を小松に見つけてくれ、両親はそこに引っ越しました。最低限の生活道具を買いにおじと金沢へ行った帰り道に、「お父さんお母さんのことはおっちゃんがなんとかする。お前は仕事がんばれ」と言ってくれました。あの時おじがいなければ、まだ両親を抱えて生きていく力も社会的基盤もなかった私はその重みに潰され、仕事どころでなかったかもしれません。31歳でミシマ社をつくるまで、私が仕事に専念できたのもおじがいたからこそでした。
そのおじは、私が思っている以上にミシマ社ファンだったようで、「僕の手書きの字が汚い」と笑いつつも、サポーター新聞を毎月楽しみにしてくれてました。おじが、「最後の京都になるから」と昨年10月、突然ミシマ社に来てくれたとき、「ほんといい会社になった」と嬉しそうに何度も語ってくれました。それが、おじとの最後のひとときでした。
心を込めておじを見送ります。
長年ミシマ社サポーターをやってくれてありがとう! これからも頑張りますからね! 安心しておやすみください、ありがとう、と。サポーターの皆様、いつも、有形無形のお力添えを心から感謝いたします。皆さんに支えられて日々楽しく活動できております。
これからもお力添えいただきましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。三島邦弘
葬儀からもうすぐひと月が経つ。京都で一人くらしをしている母へときおり電話をする。
「元気か」「元気やよ」。そう応える母の声がいつも涙声に聞こえる。物心両面で長年支えてくれた人を失った。その喪失感は私の想像が及ぶところではない。
だが、励ますことはできずとも、ただ顔を合わせ、無為な時間を一緒に過ごす。それくらいはしたいのだが、コロナで会うこともままならない。
思えば、おじの孤独はいかばかりだったろう。通夜、葬儀をとおしてずっとそのことが頭から離れなかった。通夜へ向かう日の朝、京都は大雪だった。とはいえ、午後にはすべて溶けてなくなる。おじの住む石川県のちいさな街とは比べ物にならない。そこは雪国そのものだった。雪の中で家に閉じこもって一人暮らす。その孤独を実際のところわからずにいた。
10年くらい前に定年退職して以降は、個人の仕事もじょじょに減らし、数年前ーーおばが亡くなった時期と前後するーーには完全に仕事をやめたようだった。子どもたちも独立し年月が経ち、稼ぐ理由も無くなっていたにちがいない。私の母も、父が亡くなった一年後の四年前には、私の近くで暮らす方がいいだろうとなり、京都へ来た。親戚、家族がどんどんいなくなり、仕事の交遊も皆無に近くなる。母が石川県を離れて以降は私も法事でしかおじと会う機会がなくなっていた。コロナ以降は法事があれど行くことも叶わず。
ただ一人、それなりの広さのある家で暮らしていたのだ。苦手な料理をときどきはして・・・。
おじが昨年10月の下旬に突然、京都に来た。顔を見るのはおばの一周忌以来約2年ぶりだった。「体の調子がちょっと良くなったんで」「最後の京都やと思うから」とおじは訪問理由を語った。
戻ったあと、程なく入院したと聞いたが、まもなく退院した。旅の疲れが出たのだろう。その程度の認識だった。
翌月の11月、ミシマ社サポーターへのプレゼントに毎回お送りする『ちゃぶ台』がでた。特集タイトルは、「「さびしい」が、ひっくり返る」。
おじに向けて企画したわけではない。むろん、私の母に向けてでもない。
だが、「昨年末、おじは読んでくれていただろうか、少しでも読んで、何かが届いていたらいいのに」と今は思うばかりだ。そして、現在の母にもどうか届きますように、と切に願う。
*
今月、発刊となるのが、平川克美さんの『共有地をつくる』だ。
家族や仕事や友人や地域というコミュニティが薄れゆく社会の流れのなかで、ぽっかり欠けてしまった場。そうした場がもっともっとあれば、とこの本を編集しているとき、自分の近くの二人のことを思い浮かべては何度も思わずにいられなかった。
そのたび、いや、今からあるようになっていけばいいんだ、今からだ、と思い直した。
編集者としては、『小商いのすすめ』が出た10年前のようになって欲しいと祈るような気持ちでいる。新自由主義の突風が吹き荒れる2000年台初頭の流れの中、「スモールビジネス」という言い方がスタートアップとセットで膾炙した。だが、多くの生活者の実感からは乖離していた。暮らしと共に仕事がある。そうしたあり方を「小商い」と平川さんは名付け、すでにあった言葉に新しい命を吹き込んだ。
この「共有地」も同じことが言えるだろう。
共有地は、近代を迎える際に日本の農村が一度は捨てた概念(場所)である。けれど、結局、農村のみならず都市部も含めて日本中で、中途半端な近代化と共有地の欠如が起こった。つまりは、何もない、ただ「さびしい」がある。そのようなことになってしまった。近代以前の共有地的なものの代わりを果たしてきた家族や会社という共同体にもう一度戻ろうという動きがあるが、限界があろう。そもそもそれがいいかどうか、再考の余地がたっぷりある。
だからこそ第3の場が求められる。ただ、それがコミュニティ、コモンと言われると、ピンと来ないし、自分とは関係ないと思ってしまう人たちが確実にいる。おじや母はまさにそうした人たちだ。
このようなカタカナ用語から漏れる生活者たちはどこに行けばいいのだろう。
この本が、小商いの先にある光となって、誰かひとりのすくいになってくれたら、と祈らずにはいられない。
編集部からのお知らせ
『共有地をつくる』著者・平川克美さんと辻山良雄さんの対談を開催します
『共有地をつくる』の著者である平川克美先生と、書店「Title」店主の辻山良雄さんをお迎えし、対談いただきます。
平川先生は、経営する会社を畳んで隣町珈琲店主に。辻山さんは、大手書店チェーンを退職して「Title」店主に。辻山さんが個人店を開くきっかけになった本は、平川先生の『小商いのすすめ』でした。今新たに「共有地」という言葉をめぐり、お二人はどんなことを考えておられるのでしょうか? 各地で芽吹いている動きの発信源であり最先端である実践者の、初めての対談です。
出版界の「共有地」 応援のお願い
『共有地をつくる』の中で平川さんは「喜捨」という方法で、自身の共有地「隣町珈琲」をつくられました。それに倣い、私が参画する「一冊!取引所」という出版の世界の共有地でも「喜捨」をお願いしております。「一冊!寄付のお願い」、どうぞよろしくお願い申し上げます。