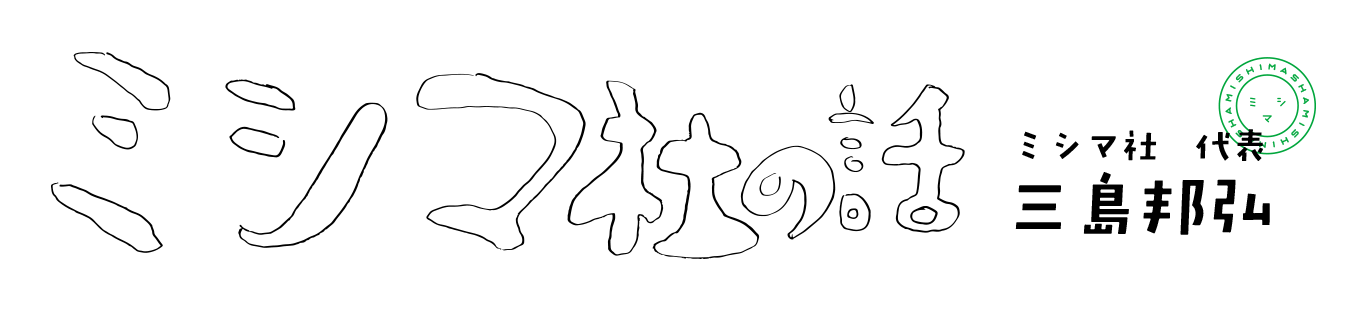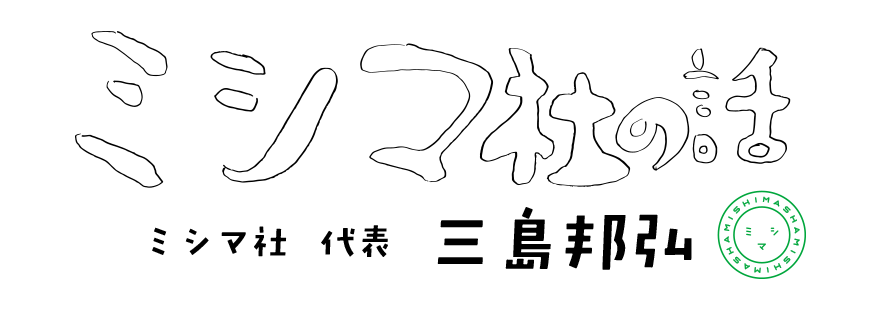第95回
ここだけの2023年ミシマ社ふりかえり
2023.12.21更新
今年ももう残すところ10日です。
この一年のミシマ社をふりかえると、「ストーミー」。なかなかの嵐の日々でした。幸い、無事に抜けることができました。
もっとも、書籍の充実、一つひとつの販促の取り組み(絵本便がスタートしたり)などは、17年の継続の力がかたちになって出たようにも感じています。継続は力なり。を全身で実感した一年でもありました。
特にこの秋以降いくつも嬉しい出来事がありましたが、個人的には、拙著『ここだけのごあいさつ』(ちいさいミシマ社)の韓国語版の刊行が決まるという驚きがあります。
今日は、その韓国版に寄せて書いた文章をそのまま掲載します。
この一年のミシマ社ふりかえりテキストにもなっていると思います。
*
序 韓国版に寄せて
韓国の皆さま、アニョハセヨ。
この本を手に取っていただき、ありがとうございます。望外の喜びというほかありません。というのも、ここに書かれているのは、日本のちいさな出版社のちいさな話です。しかも、もとはといえば、サポーターという私たちの会社を応援してくれている人たち数百人に向けて書かれた、「ここだけ」の話(本書の第二章)のみを収録した本をめざしていました。ですので、韓国の出版事情に合うのか、そもそも、私たちのようなちいさな会社がどれほど韓国社会で求められているのか、すこし不安ではあります。
それでもこうして翻訳いただけることになった。その意味を自分なりに考えてみると、ひとつ、思い至ることがあります。それは、本書が、「ものすごくうまくいっているわけではないが、それなりにいい感じには回っている会社のなまの話」であることと関係します。
ざっくり言えば、「それなりにいい感じに回っている」と「なまの話」、この二つの要素で本書は成り立っています。
「ものすごくうまくいっているわけではないが、それなりにいい感じに回っている」。この状態を、私が住む関西ではかつて、「ぼちぼちでんな」と言いました(これ、韓国語に訳せるのでしょうか?)。
「ぼちぼち」というのは、成功と失敗、天と地、が高速で繰り返し起きるジェットコースター的世界の正反対。大きな成功もないが大きな失敗もない、俯瞰すればけっこう安定している。なにより、楽しい、おもしろい、を継続できている。
とはいえ、こういう会社の話はけっしてドラマチックではありません。ドラマや映画にはなりにくいでしょう。けれど、日常はそもそもドラマではない。ハッピーエンドも最悪の結末もなく、生きているかぎり、少なくとも働いているかぎり、いいことも悪いことも、どっちもある。そして間違いないのは、日常には終わりはないということです。
その終わりのない日常を、「それなりにいい感じに」過ごしている。
強いていえば、この「いい感じ」の中身が、ミシマ社という出版社の特徴と言える気がします。どういうことかというと、「いい感じ」でいつづけるには、自分たちの活動を、自分たちから出る本たちを「おもしろい」と自分たち自身が感じられていることが欠かせません。会社を回すことそのものが目的となってしまい、自分たちの考える「おもしろい」を手放してしまっては、「いい感じ」ではいられない。「おもしろい」を実現し、結果、ある程度は「売れる」。それによって、会社も回る。
この順番が重要で、売れさえすればいいわけではありません。マーケット側にある「おもしろい」を当てに行くようなことばかりつづけていれば、「いい感じ」でありつづけるより、消費的、投機的にならざるをえない。結果、疲弊する可能性が高くなる(もっとも、ときどきそういうのはあえてやる、というのは、それ自体に「おもしろい」が含まれるので、全く否定するものではありません)。
自分たちが大切にする「おもしろい」を温めながら、淡々とドラマチックではない日常を生きる。それは、マーケットの顔色をうかがいながら、他者基準のおもしろさを追いかける行為とは違う。
もっと踏み込んで言うと、売れさえすればいいとは考えていない。もちろん、売れてほしい。というか、売れてもらわないと困る。けれど、自分たちの「おもしろい」が入魂されていない本をつくってまで売れてほしいとは思わない。
まあ、当たり前といえば当たり前です。その意味では、当たり前のことをやろうとしている会社のふつうの話、と言えます。私も編集者の端くれではあるので、その立場から言えば、「いい感じに回っている」だけでは出版企画としては弱くありません? と思わなくもありません。
では、「なまの話」が本書の鍵なのでしょうか。
たしかに、「いい感じ」と「なま」の掛け算によって、あまりない話になっていると言えなくもありません。が、それだけでは、この程度――「当たり前のことをやろうとしている会社のふつうの話、それもかなり本音の」――でしょう。
うーん、編集者である私も、この企画に対し、なかなかゴーサインを出すのはむずかしい。
ところで、コーチングというものをご存じでしょうか?
最近、周りの何人かの知人が受けているとたて続けに知りました。コーチングのプロと言われる専門家と月に一度、話す時間をもつらしいです。ただし、その専門家はティーチングではないので教えることはしない。あくまで質問だけ。質問をとおして、本人が語り、本人が自ら気づくようにする。
知人たちは声をそろえて、「会社がすごくよくなった!」と言う。
そんなもんかなぁ、と思って聞いていました。すこし興味は湧きました。本書に書いたように、私も人に聞いてほしい話はやまほどあります。話すことで会社がよくなるなら、そりゃあ、頼みたい。
と思いつつも、実際には頼まないだろうな、と思い直しました。けど、なぜ頼まないのかな? と考えたとき、はたと気づいたのです。
「ああ、僕は毎月、サポーターに向けて手書きを書くことで、本音を吐露している。それを通じてコーチングをしてもらっていたんだ」
その視点に立てば、本書の著者(私です)は、やたらと発見、気づきをくりかえします。2年前に「わかった!」と言っていたような内容を、2年後、また「わかった!」とまるで新発見のように書いています。もちろん大真面目に。
読み返すたび、我ながらおかしなやつだ、と思っていました。けど、コーチングという視点にたてば、それを「受けていた」と言えるかもしれない。とすれば、本書は、文字によるコーチングの過程が露になっている書物である。そう言えるかもしれない。そんな気がしてきたのです。
こう考えると、本書はすこしは読者のお役に立てるかもしれないと思えてきました。
「おもしろい」を手放さず、ぼちぼち会社をつづける。その実際の日々は、ひとりで勝手に話し、勝手に気づき、合点し、反省し、行動することの連続だった。その過程がつづられた一冊。
と編集者である私は、この原稿を手にして読んだなら、記すかもしれません。まあ、思いっきり自作自演ですが。
ともかく、コーチングを書くことで一人受けていたとします。その結果、知人たちのようにどんどん会社が良くなったのか? といえば、逆です。
本書の終盤(つまり今年の春先)に向けて、嵐が近づいてきたのです。
嵐、ストーム。ビジネスの世界では、会社が次のステージに立つ前、必ずストーミーな状態になるらしい。と、コーチングを受けている知人が教えてくれました。
これには、心底、納得します。
ストーミーの最中は、自分たちが嵐にいることに気づきません。「いま、嵐が近づいています」。と、天気予報のように誰かが知らせてくれるわけではない(もしかすると、コーチングを受けていると、教えてくれるのでしょうか)。
たいていは、事後的にわかるものです。ああ、あれはストーミーだったのだ、と。
ちょうど今、私がその実感の中にいます。それは何より、嵐のあとにしかないだろう、清々しさを感じているからです。嵐が抜けたあと、空気が清浄になり、場が整う。しばしばこうした話を聞きますが、会社も、この自然現象同様であることをしみじみ思います。
自社でいえば、まるで別の会社のようになった。微修正の連続ではこうはならなかった気がします。嵐を抜けた者だけが身につけうる逞しさが、現メンバーにみなぎっているのを実感します。
このように書けば、本書が会社が成長するために嵐をどう抜けたか、が書いてあると思われるかもしれません。が、それはちょっとちがいます。残念ながらまったく書いてありません。
今からふりかえればはっきりわかりますが、本書を書き終わるあたりには、嵐に突入しはじめていました。その真っ最中に考え、行動した記録が第三章には記してあります。
とはいえ、その時点では嵐を抜ける段階からはほど遠く、抜け出る方法など書きようもなかった。嵐の真っ最中に、嵐の抜け方を語っていたら、「やばい」ですよね。シノゴノ言わず、抜けるために行動することが先決です。
では本書に記述されているものは何かというと、ひとや組織が嵐に巻き込まれる前後、こういうことを考えるのだ、という事実の断片です。
ですから編集者としては、次のようにこの本を位置づけたいと今は思います。
「一人コーチングの先に、嵐がやってくる!?
『いい感じ』から『もっといい感じ』を求める人には何らかの参考になるかもしれない本」
こんな本ですが、韓国の皆さま、どうぞよろしくお付き合いくださいませ。
最後に。嵐を乗り切るにあたりいくつかの大きな出来事がありましたが、その最大のものが、9月に訪れた韓国・坡州での時間でした。韓国でお会いした方々からいただいたエネルギーがあったからこそ、です。そのことはいずれ別に書こうと思いますが、その時お会いしたご縁で本書が誕生しました。YuYu出版の方々、本書を翻訳くださる朴先生に、あらためてこの場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。
韓国の皆さんとまたこうして再会できて、とても嬉しいです。
三島邦弘