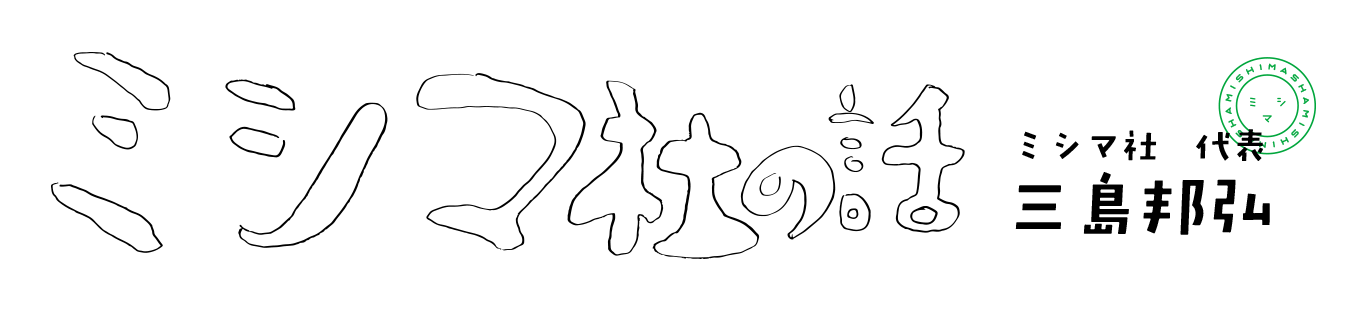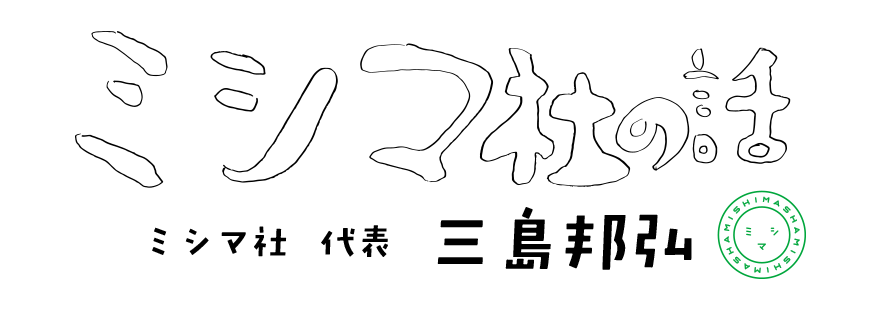第97回
遠くへ
2024.03.04更新
地震が起きたとき、僕は石川県の加賀市にいた。『雪の結晶』で有名な中谷宇吉郎の生家の近くであり、亡き我が祖母の故郷付近でもある。たまたま大晦日からその近辺の旅館で、家族、親戚の人たちと過ごしていた。
2024年1月1日午後4時過ぎ――。足元がぐらりと揺れた。立ってはいるものの、まっすぐ立てている実感がない。波打つ地面にいるだけでこれほど不安をおぼえるなんて。と思ったのは、幾日も経ってからだろう。その時点での最大の恐怖は、音だった。
呑気な話だが、このとき僕は一階ロビーで温泉饅頭をもらうため列にいた。足元が危うい。という表現があるが、まさにそれ、床がパキッと割れて地中へ落ちてしまうのではないかと思った。もっとも、そう感じる直前には、けたたましい警報音が各所から鳴り響いたのだった。スマホの警報音であることを認識したときは、もう、足元が危うかった。同時に、カタカタカタ、という不穏な音が頭上を覆う。吹き抜けのロビーを囲む各階のガラスの柵や窓がいっせいに音をたてた。
割れて落ちてくる! そこにいる誰もが思ったことだろう。旅館の仲居さんの誘導もあり、急ぎ、近くのテーブルの下に頭を隠した。知らない人たちと、いつ収まるともわからない揺れに怯えながら、息をひそめた。数分だったかそれ以上だったか、わずかの時間に過ぎないが、同じ傘のもと、ならぬ同じテーブルの下、会ったばかりの人たちのなかに連帯感、仲間のような感覚を覚えたのは確かだ。
揺れがひと段落した隙間に、部屋へ戻った。間抜けなことに、温泉饅頭をしっかり片手に持って。
その日の夜、何より僕を救ったのは本の存在だった。そのとき偶然持ち合わせていた一冊が、梨木香歩さん『西の魔女が死んだ』。それも文庫ではなく、新装の上製版。出発前、なぜかそれを鞄に入れたのだった。
「今、現実には見えないもの、例えばこの箱の中身だとかそういうものを見たいと思い、実際に見えるようにするんです。(略)いちばん大事なことは自分で見ようとしたり、聞こうとする意志の力ですよ。自分で見ようともしないのに何かが見えたり、聞こえたりするのはとても危険ですし、不快なことですし、一流の魔女にあるまじきことです」(梨木香歩『西の魔女が死んだ 梨木香歩作品集』新潮社、p81)
学校に行けなくなったまいは、おばあちゃんのところで暮らすことになる。やがて、おばあちゃんの祖母が魔女であることを知らされ、「魔女の心得講座」のような時間を二人でもつ。その始まりが上の会話だ。
*
前回、次号の「ちゃぶ台」の特集が「三十年後」に決まったと述べた。その決定には、読者の存在が大きかった、とも。たしかにその通りであるが、もう一つ、年始に地震があったこと抜きには語れない。
昨年末の段階でいったん決着した特集テーマは、こういうものだった。
「私と⚪︎⚪︎の間に、線をひきなおす」
これに決めたのは、この間、発刊した自社本の存在が大きい。猪瀬浩平『野生のしっそう』(2023年11月刊)は、世間で障害者と呼ばれる兄と健常者と見なされる著者との間に「ある」とされる線を溶かし、自分も(著者のみならず、読む私たちもまた)同じではないか、という問いを浮かび上がらせる。二人の間にあったはずの線はなくなったのか、そして兄と私を囲うようにして線が引き直されたのか? 同月に「ちいさいミシマ社」レーベルから出た佐藤ゆき乃さんのデビュー小説『ビボう六』では、現実世界と妖怪たちの住む世界が交差する。読み進むうちに、主人公と怪獣ゴンスの同居する世界のほうが自然で普通に思えてくる。昨年12月に刊行した絵本『ゆきのゆきちゃん』(作絵:きくちちき)も、自他の境界線を溶かす。猫のゆきちゃんと、りす、うさぎ、ふくろう、しか、と人間たちは動物たちを種類分けする。けれど、本当にそれらは違う生き物なのだろうか? 絵本でしか実現しない銀世界が目の前に広がったとき、自分たちが無意識で引いてきた線の窮屈さから解放される。「ゆき きらきら ゆきちゃん きらきら みんな きらきら」。雪がゆきちゃんと動物たちと山と野原の境界線をなくし、みんな一緒に。同時に、それでもそれぞれの動物たちは、それぞれの動物として「ある」。
こうした本たちに共通するのは、
「これまで常識とされてきた境界線をなくす」と「自分と他者のあいだに新たな線を引きなおす」だ。
昨年終盤の刊行物の流れを受けての特集企画であった。
が、地震で、不安が芽生えた。今被災している方々に、より直接響く特集のほうがいいのではないか? そんな思いがなかったと言えば、嘘になる。
とはいえ、半年後に出る雑誌でいったいどのような支援ができるというのだろう?
正直なところ、行き詰まった。前回、かつてなく難航したと書いた背景には、こうした経緯があった。
「魔女は自分の直観を大事にしなければなりません。でも、その直感に取りつかれてはなりません。そうなると、それはもう、激しい思い込み、妄想となって、その人自身を支配してしまうのです」(前掲書、p117)
いったん企画を白紙に戻す。そこからやり直すのが最善なのだろう。
*
最相葉月さんの『母の最終講義』が、今年の最初の刊行物として自社から出た。著者のデビュー30周年にあたるエッセイ集ということもあり、早々にいくつかの媒体から取材依頼があった。その取材の二つに年始、同席する機会を得た。阪神淡路大震災で中井久夫先生のチーム(心のケアの活動)を取材された最相さんに対し、いずれの記者も取材者としての苦悩を打ち明けるように訊ねた。記者の問いには、自社の記者たちが現地で「すぐに役立つわけではない」活動に対し負い目を感じたり、ときには邪険にされていることへの戸惑いが見え隠れしていた。最相さんは、「ことばや記録」の大切さに言及された。「関東大震災の記録に自分だけがこの苦しみを味わったのではない、と知るだけで救われることもある」「(中井久夫先生の『災害がほんとうに襲った時』を震災後ネットで無料公開したことを訊かれ)災害時は誰もが何かしなければと熱くなりがちですが、中井先生のような美しいことばに触れることで静まる」ことがある、このようなことを述べられた。そのとき、私のなかで自分の仕事の意味が更新された。
ことばを、遠くに――。
地震や災害が起きると、どうしても、この瞬間起こっていることに全意識をもっていかれてしまう。けれど、この瞬間を生きていること、その中で滲み出てきたことばを残す、自分たちの役割はそっちのほうだ。
きっと、震災時にかぎらない。平時だって同じだ。
SNSに流れてくる電子記号、天候、気候の変化・・・自分の目の前、すぐ横で起きたり、通り過ぎたりする事象に囚われ、その一点に対し反応してしまう。もちろん反応することは自然の行為であり、感覚がしっかり機能している証左だ。雨模様に素直に反応すると、心も必然、雨模様となる。全面的に反応すれば、雨模様一色に。空も心もどんより。で、もう、何も手がつかない。こうなる。しかし、これではなかなか困る。何が困るかはよくわからないが、人間が困るということなのだろう。自然に従い生きる。自然人のススメ。「晴耕雨読」という熟語があるが、自然人とて、雨に自分を完全同化させるわけではなく、書を読む。雨だから書を読もう。この「切り替え」を経ての雨読である。そう思うと、ゆきちゃんも「切り替え」しているように思えてくる。雪によって他の動物との区分けがなくなったゆきちゃんは最後のページで、「ゆきちゃん」として一匹、「わたし ゆきちゃん」と言う。
自分の仕事に置き換えたとき、出版人としては、条件反射で企画を立てるようなことは慎むべきだろう。紙の本、紙の雑誌でSNSと変わらぬ「溜め」のないことばを発信してしまったら、自分たちの存在自体を否定してしまうにひとしい。
だから、ことばを、遠くに。もっともっと遠くへ投げよう。
遠投だ。
実は最近、毎週僕は小学生野球のコーチをしている。その話はいつかに譲るが、ウォーミングアップのあと、必ずキャッチボールから練習を始める。下投げから始まり、上投げに。少しずつ距離を延ばし、最後は、かなりの距離から投げる。全力で投げる。
もちろん、遠投の練習をするのは、外野手がバックホームなどで実際に投げる場面があるからだ。外野手にかぎらない。ピッチャーのように短い距離しか投げない選手も遠投する。それは、近距離で力を出すのにも効果的だからだろう。一流ピッチャーが、「キャッチャーミットめがけて投げる球は弱い。その先のバックネットにまで突き抜けるように投げる」と言うのをしばしば耳にするが、遠投をしてこそ球威も増すにちがいない。
ただし、遠投するのはそうした実際的理由だけでない気が最近し出した。
妄想や思い込みを振り払うために、投げる。
今からまっさらな気持ちで練習に臨む。その状態に心身を持っていくためのひとつの儀礼としての遠投。魔女でなくたって、気になることや思い込みに自分が支配されていては何もできないだろうから。
年始の出来事の大きさに必要以上には引きずられない。そのためにこそ遠くへ投げる。三十年後の人たちに向けてつくる。それくらいの気持ちで遠くへ投げよう。
編集部からのお知らせ
ミシマ社ラジオ、はじめます!
3月1日から、ミシマ社のポッドキャスト「ミシマ社ラジオ」がスタートしました!!
本をあまり読まない人も、本好きな人も、思わず本を読みたくなる、そんな時間をお送りします。
出版社ミシマ社が運営する、本との出会いがちょっとだけ広がるラジオです。
「#0 ラジオをはじめます」では、この番組でやっていきたいこと、意気込み、などを慣れないマイクの前で、代表・ミシマとアシスタント・フジモトがお話ししました。
今後、トークイベントのアーカイブや新刊にまつわる話を公開していきます。
どうぞ気軽にお聴きください。よろしくお願いいたします!