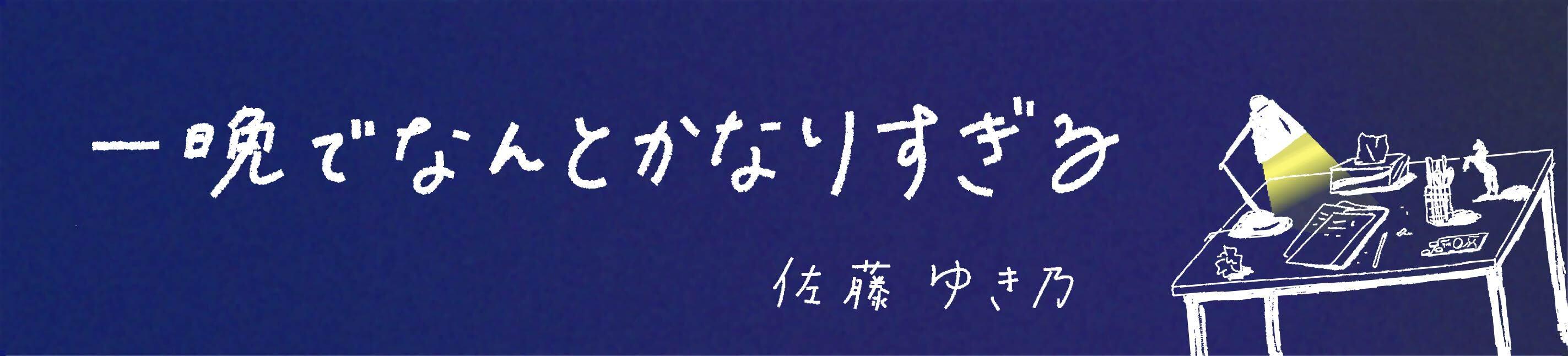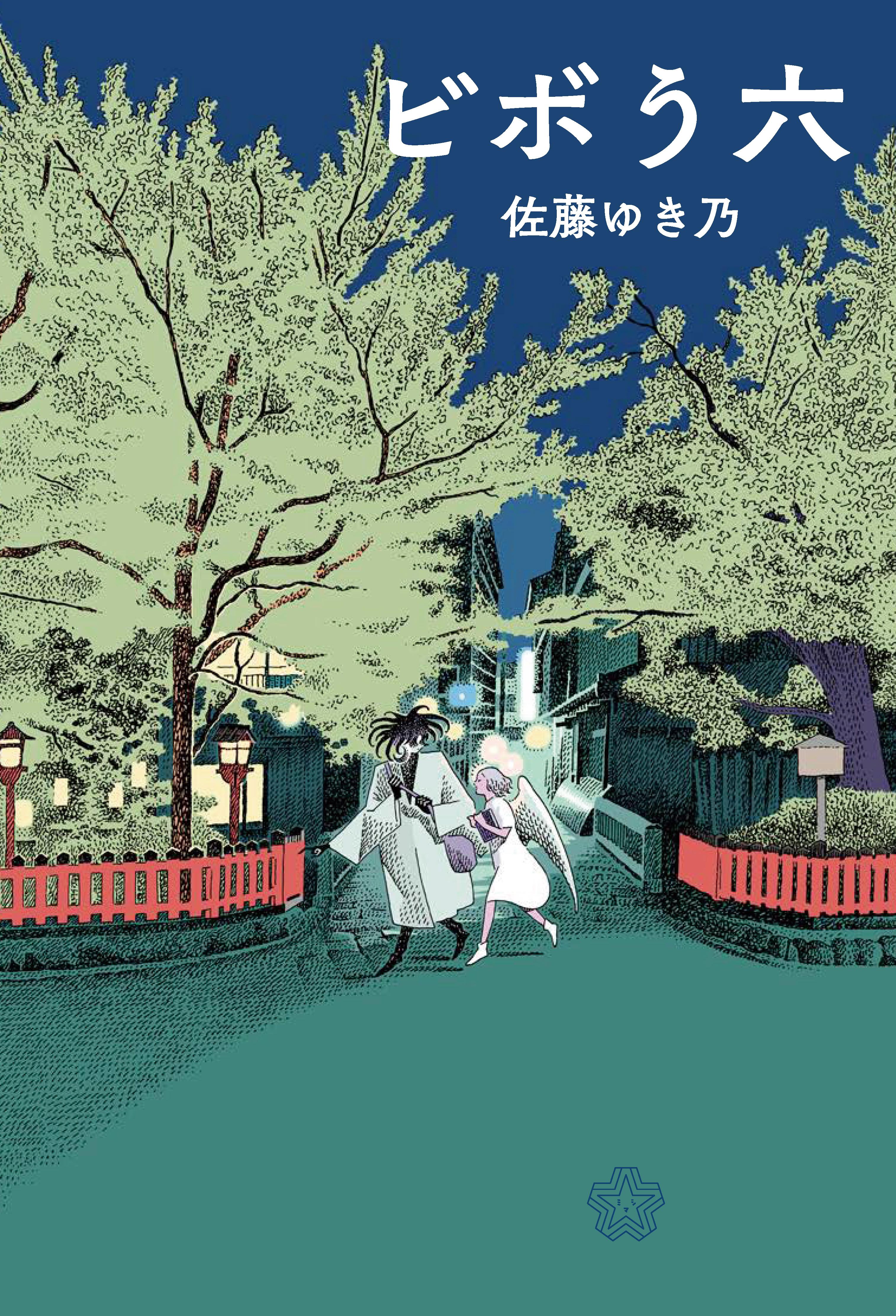第12回
どこまで遠くへ来られただろうか
2025.03.25更新
その日、はじめて有給休暇を使った。
「休む」権利が自分にも与えられているということを存じてはいたものの、何しろ東京で働き始めてまだ一年目。なかなか申請する勇気が出ずに、入職して何か月も経ったころ、最初の有給を一日もらった。
朝起きてまず、布団から出もしないうちに、「今日は仕事へ行かなくていいんだ」という事実をかみしめる。あまりに嬉しくて、胸の奥が広くなるようだった。
充実した休日をスタートさせるために、まずはおにぎりを作って食べようと台所に立つ。うきうきしながら炊飯器を開けようとするも、残念ながら米は炊けていなかった。
そういえば前日の夜、はじめての有給が嬉しすぎて、一人で盛大に酒盛りをしたのだが、それで酔っぱらってしまって、米をといだはいいものの、炊飯の予約スイッチを押し忘れていたのである。
出鼻をくじかれてがっかりしたが、仕方がないので早炊きモードで炊いた。
米農家の孫として育ったため、米の味はよくわかるはずという自負がある。だから「早炊きだとちょっとかたすぎるんだよね~」などと得意ぶって、普段はこの機能を使わないが、このときはじめて食べてみた。
熱々のうちにおにぎりにして、塩をたっぷり振って、のりを巻き、がぶりとほおばったところ、意外なことに、味の違いなどまったくわからないのである。なんだか拍子抜けしてしまった。
朝食のあと、簡単に部屋を片付けてから、一張羅の綺麗なワンピースを着て出かける。
電車を何本も乗り継いで、浜松町の自由劇場というところへ。浅利演出事務所主催の『ユタと不思議な仲間たち』というミュージカルを観に行った。大学時代は演劇サークルに属したほど、舞台を観ることは大好きなので、本当にうきうきした心持ちだった。
この『ユタ』という作品には、昔から何かと縁がある。
原作は三浦哲郎氏による児童文学作品だが、この著者は自分と同郷で、岩手県二戸市にルーツを持つ作家らしい。
だからか、二戸で過ごした子ども時代は、とにかく『ユタ』に触れる機会が多かった。
人生ではじめて文章のコンクールに入賞したのも、そういえば『ユタ』の読書感想文であった。劇団四季のミュージカルも、小学生のころに二度観た(一度目は二戸市民文化会館で、二度目はたしか、近くの中学校へ劇団の方々が訪問してくださり、体育館の床にござをひいて観劇した)。
それでもなぜか、『ユタ』という物語に対して、どうしても少しの苦手意識があったような記憶がうっすらと残っている。
どうしてだったろう、と考えながら、チケットとパンフレットを握りしめ、自分の席を探して座った。
開演前の客席を見渡してみると、おしなべて素敵な装いのお客さんで満員である。
こんなにきらきらした、おしゃれな東京の人たちが、『ユタ』という、岩手北部の田舎を舞台にした、(垢抜けなくて、たぶんダサい部類の方言である)南部弁で語られる物語を求めて大勢集っているということは、なんだかとても不思議に感じられた。
やがて幕が開く。自分が『ユタ』の物語に抵抗感を持った理由は、開演してすぐに思い出した。
物語の冒頭、主人公・ユタがいじめにあうシーンがあるのだが、ここがいきなりとてもハードなのである。
ユタは東京から(おそらく二戸をモデルとした田舎町へ)引っ越してきた転校生で、「東京のもやしっ子」などと因縁をつけられ、地元の子どもたちからバカにされている。
劇中では、とぼとぼと下校してきたユタを、クラスメイトが大人数で取り囲んでからかう。大声ではやし立てながら殴ったり蹴ったり、引きずりまわしたりなど、かなりビビッドな表現で、悲運なユタの境遇が描かれている。
このシーンを観た小学生のころ、自分が完全に「そちら」側、よそ者をひどくいじめている側の、粗野で野蛮な田舎の子どもである、ということを突き付けられたような気がして、それがすごくショックだった。声が大きくて、乱暴で、意地悪。頬に泥をつけ、時代遅れの服を着て、野山を駆け回っている、自分はそういう部類の子どもなのだ、と思い知らされるのは悲しかった。
たぶん、舞台があまりにも地元すぎたので、どうしても彼らと自分のステータスを同一視してしまうのである。
これはフィクション、架空のお話、と子どもながらに理解してはいたはずだが、劇中を通して用いられる南部弁のメロディが、自分の血肉に深く濃く刻み込まれているものだから、みるみるうちに、いじめっ子のキャラクターたちに自らが重なっていってしまう。
物心ついてからずっと、「田舎の子ども」として生まれてしまったことにはとにかくうんざりしていて、だから物語を渇望した。小説や音楽、たまに連れて行ってもらえるお芝居がなにより大事なよりどころであった。しかして『ユタ』の世界に限っては、その真逆のことが起こってしまうのである。逃れたい現実を、より誇張して差し出されるので、『ユタ』は特異な作品だった。
そんなことを思い返しつつ、素晴らしい演技と圧巻の演出に引き込まれ、夢中で観た。やがて、あっという間に一幕の終盤に差しかかる。
そこで歌唱された劇中歌『ともだちはいいもんだ』を聴いて、不覚にも涙が出てしまった。
この歌は、二戸では定番の合唱曲であった。小学生のころ、何度も何度も繰り返し歌ったので、細胞の芯に染み込むように覚えていて、いまでもやすやすと口ずさむことができる。
「ともだちはいいもんだ」と何度もリフレインする歌詞。二十年近く前、まさしく自分と同じく「田舎の子ども」である同級生たちと声を合わせてこれを歌いながら、正直、なんて押しつけがましい歌だろうと思っていた。そのころ、クラスに友だちと呼べるくらい仲のいい相手は本当にごくわずかしかいなかったのだ。こんな環境の中で、無理やり友だち賛歌を歌わされて、ああ早く大人になりたいな、と考えていた遠い日々が鮮明によみがえる。
それでもいま、こうして大人になってみると、どういうわけか、ものすごく素直な気分で「ともだちっていいよなあ」と共感できるのであった。歌詞が南部弁にアレンジされていたので、たまらない郷愁をはらむメロディとして体にするりと入り、さまざまな記憶を巻き込んでは、巨量の感慨が膨らんでゆく。「ともだちはいいもんだ」。幾人かの顔が頭に浮かんでは、あの人もこの人も、地元を、二戸を出てから出会った友人であることに思い至る。「田舎の子ども」時代から、ずいぶん遠くへやってきたような気がした。
幕間、休憩のために一度客席を出る。
ロビーで、母親らしき女性が、小学生くらいの子どもへ「台詞は聞き取れた?」と聞いていた。その子は「方言だったから、よくわからなかった」と答えた。
それには大変驚いた。自分にとって、標準語よりもっと標準に感じるリアルな南部弁が、東京の人には伝わらないらしいのである。これが「地元を離れる」ということ。考えてみれば当然のことではあるが、すごく強烈な印象として残った。
二幕はずっと泣き通しだった。ストーリーが素晴らしいことはいうまでもないが、なによりノスタルジーがあまりに濃くて、二戸で過ごした遠い子ども時代を思い返しては、胸がいっぱいになってしまう。
あのころ、ずっと遠くへ行きたかった。二戸ではないところへ、ユタがもともと住んでいたという東京へ。「東京の子ども」が本当に羨ましかった。汚くもうるさくもない、意地悪もしない人になりたかった。なれただろうか。はたして、どこまで遠くへ来られただろうか。
きっとなれたはず。たぶん、すごく遠くへ来ている。だって今日、劇場へ来る途中で、山手線に乗った。渋谷駅を使った。スカイツリーだって見た。いま、東京で暮らしている。故郷からは遠く離れた場所で。
それでも、そこで地元の言葉を聞いていると、すっかり引き戻されてしまうのであった。
登場人物たちの語りは、すでに鬼籍に入った祖母や大叔母が生前に話していたのと完全に同じ音色で、だからどれも、もういない家族たちからの言葉のようにも感じられる。
劇中に「(二戸の空に浮かぶ)これが本物の満月だよ」という台詞があった。同じようなことを、そういえば祖母も言っていたような気がする。あるいは言っていなかったかもしれないが、その教えは、ほとんど過去の祖母からのものとして、いまの自分へまっすぐに届く。
たしかに「田舎の子ども」だった時代、あれからたくさんの別れがあって、同じように出会いもあって、いま、こうして東京にいる。どのくらい遠くへ来たのかはわからない、でも、戻り方を知っている。南部弁のメロディを聴くだけ、『ユタ』の世界を再訪するだけで、いつでも帰ることができる。できてしまう。
切っても切り離せないもの、忘れたくても忘れられないことの数々。自分と地元を結びつけるなにか。昔は嫌でたまらなかったはずのその縁を、大人になった今日は、こんなにもありがたく思う。本当に心に残る観劇体験であった。
劇場を出て、余韻に浸りながら帰る途中、都心の高層ビルの入り口で、小学生と思しき子どもたちが、スケートボードで遊んでいるのを見かけた。
どんなに頑張っても、私はあの子たちにはなれない。東京の子どもには絶対になれないのだ、と、このとき、妙に深く納得した。
夕暮れの電車に揺られながら、無性に米が食べたかった。帰ったら、実家の白米を極うまモードで炊いて、はっきり塩味をつけたおにぎりを作って、それでお酒を飲み、はじめての有給休暇を締めくくろう、と思いつく。しかし、そういえば自分は、早炊きモードで炊いたって、味の違いがわからないんだった。思い出して内心で苦笑する。
それでも、「自分には米の味がわかるはず」と自信を持てることが、私があの地元で会得した、大切なアイデンティティなのだと思う。東京での一人暮らしは、その自負に大いに支えられている。