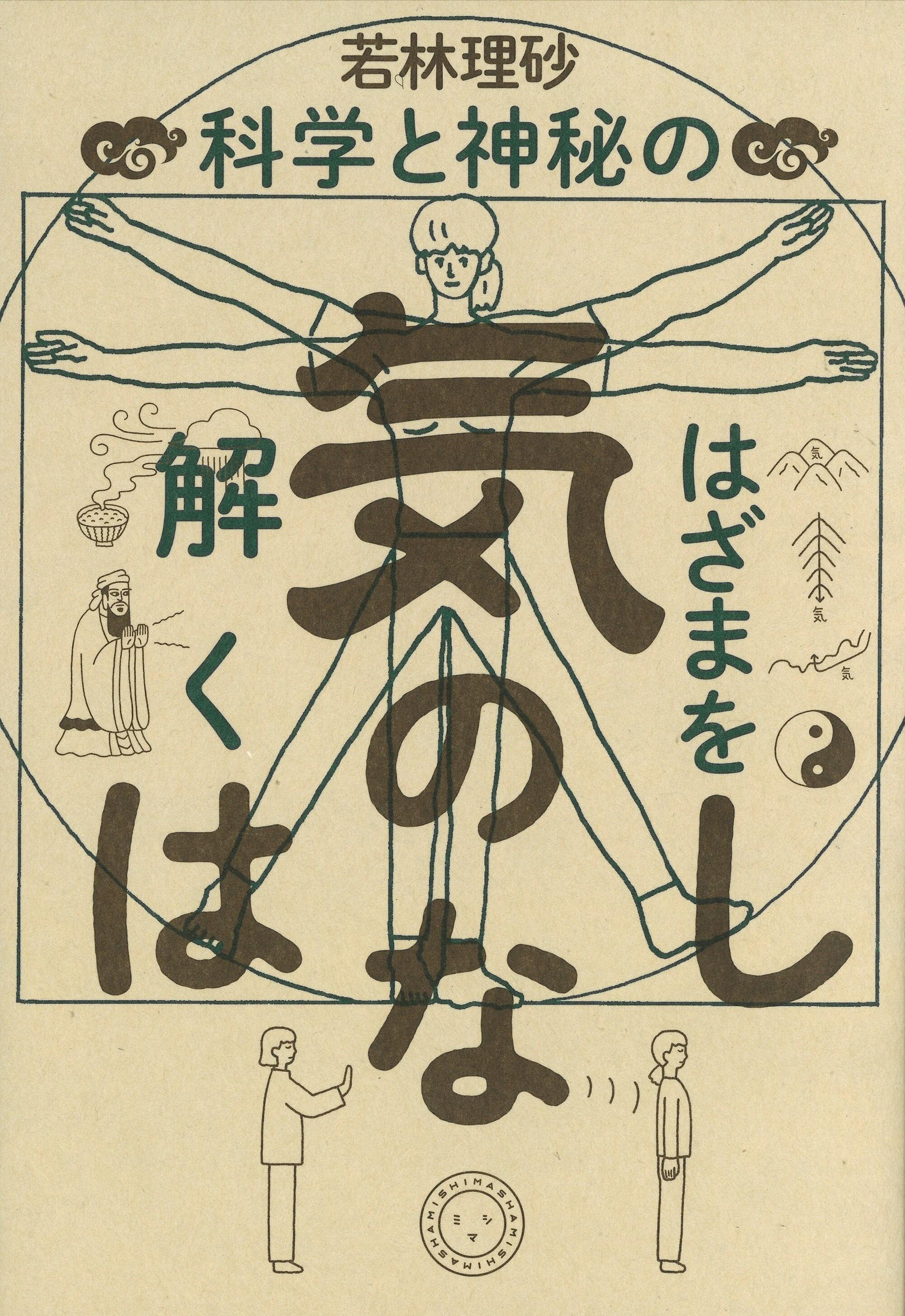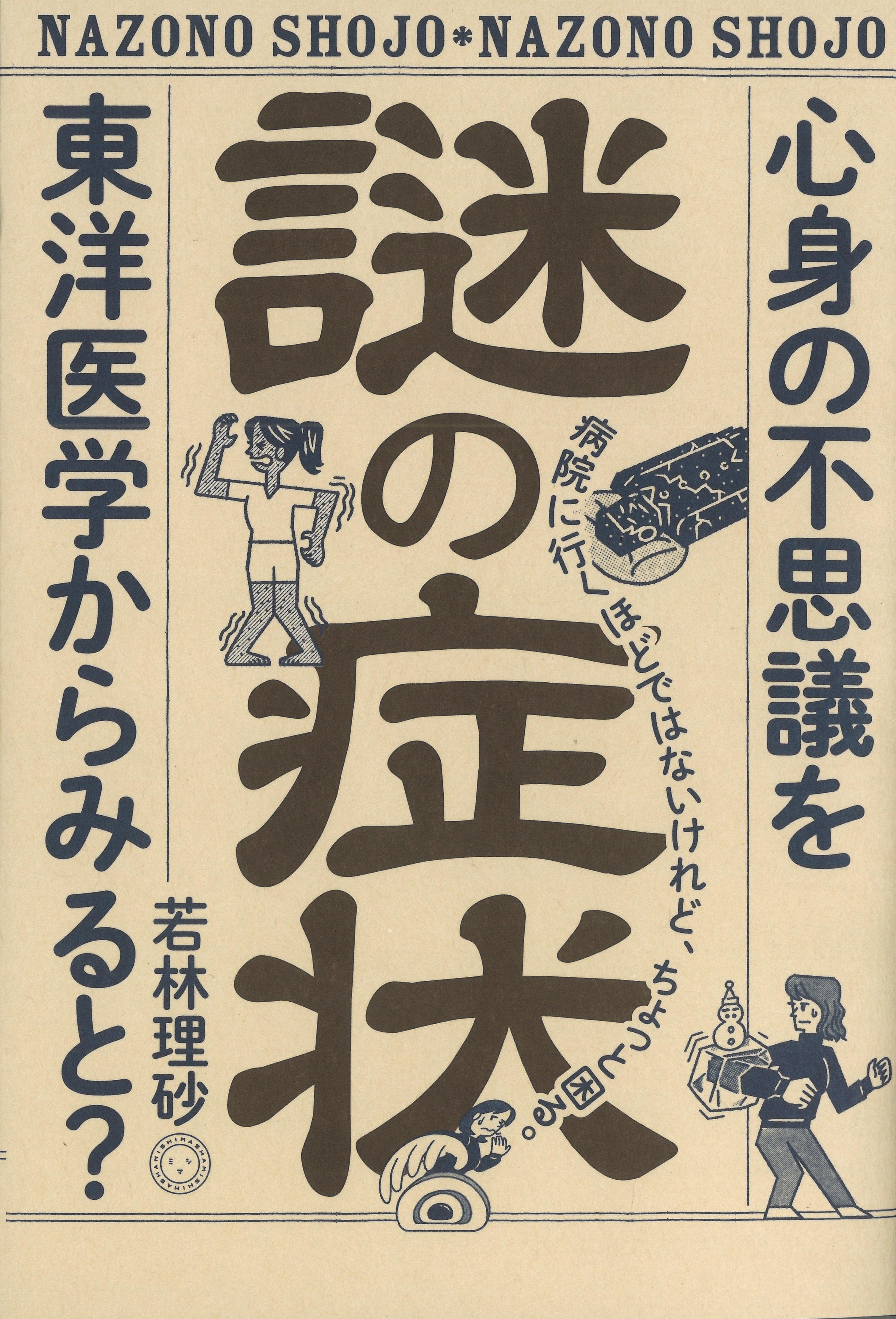第1回
パンの耳と、白いところを分ける
2025.03.10更新
......パンの耳って、ありますでしょ? 食パンの白いところと、茶色いところのうちの、茶色いところが耳。サンドイッチ用にスライスされた場合、パン屋さんでは削ぎ落とされて、ものすごく安く売られたりしています。場合によってはタダでもらえることもありますね。だけど、私はパンの耳の部分、結構好きなんですよ。香ばしくて。もしも焼きたてだったら、耳のところの方がごちそうだと思ったりします。
で。クロワッサンって、ありますでしょ。あれってどこが耳だって言ったら、「皮」のところが耳ですよね。皮のところが美味しい。クロワッサンの皮だけ剥いで食べると、真ん中のところが残ります。やったことありますか? 皮を外すともちもちしていてそれはそれで美味しいのです。クロワッサンの皮や食パンの耳を取り除くと、白いところだけが残ります。パンの本体って言ったら、そこのところが本体なのはみんな異論はないだろうなと思います。
じゃあ、デニッシュロールはどこなんだ? って、そうなってくるともう、耳と本体が分けられないくらいサクサクしてますよね。耳が本体? なのかな。パンで言うと、耳と本体が分離し難いデニッシュロールくらいに本体と枝葉が混じり合っているのが、東洋医学の古典の内容なのです。
「東洋医学は経験医学で、古代からの臨床知識の集積である」と、皆さんも聞いたことがあるのではないかと思います。だけど、そこには、「パンの本体」と言える医学的な臨床知識の積み重ね以外に、「耳」の部分が複雑に混ざり込んでいるのです。具体的に言えば、道教の考え方であり、中国の古代思想であり、陰陽や五行などの哲学であり、その時代の文化です。
伝統医学というのは、土着の信仰や風俗などその土地由来の文化的な側面を切り離して使用することは難しいものなのですが、中国医学は国策としてある程度切り離して「中医学」の形に整え、全世界に広めることに成功したかなり特殊な伝統医学です(この辺のお話もおいおいしますね。)
切り離して薄めた主なものに神仙道の影響があります。これは、健康で長生きをするための「養生」の源流となっているものです。病気を治すことだけではなく、養生の道を説いてるのが東洋医学の特徴的なところなのですが、これは宗教由来のものなのですよ。ですが、東洋医学は神仙道・道教の影響を決して消しきれないほどの大きな影響を受けており、医学古典の中にもあちこちにその痕跡を見ることができるのです。
今回の連載では、そういった「パンの耳や皮」の部分にあたる、病気を治す以外の部分......飲食起居、生老病死の「病」以外のところを、医学古典や宗教経典やその他物語などに当たって、その時代の人たちがどんなふうに生活一般に関わることを扱っていたのかを書き連ねようと思っています。そうやって「パンの耳や皮」を丁寧に外して分けていったら、「パンの本体」である臨床知識の集積の部分がはっきりと浮かび上がってくるのではないかと。
パンの本体は、もしも、きれいに耳と皮が剥がせたらお見せしますね。そちらはそちらで楽しみに待っていてください。でも、デニッシュロールだから、剥がすと本体がほとんど無くなっちゃうかもしれないのですけどね!