第2回
医学と宗教!? 〜道教・儒教・仏教の影響
2025.04.11更新
まず、東洋医学って、自然科学+思想で成り立っている医学であるという話。元々、世界中にある伝統医学は必ずその地域の思想や宗教を内包した形で成り立っています。医学技術がまだ未発達であった時期は、超自然的な存在が病気にしたり、病気を治したりしていると考えられていたので、医師=呪術師であった時期が長かったんですよ。これはレヴィ=ストロースが「呪医」として世間に知らしめたアレです。ですので、みんなが「これは東洋医学」と認識しているものの中にも、さまざまな思想宗教的意味合いの強いものが混じり混んでいるわけなのです。
日本人の生活に密着している宗教というと、仏教と神道をみんなは思い浮かべると思うんだけど、それ以上に隠れているけれどもんのすごく大きな影響を受けているものが、道教と儒教という中国由来の思想・宗教なのですよ。まず、道教と儒教の説明から。
【道教】
中国古代の道家思想を基に発展した宗教・哲学で、老子(『道徳経』)や荘子の思想に由来する「道」を宇宙の根本原理とし、自然と調和しながら生きることを重視します。とはいえ、内包される概念は広大でおおまかに把握するのも苦労するほど。その内容は、長生不老や仙人思想、気の流れを整える養生術(内丹術)、道観(道教寺院)での祭祀や符籙(護符)を用いた呪術的技法などが見られます。後にきちんとした教団を形成していき、天師道や正一教、全真教などの宗派が成立していきますが、民間信仰的な道教は別系統で発展しています。
【儒教】
儒教は、孔子(紀元前6世紀)が説いた倫理・道徳体系で、社会秩序の維持を目的とします。『論語』を中心に、仁(人への思いやり)、礼(社会規範)、忠(忠誠)、孝(親孝行)などを重視しています。ですので、いわゆる宗教とは本来は異なっていると考えてもいいくらいです。前漢時代に董仲舒が儒教を国家の統治思想に採用し、以後、科挙制度を通じて中国の支配思想となりました。なんというか、「政府は儒教、民間は道教」といった様子です。宋代の朱熹は朱子学(新儒学)を体系化し、日本や朝鮮にも影響を及ぼしました。現代においても日中韓の人々の考え方の根底に儒教が脈々と受け継がれています。
【仏教】
紀元前5世紀ごろインドの釈迦(ゴータマ・シッダールタ)によって開かれた宗教で、「四苦(生・老・病・死)」を超越し、悟り(涅槃)にいたり、輪廻から外れることを目的とします。紀元前後に大乗仏教が生まれ、これが中国には1世紀ごろ伝来し、道教の影響を受けながら天台宗・禅宗・浄土宗などが成立します。隋・唐代には国教に近い地位を持ち、日本や朝鮮にも広まっていきます。特に禅宗は、実践重視の修行体系として独自の発展を遂げました。
これらは三教と呼ばれて、創始者が同列に並べられて描かれていたりします。
仏教は釈迦がインドで確立したものですね。中国から日本に大乗仏教が伝わったのですが、仏教はもう一つ、インドから南下してタイなどへ伝わっていく上座部仏教の系統に分かれます。これは自力救済という、出家と修行によって自ら解脱を目指す原始仏教の形を色濃く残すものです。中国方面を北伝、タイ方面へ行くのを南伝と言います。そして、北伝の方は中国にて道教・儒教の考え方がそこここに混ぜ込まれ、その後に日本へと入ってきたのです。
例えばの話なんですが・・・お寺さんで「ご先祖様を大切に」と言われたりしませんか。これは、儒教由来です。孔子が儒教を作り上げる前の民間信仰にも祖先崇拝があり、それを取り込んで発展したようです。仏教の創始者である釈迦は、親子の縁を絶って出家し、解脱を目指したのですから、「祖先や親子の縁を大切に」という思想と相反するのが仏教なんですよ。何より大切にしろと言われたりする「お位牌」「仏壇」も原始仏教には存在せず、あれは儒教由来のものです。
全ての人との縁を切って親子配偶者を捨ててただ真理のために歩み、輪廻の輪からの解脱を目指すってのが、仏教です。ブッダとイエスが立川で二人暮らしをしているという設定の漫画『聖⭐︎お兄さん』の中に、出家直後、衣服すら否定するブッダを「パンク」と表現するコマが出てきますが、本当にそうなんですよね。
一方、中国で一番古い土着信仰の流れを汲んでいる道教、それよりも時代が下っての儒教は、祖先崇拝を含んでいます。道教では、先祖の冥府での幸せが自分たちの現世利益につながるとされているのですが、祀る側は基本的に男系男子でないとならないとされていてですね。女子とか、養子ではダメなんですよ。やむを得ず女性や養子が祭祀を行う場合は、一族の長老の赦しを得る必要がある上、宗教的な手続きが必要です。祖先に占いで女性や養子が祭祀を行なってよいかお伺いを立てたりすることもあります。なので、長老の許可が得られなかったり、占いで否定された場合は祭祀することができません。ここに、女性がどうしても婚家で男子を産まないとならないと言われる理由があるのです・・・現代人の感覚からしたら、すごくイヤでしょ。私もすごくイヤです。
ちなみに、その辺で行き倒れて身元不明の遺体になったり、男系男子が生まれなかったりした家はなんらか手続きを行わないと祭祀が絶えることになりますが、その際、祖先は冥府でえらい目に遭って祟り神になりますし、行き倒れた人はキョンシーになります。キョンシーって、元はその辺に転がっていて祀られなかった遺体なんだよ、知ってた?
さて、じゃあどの思想が東洋医学に影響を強く与えているかというと、主に道教です。いわゆる養生思想は道教に端を発しているのですよ・・・それも、神仙道由来の考え方です。不老長寿を目指す一歩手前では、長命長寿を目指してそれをできるだけ保つことが目標にされました。そのための養生なのです。だから、東洋医学の中でも古い医学古典である『黄帝内経 素問・霊枢』を紐解いても、そこまで細かい養生法に関しての記述は出てこなかったりします。
『馬王堆帛書』の中には養生法・導引・胎産書・雑療法の三つが同じ絹布に書かれていたのですが、養生法は精力増強剤や補気・補血財、寿命を増す薬などの神仙道にあるようなものの紹介に終始ししており、私が考えていたものとは違っていて、読んだ際に当てが外れた! と思いました。ちなみに導引は気功法の原点のような体操の絵と少しの解説、胎産書は胎児がどのように育つかを書いており、呪術で女児を男児に変える方法が記載、雑療法は男性の精力を増して女性を興奮させ、これにより気を増すための方法や胎盤を埋める方角を決める呪術的な方法が記載されています。
『黄帝内経』で養生に関連して一番有名なのがこの部分でしょう。
【上古天真論第一】
昔在黄帝、生而神霊、弱而能言、幼而徇齊、長而敦敏、成而登天、廼問於天師曰、余聞上古之人、春秋皆度百歳、而動作不衰、今時之人、年半百、而動作皆衰者、時世異耶、人将失之耶、
岐伯対曰、上古之人、其知道者、法於陰陽、和於術数、食飲有節、起居有常、不妄作労、故能形与神倶、而尽終其天年、度百歳乃去、今時之人不然也、以酒為漿、以妄為常、醉以入房、以欲竭其精、以耗散其真、不知持満、不時御神、務快其心、逆於生樂、起居無節、故半百而衰也、夫上古聖人之教下也、皆謂之虚邪賊風、避之有時、恬惔虚無、真気従之、精神内守、病安従來、是以志閑而少欲、心安而不懼、形労而不倦、気従以順、各従其欲、皆得所願、故美其食、任其服、樂其俗、高下不相慕、其民故曰朴、是以嗜欲不能労其目、淫邪不能惑其心、愚智賢不肖、不懼於物、故合於道、所以能年皆度百歳、而動作不衰者、以其徳全不危也、
昔在黄帝、生而神霊、弱而能言、幼而徇齊、長而敦敏、成而登天、廼問於天師曰、余聞上古之人、春秋皆度百歳、而動作不衰、今時之人、年半百、而動作皆衰者、時世異耶、人将失之耶、
岐伯対曰、上古之人、其知道者、法於陰陽、和於術数、食飲有節、起居有常、不妄作労、故能形与神倶、而尽終其天年、度百歳乃去、今時之人不然也、以酒為漿、以妄為常、醉以入房、以欲竭其精、以耗散其真、不知持満、不時御神、務快其心、逆於生樂、起居無節、故半百而衰也、夫上古聖人之教下也、皆謂之虚邪賊風、避之有時、恬惔虚無、真気従之、精神内守、病安従來、是以志閑而少欲、心安而不懼、形労而不倦、気従以順、各従其欲、皆得所願、故美其食、任其服、樂其俗、高下不相慕、其民故曰朴、是以嗜欲不能労其目、淫邪不能惑其心、愚智賢不肖、不懼於物、故合於道、所以能年皆度百歳、而動作不衰者、以其徳全不危也、
【現代語訳】
昔、黄帝は生まれながらにして神秘的な才能を持ち、幼いうちから話すことができ、少年期には物事をよく理解し、成人してからは聡明で勤勉になり、ついには天に昇った。そこで天師に尋ねた。
「私は聞いたことがある。昔の人々は皆百歳まで生き、しかも老いることなく健康でいられたという。しかし、今の人々は五十歳を迎えるころには衰えてしまう。これは時代が変わったからなのか、それとも人々が何かを失ってしまったからなのか?」
すると、岐伯が答えた。
「昔の人々の中で道を知る者は、陰陽の理に従い、生命の法則を守り、飲食を節度あるものとし、規則正しい生活を送り、無駄に体を酷使することがなかった。だからこそ、身体と精神が調和し、天が定めた寿命を全うし、百歳を超えてからこの世を去ったのです。しかし、今の人々はそうではありません。酒を水のように飲み、無秩序な生活を当たり前のものとし、酔ったまま情欲にふけり、性欲によって精を使い果たし、真の活力を浪費しています。身体を適度に保つことを知らず、適切な時に精神を養うこともせず、ただ快楽を求めることに夢中になり、自然な生き方に逆らっています。そのため、生活に規則性がなく、五十歳を迎えるころには衰えてしまうのです。
そもそも、昔の聖人たちは人々に対し、邪気や害となる風を「虚邪賊風」と呼び、時に応じてそれを避けるように教えていました。心を穏やかにし、無欲であることで、真の気(生命力)が自然に保たれ、精神は内に充実し、病気とは無縁でいられたのです。そのため、心は静かで欲望が少なく、安心して生き、恐れることもなく、体を動かしても疲れを感じず、気の流れが自然と調和していました。人々はそれぞれ自分の生き方を尊重し、願うものを得ていました。だからこそ、食事を楽しみ、好きな服を着て、その土地の風習を大切にし、身分の上下を気にすることもありませんでした。こうした人々は純朴で、過度な欲望に目を奪われることもなく、不道徳な行為に心を惑わされることもなく、賢者も愚者も、貴い者も卑しい者も、物事に恐れることがありませんでした。そうして、自然の道に適った生き方をしていたのです。
だからこそ、昔の人々は百歳を超えても老いることなく元気でいられたのです。それは、彼らが徳を全うし、危険を避ける生き方をしていたからに他なりません。」
養生に「不道徳な行為に心を惑わされることなく」とあります。また、禁欲的であれとしているのも、宗教的意味合いを感じますね。
あとこちらもそうですね。
【四気調神大論篇第二】
春三月、此謂発陳、天地倶生、万物以榮、夜臥早起、廣歩於庭、被髮緩形、以使志生、生而勿殺、予而勿奪、賞而勿罰、此春気之応、養生之道也、逆之則傷肝、夏為寒変、奉長者少、夏三月、此謂蕃秀、天地気交、万物華実、夜臥早起、無厭於日、使志無怒、使華英成秀、使気得泄、若所愛在外、此夏気之応、養長之道也、逆之則傷心、秋為痎瘧、奉収者少、冬至重病、秋三月、此謂容平、天気以急、地気以明、早臥早起、与雞倶興、使志安寧、以緩秋刑、収斂神気、使秋気平、無外其志、使肺、此秋気之応、養収之道也、逆之則傷肺、冬為飧泄、奉蔵者少、冬三月、此謂閉蔵、水冰地坼、無擾乎陽、早臥晩起、必待日光、使志若伏若匿、若有私意、若已有得、去寒就温、無泄皮膚、使気亟奪、此冬気之応、養蔵之道也、逆之則傷腎、春為痿厥、奉生者少、
天気清淨光明者也、蔵徳不止、故不下也、天明、則日月不明、邪害空竅、陽気者閉塞、地気者冒明、雲霧不精、則上応白露不下、交通不表、万物命故不施、不施則名木多死、悪気不発、風雨不節、白露不下、則菀稾不榮、賊風数至、暴雨数起、天地四時不相保、与道相失、則未央絶滅、唯聖人従之、故身無奇病、万物不失、生気不竭、逆春気、則少陽不生、肝気内変、逆夏気、則太陽不長、心気内洞、逆秋気、則太陰不収、肺気焦満、逆冬気、則少陰不蔵、腎気独沈、夫四時陰陽者、万物之根本也、所以聖人春夏養陽、秋冬養陰、以従其根、故与万物沈浮於生長之門、逆其根、則伐其本、壞其真矣、故陰陽四時者、万物之終始也、死生之本也、逆之則災害生、従之則苛疾不起、是謂得道、道者、聖人行之、愚者佩之、従陰陽則生、逆之則死、従之則治、逆之則乱、反順為逆、是謂内格、是故聖人不治已病、治未病、不治已乱、治未乱、此之謂也、夫病已成而後薬之、乱已成而後治之、譬猶渇而穿井、鬪而鑄錐、不亦晩乎、
【現代語訳】
春の三か月は、「発陳(はっちん)」と呼ばれ、天地がともに生命を育み、万物が栄える時期である。夜は早く寝て朝は早く起き、庭を広く歩き、髪を下ろして(結ばずに)体をゆったりさせ、心をのびやかにする。生き物を殺さず、与えたものを取り上げず、褒めて罰しない。これが春の気(季節のエネルギー)に適応した養生の方法である。もしこれに逆らえば、肝を傷つけ、夏に寒気を感じるようになり、成長する力が減少する。
夏の三か月は、「蕃秀(はんしゅう)」と呼ばれ、天地の気が交わり、万物が花を咲かせ、実を結ぶ時期である。夜は遅く寝て、朝は早く起き、太陽の光を嫌がらず、心が怒らないようにし、花が咲き、実がなるように促し、気が発散されるようにする。まるで、自分の大切なものが外にあるかのように過ごす。これが夏の気に適応した養生の方法である。もしこれに逆らえば、心を傷つけ、秋にはマラリアのような病気にかかりやすくなり、秋の「収める力」が弱まり、冬には重い病気になる。
秋の三か月は、「容平(ようへい)」と呼ばれ、天の気は厳しくなり、地の気は明らかになる時期である。夜は早く寝て朝は早く起き、鶏が鳴くのと同じ時間に起きるようにする。心を穏やかにし、秋の厳しい変化を和らげ、精神を引き締め、秋の気が安定するようにする。気を外に向けず、呼吸を落ち着ける。これが秋の気に適応した養生の方法である。もしこれに逆らえば、肺を傷つけ、冬には消化不良になり、冬の「蓄える力」が弱まる。
冬の三か月は、「閉蔵(へいぞう)」と呼ばれ、水が凍り、大地が裂ける時期である。陽気(活動的なエネルギー)を乱さず、夜は早く寝て朝は遅く起き、日の光を浴びるまで起き出さないようにする。心を静かにし、隠れるように過ごし、何かを密かに持っているように、すでに得たものがあるかのように生きる。寒さを避け、暖かい場所にとどまり、皮膚から熱が逃げることを防ぎ、気が急激に奪われるのを避ける。これが冬の気に適応した養生の方法である。もしこれに逆らえば、腎を傷つけ、春には手足が冷えたり、萎縮したりする。春の「生じる力」が弱まる。
天の気(エネルギー)が清らかで静かで輝いているときは、徳(善いもの)が蓄えられ、失われることがないため、気が地に降りてこない。
もし天が濁ると、太陽や月が明るく輝かず、邪悪な気が空の隙間を満たし、陽気が閉塞し、地気が天の光を覆い隠してしまう。雲や霧が濁っていると、天の働きと地の働きがうまく噛み合わず、朝露が降りなくなる。天地の交流がうまくいかないと、万物の命は育たず、成長しなくなる。そのため、大木が枯れ、邪悪な気が発生せず、風や雨の調和が乱れる。白露(朝露)が降りなければ、穀物や草木は栄えず、異常な風が頻繁に吹き、暴風雨が頻発する。天地の四季が互いに調和しないと、宇宙の道(自然の秩序)に合わなくなり、すべてが壊れて消滅してしまう。ただし、聖人はこの道に従うため、奇妙な病気にかからず、万物は失われず、生命力は尽きることがない。
春の気に逆らうと、少陽(肝のエネルギー)が生じず、肝気が内部で変化してしまう。
夏の気に逆らうと、太陽(心のエネルギー)が伸びず、心気が内部で消耗する。
秋の気に逆らうと、太陰(肺のエネルギー)が収まらず、肺気が乾燥し、満ちすぎる。
冬の気に逆らうと、少陰(腎のエネルギー)が蓄えられず、腎気が沈んでしまう。
四季の陰陽の変化こそが、万物の根本である。そのため、聖人は春夏には陽気を養い、秋冬には陰気を養い、自然の法則に従って生きる。これにより、万物と共に成長と休息の流れに乗ることができる。しかし、この流れに逆らえば、生命の根を切り、本質を壊すことになる。陰陽と四季の変化は、万物の始まりと終わりであり、生と死の根本である。それに逆らえば災害が生じ、それに従えば病気は起こらない。これこそが「道(自然の摂理)」を得ることである。
この道は、聖人は行い、愚か者はただ身につけるだけである。陰陽に従えば生き、逆らえば死ぬ。従えば社会は安定し、逆らえば混乱する。順に従うことをやめ、逆に行うことを「内格(ないかく)」という。だからこそ、聖人はすでに発病した病を治すのではなく、未然に病を防ぐ。また、すでに乱れた状態を治めるのではなく、乱れる前に予防する。これこそが本質的な考え方である。
病気になってから薬を飲むのは、喉が渇いてから井戸を掘るようなもの。
社会が乱れてから改革するのは、戦いの最中に武器を作るようなもの。
これでは、あまりにも遅すぎるではないか。
こちらでは、季節の気の流れに合わせることが養生として語られています。また、陰陽に従えば社会は安定し、逆らえば乱れるとも言っています。ちょっと唐突な感じがするでしょう? これは、天人合一思想と呼ばれるもので、人の営みと世界のことわりが一致していると、世界が安定すると考えられていたのです。特に為政者がきちんと四季に合わせた行動をとることが大切と考えられており、漢代の皇帝は明堂と呼ばれる季節に合わせた五行の方角の部屋がある宮殿で政治を取り行っていました。春は東、夏は南、秋は西、冬は北、四季の間の時期は中央の部屋にいたのです。このようにすることで、きちんと四季が訪れて、世界は平穏を保つと考えていました。
おまじないみたいだと思うでしょ? そうなんですよ。おまじない。人の営みと世界の気の流れが相互に作用すると考えた、おまじないの部分と、本当に季節に合わせた生活がごちゃごちゃに伝わっているのが、古典の中の養生なんです。
私が提唱している養生は、この、おまじないの部分を取り除いて簡略化したものです。簡略化すると、寝る・食う・動くのシンプルなところに落ち着いちゃうんですねー。ご理解いただけました? えへへ。




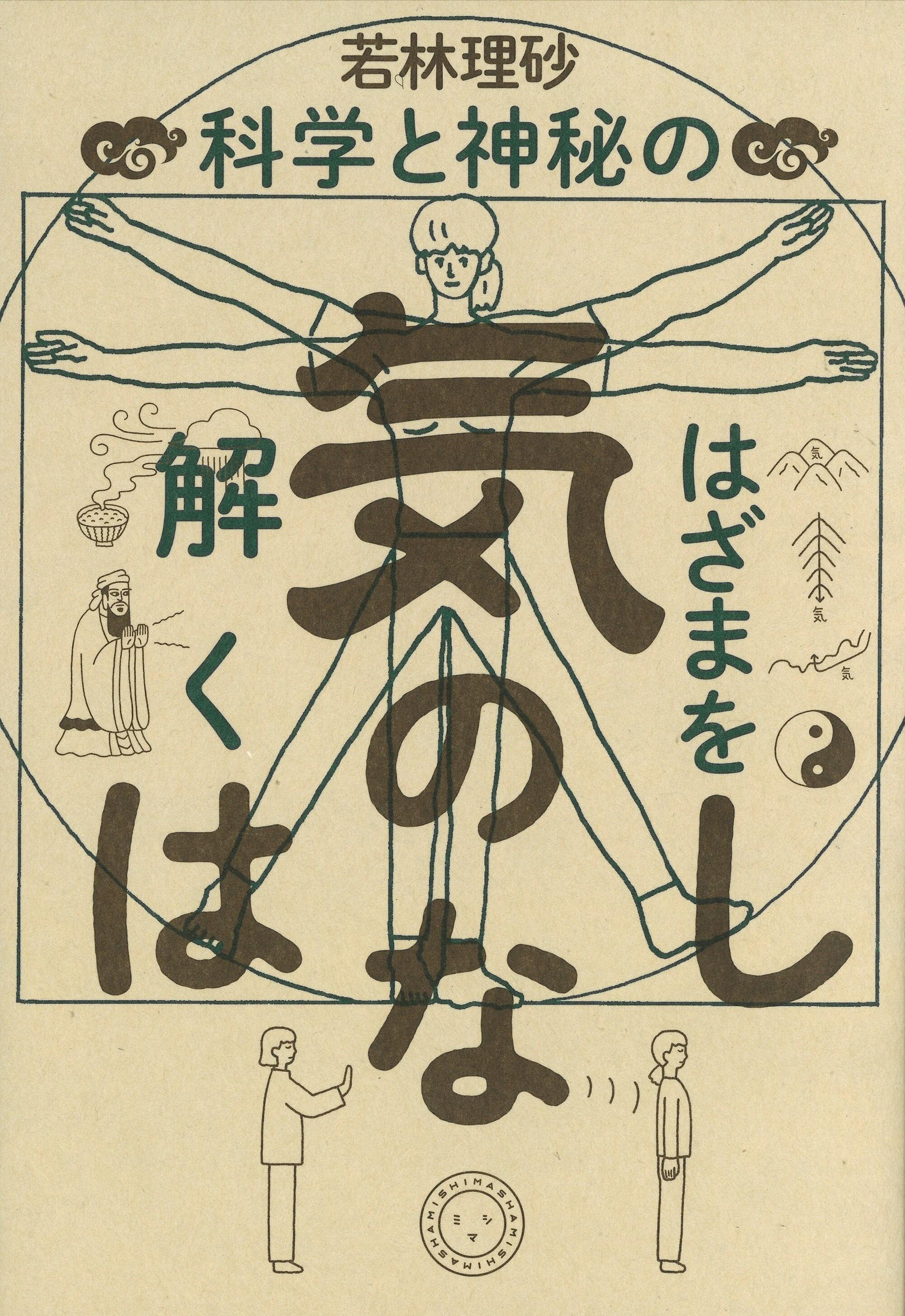
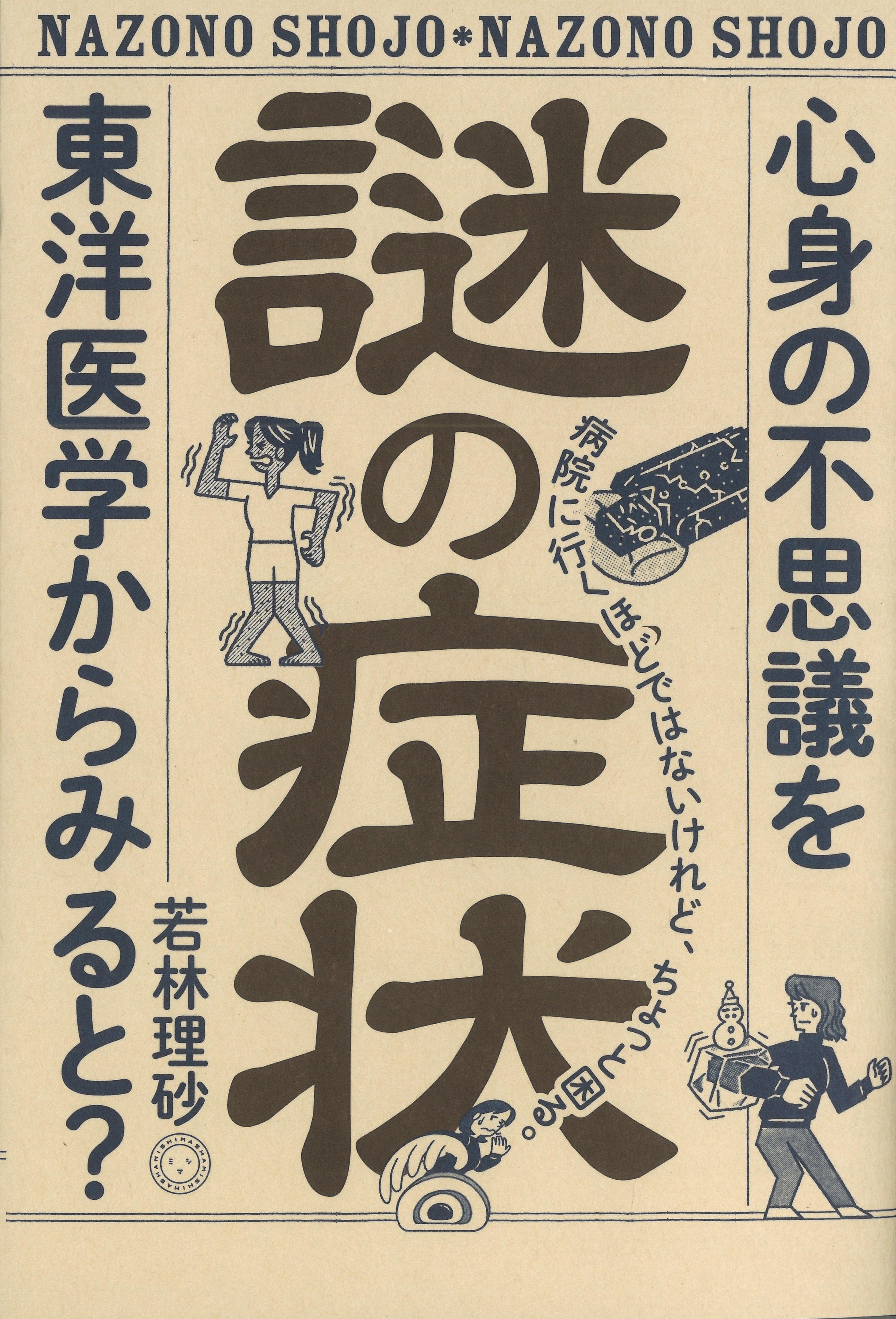

-thumb-800xauto-15055.png)



