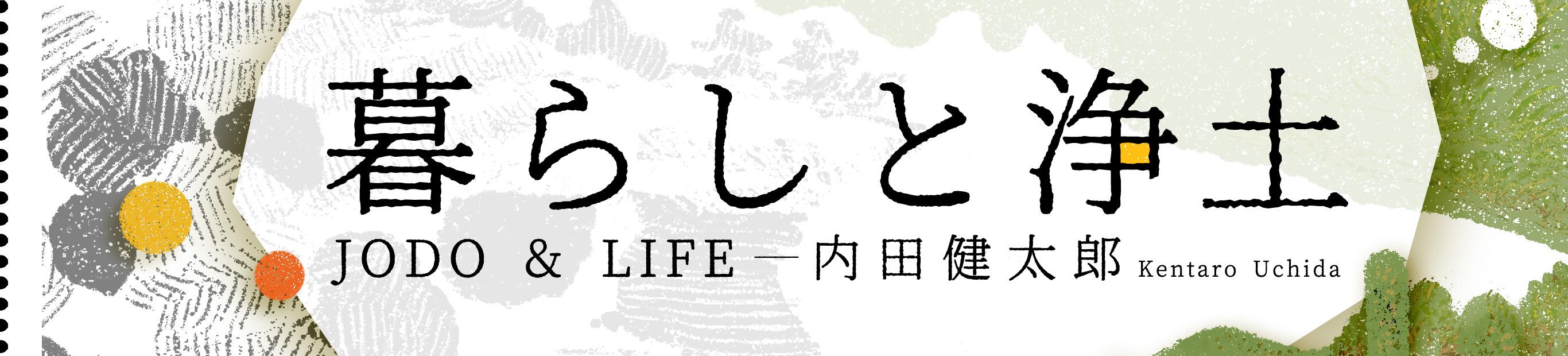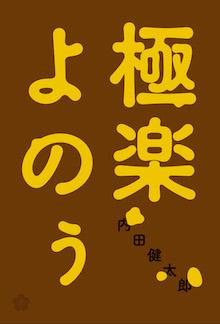第1回
マザーテレサと仏の手
2021.07.28更新
内田健太郎さんによる連載「暮らしと浄土 JODO&LIFE」がはじまります。内田さんは、東日本大震災をきっかけに関東から周防大島に移住。養蜂家として「瀬戸内タカノスファーム」を主宰しながら、執筆や映像制作の活動をされています。「暮らしと浄土 JODO&LIFE」は、これまでミシマ社が刊行する雑誌『ちゃぶ台』にて掲載してきたシリーズの新作を、今月より隔月掲載のペースでミシマガジン上でも発表していく連載です。内田さんによる聞き書きは、活字版と映像版があります。雑誌でもウェブでも、ぜひお楽しみください。
●「暮らしと浄土 JODO&LIFE Vol.1」活字版はこちら/映像版はこちら
●「暮らしと浄土 JODO&LIFE Vol.2」活字版はこちら/映像版はこちら
2021年3月20日、朝10時。
僕は再び小羊の家を訪れていた[1]。房野先生は1週間後の引越しに向けて準備に追われていたが、どうしてもあと少しだけ話を聞いておきたかった。
台所から出てきた房野先生はいつものように優しく迎えてくれた。引っ越しに際して最も気がかりだったという、持っていくことのできないものたち。食器や家具や、本や、ピアノに至るまで、そのほとんどが誰かにもらってもらえた、何も捨てないですんだと、安心した笑顔で話してくれた。その話し方から、房野先生が簡単にものを捨てるような人でないこと、なるべくものを持たずに暮らしたいという人柄が滲んでいた。
先生は奥の部屋へ案内してくれた。先生の家族である三匹の愛猫が暮らす部屋。かつて小学校だったという建物の面影はそこにも残っていて、部屋の入り口には「工作室」と書かれた木札が貼ったままになっている。台所からその部屋へ案内してくれる途中、壁に残された一枚の女性の写真に気がついた。
マザーテレサだ。
その写真の前を先生が横切るその瞬間まで、僕は全く気づいていなかったが、二人はとてもよく似ていた。頭の上にある布の巻き方まで同じように見えた。
三匹の猫の中の1匹、すなわち二匹の親である老猫は耳に癌を患っていた。耳の内側に大きな腫瘍となって赤くなっている様は痛々しくもあった。その猫の耳の血を拭いながら先生は、子供の頃に見たという忘れられない紙芝居について話してくれた。
今でも忘れないあの紙芝居の場面。
お釈迦さんの大きな顔と、その横に小さな孫悟空。
「お前はそんだけ威張ってるけど、この私の手の中から出られるか?」
「そーんなもん、筋斗雲に乗ってひとっ飛びじゃ。」
で、地の果てと思しきところへ来たら、柱が3本立ってた。
子供向きの紙芝居やからちょっと笑わせるんよね。
「孫悟空、地の果てへ来たる」と書いて、その柱におしっこをかけました。三本の柱の下にチョロチョロっとおしっこがかかった。
「お釈迦さん地の果てへ行ってきたぞー」って孫悟空が言うと、そしたらお釈迦さんがこうして手を見せて、「お前はここへ行ってきたんだろ?」って。
あの紙芝居で、孫悟空がギャフーンと尻もちついてる場面、ほんと今でも忘れない。
あの当時なんでも怖かった。自分の影まで怖かった。なんでも怖かったけど、はあー何にも心配せんでも、私を受けてる手があるんや。
なんにも心配せんでも、うち一生懸命に生きても、この私を受けてる手があるから、どこへも落ちいひん。どこへも落ちない。そう思うたのありゃ忘れられん。ものすごい安心した、だからいまだにあの紙芝居の場面も忘れない。
ほいでそれからしんどいまま大人になって、とにかく背中が大きな荷物を背負わされてるように重かった。
「お母ちゃん、背中から眠たい」って言ったら、母が変な顔してたけど、しんどいっていう表現の仕方がわからんから、背中から眠たいっていうたんよ。
そうやなあ。学校休んで寝てたり、しんどいことが当たり前のような生活で。宗教巡り始めた。明日死んでもええものを信じたい。思うてたけど、18の時に、うーん、本当に探しくたびれた。行けるだけの宗教、全部行ったけど、最高の死に方を教えてくれる宗教がない。
ほいで泣きながら歩いてたんよ。で、空に向かって大きな声で、
「もう探しくたびれた! でもどっかに本当の神様おるんでしょ! あなたが私を捕まえててください」
うーん、言うて得したっていう感じやけど。言うてよかった。そのこときっかけから聖書研究っていうものに参加し始めて、18から始めて、21の時にもう納得して。よっしゃ。この方に命預けたら、明日死んでもええ。思うて洗礼受けて。
・・・生きてるねえ。まだ。
21のイースターに洗礼受けて、今年もうすぐイースターやから・・56年? はあー56年! ふーん、明日死んでもええはずが56年。そして新しい出発をするんよねえ。新しい出発に付き合うてくれるん、君が?
子供に話すように、猫に優しく語りかける房野先生。猫の耳にある腫瘍の血を丁寧に何度も拭ってやる。
なあ? 一緒に行こうね。途中しんどいけど、頑張れよ。
ねー。よくなりますように。助かってやー。助かってやー、うん、キレイキレイしよう。目も綺麗にしとこう。男前やなあ。
***
ーー都会での暮らしと比べて周防大島での暮らしはどうだったんでしょう?
都会の人とはずいぶん違う。うん、この大島の人が、気候もええし、種まいときゃ育ってくれる。草引いときゃ育ってくれる。そういう恵まれた環境が、この土地の人を穏やかにしてるのかもしれんけど、うーんやっぱりよそと違うのは、「死」っていうものと一つになって生きてるような気がするね。この辺の人はみんな庭に花植えてる。なんするためか言うたら、お墓へ毎日持っていくため。毎日の墓参りが当たり前というか。
で、誰かが認知症になってきた。
「うん、みないく道よ」って言って、それを包む。
「誰々がボケたんとよ」て言いながら「うん、わしらも行く道よ」いうて、それを包んでいく。
・・・確かに違うね。よその土地の人と。
だから、ここから出んならんって、なあ、私も歳いったからいうので、終活コースに入るけど、ここから出たくないねえ。うーん大島が最高にええなあ。
けどま、まだこうやって体が動くうちに大島を出たら、京都、大阪で手を受けて待ってる人がもういるしね。
妹に、帰るからねーって電話したら、「心変わりせんで帰ってきてや」って言うしなあ(笑)
だからまだこうして、体が動く間に、終活コースのスタートを切ったら・・・また何か楽しいことがあるやろうと思うて行きます。けどね、けど、都会が嫌で、ここへこうして逃げ出してきて、この景色なのか、大島の空気なのか、それともこの広―い範囲(家)で住ましてもらって、24年間。・・・都会で経験したことのない人間関係が、確かに24年間で私を変えた。本当に変えてくれた。
細かい人間関係がないからその間、心を養うように聖書を読む。祈る。一人でするのは信仰でしょ。社会的な宗教活動とは違う、信仰生活がここで24年間。
受け入れて入ってくる人。こういう出会う生き物たち。みんなこの、あのお釈迦さんの手の中で暴れまわっては大人しくなり、暴れまわっては参ったって言う孫悟空と、ひとっつも変わらん。いまだにひとっつも変わらん。
だって出会う人出会う人出会う人出会う人がみーんなこの手の上におるんやもんね。
歳いった患者さんが「如来様にお願いしよ」って言うけど、私が「イエス様」っていうて、イエス様の懐ん中に入って生きてるような生き方と、おんなじかもしれん。おんなじかもしれん。行き先が違うのかどうか知らんけどね(笑)
キリストは上からきて、一旦地上に降りて、人とおんなじ生き方をして、天というのはね、天国というのはねって話してくれた。
お釈迦さんも、霊的な、天的なものを持って王子として生まれた。そいで地上の苦しみ、生老病死を全部悩んで悩んで悩んで悩んで、「この地上のこと、苦しいことがいーっぱいある、けどなあ、その先があるで」ってお釈迦さんが言ってくれた。
だからちょうど、上からこういう風にして降りてきた漏斗と、下から漏斗をひっくり返してこうなって、なーんかお釈迦さんとキリストさんはこうして、漏斗の口と口とが繋がって、こう広がっていくような気がするんよ。キリストさんの漏斗と、お釈迦さんの漏斗が繋がってるような気がする。うーんだから、歳いくほどに、キリスト教でなければいかん、仏教でなければいかん、私たちは仏教者だから、我々はキリスト教だから。昔は派の違うもの同士戦争したりしたけど、そーんなはずない、そんなはずない。
どこへもお賽銭持って行かんでいい。どこへも願掛けに行かんでいい。
こんなん言うたら困る宗教もできるけどなあ(笑)
でも、その場で、お風呂の中やろうが、トイレの中やろうが、寝床の中やろうが、その場で、一番広い世界に向かって、「なんとかしてください」。(祈れば)必ず聞かれるもんね。
私が一人で祈ってたのは、「世界中の軍需産業の動きを止めてください。兵器の動きを止めてください。」
武器があるから難民が生まれる。なあ?
そうでないと、本当の浄土、本当の神の国・・・・・・死んでからいくところじゃないと思うよ。
***
2021年3月27日。朝、7時。
新しい出発の日。
僕がカメラを携え、小羊の家に伺った時には、すでに多くの人が動き回っていた。2トントラックの荷台が次々に荷物で一杯になっていく。乗り切らない荷物の、優先順位を房野先生が相談している。手伝いだけでも若者から年寄りまで10名くらいだろうか。その他にも別れを惜しみにくる人。少しでも何か手伝いたいという人、猫にお別れを言いにくる人。早朝にも関わらず、次々と近所の人たちが訪ねてくる。そこに立っているだけで、房野先生が本当に慕われている人であること、そして、小羊の家が多くの人にとってとても大切な場所であったんだということが感じられた。ついこの前は、ベッドの上で横になっている患者さんが何人もいて、一日中終わらない会話がそこにはあった。24年という歳月がまるで嘘のように、治療室の中に今はもう何もない。残されたのは向日葵の絵や、古びた椅子、それに先生がいつも丁寧に手を洗っていた水道の蛇口からポタポタと落ちていく水滴だけだ。
いつも以上に元気な声で最後の出発の準備をしている房野先生。多くの友人や、先生を慕う人たちに囲まれて、今、最後の歌が歌われようとしていた。集まった皆の手元には讃美歌の歌詞が印刷された紙。普段教会で、演奏されているという房野先生の友人によるピアノ伴奏とともに歌が始まった。
涙を堪えるようにして歌う房野先生の横顔を見ていると、本当にこれが小羊の家の最後なんだと、胸が苦しくなった。
歌の途中、先生は集まってくれた人たちの方へ歩き出した。そして一人一人に声をかけていった。
「この娘はちょっとやんちゃなとこがあるけど、根はいい子なんだから仲良うするんやで」涙ぐむおばあちゃんとその娘らしき人、二人を抱きしめて祈る房野先生。
「どうかこの親子二人に平安がありますように、仲良くできますように。」
入り口のところに近所の青年が駆けつけてきた。介護の事業を始めたばかりの若者だ。彼を抱きしめ、おでこにピッタリと自分のおでこをつけて目をつぶる房野先生。
「どうかこの事業がうまくいきますように。どうか多くの人の助けとなりますように。」
力強く、そしてとてもはっきりとした声で神様と青年に語りかける房野先生。
青年の横には杖を持って立つ老婆の姿。よしこさんだ[2]。90歳を過ぎたよしこさんは先生の一番の仲良しの友人だ。先生とよしこさんは長い間、体を寄せ合っていた。ピアノの音色が室内を包んでいる。二人の目からは涙が溢れていた。
「音痴でごめんね」
そう言って先生は笑った。そして讃美歌の続きを歌い出した。
「また会う日まで また会う日まで かみのまもり 汝が身を 離れざれ」
[1]小羊の家と呼ばれる鍼灸の診療所とそこを営む房野郁子さんについては、『ちゃぶ台7』収録の「向日葵の道」にてご紹介しています。
[2]よしこさんについても、『ちゃぶ台7』収録の「向日葵の道」にてご紹介しています。