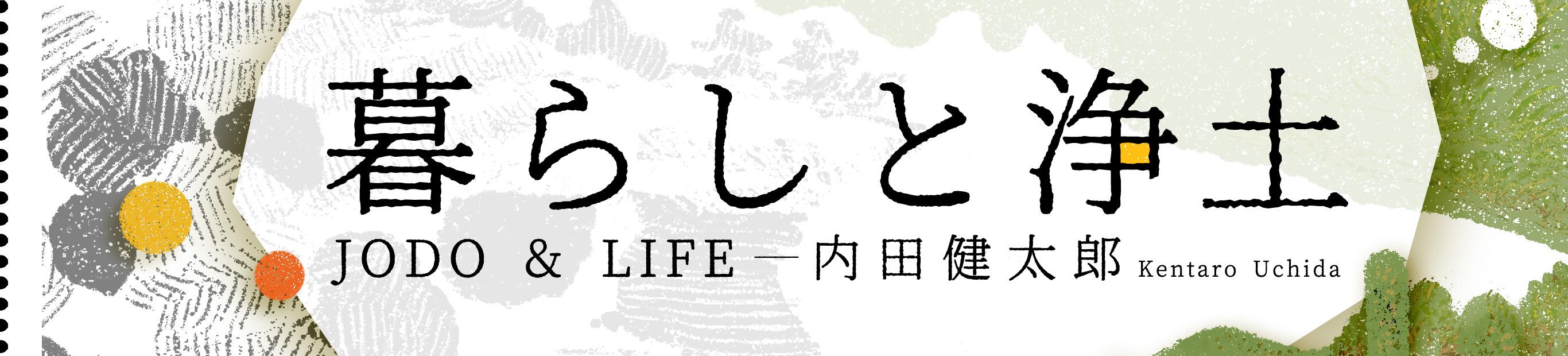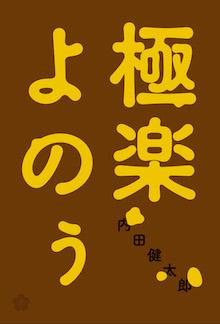第9回
生きている瞬間(1)
2022.07.03更新
砂を集める姿が美しかった。
誰もいない浜辺で静かに砂を集めている、彼のその手がなぜかとても美しいものに見えた。
彼は一人しゃがみ込み、傍に置いたカゴへ黙々と砂を移していく。
僕は少し離れたところから彼を見ていた。
この時彼が一体何のために砂を集めているのか、僕にはさっぱり見当がついていなかったが、彼の慣れた手つき、迷いのないその動作が、今までに何度もこうして砂を集めてきたことを思わせた。
彼の名前は末弘隆太。
周防大島に暮らす親しい友人だ。
僕らが初めて出会った時、彼は町立病院で理学療法士をしていた。
だが3年ほど前に、世間からみれば安泰なこの仕事を、周囲の反対を押し切って彼は捨てた。
そして今の仕事である「ねっと」を起業した。
訪問介護や介護タクシーと呼ばれる、いわばお年寄りのお助けマンだ。
その日によって本当に仕事はさまざまだという。買い物や料理、庭仕事に、畑仕事、病院への付き添いや、時にはみかんの収穫、田植えまであるそうだ。
全くのゼロからのスタートだったが、彼の温厚な人柄、その丁寧な仕事ぶりに、多くの人が信頼を寄せ、今や引く手数多で大忙しの毎日を過ごしている。
そしてこの日はお墓参りへ一緒に行く日だという。
彼が開業した時からの利用者であるという大田さん(96)からの依頼だ。
彼が一体どんな仕事をしているのか、以前から興味があった僕はこの日初めて同行させてもらうことになった。
「潮が引いていて助かったよ、ここは満潮だと浜がなくなっちゃうから」
砂を集め終えた末弘くんはカゴを抱えて立ち上がり、大田さんが待つ車へと歩き出した。
なぜ墓参りに砂を?
僕は後ろからついて行くだけだったが、依然として状況が飲み込めていなかった。
大田さんは一人暮らしの女性だ。
娘さんが2人いるが、それぞれ家庭を持ち島の外で暮らしている。
教員をされていたご主人は若くして病気で亡くなったそうだ。21の時に結婚をして、27の時にご主人を亡くしてからおよそ70年。今まで一体何度大田さんがお墓参りに来たのかを僕には知る術はないが、一人で自由に歩くことができなくなった今でも毎月欠かすことなく訪れているという。
「着きましたよー」
車が墓地へと到着し、まず末弘くんが降りた。彼は素早く踏み台を用意して、大田さんの扉を開けると、その足元へと置いた。
末弘くんの手を借りながら車を降り、一歩ずつ、ゆっくりと墓地へと歩みを進めていく大田さん。
***
ーー末弘くんに依頼してくる人ってなんて呼べばいいの? お客さん?
難しいよね、これはいつも迷う。
お客さんっていう感覚もちょっと違うし、よく介護系の事業者とかは利用者さんって呼び方する。病院にいるときは患者さん。病院から地域に出て、介護施設とかに入ったりデイサービス使ったりするときは、利用者さんってみんな呼んでる。
・・・けど、うーん、なんかどっちも違和感がある。ていう感じかな。大田さんは大田さんなんよね。利用者さん、確かに利用してる者なんだけど、でも、僕の中ではちょっと違和感がある。だからこう・・家族と業者さん、そのなんか、グラデーションの中のどっかに僕がいる。
だからそれは利用者さんによって、どこまで近いかは本当に人それぞれ。利用者さんによって完全に事業者としての対応の人もいるし、そうじゃない、すごい家族に近くなってる人もいる。大田さんはけっこう家族に近いかもしれない。だからお墓参りとか行くときに、なんていうか、自分の家族の墓を掃除するぐらいの感覚ではいる気がするね。
病院に勤めてたときは、患者さんが亡くなったときに後輩が泣いちゃうみたいなことがあって、そういうときは、プロなんだからあんまり深入りしすぎず、冷静にご家族と接することが必要だよ、みたいなことをずっと後輩に言ってたんだけど、言ってた僕が今、どっちかっていうと家族よりに入っちゃってる。
利用者さんが亡くなったときとか、泣いちゃうんだよね。泣くし、喪失感がすごい。だからけっこうダメージはある気がする。
ここまで入り込みすぎちゃうのが、プロとしてあんまりよくないんだなあと思うんだけど、そうじゃない関わりをしてるから、普段こう、共有してる時間が良くなってる部分もある。いいのか悪いのかは、そういう判断はできないけど、今後も多分このスタンスではいくと思う。それは多分崩さないと思う。
ーー利用者さんが亡くなったときの話、もう少し聞かせてもらっていい?
この前、どっぷり家族寄りっていう人が亡くなったんよね。
笑っちゃいけないけど、ご家族のほうが亡くなったとき冷静で、僕のほうが取り乱して(笑)
お悔やみ行ったときに、僕だけ泣いて。そのときもすごいショックだった。ショックだったし、あれやってあげればよかった、これやってあげればよかった、ってやり残したことがすごい頭に浮かんできて。
・・・苺が食べたいって言ってた。最後のスーパーに行ったときに、苺がなくて、何か別の果物で、りんごだったかな。これで今日は我慢しようみたいな感じになったんだけど、いや買いにちょっと走ればね、行けたんじゃないかなとか、思ったりして。
あとは、ちょっと認知症があるような方だったから、あまり新しいことを覚えてられない。けど、昔の話はよくしてくれて。娘さんが小さいときの話とか、たまにしてくれてた。
娘さんが小さいときに、お風呂を炊く当番をさぼって遊んじゃって、それに責任感を感じて、家に帰ってこなかった事件があったらしくて。それで集落中大騒ぎになって、みんなでその子を探しに行ったんだって。
そんときにようやっと見つかって、やっぱり責任感、自分が任された仕事やれなくて遊んじゃった責任感で泣いてたとか。
そのおばあちゃんが子供に対して、こんなちっちゃい子にそういう責任を持たせてしまってすごい申し訳ないって、そのとき思って涙が出てきたっていう話をずっと聞いてたんだけど、これ何か、すごいこと聞いちゃってるなあと思って。
すごい大事な話を僕が、家族じゃない僕が聞いちゃってるから、これ伝えなきゃと思って。お悔やみのときに、初めてその娘さんと会ったんだけど、こういうことをおっしゃってましたよって言ったら、そんな話聞いたことなかった、そんなこと思ってたんだって・・・言ってくれたりして。
なんか本当にその・・・家族寄りだよね。
やっぱり聞く話とかも、すごい大事な話を聞いてることがあるから、伝えなきゃっていうのも思うし、だから、よけいね、亡くなったときはすごい悲しい。
ーー病院時代とは違う?
全然違う。違うね。病院時代はね、すごいロジカルに、考えちゃうから。理学療法士として、もうちょっとこういうアプローチができたんじゃないか、こういう治療ができたんじゃないか。本当は家に帰せたんじゃないかとか。そういう論理的に反省点みたいな感じで思い浮かぶ。
もちろん人と人だから、やっぱり悲しいとか、びっくりするとかっていうのはあるんだけど、今のこの「ねっと」の仕事をやっているときほど、喪失感とか、感情の入り方とかっていうのは無かったと思う。どっちかっていうと冷静に冷静に、取り乱さないようにとか考えていたんじゃないかなあ。
ーー後輩に指導してたように、末弘君も割り切ってやれてた?
割り切らないと仕事にならなくなっちゃう。亡くなる人の数も多い。病院の方が関わる人が多いから、やっぱりどんどん亡くなる。病院の中で。その数に・・数だよねやっぱり。
その数っていう感覚になるんだけど、亡くなる人たちの数だけ、ダメージを受けたら、明日からの仕事ができなくなっちゃう。だから後輩も泣いてしまって仕事が手につかない。で、午後からお休みとか。そうなったらそれはもう、プロとしての仕事ができてないでしょうっていうことになる。
だからそういう指導してたと思う。
でも・・・今それをやったとしても、今その感覚で関わったとしたら、あんまり誰も喜ばない気がする。僕もそういう、ちょっと冷たいような関わりっていうのかな。そういうことをしないことで、日々、得られるものがある。ものすごい喜んでくれたりとか・・・喜ぶっていうかは、なんて言うのかね。寄り添う。寄り添うも違うね。・・・暮らしを大事にする。違うね。・・・あ。生きててよかったと思う瞬間が作れるかどうか。これはやっぱり今みたいな関わりしてるからのような気がする。
やっぱり年をとっていく、年を重ねていって、できないことが増えてくる。今まで大事にしていたことが、できない。社会からはあまり必要とされないようになってきちゃう。
それでも、ああ生きててよかったなあと思ってもらえる瞬間、を感じてもらいたい。
それは、僕が関わるその人もそうだし。家族もそう。だから・・・、だから、家なんじゃないかな。ただ、生活できていればいいんだったら、やっぱり施設の方が安全だし、家族も安心。だけど、生きててよかったなと思ってもらいやすいのは、家の方が、そう感じてもらいやすい。
僕が関わることでそう悲観せずに、生きててよかったと思って、ずっと家で暮らしてほしい。
そのためには、やっぱり深い関わりをしなきゃいけない。するのが必要だし、そうしないと、達成し得ないものがあると思うし、それで生きててよかったと思ってもらえるってことが、僕としては一番嬉しいし、やりがいを感じられる瞬間。そういう本人を見て、家族も喜んでもらいたいなと思う。
だから、まあタクシーも、介護保険使わない介護っていうのも、本当に手段で。
実現したいのは、そういう瞬間を作っていくってこと。
・・・じゃないかなって今思いついた。