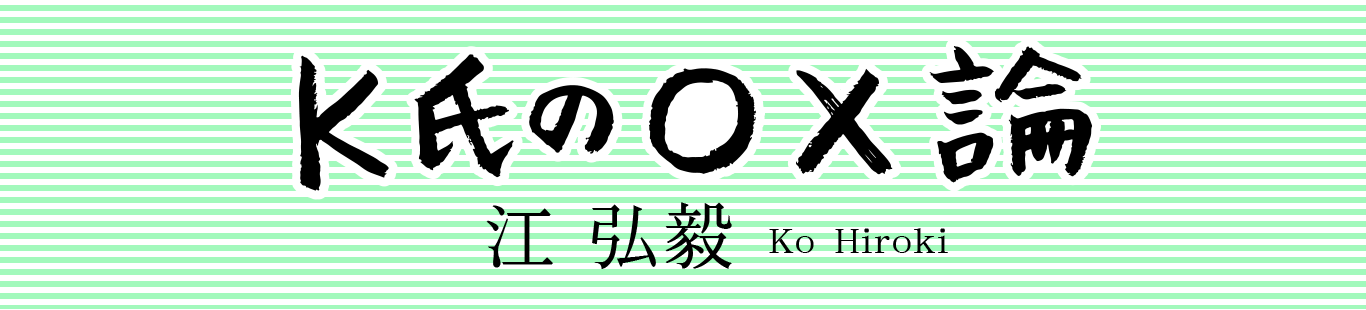第1回
スポーツ界のスターたちが吐く、大阪弁のブンガク性
2018.04.24更新
「大阪弁を喋るから大阪人であって、ものの感じ方や見方も、人と人のいろんな関係性の上に成り立つコミュニケーションのありようも、これ全部、大阪弁がベースやねんな」
常々そう主張するK氏であるが、一昔前の大阪弁話者の野球スター選手に大阪人の人間としての「典型」を見ることがある。これは分かる人には分かりすぎるが、それはイチローではなくて江夏豊や福本豊である、ということだ。清原和博もある意味、典型である。
かれらの発する大阪弁による言葉のクオリティには凄いものがある。
福本豊が83年にルー・ブロックが持っていた盗塁の世界記録(メジャーリーグ記録)を抜いた。ときの首相だった中曽根康弘は福本に国民栄誉賞を打診する。福本は固辞するのだが、その時の理由はこうだ。
「そんなん貰ろてしもたら、立ちションベンも出来んようになるがな」
その後、福本豊は松井秀喜が国民栄誉賞に輝いた際、週刊ポスト(13年4月19日号)にこうコメントしている。
「松下電器の人を通じて、政府が国民栄誉賞を考えてるって聞いたから、『立ちションベンもできんようになるがな』っていいましたわ。ボクはあの頃、酔っぱらったら(立ちション)してたからね。国民の手本にはならへん、無理や、ということで断わりました」
その裏には、他の軽い気持ちから出た言葉とは違う、賞に対する真摯な思いがあった。
「王さんが世界記録を作ったことで創設されたのが第1号。ボクも世界記録やからということでしたが、ボクには王さんのように野球人の手本になれる自信がなかった。野球で記録を作るだけでなく、広く国民に敬愛されるような人物でないといけないという、当時のボクなりの解釈があったんです。
その後、数多くの受賞者が出た今も、その思いは変わっていないという。
「ボクは、麻雀はするし、タバコも吸うし、悪いことばかりしてましたから。受賞してたら、ちょっとしたことでも、ああだこうだいわれたり書かれたりするでしょう。他の受賞者にも迷惑がかかるから、やっぱりもらわんで良かったです」
子どもの頃から地元南海ホークスに親しんできたパ・リーグ派のファンだったK氏は、その福本豊ほかを育て上げて阪急ブレーブスの黄金時代を築き、その後近鉄バッファローズに移り優勝に導く西本幸雄監督を書いた『パリーグを生きた男 悲運の闘将 西本幸雄』(ぴあ)にもう一人の大阪人≒関西人(和歌山市出身)の典型を見る。
 『パリーグを生きた男 悲運の闘将 西本幸雄』(ぴあ)
『パリーグを生きた男 悲運の闘将 西本幸雄』(ぴあ)
「この名監督は、とてつもなく人格が素晴らしいんや。それがいろんな場面の台詞に現れてる。近鉄に移ってきた時にエースの『草魂』のやでぇ、鈴木啓示にいきなりこう言うんや。ここや」と開いたページはP.123である。
西本監督がリーグ優勝に導いた阪急ブレーブスから近鉄バファローズに移ってきて言った言葉である。
「スズ、お前は20勝しとってもつまらんピッチャーやなあ。同じ20勝するんでも負け数をひとケタにせんと、ほんまもんのエースとは呼ばれへんぞ」
当然鈴木は「このオッサン、何考えとんねんと思う。「『オッサン、このチームでずっと勝ってきた俺にケチつけたな』『あんたにピッチングの何がわかるんや』と(略)プライドが、今考えたらわがままなプライドなんですが、それがあって許せんわけです。あんたみんなの前で恥をかかせたな、と」
「西本さんは『トレードしてくれ』とまで言う鈴木を見事に成長させる。鈴木に自分のこととチームのことを思う熱意が伝わるんや。力任せの直球主体の投球を改めさせ25勝させるんや。鈴木以後、25勝したピッチャーはおらんで。ひと皮剥かせたんやなあ」とK氏は熱弁する。
「ところがその年に西本さんの監督としての古巣の阪急ブレーブスとの優勝を賭けた最終戦の『藤井寺決戦』で阪急の同じエースの山田久志と投げ合いになるんやが、鈴木は8回に力尽きて打たれてしまうんや。その時に、鈴木にどう言うたか。『スズ、ご苦労さんやった』とだけ言うたんや」
翌年、近鉄は悲願のリーグ優勝するのだが、山場である阪急との一戦に鈴木は完封勝ちする。「どないやこないや言うても、やっぱり鈴木は日本一のピッチャーや」と初めて賛辞を送る。
「その後、鈴木は84年にやっとこさで300勝を達成する。それで西本さんは『これでほっとしたらあかんぞ』と鈴木の両手を握って言うんや。翌シーズンがこれまた大変で、むちゃくちゃ打たれた鈴木は引退を決めるんやけど、それを見透かした西本さんは『おおスズ、お前の目はもう死んどるわ。長い間、ご苦労さんやった』と言うんや」
鈴木引退の報を聞いた阪急の上田監督は、その年自分が全パ監督として率いるオールスター戦で、引退の花道にと鈴木に出場を持ちかける。舞台は近鉄の本拠地である藤井寺球場だ。
その申し出を鈴木は辞退する。「『パリーグの選手皆で胴上げしたるから出てくれ』と言われたが、有り難い話やったけど、歴史のあるオールスターを俺一人の舞台にしたらアカンと思って断った」と言った。
「福本も鈴木もそういうとこを西本さんの教える野球を通じて学んだんや。この本での西本さんを取り巻くかれらの大阪〜関西野球人の大阪弁表現の連発がホンマにエエ。『感動をありがとう』とかと次元が違うんやな」
三振を奪うことこそが使命だと思っていた不世出の大投手、江夏豊については、ブレーンセンター刊の「後藤正治ノンフィクション集第6巻『牙/不屈者』」のなかの『牙 江夏豊とその時代』を「江夏豊本の最高傑作や」とK氏は挙げる。
「京都生まれ大阪育ちの後藤正治さんは、デッドボールのほとんどない江夏のことを
投球術において老練な技を駆使したけれども、ダーティーな手段を弄したことはまったくない。江夏という投手のもう一つの側面である
と書かはる。一方、巨人は心臓疾患に悩んでた江夏さんに待玉やらバントやら連発して、策を選ばず向かうんや。イヤな野郎だなあ(ここだけ東京弁)」
K氏の巨人嫌いは阪神ファンのそれとはちょっと違うが、「けれども巨人のそういうやり口を『汚い』と思ったことはない」と江夏から聞いて台詞を記した後藤正治と同質的な大阪的感性ゆえのことだ。
73年のペナントレース残り2試合、勝てば「阪神優勝」という中日戦の前日、江夏は球団事務所に呼ばれる。球団幹部に「カネがかかるから優勝などしてくれんでいい。このことは監督も承知していることだ」と言われ、思わずテーブルをひっくり返して席を立ったという。
「この話は事実かどうか確かめるすべがない」と後藤は書くが、何ともキツい話だ。
「江夏とイッたら清原もイカなあかんわなあ。どっちもああいうふうにシャブに行ってもたけど、『清原和博番長伝説』(講談社)はエエと思う。24年間例の『おお、ワイや』の清原節で『FRIDAY』が追いかけた担当編集者との絶妙な距離感が絶品や。途中で担当の異動があるんやけど、『傷つきやすく涙もろい、繊細な人間味あふれる素顔』こそが男前や、と書くんやなあ」

『清原和博番長伝説』(講談社)
さすが編集者K氏の読み方である。加えて清原の言葉を以下のように書いた編集者の力量を誉める。
20代はもうガーッと勢いだけで来たけど、30代で故障やいろんな挫折を何度も味わって、やっぱりオレも人間や。ドツかれすぎたら卑屈になったり、おかしなったりするよ。それを何とか自分で克服するためにね、身体を鍛えたり、オリャーって言うてみたりね、もう自分を守るのにそれで必死やったよ(P.24)
「『ガーッ』とか『オリャー』とかのオノマトペやら『ドツく』とか、編集者担当者もこれまた完全に大阪弁話者やとわかるやろ。この本はまえがきと、この第一章インタビューだけでも一冊の値打ちがある」というK氏は清原と同じ岸和田育ちであり、実家にはK氏の母親が、後に「あんたがタトゥー入れるんやったら、わたし死ぬ」と言った清原のお母さんを通じて貰ってきた、西武のルーキー時代のサインがある。
話は清原に行ったが、K氏がスポーツ界でいちばん大阪人的に「最高におもろいんや、この監督の言い方」とことあるたびに名前を挙げるのはシンクロナイズドスイミングの井村雅代さんだ。繰り返すまでもないがその「おもろい」は、お笑い的におもろいということでは全くない。先の後藤正治の『不屈者』の第1章は井村雅代で、後藤は井村の本質は「大阪人」だと書いている。
K氏は井村さんと一度だけお会いしたことがある。
「とある大新聞社が主催の南海電鉄沿線フォーラム『はじまりは堺から』でご一緒にパネルディスカッションに出たんや。07年やった」
パネルディスカッションが始まると、井村さんが浜寺(堺市)の水練学校に室内プールがない時代、シンクロが「身黒」と表現されていた、という駄ジャレで笑いを取った。「あんたはブスやから、ブスッとせんと、もっとかわいらしい顔しなさい」という例の調子だった。
そして井村さんはフォーラムが終わるやいなや、お茶も飲まずに「お先にしつれいします」と黄色のミニクーパーをかっ飛ばして帰られた。「『ほな、さいなら』ちゅう感じでぴゅーと行くんや。この人らしいなと思た。で、井村さん以外のわたしらは送迎のタクシーやった(笑)」。
K氏が挙げる井村さんの著書は『愛があるなら叱りなさい』(幻冬舎文庫)である。
え、K氏、そんなん読むんかいな? というのはこの本を未だ読んでいないゆえのことだ。
井村さんの指導力は強烈である。内田樹さんはじめ東京在住の柴崎友香さんまでがトーク・ゲストに呼ばれた大阪の谷町六丁目の街の書店「隆祥館」の店主・二村知子さんは、「AERA」の「現代の肖像」にも登場しているが、70年代半ばシンクロをやっていて元日本代表だが、コーチは誰あろう井村さんだった。二村さんは一度、練習の時に「もう限界です」と井村さんに言ったことがある。井村さんは「限界かどうかはあんたが決めることじゃない。わたしが決める」と言った。
「ほんまコワかったです。親よりもコワかったです。今でもコワいです(笑)」と二村さんがこれまた大阪的に話す。もちろん「コワい」は「怖い」の単なるパワー的恐怖ではなく、畏敬を含んでいる。
井村さんの指導力は強烈である。「この人の教育はいつもカラダを張っているんや」とK氏が言う。
つねに目一杯やっているから、「文句があるんやったら、いつでも来い」
と構えていることができます。
指導者たるもの、そうあるべきではないでしょうか。(P.172)
という姿勢である。保健体育教員として勤めていた大阪市内の中学校には、教師に向かって「殺すぞ!」と脅すような、札付きのワル生徒がいた。先輩である男性の先生が井村さんに「殴られそうになったら、僕が体を張って守るから」と言う。とはいえ彼らを前にすると、いくら井村さんでも本当に怖い。けれども「やる」と決心したところ、校長はこう言った。
「きみらの気持ちはありがたいが、殴るんやったら、校長室に連れてくるんや。わしが殴るから、きみらは殴ったらあかん(P.187)
「今なら考えられへん。大阪は維新が出てから校長が君が代を唄てるか口パクチェックをする教育になってしもたが、そういう学校やったんやなあ。うちの岸和田の中学もそうやった。井村さんは大阪府教育委員をされてたんやけど、橋下知事になって辞めはった」とK氏。
そういう学校、そういう校長だったから、井村先生はワルには積極的に話しかける。
「髪の毛、どないかせい」
「そんな制服、ぶっさいくやなあ」
これはワルの生徒の言葉ではなく、井村先生の言葉である。挙げ句のはては、
「ちょっと、うるさいよ。授業をする間は静かにしてほしいから、遠慮せんと寝とき」(P.222)
である。とにかく人を「教える」「導く」際の大阪弁の言葉が凄まじい。
「喜怒哀楽を全部含んで言うてしまうところの『情』が、生徒にとっても喜怒哀楽すべてを感じ取れるんやろなあ。それから『言うてきかす』ところの『理』。『情理を尽くす』というのは正味、こういうこっちゃ」
井村さんはこの本を著した後、海を渡ってシンクロ中国代表チームの監督に就任し、北京オリンピックと続くロンドンオリンピックでメダルに導く。大阪弁の「エクリチュール」が「ラング(言語体)」のはるか頭上を超えたのだろう。
編集部からのお知らせ
リニューアル前の「みんなのミシマガジン」で連載していた、「K氏の大阪ブンガク論」が、タイトルを新たに書籍になります!
『K氏の大阪弁ブンガク論』
江弘毅(著) 2018年6月中旬刊行予定。デザインは尾原史和さん。
なぜ、大阪出身の作家は突き抜けられるのか?
町田康、西加奈子、黒川博行、川上未映子、和田竜etc. ……いま日本の文学界を牽引する、関西出身の作家たち。彼らは、自らの作品のなかに大阪弁、関西弁を使う場合もあるが、使用しない場合もある。しかし大阪弁、関西弁を使っていなくても、そこには大阪、関西の水脈が流れている。現役の作家から司馬遼太郎、山崎豊子といった国民的作家までをふりかえりながら、大阪が生んだ街のブンガクを、長年街場を見つめてきた著者独自の目線で綴る、唯一無二のブンガク論。
刊行をお楽しみに!