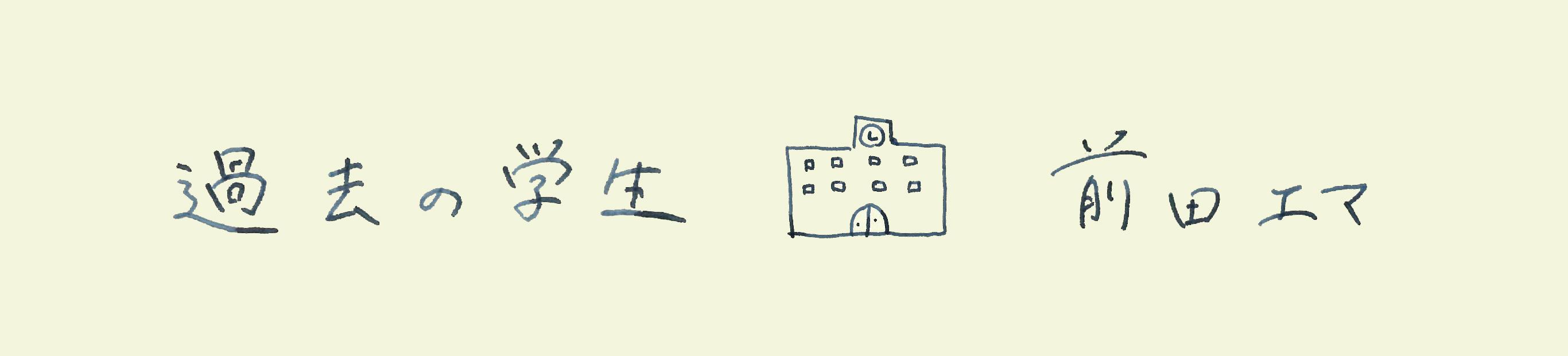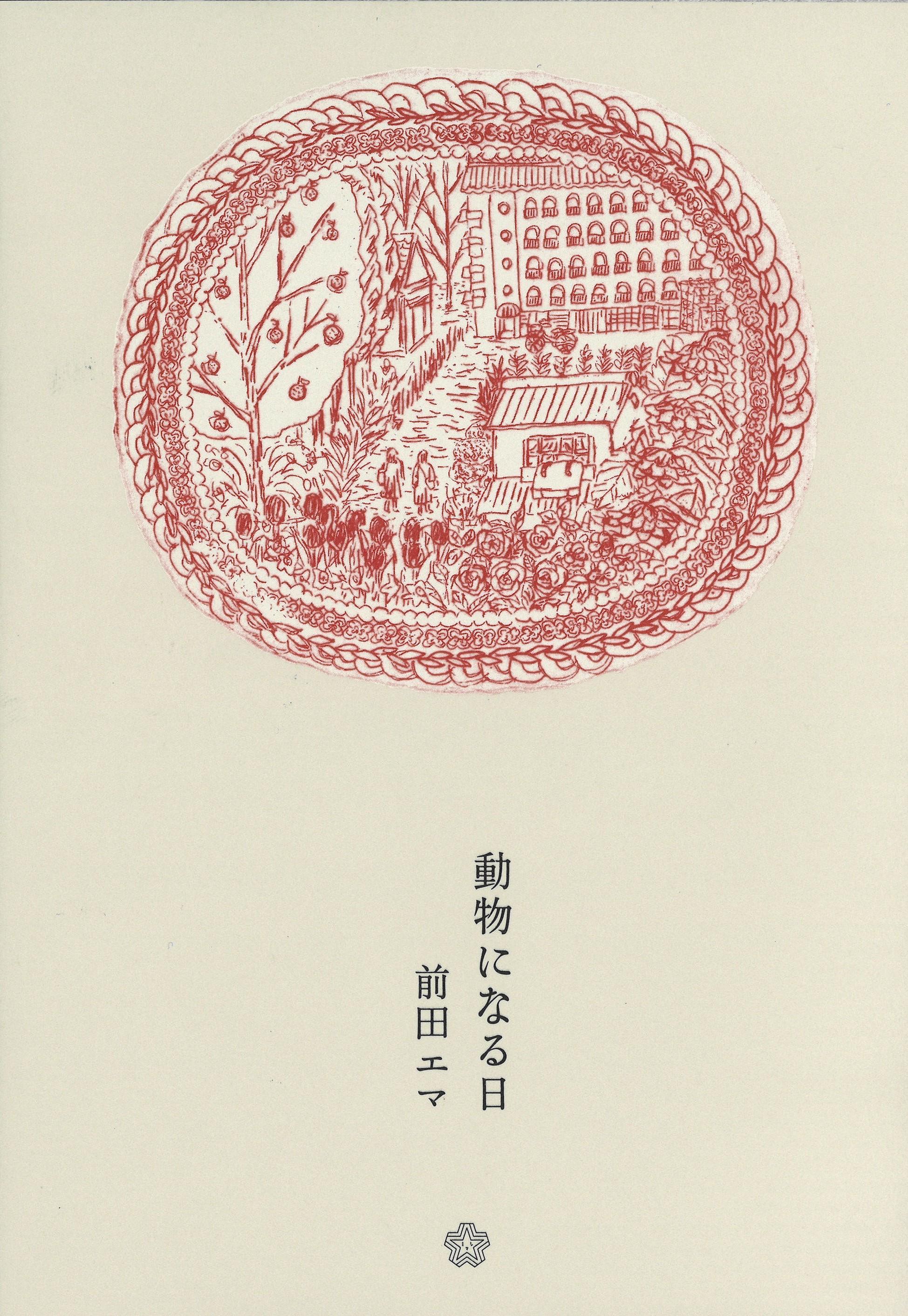第4回
太陽を消しなさい
2022.12.23更新
小学3、4年生の頃、美術の授業で絵を描いた。青空の下で、私と友人たちが遊んでいる場面を描いたと思うのだが、完成した作品を見て担任がこう言った。
「太陽はこんなに近くにないのだから、太陽を消すか、描き直すかしなさい」
私は画用紙の右上の端に太陽を描いていた。晴れ渡る水色の空に、白い雲をリズムよく点在させ、赤とオレンジを混ぜて太陽をちょこんと隅に描いた。そのほうが遊び心も出るし、画面が引き締まると思ったのだ。
先生の言葉を聞いて、びっくりした。私は幼い頃から星とか太陽とか宇宙とか、空のことに全く興味がなかったので「みんなは太陽と自分との距離を知っているのか!それを理解した上で絵を描いているのか!」と、ひとまず感心した。しかし、そんなことを絵を描くときに気にしなければならないなんて知らなかった。これは理科の授業じゃなく、美術の時間なのだから、良い絵を描けば良いのだと思っていた。
先生よりも私のほうがこの作品と何時間も真剣に向き合って大切にしてきたのに、その全てが「太陽を消す」という行為によって踏みにじられるような気がして、悲しくてたまらなかった。しかしこの頃の私はまだ、先生という存在を疑う心を持っていなかったので、太陽の部分をハサミで切り取り、水色に塗った画用紙を後ろから貼り付けた。作業をしている間、大粒の涙が画用紙にボトンボトンと落ちた。涙が絵を汚していった。しかし、画用紙にハサミを入れた時点で、私の絵はもう死んだも同然だったので、構わなかった。むしろもっと涙で絵がめちゃくちゃになって、先生が罪悪感を感じればいいと思った。私の"良い絵"を殺した犯罪者を、心の中で恨んだ。
出来上がった死んだ絵が、他のクラスメートの作品と一緒に廊下に展示された。先生に「私の絵を剥がしてほしいです。誰にも見られたくないんです」と頼んだが聞いてもらえず、一ヶ月もの間、まだなま温かい心臓がゴミ箱に入られたまま腐っていくような気持ちで過ごさなければならなかった。
小説『動物になる日』に、作文を赤ペンで添削されて怒りをあらわにする少女を描いたのは、このときの悔しさを残しておきたいと思ったからだった。
先日、弟にこの出来事を話したら、
「小学生の頃、水彩画の授業があったんだけど、鉛筆で下書きをしていたら、モノクロの方がこの絵の良さが引き立つなって思って、先生に相談したら、いいよってことになったよ。美術ってさ、本当に先生によるよね」と言っていた。
大学生の頃、小学校に上がる前の子どもたちが通う画塾で3ヶ月だけアルバイトをしたことがある。子どもの創造性を伸ばすとうたっていたので働きたいと思ったのだが、そこは"大人が理想とする子どもの描いた上手な絵"に近づけさせる塾だった。楽しそうに絵の具と戯れ、色の海へと潜っていく子どもは「ちゃんと描こうね」と注意されていた。真っ白な画用紙に線や色をのせることを、極端に怖がる子どももいた。画用紙に、自分の筆の痕跡を残した瞬間、人生の大失敗かのように「描き直す!!」と言って、何枚も何枚も、一本の線、一色の点しか描かれていない真新しい画用紙が、破棄されていくのを見た。毎週のように泣くその子を見るたびに、自ら他の子と比べてしまうこの環境にいるくらいなら、今すぐに辞めさせてあげたいと思った。
美術の時間は、いったい何のためにあるのだろう。絵を上手く描くことが本来の目的ではないと私は思う。私はたまたま絵を描くことや手を動かすことが好きで、美術の授業が得意だったけれど、そんなことははっきり言って、どうでもいいことなのではないか。大人になっても絵を描き続けたり、モノを作り続ける人なんてほんのちょっとだし、続けたい人は勝手に続ける。
アートがあってよかったなと私が心から思うのは、いろんな人がいるということを知れることだ。今までも、そして現在も、いろいろなアーティストが生きていたし生きている。彼らの作品や人生は私に「こんな価値観もあるんだ」「こんなふうに社会や時代と向き合うことができるんだ」ということを見せてくれる。それは何か困難に直面したときや、夢を抱いたとき、疲れてしまったときに、直接的ではないかもしれないけれどヒントをくれるかもしれない。すぐには役には立たないかもしれないけれど、少し心の世界が広がるかもしれない。そしてそんなことが言葉で分からずとも、アートはさまざまな体験をくれるものだし、受け取り方に正解がなくて良いものなのだ。
私はアートの楽しみ方を、もっと教えるべきだと思う。いや、教えなくたっていい。その扉を用意するだけで、子どもは何かを自ら受け取り繋げていくような気がする。学生時代の一瞬だけではなく、長くて短い人生の中で、アートと幾度となく出会う道しるべを美術の授業で教えられるのではないか。美術館や芸術祭、ギャラリーなんかが、もっと身近な遊びや学びの場のひとつになったらいいのになと願う。「美術なんて分からないから」「絵が上手じゃないから」そんな悲しい言葉が、この世界からなくなってほしい。

死んだ絵は手元に残っておらず、これは1年生の頃に描いた似たような絵です