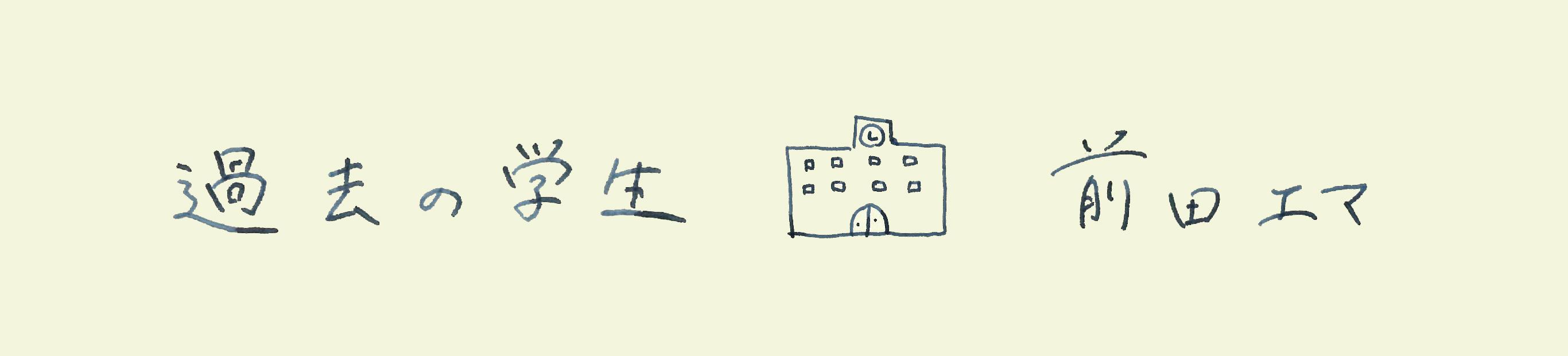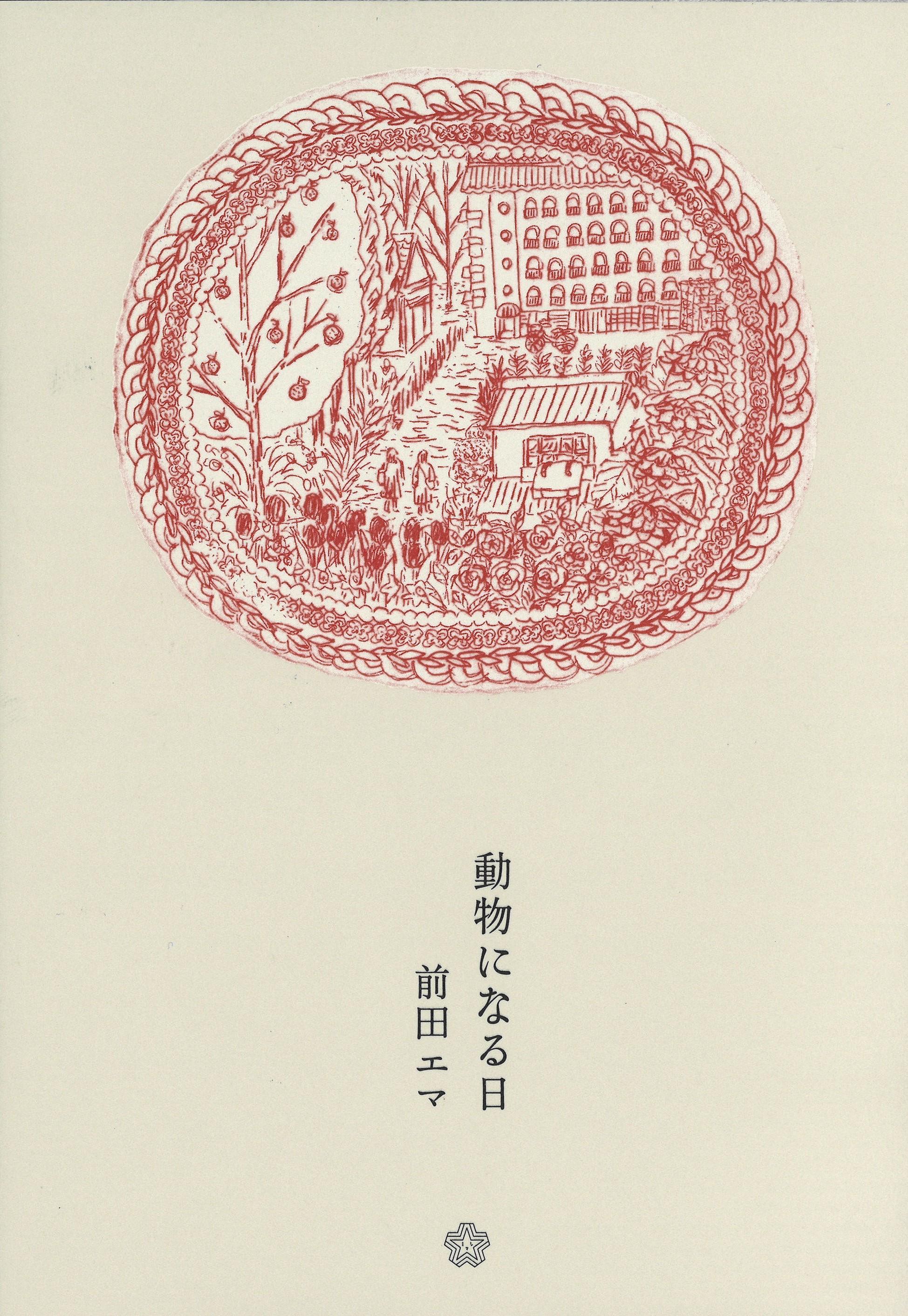第5回
魚屋の息子
2023.01.23更新
家の近所に、同級生の家族が営んでいる魚屋がある。たまに買いに行くと、心地よい明るさのお母さんが「美容室で読んだ雑誌に、エマちゃん載ってたよ〜」と声をかけてくれる。バレーボールとかハンドボールの選手だったのかな、と思うような、快活でショートカットが似合う素敵な女性だ。私は「ありがとうございます。うれしい〜」と言って、刺身の盛り合わせをお願いしたり、南蛮漬けにするアジを捌いてもらったりして、あたたかい気持ちで家に帰る。住宅街に文字通りポツンと現れる個人商店で、駅からも遠いのに週末には長蛇の列ができる。この店の次男と私は、小中学校が同じだった。
小学4年生の頃だったと思う。月に一度の全校朝礼で、詩のコンクールの受賞者が発表、表彰された。佳作だったか入賞だったか忘れたが、私の名前が呼ばれ、拍手に包まれた。優越感に浸っていると、教頭先生が「さて、この学校から最優秀賞が出ました」とうれしそうに言った。壇上に上がったのは、魚屋の次男だった。
魚屋の次男が書いた詩は、土曜の丑の日に鰻を焼く、夏の日の店の様子だった。
僕ん家は魚屋
夏になると店の前でうなぎを焼く
すると匂いにつられて お客さんがやってくる
僕も手伝う お客さんがわくわくしながら帰っていく
僕はそれを見るのがすき
詩はもっと長く、細かにいろんなことを書いてたと思うし、言葉の雰囲気などもだいぶ違うだろう。何しろ20年も前のことなのでうろ覚えだ。(魚屋の次男に対して申し訳ない)しかし、内容はそれほど大きく違わないはずだ。
その日、私は何度も自分が書いた詩と、彼が書いた詩を読み返した。
私が書いたのは、今までに読んだことのある詩の表面だけをなぞった、今考えると恥ずかしくなるような猿真似だった。しかし幼い私としては、擬音を羅列させたり、リズムを感じられるような言葉を取り入れてみたりと、みんなよりも"詩っぽい"ものを書いている自信があった。
彼の詩を読んだとき、え? これって詩なの? ただ出来事を書いただけじゃん! と思った。しかし同時に、私は完璧に負けたのだとも、最初からわかっていた。これが詩なのかどうかはわからなかったけれど、温度や匂いが、ここにはぎゅっと詰まっていて、読んでいると目の前に情景がぱーっと広がり、たのしい気持ちになった。他人と自分とを比べることにほとんど興味がなく、ヘラヘラと生きてきたけれど、私ははじめて悔しい気持ちになった。淡々と風景を描写するだけで、人の心まで手が届くのだという強さを知った体験だった。
中学生になった魚屋の次男は、女子からダントツで人気があった。野球部で寡黙。部活熱心。女子とはあまり話さないが、男子といるときはいつもたのしそうに笑っている。愛想がいいわけではないけれど、清潔感があってさわやか。とても体格がいいけれど、まだ少年らしさがちゃんと残っていて、こんがりと焼けた肌はサラサラとしていた。モテるのも納得という好青年だった。
中学時代、私たちはしょっちゅう席が隣になった。女子たちから非常に羨ましがられたけれど、私の心の中はいつも、勘弁してちょうだい! という感じだった。私は昔から、四六時中いつも誰かに話しかけているようなおしゃべりな人間だったので、授業の合間の少しの時間も、昼食中も、掃除の時間も、授業中だって、誰かと話したかった。私の隣に座った人たちは、話にツッコんだり、一緒に笑ったりと何かしら反応を返してくれた。しかし魚屋の次男だけは、全く違った。彼の隣だと私は、誰にも聴かれることのないラジオ番組のパーソナリティをしているような、音が永遠に流れ続ける壊れたレコードプレイヤーのような、そんな感じだった。暖簾に腕押し。糠に釘。言葉が届かず、ふわふわと宙を彷徨い続ける感じがした。そのたびに、彼が書いた鰻の詩を、まぼろしのように思い出した。彼は飛び抜けて国語ができるわけでもなかったし、本だってちっとも読んでいなさそうだった。しかし、彼の内側にはとても豊かな言葉がある。私の焦がれた散文が、この人の身体から出てきたことを不思議に思いながら、席替えの日が早く来ることを願った。
ある日、道徳の時間に"クラスメイトの名前をフルネームで書けるか?"という、今考えると本当にどうでもいいような、ゲームのようなことをさせられた。私の名前はこのなかでいちばん簡単だろうという自信があった。"前田"はオーソドックスな苗字だし"エマ"なんてカタカナなのだから間違えようがないだろうと思った。しかし魚屋の次男は「前田・・・」で筆を止めたのだった。
家を出て、結婚をし、父親になった彼は、今ももちろん私にはこれっぽっちも興味がないだろう。しかし私は文章を書くたびに、いつかあの鰻の詩を超えたい、いや、超えられずとも並びたいと思いながら、去年の夏もあの魚屋で、鰻を買った。

鰻の詩に衝撃を受けた頃の私。7つ離れた弟と。