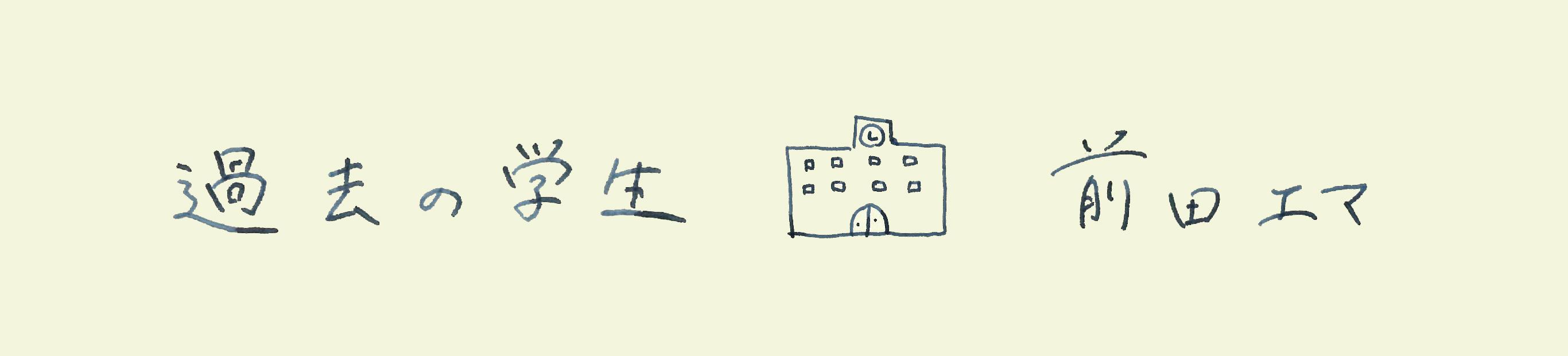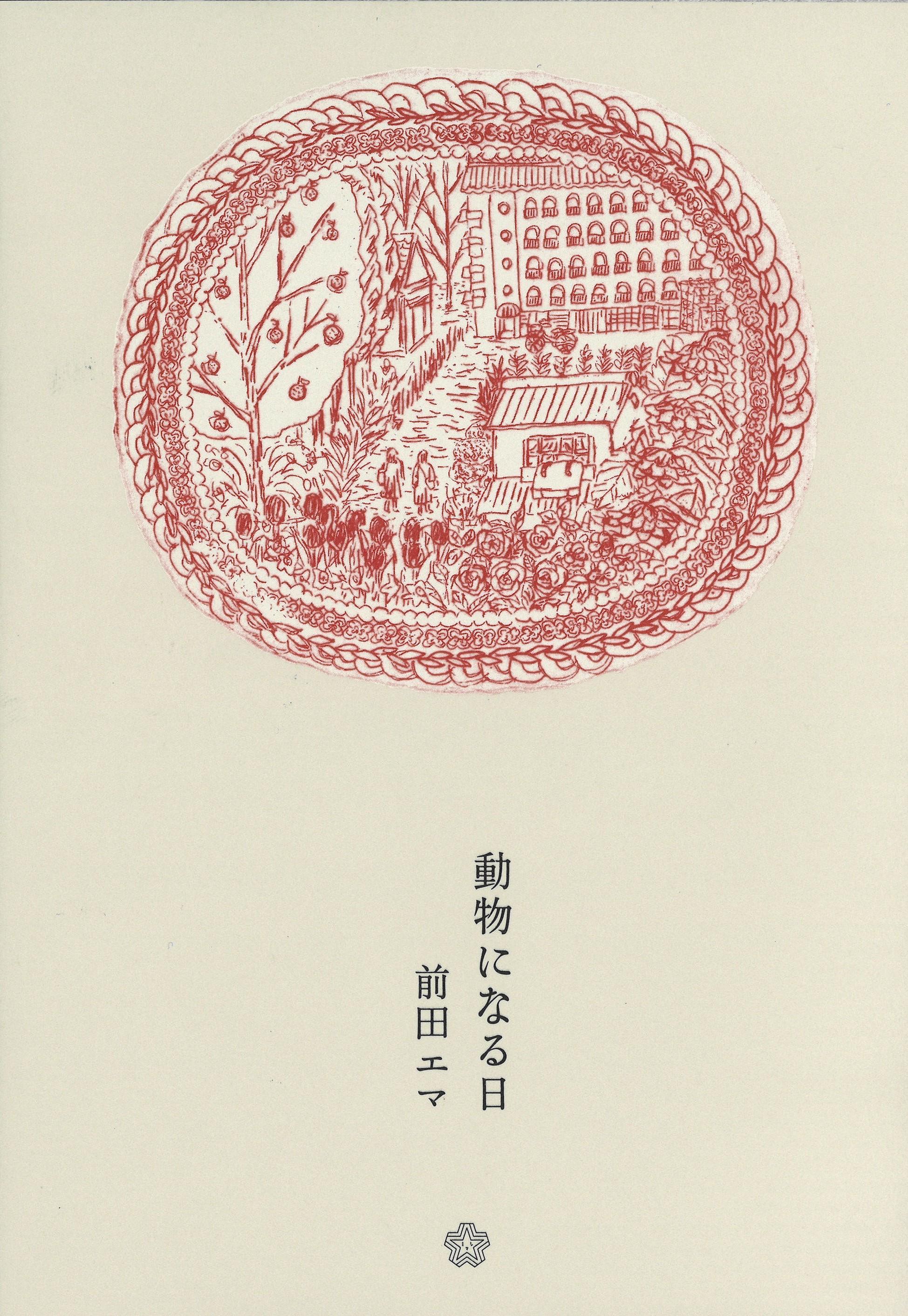第6回
九九が言えない
2023.02.23更新
九九が言えない。
七七までは言えるのだが、七八から後が、むずかしい。
七七...四十九。七八...わからない。七九...わからない。
しかし八の段になると、また少し大丈夫になる。
八一は、一八のことだから...八だ!
八二は二八のことだから...十六だ!
時間はかかるがそんな具合で進めていくと、八七に突き当たり、また、わからなくなる。
小学2年生の頃、九九が言えなくてひとり放課後の教室に残されたのだが、結局最後まで言えないままに帰宅した。家のお風呂場に九九の表を貼ってみたりしたのだが、母はまだ一歳の弟の世話で忙しかったような気がするし、ときどき家にやってくる父は、長風呂が苦手なので、いつも五の段くらいで上がってしまった。こうやって書くと、九九が言えないのは親のせいだと言っているみたいに聞こえるかもしれないが、親が付きっ切りで手取り足取り教えていたとしても、私はおそらく言えなかったと思う。
右と左も、車の免許を取るまで、あやふやだった。
多くの人が右と左を理解する年齢になった頃、私もみんなと同じように覚えようとしたが、どうにもダメだった。母だけでなく、祖母や叔母も総動員で私に覚えさせようとしたが、お手上げだった。4歳から18歳まで私はピアノを習っていたのだが、ピアノの先生も途中で諦めたようで「お茶碗持つ手が違う!」「お箸を持つ手だけで弾いてみて!」というように、私がわかる言葉で指示していた。
高校3年生の頃、免許を取ったときは「25万円を絶対に無駄にしない! 追加料金は払わない!」というケチ精神で、右と左を必死に覚えて、いざ教習所へと向かったのだが、私を待っていたのは、右と左だけではなく右折と左折もわからないと話にならないということだった。
九九もそうなのだが、私は "ただ素直に覚える" "そのまま暗記する" ということが苦手だ。何かしらつながりを持たせたり、体験したり、図や絵といったイメージに変換しないと頭に入ってこない。かといって、勉強ができるわけではないので、物事の根底に横たわっている理論や理屈なんかは、ちっともわからない。
教習所の指導教官から「ウセツしてください」と言われる。すると私はまず "ウセツ" という言葉を頭の中で漢字の "右折" に変換する。それから右折の "右" だけを取り出し、それを "ミギ" と読むことを頑張って思い出す。こうして "ウセツ→右に曲がること" だとやっと理解する。しかし、そんなことをいちいち考えてウインカーを出している時間はないので、運試しのように、勘で右に曲がったり左に曲がったりして、何度も教官に叱られた。「なんで左折するの! 右折って言ったでしょ!」と。
こんな風にして、他の人よりも遠回りをしなければわからないこと、遠回りをしてもわからないことが、私にはいくつもある。それはこの世界を生きていくのに少しばかり不便だが、このことを悲しんだり、哀れに思ったことはない。それは両親が、できないことがあるということを個性のひとつと考えて、私を育てたからだと思う。
小学一年生の頃の成績表を見ると「算数が苦手なので、夏休みにおうちで復習してきてください」と書いてある。それを期に、私は公文式へ通うようになったのだが、4年生になっても(九九が言えないので)ずっと2年生のテキストが終わらず、辞めた。5年生になると、私の学校では学年の7割近くが中学受験の準備をし始めた。私の母は中学から有名な女子校へ通っていたので、自分の娘もそういう人生を送るのかしらと思っていたようだが、(九九も言えないので)どうやら違うようだと悟り、受験対策の塾ではなく補習塾へ通わせた。
ある日、塾の面談で母が言った。
「塾はたのしいみたいなのですが、学校の勉強がわからないのでここへ通っているのに、全然理解していないようで...どうしてでしょう?」
すると先生は、しょぼんとした様子で
「そうですか...。私たちもエマさんにはどう教えたら良いかわからなくて...」と、申し訳なさそうに言った。
中学生になると「ここは数学の成績が伸びると評判なのよ」と言われる塾へ入った。しかし、まわりの成績が上がるなか、私だけ下がった。
3年生になり高校受験が迫った夏休み。母は一週間仕事を休んで、地方の山奥の旅館に閉じ籠り、私に勉強を教えた。母は大学生の頃に家庭教師をしており、生徒たちの成績を上げていたので自信があったようだが、私には無意味に終わった。
学校の面談では、担任の教師が母に言った。
「数学の授業だけ、他の生徒と違う教室で受けられるよう、教育委員会に行って、適正検査を受けませんか?」
しかし母はこう言った。
「数学ができないのは、エマの個性なので問題ありません。他のみなさんと同じように、今のままで結構です」
そう言い切る母のことをかっこいいなと思いつつ、心の中では「特別教室へ行けたら、 "特別な子" って感じがして、優越感に浸れるのにな...」と、少しだけ残念だったりもした。
ハタチの誕生日に、母がくれた漆塗りの大きな箱がある。そこには、へその緒や母子手帳、まだ母のお腹にいる私が写ったエコー写真などと一緒に、一冊の日記が入っていた。それは予定日よりも二カ月半ほど早く誕生した私が退院するまでの間に、母と看護師さんとの間でやりとりされた交換日記だった。母は私が生まれた瞬間から、私のことを何があっても他の子と比べないと心に決めていたそうだ。身体の大きさも、成長も何もかもが、標準の目安とは違っていた。
父は、私ができないことがあると、それを面白がり、褒めてくれる人である。
高校生の頃、"月極駐車場" の看板を見た私が「ねえ、このゲッキョクって、どこにあるの? 北極や南極みたいなところだよね? そこが運営している駐車場なんだよね?」と言うと、「こりゃまた "エマ語録" に書き足さなくちゃ」と、ニヤッとした。
必死に勉強したのに、7点しか取れなかった数学のテストは "名誉" だとして一週間ほどリビングに飾られた。
大学生からはじめた飲食店でのアルバイトでは、今でもお釣りの計算にものすごく時間がかかる。あたふたする私に毎回付き合ってくれる店長には、頭が上がらない。今でも九九は言えないままだ。

初めてのピアノの発表会で。