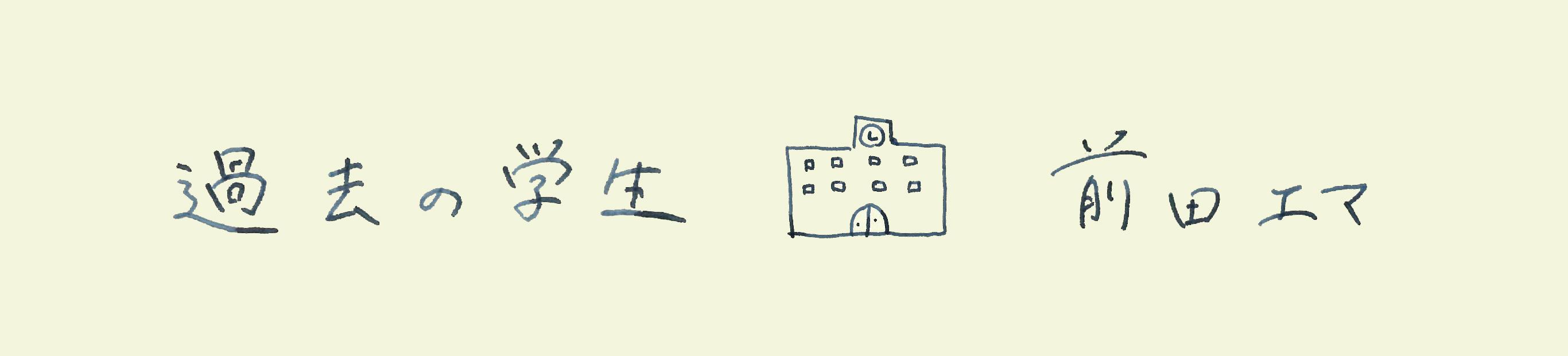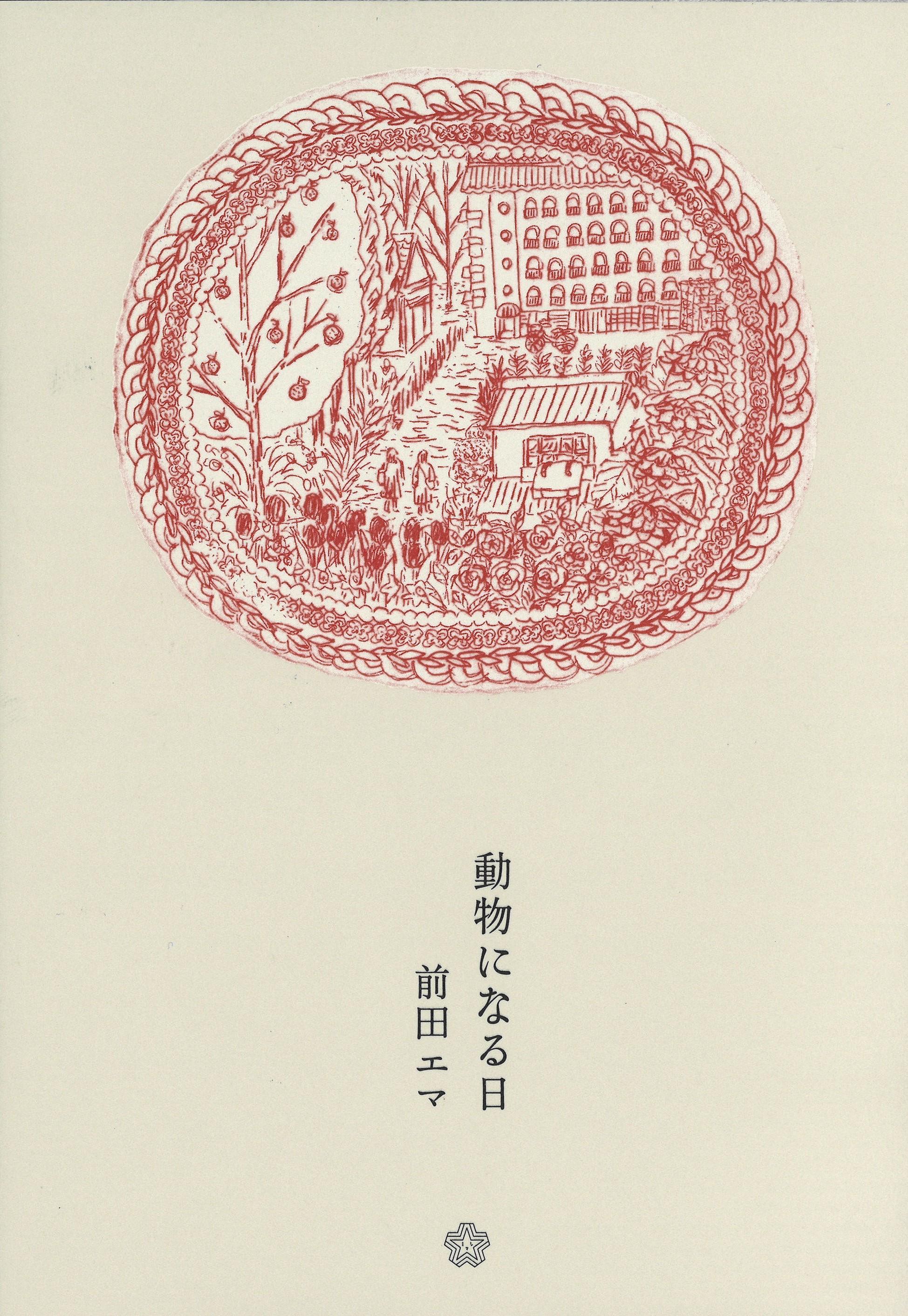第13回
鰻
2023.09.23更新
数年前、母と弟がインフルエンザにかかった。
当時、私たちは3人で暮らしていたので、私だけでも健康に過ごして、生活をまわさなくてはと思い、決して広くはないごく普通のマンションの一室で、ふたりと隔離した生活を送った。
ふたりが過ごすリビングには極力近づかず、ふたりが各々の寝室で寝ている最中に、私は台所で簡単にお粥や鍋を作り、置いておいた。洗面所やトイレは使用前後のアルコール消毒を徹底した。私は衛生管理に厳しい飲食店でアルバイトをしているのでこういったことに慣れており、いつもの仕事のようにテキパキとこなした。
心配した祖母が、何度か電話をかけてきた。
ふたりがインフルエンザにかかって二日ほどが経った頃だろうか。
「あーちゃん(祖母)がお金を出すから、鰻でも食べて元気を出しなさい」
電話口でそう言われた私は、その日の昼、駅前の老舗の鰻屋に行き、うな重を食べた。
これを栄養にして、なんとしてでも私はインフルエンザにかからないぞ。家族の平和は私が守るのだと再度決意を固くし、もぐもぐ、たらふく頂いた。
数日後。元気になった姿を見せに、母と弟と共に祖母の家に行くと「この間の鰻代、いくらだったの?」と聞かれた。
「え?エマ、いつ鰻食べたの?」と、母。
「ふたりが寝込んでる時。あーちゃんが鰻食べて元気出しなさいって言ったから」
「あら、エマ、ひとりだけ、鰻食べたの?」と、祖母。
「うん。だって、エマが元気でいるための鰻だよね?ふたりの看病するために」
「あらまあ。鰻でも買ってきて、3人で食べて元気出してねって意味だったのよ」
「え、そうなの?だって、ふたりは病人だよ?病人も鰻、食べるものなの?」
「はい、出た!エマちゃんのそういうところ〜。まあ、いいけどさあ」と、弟。
鰻をひとりで食べていたことに始まり、たいした看病はしていないだの、貧相な食事しか作ってくれなかっただの、病人である私たちを徹底的に避けていて傷ついただの...。そんなこんなで、私は家族からひんしゅくを買うこととなったのだ。
鰻なんて脂っこいものを病人が食べるなんてこれっぽっちも想像しなかった。貧相な食事といえばそれまでだが、消化にいいものを作った自信があった。家族みんながインフルエンザになったら、何かあった時に動ける人が誰もいないのだから、自衛こそが私にとっての一番大事な仕事だと思っていた。私としては、出来得る最大限の行動をしたつもりだったのだが、どうやら何かがとてもズレていたらしい。
思い返せば幼い頃から、自分としては一生懸命にやったつもりだったが、他人からすれば非常識だったり、あり得ないと言われることが多々あった。
今までの人生で何度も、他人の私に対する「え?有り得ないんだけれど...」という表情をたくさん見てきた。サッと表情が変わる瞬間を、唖然を通り越した冷えた表情を、そのひとつひとつはよく覚えているのだが、具体的な内容を思い出そうと思ってもなかなか難しい。自分では真っ当な考えだと思っての行動なので、なおさらだ。
そんな私でも大人になるにつれ、他人のあの表情を見ることが減っているような気がする。しかしもしかしたらそれは、私が誰かに対して、あの顔をする側にまわっているのかも知れない。いや、ただ単に、他人があの顔を上手く隠すようになっただけで、私は変わっていないのかもしれないけれど。