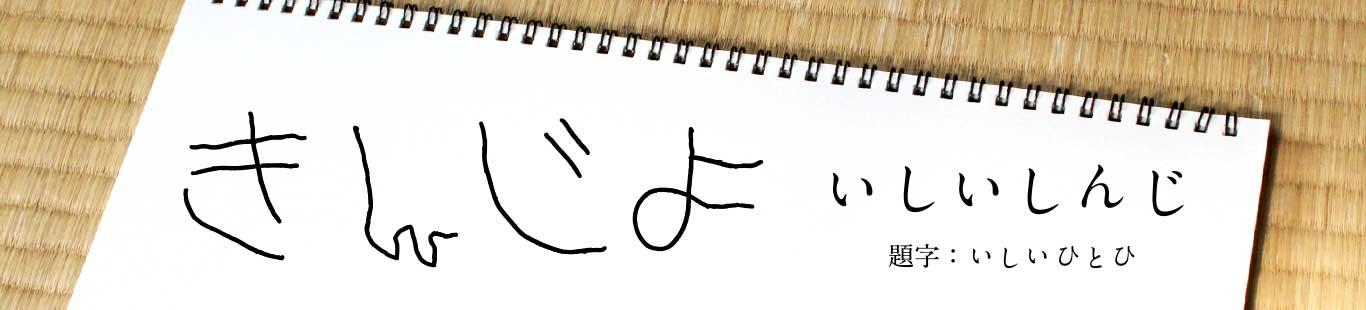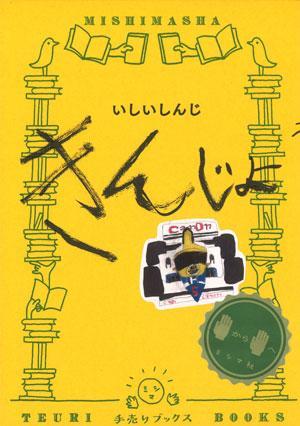第43回
せいりけん いりまへんか〜〜
2018.10.26更新

今年の夏、うちの暮らしは「きんじよ」祭一色だった。いや、イベント自体が多種多彩だから、タミヤカラーを全色いっぺんに、家のべんがら格子にぶっかけたみたいなものだった。その影響で、ひとひは秋になってからウィルス感染したり、その翌々週に入院したり、といろいろあるのですが、まずは「きんじよ」祭のことを整理しておきましょう。
七月十四日、ゼスト御池・ふたば書房でのスケラッコさんとの「似顔絵対決」。
七月十八日、ホホホ座店長・山下賢二さんとの「夏の小説ゼミ」(秋、冬、春も予定しています)。
そして迎えた八月の五日、丸善京都本店での「宇宙人トーク」が、一連のイベントの「へそ」だった。おっさんら四人がただ脈絡もなく話を振りあっているだけだったのですが、その六十分ほどの時間が「きんじよ」祭の底を下支えしていたし、いまもしている、そんな実感がしています。
出演は、100000tアローントコの加地猛くん。ホホホ座の山下くん。ぼく。そして、ひとひの友人にしてシトロエン2CV乗りの奥村仁さん。
加地くんはいつもの加地くんで。山下くんは「夏の小説ゼミで、話しつくしたんで」みたいな、余裕のさっぱり顔で。と考えてみると、「宇宙人トーク」のなかの真の宇宙人って、やっぱ奥村さんだったのだな、とあらためて気づく。
ひとひとの出会いのシーンをかんたんにしゃべったあと、奥村さんは口から、ひたすら仮面ライダー関連の話を噴射しつづけた。残りの三人が、生半可な程度についていけたこともあるだろうが、そんな事情を凌駕する、奥村さんのライダー愛に、場内は打たれ、笑い、そんなところにいくとは思ってもみなかった地平へともっていかれた。
奥村さんは初代から最新作まですべてのライダーをリアルタイムで、録画でなく、見続けている。おそらく、すべての回のストーリーを記憶し、怪人の名前、得意技なども暗記している。
「あーもう、なんでわし、こんな場違いなことしゃべっとんにゃ!」
と身もだえしながら、奥村さんの宇宙人トークはつづく。いま放送中のライダーのなかでは、宇宙はすでに、いったん滅亡しているらしい。人類は、滅亡したあとに残った、仮想宇宙みたいなところで、架空の生を生きている。ライダーはその仮想宇宙をリアルな宇宙に戻すために日夜たたかっている。
奥村さんもたたかっている。加地くん、山下くん、そしてぼくも、奥村さんについてたたかう。ヴァーチャルなんて焼き尽くせ。口で肉をしゃぶり、小便をぶちまけろ。トークは誰も予想しなかった宇宙の果てまで突き進み、そうして突然、一気に収斂した。書店でのトークイベントで、緊迫感があれほど自在に伸び縮みするのはまれだろう。その意味、「きんじよ」という本の火種は、北白川ライフでの、ひとひと奥村さんとの、2CVをさしはさんでのビッグバン的出会いの際、時間のなかに埋め込まれていたのかもしれない。
なればこそ、その必然として、翌六日、ひとひはひとりでイベントのマスターをつとめた。
京都への観光客、意識高い系のOL、大学生、高級住宅街の奥様方がお茶している、お昼過ぎの京都岡崎 蔦屋書店。
午後一時、店内アナウンスがはいる。
「アー、アー。いしいひとひの、くねくねしょどう。サイン、いりませんかー、えー、いりませんかー。いしいひとひの、くねくねしょどう、やってまーす。オワリ」
声をかけてくれたひと、目を合わせてくれたひと。ひとひは駆けより、手製の「せいりけん」を手渡す。わざわざ駆けつけてくれたひとひファンもいる。
ぼくのイベントに参加し、ちょこちょこ走りまわったり、マイクで曲紹介したり、カラーペンでサインしたり、と、そういうことはこれまでに何十回となくやった。けれどもこの日はひとひだけの、「きんじよ」サイン会だ。その辺、わかっているのかわかっていないのか、ひとひはいつものように、物事の隙間を縫いながら、鮎が川の岩間をさかのぼるように、楽しいほうへ、楽しいほうへ、身をくねらせて泳いでいく。
こどものからだは、それだけで字だ。う、と流れ、つ、と曲がり、ん、と跳ねる。レジに走りこむと、勝手知ったるボタンを押し、「アー、アー、アー、いしいひとひの、くねくねしょどう、くねくねしょどうは、いりませんか」とアナウンス。
蔦屋を駆けまわるひとひ自身のからだが、空間に、くねりくねりと字を書いていく。ひとひの走る振動で書棚が揺れ、端正にならんだ本からも透明な字がパラパラとこぼれ落ち、店じゅうに舞いあがる。こどものからだと本の字が、手をつなぎ、輪舞し、重なり合う。
サイン会、絵描きイベントというより、だから、「いしいひとひのくねくねしょどう」は、一種のおどり、群舞、ダンスパフォーマンスだった。八月六日、あの一時間弱、店内に居合わせたひとなら、そのことが、からだの芯で実感されるだろう。誰もが昔、こどもだった。からだ全体で、字になって語り、音符になってうたっていた。その記憶はぼくたちの内奥に保存され、けして消え失せることはないのだから。
八月十一日は、僕とひとひがガイドをつとめる「ごきんじよツアー」。
思い返していただきたい、二〇一八年八月のあの炎暑を。この日も暑かった。集合場所の誠光社から外へ出ていくのを、ガイドのぼくだけでなく、参加者全員、一瞬以上ためらったはず。けれどもぼくたちは乗りだした。ごきんじよを巡る夏の旅へ。光と闇との境目を、ていねいにたどりながら。
境目とはつまり、日陰のこと。ツアー出発は午後1時だったから、太陽はまだ高みから京都を照らしつけていたが、わずかに南西へかたむいていた。つまり建物の北か東側をつたって進むなら、炎暑はさほど致命的にはならないのだ。気温はいつものように四十度近くまであがったが、湿度はさほどでもなく、また、乾いた風が南からゆるやかに吹きつけていた。
陽を遮るもののなにもない、丸太町橋をわたるときがいちばん暑かった。細い路地にはいると町家の屋根から落ちる影がぼくたちを守った。ひとひが影の稜線を走ってツアーを先導する。と、家の引き戸をあけて、
「おつかれさまー」
と園子さんが、お盆をもって現れる。ひとりに一杯ずつの、自家製しそジュース。うちの家の前が、水分、糖分、数値化されない「きんじよ」エネルギーの補給ポイントだ。
冷泉通を南に渡り、小さな家が密集する住宅地へ。じつはここ、明治初年までは二条新地という花街だった。祇園、上七軒とならんで栄え、川向こうの先斗町は、二条新地の出店だった、という話もある。
そうか、とおもって見あげれば、遊郭の風格をまとった家屋がそこらに残っている。明治にはいって吉田に京大ができ、こんな近くに岡場所があっては、ということで、明治二十年にいきなり廃止になった。ツアー一行は神妙に、残り香をたどるように歩を進めていく。どんな旅行会社のツアーでも、こんな風情のところへは入ってはこられまい。
お漬けものの名店「加藤順」に寄る。参加者のひとりが辛抱たまらなくなって買い物に走ってしまう。すぐ近くのブックカフェ「ユニテ」で待つ。が、ここでもたまらず、買い物に走ってしまう参加者が。みんな、そんなになにか買いたくてたまらないのだ。ぎりぎりまで待つ。冷房が皮膚の底にしみこみ、さあ、と出発するが、二条大橋を西側へ渡っていく途中、早くも「じゅっ」と、冷えた空気は跡形もなく蒸発してしまう。
河原町通の東側を歩く。午後三時にもなるともうずいぶんと影は長くそして濃い。ツアーのクライマックスはHi-fiカフェ。マスターの吉川さんは、このツアーのためだけに、特製の「コーヒー牛乳」を抽出し、待ってくれていた。この一杯だけでも、ぼくは、ツアーを企画してよかったとおもったし、参加者の誰もが、ここに来られてよかった、と思ったはず。コーヒー求道者の吉川さんは、このオリジナルHi-fiコーヒー牛乳のため、豆の焙煎まで行ってくれたらしい。通常のメニューにはない、この日だけの特別な一杯。でもふだんから通っているひとは、吉川さんはどの一杯にも魂をこめていることを知っている。ほんとうにごちそうさまでした。
三月書房でまた、参加者おおぜいの足がとまる。見まわすと、誠光社で出発したときより、ツアーメンバーの人数が明らかに増えている。別に遅れてきたわけでなく、「え、おもしろそう」と、ぞろぞろついてきたひとが何名もいる。すばらしい。それでこそ「ごきんじよ」ツアーだ。店主・宍戸さんの奥さんも店頭まで出てきて見送ってくださる。誠光社と三月書房を糸で結ぶような、本をめぐる徒歩の旅。
打ち上げ会場は國田屋酒店だった。乾杯用の生ビール一杯ずつも、ツアー料金のなかに含まれているのだった。メンバーの何人かは店先でケラケラ騒いだのち、さらなる夜の二次会へと向かったようだった。夏の陽ざしのかけらを軽く払い落としながら、夕暮れの丸太町橋をわたって家に帰った。
つづく